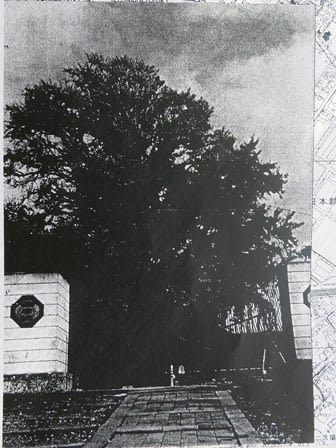2016年10月期:第五回
川口川をさかのぼる③(最終回) 釜の沢橋から今熊山山麓まで
野外講座は2月がお休みでしたので
お仲間とも久し振りに会えて
話も弾み元気に歩いてきました。(3月18日)
長閑な早春の風景を眺め、寺院を訪ねながら
流域紀行の最終回に相応しく里山を楽しんで来ました。
上川霊園行きのバスでバス停「森下」で下車。

最初に訪ねた熊野神社に参拝する。

暫らく歩いて三光院の山門から撮りました。

山門には阿形・吽形の双龍が堀込められています。


長閑な風景を楽しみながら歩く…

鎌倉古道の残る道に沿って石仏や石碑が並んでいます。

その奥にある馬頭観音堂、落ち着いた雰囲気のお堂でした。

静かな早春の景色を楽しみながら歩きました。

大仙寺の山門が見えてきます。

入り口には古い石仏や石碑が
歴史の古さを物語っている様でした。

境内には納め札が沢山貼られた古いお堂がありました。

本堂です。

この大仙寺の山門前から今熊山が望めます。

昼食は農村環境改良センターでそれぞれ持参したお弁当を食べた~
午後の最初は田守神社。

正福寺に向かう道の枝垂れ梅が満開でした。

前方に正福寺が見えてきました。

向拝の上部に龍や獅子などの素晴らしい彫刻が拝見出来ました。


正福寺前から眺める今熊山の眺望です。
今熊山は標高505メートル、山頂に今熊神社が祀られています。

この流域紀行を歩き始めたのが2014年4月でした
先ず浅川を遡り、湯殿川、山田川、南浅川、城山川、北浅川、川口川等…
一つ一つ振り返ると思い出は尽きませんが
寺社や地域の歴史を新たに知る事が出来た楽しい流域紀行でした。
2017年4月期からは表題も新たに「大人の遠足」が始まります。
一日散策の遠足です。
探訪先は 東京・神奈川・埼玉・山梨 (時には千葉も)方面です。
略して 「と・か・さ・や」だそうです。またまた楽しそう…
今から楽しみで…わくわくしています。
来月4月は先ず東京からです。どんな景色に出会えるか楽しみです。
馬場ファミリーは4月期からも元気に歩きます。