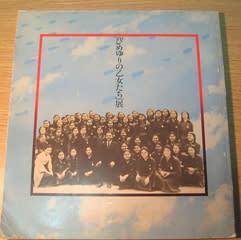赤野観音堂
赤野観音堂を1キロほど下った沼津市柳沢の集落の真中あたり、高橋川が堀のように取り巻いて流れている桃沢神社で、お昼の弁当のゴザを敷いた。このあたりは愛鷹茶の栽培がさかんなことと、時を経ても昔と変らない静かな村の佇まいが忙中閑あり、心を洗わせてくれる。

社の傍らに先の戦争で亡くなった人を記録した護国碑と彫られた慰霊石塔を見つける。
こんな、のどかな村落からも多くの若者が出征して、尊い命を落としている。
今日もまた昼休みを返上して碑文を指でなぞる。

護国碑は昭和29年8月10日、愛鷹村柳沢区民之建とある。沼津市に合併される前年に区民有志の寄付で建てられた。寄付と建立に携わった92名の名前が台座に刻まれている。柳沢のからは日支事変から終戦までに延べ80名が出征された。53名は生還したが27名が戦死。内訳は陸軍21名、海軍1名、陸軍航空兵1名、開拓団2名、警察官2名、その27人には氏名の下に年月日と戦没場所が刻まれている。多くは陸軍の一兵卒として召集され、戦没場所も本土を南に遠く離れた比島レイテ、ニューブリテン島ラバウル南方、そしてさらに遠いブーゲンビル島、西に転じてみれば南京、満州、ビルマ、ソ連、(戦没場所不明2人)に至るまで、当時日本が主張していた大東亜共栄圏の隅々まで行き渡っている。
先日、寅の子文庫で【墓標なき八万の死者~満蒙開拓団の壊滅/角田房子著】と言う本が売れた。角田さんの言葉を借りれば、『~人間が平常の感情、常識を失えば狂人と呼ばれる。しかし生きぬくことに精魂を傾けつくす状態におかれた人々は、狂ったのではない。極度の疲労が人間の心をすりへらし、感情を枯らして、それを自分以外のものに向けることを不可能にしたのである。子供も妻もまた、自分以外のものであった~。』 とあるが、満州では昭和20年8月9日、ソ連軍の参戦により虐殺や集団自決という狂気が日常のように繰り返され、開拓団の多くはこの世の地獄を見て壊滅する。この柳沢からも開拓団として海を渡った鈴木儀作さんと石渡さきさんの2名が終戦の前と後、20年7月5日と21年2月23日に亡くなっている。また小野力雄さん春枝さんご夫妻は警察官として終戦直後の20年9月20日に満州吉林省で一緒にお亡くなりになられた。理由を知る術もない。陸軍に召集された小野豊さんはソ連ブリヤードモンゴル自治州ブカチャ収容所で同じく終戦後20年12月25日に亡くなられている。人生半ばも行かず不本意にも命を落とした方たちの無念と残されたご遺族の無念。故郷を遠く5000キロも離れた南の島で、バンザイと叫びながら自ら命を落さねばならなかった青年たちが居たことを忘れてはならない。日本の全国の郷土にはこのような招魂碑、あるいは忠霊塔と言われる供養塔の類が幾千幾万と建立されているのだろう。今日八月十五日、暑いセミの声に打たれながら自らには経験の無い60年前の戦争を思い、手を合わせた。
【昭和万葉集巻六、太平洋戦争の記録/講談社/54年2月8日初版】から三首紹介。
玉砕の命下りし夜の北の空四人の吾子の姿映りぬ /平出孝行
ソロモンに往き戦ひし大き掌がわが掌をつかむさらばといひて /水上すゞ子
夏の月すずしく照れりわれは聞く云はぬこころの限りなき声 /窪田空穂