
おはようございます。株式会社ティオ代表、motown21主宰の山本です。
今日は、自整業で給料の3倍稼ぐにはー2.労働分配率50%は無理なのか、です。
給与の3倍を稼げていない多くの整備工場の場合、その原因は労働分配率にある。
経営指導で出会った整備工場では、60%を超えているところが殆どである。
労働分配率が60%を超えているのは、粗利益の額が少ないからだ。
ということは、整備売上が低いことになる。※粗利益率が60%を保っているとして。
もう一つは、ムダな人員が存在することで、給与額が膨らんで
いるいために労働分配率が高くなっているからだ。
それを判断するのは、付加価値生産性という指標だ。
付加価値生産性とは、従業員一人あたりの粗利益の額。
これが、少なくても100万円は欲しいところだ。
それが、70万円とか、60万円となっている。
社長含めて3人程度の整備工場の場合は、人員オーバーはないが、
指定整備工場などでは、十分に考えられることだ。
特に、整備要員が余剰となっているケースが多い。
いやー、当社ではむしろ少ないぐらいだ、と言われるが、本当にそうだろうか?
そこで、まず稼働率を調べること。
少なくても65%以上の稼働率が欲しい。車検やオイル交換などで引取納車を
行なっている整備工場は、50%を割っていると思う。
つまり、引取要員としてメカニックをキープしているのが実態だ。
であれば、メカニックを一人減らして、パートで引取回送要員を雇ったほうが、
人件費は低くなる。
稼働率が悪くないようであれば、作業効率を判断してほしい。
作業効率とは、標準作業時間に対して、実際に要した作業時間の割合だ。
メカニックの平均年齢が40歳を超えるような整備工場であれば、少なくても
標準作業時間よりも、少ない時間で作業を終えなかればならない。
60分作業であれば、50分作業で終えることだ。
この場合の作業効率は、120%になる。
稼働率が良くても、作業効率が悪ければ、一日に作業できる台数は
少なくなってしまい、結果的にメカニックを増やすことになる。
こうした、現場の生産性を疎かにしていて、単純に残業が多いいからと、
メカニックを増やしてはならないのだ。
こうしたことをやっていると、労働分配率50%以下にすることは、困難になる。
稼働率、作業効率共に問題が無い、ということであれば整備売上高が
低いために、労働分配率が高くなってしまうことになる。
この場合考えられる原因は、レバレートが低いか、値付けが不適切
という原因が考えられる。
毎年物件費や人件費が上がっているにも拘らず、レバレートが変わらないのは、
不思議な現象である。
その年の経営計画に基づいて、レバレートも改訂して、初めて適正な
工賃請求が出来、結果工賃売上が向上して、労働分配率を改善することになる。
もう一つ、工賃値付けを見てほしい。
特に、故障修理の場合だ。
大概が「交換工賃」しか請求していない。
交換前に行った、点検や測定などの診断的な作業の請求が
なされてない。
あるいは、調整的な作業に対する工賃請求が出来ていない。
ゆえに、交換工賃だけで適正な工賃売上になっていないのだ。
給与水準を下げずに、労働分配率を50~55%にするには、一人あたりの
稼ぎから、売上不足なのか、人員オーバーなのかを判断し、原因があれば
メスを入れて改善することだ。















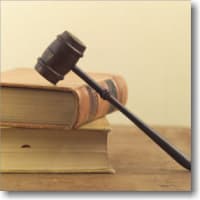




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます