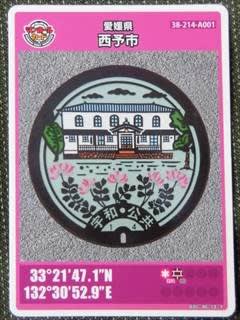西宇和郡伊方町(いかたちょう)は愛媛県の南予地方、佐田岬半島に位置する町です。2005年4月1日 - 西宇和郡瀬戸町、三崎町と合併し、新たに伊方町となりました。八幡浜市に、また海を隔てて宇和島市、西予市。豊予海峡を挟んで、大分県大分市、国東市。瀬戸内海を挟んで山口県上関町に隣接。町内全体が佐多岬半島の基部から先端にかけての地域で、稜線が半島の背骨の如く延び、半島の両側に急速に海に落ち込む地形をしており、大規模な河川は無く、平地はわずかであるために穏やかな傾斜地に集落とミカンなどの耕作地が集中。四国電力伊方原子力発電所があり、一時は四国の電力消費量のおよそ4割を供給していましたが、全発電機が定期検査に入った2012年から送電を停止しています。「町の木:ウバメガシ」「町の花:ツワブキ」「町の魚:アジ」を制定。
キャッチフレーズは「よろこびの 風薫る町 伊方」

マンホールには町章を中心に「町の木:うばめがし」「町の花:つわぶき」町の魚:あじ」「町の特産品:ミカン」がデザインされています。
が・・滑り止め防止の加工が施されているので、遠目で見るとただの規格蓋に見えます。


2005年 11月7日に制定された三代目の町章は「美しい海に突き出した日本一細長い佐田岬半島を中心にデザインし、それを取り巻くように「i」の字をエネルギーと波にして躍動感と明るい未来への広がりを表しています。」HPより



------------------------00----------------------
旧西宇和郡伊方町(いかたちょう)は、佐田岬半島のほぼ中央に位置した町です。八幡浜市、西宇和郡瀬戸町に隣接。北を伊予灘に、南を宇和海に面し、中央には南北に佐田岬半島を形成する山地が東西に横たわっています。伊予灘側はけわしい海岸が続き、宇和海側の入り江にいくつかの集落が点在する農・漁主体の町です。「町の木:黒松」「町の花:ツワブキ」を制定。

明治22年(1889)、町村制の施行により、西宇和郡町見村・伊方村が発足。
1955年、伊方村と町見村が合併、町制を施行し西宇和郡伊方町が発足。
昭和40年(1965)3月31日制定の初代町章は「オレンジと緑で蜜柑の花を象徴し、「伊方」を円形に形どったもの」。この後「い」を青とオレンジで表した二代目町章が制定されますが、今回は敢えて初代の町章を紹介しました。

------------------------00----------------------
旧西宇和郡瀬戸町(せとちょう)は愛媛県の南予地方、佐田岬の先端部近くに位置した町です。西宇和郡三崎町・伊方町に隣接。集落は瀬戸内海側と宇和海側に分かれており、町内の地域間の交通の確保が課題となっています。稜線では風況がよく、風力発電が行われ、風車が林立する姿は新しい景観を形成しています。高輝度青色発光ダイオードを発明・開発し、2014年にノーベル物理学賞を受賞した「中村修二氏」の出身地として知られています。「町の木:ウバメガシ」「町の花: ツワブキ、サザンカ、スミレ」「町の魚:アジ」を制定。

明治22年(1889)、町村制の施行により、西宇和郡三机村・四ツ浜村が発足。
1955年、三机村・四ツ浜村が合併、町制を施行し瀬戸町が発足。
2005年、西宇和郡伊方町・三崎町と合併し伊方町となりました。
昭和41年5月10日制定の町章は「頭文字の「セ」を鳩の形に表したものです。」

------------------------00----------------------
旧西宇和郡三崎町(みさきちょう)は愛媛県の南予地方、佐田岬の突端に位置した町です。西宇和郡瀬戸町に、豊予海峡対岸で県を跨いで大分県大分市に隣接。半農半漁の町で傾斜地を活かしてかんきつ類の栽培が主体。また周辺は潮流渦巻く好漁場であり、一本釣りのアジ、サバのほか、イセエビ、アワビ、サザエ、ウニなどの高級食材の生産地としてしられ、岬近くに蓄養場も有しています。四国最西端の港湾「三崎港」には、九州:佐賀関港とを結ぶ国道九四フェリーが就航。フェリーの上から佐田岬半島の先端に建つ「佐田岬灯台」を見る事も出来ます。「町の木:ウバメガシ」「町の花:タチバナの花」を制定。


明治22年(1889)、町村制の施行により、西宇和郡三崎村、神松名村が発足。
1955年、西宇和郡三崎村・神松名村が合併、町制を施行し西宇和郡三崎町が発足。
2005年、西宇和郡伊方町・瀬戸町と合併、伊方町となりました。
昭和40年制定の町章は「「ミサキ」を意匠化し、三本の曲線を表したものです。」

(※)旧西宇和郡瀬戸町、三崎町では、ご当地マンホールは発見できませんでした。
撮影日:2011年6月14日&2015年2月26日
------------------------00----------------------
2011年と2015年の車泊旅では「道の駅:伊方きらら館」にて車中泊をさせていただきました。瀬戸内海と宇和海を一望できる立地で、もの凄く期待していたのですが一度目は生い茂る木々に邪魔され、二度目は生憎の雨。でも特産品のミカンがビックリするようなお値段で販売されていて、車内での置き場に苦労するほど買いすぎてしまいました。

車で旅をする私たちにとって、こうした施設は本当にありがたく大切な場所です。
改めて、その節は有難うございました🙏🙏