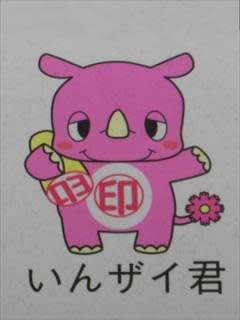印西市萩原に鎮座される「鳥見(とみ)神社」。御祭神は『饒速日命(にぎはやひのみこと)、宇摩志麻治命(うましまぢのみこと)、御炊屋姫命(みかしきやひめのみこと)』

境内由緒に【この地は古来鳥見ヶ丘と呼ばれ、その名称はこの地域に関して記された江戸期の文献に多く登場している。かつて萩原村と近隣の松虫・荒野の鎮守であった鳥見神社の起源については、神社の由緒書のよれば「大五代考照天皇の御代大和国城上郡萩原村の鳥見山の神々の霊を当地に遷座した」と伝えられており、今日も地域の産土神として人々の宗敬を集めています。】

印西市の「鳥見神社」ですが、同名の神社が小林・大森・平岡・和泉・小倉・中根・浦部地区にも鎮座されています。 ネットなどで見ると、旧社格は小林地区の「鳥見神社」のみ郷社で、他は村社となっています。でも私たちには社格は二の次、良い狛犬、良い宮彫刻、御祭神が魅力的・・後は超有名かどうかも若干・・😆

拝殿前左右より神域を守護されるのは、明治7年(1874)建立の江戸流れ狛犬さん一対。台座には『石工:吉五郎』の銘。 阿形さんは手の下で仔狛を遊ばせていますが、仔狛はその手が邪魔だと言いたげ、きかん気の顔で親狛の顔を見あげています。

吽形さんの手は、牡丹の花が一杯刻まれた岩の上に乗せられており、さしずめ唐獅子牡丹😊 何と言うか随分と優雅に過ごしておられるようです。

神域は鬱蒼とした森の中にあり、差し込む光はとても穏やかで思わず深呼吸。 ここから数キロも離れていない場所に、ニュータウンと呼ばれる団地があるのが嘘みたい。

境内には沢山の摂社・末社があり、ささやかな石の祠もそこかしこに点在しています。 千葉県北西部の神社には必ずといって良いほど勧請されている「三峯神社」も、もちろん鎮座しています。

「境内社:子安神社」。もとは、天平宝字三年(759)に時の帝の后が懐妊した際、その安産を願って創建。一般的には『木花開耶姫命』が祀られており、その範囲は日本全国に及びます。

「境内社:大山阿夫利神社」。関東総鎮護の霊山とされる「大山」に祀られる神を勧請したものと思われます。

石碑に刻まれた神名は「羽黒神社 月山神社 湯殿神社」、いわゆる「出羽三山神社」を言います。

境内入り口近くの碑には、それぞれ「二十六夜(陰暦正月・7月の26日の夜)」「二十三夜(陰暦の23日の夜)」「猿田彦大神」の刻。

参拝日:2019年3月17日