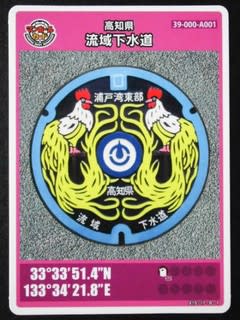高知市(こうちし)は四国南部のほぼ中央に位置する市です。南国市、土佐市、土佐郡土佐町、吾川郡いの町に隣接。市の南北方向は、北方には急峻な四国山地があり、その支峰である市域北部の北山に源を発する鏡川の下流域を中心に都市が形成。南方は浦戸湾を経て土佐湾に面し、東西に広がる海岸線から黒潮が流れる雄大な太平洋を一望できる地理的条件にあります。

一方、東西方向には、中央部に広く平地が分布するなど、比較的平坦な移動しやすい地形が続いています。約400年前、「長宗我部元親」が施政するに至った後、政治、経済、文化の中心都市として発展。慶長6年(1601)関ヶ原合戦の勲功により土佐24万石の領主に封ぜられて入国した「山内一豊」が、慶長8年(1603)大高坂山に城を築き、ここに城下町をつくったことが中心市街地の始まりと云われます。さらに幕末には坂本龍馬、武市瑞山等勤王の志士を輩出し、維新の礎を築きました。「市の木:センダン」「市の花:トサミズキ」「市の鳥:セグロセキレイ」を制定。
キャッチフレーズは「森・里・海と人の環 自由と創造の共生都市 高知」

明治22年(1889)、町村制の施行により、土佐郡直轄であった上街、高知街、南街、北街が合併、市制を施行し高知市が発足。
土佐郡江ノ口村・旭村・鴨田村・下知村・潮江村・秦村・初月村・鴨田村・布師田村・一宮村・朝倉村が発足。
長岡郡三里村・五台山村・高須村・大津村・介良村が発足。
吾川郡長浜村・浦戸村・御畳瀬村が発足。
1901年、江ノ口村が町制を施行、土佐郡江ノ口町となる。
1916年、下知村が町制を施行、土佐郡下知町となる
1917年、土佐郡江ノ口町を編入。
1925年、土佐郡旭村、鴨田村鴨部の一部を編入。
1926年、土佐郡下知町、潮江村を編入。
1927年、土佐郡小高坂村を編入。
1929年、長浜村が町制を施行、吾川郡長浜町となる
1935年、土佐郡秦村・初月村を編入。
1942年、長岡郡三里村、五台山村、高須村、土佐郡鴨田村、布師田村、一宮村、朝倉村、吾川郡長浜町、浦戸村、御畳瀬村を編入。
1972年、長岡郡大津村、介良村を編入。
1975年、南国市岡豊町蒲原の一部を編入。
1989年、南国市伊達野・稲生の各一部を編入。
2005年、土佐郡土佐山村、鏡村を編入。
2008年、吾川郡春野町を編入。
マンホールには市章を中心に「波の中を泳ぐ2頭のニタリクジラ」がデザインされています。(高知市上下水道局入口)




市章を中心に、勢いよく飛び跳ねる「カツオ」「入道雲」よさこいの「鳴子」がデザインされています。




市章を中心に「県の鳥:ヤイロチョウ」、「県の花:ヤマモモ」、「高知城」がデザインされています。




高知市中心商店街に設置されたハンドホールには、太陽の顔がデザインされています。

同じ場所に設置されていたもので、全体に星座がデザインされています。

大正9年(1920)2月15日制定の市章は「高知市の「高」の字を図案化したものです。」公式HPより

展示マンホール










水道制水弁の蓋ですが、文字は右から左で、旧漢字も使われています。多分、かなり古いものなのでしょうが、こうして残っているのが嬉しいですね。

土佐の楽市本舗マスコットキャラクター『なるこ君』とガールフレンドの『なるるちゃん』。今日はお友達の『とさけんぴ君』と『しんじょう君』も一緒で仲良く記念写真。

高知市観光PRキャラクター『とさけんぴ君』。出身地のはりまや橋の王冠を頭にのっけて、特技は、けんぴ早食いと鳴子の早鳴らし。
「まわしのとこにおる『鳴子のこなる』は相棒やきにね」と教えてくれました。


高知市中心商店街キャラクター『ピーちゃん・エスくん』。高知県内ではあらゆる場所で目にする『やなせたかし氏』デザインのゆるキャラメンバーです。

こちらは『かずとよくん・ちよちゃん』。大河ドラマになった「功名が辻」を盛り上げ、PRに大いに活躍したとか。愛馬の『おおたぐろくん』も居ると小耳に挟んだのですが、遭遇できず!

「一豊・千代」に続くのは、土佐藩15代藩主『山内 容堂』。幕末の一時代を生き抜いた人物ですが、これがゆるキャラになると・・・・・『やまぴょん』こと『山内 兎之進』。特技は剣術、苦手は算術。 どう見てもウサギっぽいのに、苦手な食べ物は「ニンジン」😔❓

山之内神社の絵馬に描かれた「山内 容堂」・・決してやまぴょんと比べてはいけません。

「環境維新・高知市―土佐から始まる環境民権運動」マスコットキャラクターは、セグロセキレイの『ケーちゃん』。高知と環境の頭文字から命名されました。

国道55号線「ふれあい海道」のマスコットキャラクター『あいか』。 花びらは四国、空き缶の体は太平洋をイメージして、ポイ捨て禁止をアピールしています。

撮影日:2013年3月19日&2014年3月21日&2018年6月14日