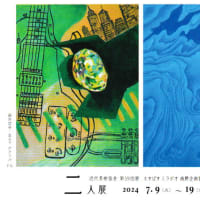2009年、田中利典師はご自身のブログ「山人のあるがままに」に、鬼の話を2回書かれている。初回は金峯山寺「節分会・鬼火の祭典」の「鬼も内」の話、2回目は前鬼山(下北山村)の小仲坊(おなかぼう)ご住職・五鬼助(ごきじょ)家の話(金峯山時報「蔵王清風」欄に掲載)である。
※写真は、吉野山の馬酔木(アシビ 2023.3.28 撮影)
どちらも興味深い話だし、互いに関連しているので、ここで2回分を一挙に公開させていただく。長くなるが、ぜひ最後までお読みいただきたい。2009.2.7 付と2009.9.10 付から、全文を抜粋する。
鬼の調伏
今年も無事、金峯山寺の節分会・鬼火の祭典を終了した。今年は管長猊下(五條順教師)が休養中でご不在のため、例年になく本山内は淋しい行事催行となったが、それでも平日にもかかわらずたくさんの参詣者で境内は大いに賑わった。
本山の節分会の特徴は「鬼も内」と唱える鬼の調伏式である。なぜ金峯山寺では鬼も内なのか…。ご存じのようにこれは開祖役行者が鬼を折伏し弟子としたという故事によって執り行われているが、その故事を以下詳しく述べてみる。
役行者に付き従う者として、前鬼後鬼(ぜんき・ごき)の二侍者は良く知られるところである。この二鬼が開祖の弟子となった説話は、開祖奇瑞(きずい)の伝承の中でも興味深いものの一つであり、特に有名な説話は役公徴業録(えんこうちょうごうろく)や役君形生記(えんくんぎょうしょうき)など江戸期に成立した役行者伝記に伝わる話…。
行者が生駒山の断髪山に登られた時(徴業録には行者21歳とある)、山中に赤眼、黄口という夫婦の鬼が住んでいて、それに鬼一、鬼次、鬼助、鬼虎、鬼彦と名付ける五子があった。この鬼が付近の人の子を捕らえて食うので、人々は困っていた。行者は山中に入って、二鬼の最愛の子である鬼彦なるものを捕らえて鉄鉢の内に匿された。
二鬼は顔色を変えて驚き四方を捜し求めたが更に見えない。遂に行者の所へ到って愛児の行方を尋ねた。その時行者が言われるのに「汝らと雖(いえど)もわが子を愛してその行方を求めるではないか。然るに何故に人の子を捕らえて食らうのか」。二鬼曰く「我ら初めは禽獣を捕らえて食うていたが、禽獣尽きて無いので終に人の子をとって食らうのである」と。
行者更に教戒して云うに「汝らよ、不動明王は空中にいまして、火焔赫然(かえんかくぜん)として、眼は電の如く声は雷の如く、金剛の利剣を提げ、三昧の索を持って常に悪魔を降伏されるのである。汝らももし改めなかったならば、かの明王の怒りに遇いて必ずや後悔するであろう」と。
二鬼大いに恐れ驚き行者に許しを請うたので、行者は二鬼に不動経の見我身者発菩提心以下の偈(げ)を授けて誦せしめ、教訓を垂れ随身とせられた。彼らは逐に悪心を転じて善心となり、深く行者に帰伏し、果実を集め水を汲み、薪を拾って食をなし、行者の命に従い山野開拓の為に尽くしたという。
橋田壽賀子の「ワタオニ」ではないが、今や世間は鬼ばかりである。我が子を殺す鬼、親を殺す鬼。無差別に人を殺す鬼。この国を平気でアメリカや中国に売り渡す鬼。赤眼・黄口も叶わないような鬼以下の人間ばかりである…。蔵王堂で暴れ狂う鬼が「鬼も内」のかけ声によって豆を撒かれ、平伏し改心する鬼の姿を見て、今こそ、役行者の調伏力が希求されていると、思うばかりの今年の節分会であった。
鬼
恒例の今月の早出しです。来月号の当山時報(金峯山時報「蔵王清風」欄)に書いた文章です。30分ほどで書いた走り書きなので、あいかわらず杜撰ですが、まあ、ご笑覧にあずかれれば幸いです。
****************
大峯には鬼がいた。一千年をこえて鬼たちは大峯の山中深く住み、その末裔が今も我々大峯行者の手助けをしてくれている。…前鬼山小仲坊(おなかぼう)の住職五鬼助(ごきじょ)家の話である。
鬼は役行者に付き従った夫婦の末裔という。ご存じの、生駒山中で役行者に折伏され弟子となった前鬼後鬼の子孫である。現当代さんは第61世。日本の家系では天皇家が圧倒的に古いが、61世となると、日本でも指折りの由緒正しい名家である。なにが凄いかというと、この鬼の子孫たちは1300年前の役行者の遺言によって大峯の山奥に住み着き、未だにその言いつけを守り続けているというのだ。
役行者は大宝元年6月7日、箕面天上ヶ岳より、母を鉄鉢に乗せ、唐の国へ昇天されたと伝えられている。このとき、侍者としてずっとそばに寄り添った前鬼後鬼は、自分たちも是非一緒にお供したいと申し出る。しかし役行者はそれを退け「おまえたちは大峯山中に住んで、これ以後、大峯行者の世話をしなさい」と遺言されたというのだ。
この言葉に従って、鬼の夫婦は前鬼山に移り住んだ。夫婦には5人の子どもがいたが、やがてそれぞれに五鬼継、五鬼熊、五鬼上、五鬼助、五鬼童の5家となって、行者坊、森本坊、中之坊、小仲坊、不動坊の5坊を営み、大峯修行者が集う宿坊として明治初期まで続いたのであった。
修験道は明治の神仏分離・修験道廃止令によって解体される時期があり、前鬼山の5坊も衰退の一途を遂げるが、今もなお、小仲坊一宇だけは存続し、われわれ大峯行者を迎え入れてくれている。ここがなければ我々の奥駈修行はいよいよ難儀をすることになるだろう。
この8月にも奥駈修行で小仲坊にお世話になった。鬼の末裔というが、この鬼はいわゆる「邪鬼」ではなく、山中生活を主とした山人たちのことだろう。
当代さんはとても気の良いご夫婦で行くたびに私は歓待を受け、親しくしていただいている。まさに今に生きる役行者伝説を体現するご夫婦なのだ。鬼というより、仏の末裔かと思うような優しい容貌である。今年もその柔和で元気なお顔を拝し、役行者とご夫婦に深く感謝する前鬼山の夜であった。
※写真は、吉野山の馬酔木(アシビ 2023.3.28 撮影)
どちらも興味深い話だし、互いに関連しているので、ここで2回分を一挙に公開させていただく。長くなるが、ぜひ最後までお読みいただきたい。2009.2.7 付と2009.9.10 付から、全文を抜粋する。
鬼の調伏
今年も無事、金峯山寺の節分会・鬼火の祭典を終了した。今年は管長猊下(五條順教師)が休養中でご不在のため、例年になく本山内は淋しい行事催行となったが、それでも平日にもかかわらずたくさんの参詣者で境内は大いに賑わった。
本山の節分会の特徴は「鬼も内」と唱える鬼の調伏式である。なぜ金峯山寺では鬼も内なのか…。ご存じのようにこれは開祖役行者が鬼を折伏し弟子としたという故事によって執り行われているが、その故事を以下詳しく述べてみる。
役行者に付き従う者として、前鬼後鬼(ぜんき・ごき)の二侍者は良く知られるところである。この二鬼が開祖の弟子となった説話は、開祖奇瑞(きずい)の伝承の中でも興味深いものの一つであり、特に有名な説話は役公徴業録(えんこうちょうごうろく)や役君形生記(えんくんぎょうしょうき)など江戸期に成立した役行者伝記に伝わる話…。
行者が生駒山の断髪山に登られた時(徴業録には行者21歳とある)、山中に赤眼、黄口という夫婦の鬼が住んでいて、それに鬼一、鬼次、鬼助、鬼虎、鬼彦と名付ける五子があった。この鬼が付近の人の子を捕らえて食うので、人々は困っていた。行者は山中に入って、二鬼の最愛の子である鬼彦なるものを捕らえて鉄鉢の内に匿された。
二鬼は顔色を変えて驚き四方を捜し求めたが更に見えない。遂に行者の所へ到って愛児の行方を尋ねた。その時行者が言われるのに「汝らと雖(いえど)もわが子を愛してその行方を求めるではないか。然るに何故に人の子を捕らえて食らうのか」。二鬼曰く「我ら初めは禽獣を捕らえて食うていたが、禽獣尽きて無いので終に人の子をとって食らうのである」と。
行者更に教戒して云うに「汝らよ、不動明王は空中にいまして、火焔赫然(かえんかくぜん)として、眼は電の如く声は雷の如く、金剛の利剣を提げ、三昧の索を持って常に悪魔を降伏されるのである。汝らももし改めなかったならば、かの明王の怒りに遇いて必ずや後悔するであろう」と。
二鬼大いに恐れ驚き行者に許しを請うたので、行者は二鬼に不動経の見我身者発菩提心以下の偈(げ)を授けて誦せしめ、教訓を垂れ随身とせられた。彼らは逐に悪心を転じて善心となり、深く行者に帰伏し、果実を集め水を汲み、薪を拾って食をなし、行者の命に従い山野開拓の為に尽くしたという。
橋田壽賀子の「ワタオニ」ではないが、今や世間は鬼ばかりである。我が子を殺す鬼、親を殺す鬼。無差別に人を殺す鬼。この国を平気でアメリカや中国に売り渡す鬼。赤眼・黄口も叶わないような鬼以下の人間ばかりである…。蔵王堂で暴れ狂う鬼が「鬼も内」のかけ声によって豆を撒かれ、平伏し改心する鬼の姿を見て、今こそ、役行者の調伏力が希求されていると、思うばかりの今年の節分会であった。
鬼
恒例の今月の早出しです。来月号の当山時報(金峯山時報「蔵王清風」欄)に書いた文章です。30分ほどで書いた走り書きなので、あいかわらず杜撰ですが、まあ、ご笑覧にあずかれれば幸いです。
****************
大峯には鬼がいた。一千年をこえて鬼たちは大峯の山中深く住み、その末裔が今も我々大峯行者の手助けをしてくれている。…前鬼山小仲坊(おなかぼう)の住職五鬼助(ごきじょ)家の話である。
鬼は役行者に付き従った夫婦の末裔という。ご存じの、生駒山中で役行者に折伏され弟子となった前鬼後鬼の子孫である。現当代さんは第61世。日本の家系では天皇家が圧倒的に古いが、61世となると、日本でも指折りの由緒正しい名家である。なにが凄いかというと、この鬼の子孫たちは1300年前の役行者の遺言によって大峯の山奥に住み着き、未だにその言いつけを守り続けているというのだ。
役行者は大宝元年6月7日、箕面天上ヶ岳より、母を鉄鉢に乗せ、唐の国へ昇天されたと伝えられている。このとき、侍者としてずっとそばに寄り添った前鬼後鬼は、自分たちも是非一緒にお供したいと申し出る。しかし役行者はそれを退け「おまえたちは大峯山中に住んで、これ以後、大峯行者の世話をしなさい」と遺言されたというのだ。
この言葉に従って、鬼の夫婦は前鬼山に移り住んだ。夫婦には5人の子どもがいたが、やがてそれぞれに五鬼継、五鬼熊、五鬼上、五鬼助、五鬼童の5家となって、行者坊、森本坊、中之坊、小仲坊、不動坊の5坊を営み、大峯修行者が集う宿坊として明治初期まで続いたのであった。
修験道は明治の神仏分離・修験道廃止令によって解体される時期があり、前鬼山の5坊も衰退の一途を遂げるが、今もなお、小仲坊一宇だけは存続し、われわれ大峯行者を迎え入れてくれている。ここがなければ我々の奥駈修行はいよいよ難儀をすることになるだろう。
この8月にも奥駈修行で小仲坊にお世話になった。鬼の末裔というが、この鬼はいわゆる「邪鬼」ではなく、山中生活を主とした山人たちのことだろう。
当代さんはとても気の良いご夫婦で行くたびに私は歓待を受け、親しくしていただいている。まさに今に生きる役行者伝説を体現するご夫婦なのだ。鬼というより、仏の末裔かと思うような優しい容貌である。今年もその柔和で元気なお顔を拝し、役行者とご夫婦に深く感謝する前鬼山の夜であった。