
大中公園周辺(高田川畔)に桜を見て詠める
高田川に絶えて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし
(高田川に一切桜というものがなかったら、春をのどかな気持ちで過ごせるだろうに)
大和高田市の高田川沿い、大中公園周辺に名所「高田千本桜」がある。「奈良県観光情報」(大和路アーカイブ)によると《昭和23年(1948年)、市制施行時に名倉市長が進駐軍に寄付を頼んで植樹した1200本の桜が高田川沿い大中公園1kmを埋める。夕闇とともにぼんぼりが灯り、ほのかなあかりに美しく浮かぶ夜桜に、見物の人の波は絶えることがありません》。

一昨日(4/9)、大和高田市へ出張した帰りに高田川の桜を見物した。幸運なことに、桜はこの日から満開であった。ソメイヨシノばかりではなく、ヤマザクラなど、白やピンクの花びらが川を蔽っていた。これだけ咲くと、もう花に酔いそうである。春の心はのどけからまし…。
戦後植えられた桜だから、という理由からか『奈良まほろばソムリエ検定 公式テキストブック』(山と渓谷社)に載っていないのは、かえすがえすも残念である。「進駐軍に寄付を頼んで植樹」という事実も、案外知られていない。「千本桜の秘話」(大和高田市の公式HP)に、名倉仙蔵氏(第2・4・5・6代 大和高田市長)の著書『人間をめぐる断想』からの引用文が載っていたので紹介する。

「市制施行」(昭和23年1月)を記念して、その年の冬に、延長2キロメートルの堤防にサクラ並木をつくる計画を立てた。サクラ苗木は、市内の町内会から、数本ずつの寄贈をうけることになってその数は千本を少し越えた。文字どおり市民のサクラ、ということになる。サクラ苗木は、吉野山保勝会へ斡旋を依頼して昭和23年12月に植樹することになった。このまま植樹ができたらなんの問題もなかったのだが、ひとつの挫折があった。河川の堤防にサクラを植える交渉を、長いあいだかかって県とやってきたがどうしても許可できないという。

従来は河川の堤防にサクラを植樹すると堤防を弱くするといわれてきたが、サクラの根の張り方からみて、植樹の位置、間隔が適当であればむしろ堤防を強くする、この論文を、知事と土木部長に提示して強く許可を求めたが、許可できないという。奈良軍政府司令官ヘンダーソン大佐に話してサクラの植樹に協力を求め。将校食堂でヘンダーソン大佐と私の趣旨説明が終わると、軍曹がボール箱でつくった寄付箱を持って食卓をまわってくれた。当時、サクラ苗木の価格は7年生、8年生、といったもので80円だった。


まず、ヘンダーソン大佐が自分と夫人の名前を書いて6本を寄贈してくれた。将校連中は、つぎつぎに自分と夫人や子どもの名前を書いて軍曹に渡してくれた。30分ほどで250本の寄贈をうけることになった。将校とその夫人、子どもの名前を書いた小さな名札をつくって苗木につけ、一挙に、250本を堤防の安全な位置へ植樹した。…250本の苗木に右へならって千本サクラの苗木を植えてしまった。枯れたもの、折れたもの、の補植に100本程度根気よくつづけてきた。…高田川畔は、いま(昭和46年)、ヤマザクラ、ヒガンザクラ、ソメイヨシノ、サトザクラなどの多くの品種が集められて、声のない陽春の音楽をたたえているように思える。

毎年3月にはいると、「サクラの国のサクラの名所」、というポスターの中ヅリが近鉄電車の電車内に出る。吉野山の美しいみごとなサクラのカラー写真がポスターの半分を占め、あとの半分には、沿線のサクラの名所が書き出されるのが恒例になっている。ここ数年、さまざまな思いを込めて、このポスターに、興味とも注意ともつかないような私なりの関心をもってきた。
「高田川畔のサクラ」が、いつになったら「サクラの国のサクラの名所」にのるのだろうか。そんな期待感をもっていた。「サクラの国のサクラの名所」のポスターに、本年(昭和46)になって初めて「高田川畔のサクラ」が載せられるようになった。

「大中公園で花見をしよう」と、現地でOH先輩(大和高田市出身・在住)と待ち合わせた。合流したあと先輩に連れられて、大中池の東側(大中公園内)にある「静御前記念碑」を訪ねた。Wikipedia「大和高田市」によると《静御前は源義経との別れの後、母・礒野禅尼の里である大和高田市礒野(いその)に身を寄せたと伝えられる。確たる文献証拠はないが、礒野の地には静御前の墓と伝える塚が残る。(中略) 付近の磐園(いわその)は「いその」の古名と考えられ、石園、礒野も同じ名に由来していると考えられる》とある。

碑の表には「しずやしず 賤(しづ)のおだまきくりかえし 昔を今になすよしもがな」という静御前の歌が彫られていた。「倭文(しづ=織物の名)や倭文、倭文の織物の麻糸をつむいで巻き取った苧環(おだまき=糸玉)から糸を繰り出すように繰り返しながら(義経様が「静や、静」と呼んでくれた)昔を今に戻す方法があればなあ」という意味だ。「賤(しづ)」は身分の低い人のことで、麻糸紡ぎを仕事にしているような人。「静御前」をかけている。

裏面には《静御前は大和高田の宿の長者磯禅師の娘といわれる。京に遊んで歌舞の名手となり、烏帽子に水干鞘巻を帯びたる麗姿は都人の称賛を浴びた。かくて源義経と結ばれたが頼朝に追われ吉野山に義経と別れ捕らえられた。鎌倉鶴岡八幡宮の社頭、頼朝政子の前に夫を想う曲を舞い、後許されて大和に帰り母子とも磯野の里におわるという。ここに静御前の遺跡を示す村絵図により記念碑を建つ 昭和五十三年七月 高田川を美しくする会 堀江彦三郎撰 玉泉米田壽夫書》とある。
それにしても、よくこれだけの桜を植えられたものである。「補植に100本程度根気よくつづけてきた」とあるとおり、陰には相当の努力が払われてきたのだ。桜が咲くのはほんの5日程度だが、桜守(さくらもり)・佐野藤右衛門氏は「残りの360日が桜にとってはたいせつなんです」という。地元・大和高田市民の支えがあって、1200本もの桜が守られてきたのである。高田川の桜がなければ、大和高田市のイメージというものはよほど違ったものになっただろうし、高田川はこんなにきれいに保たれることもなかったことだろう。何しろ大和高田市は、奈良県で最も人口密度の高い市町村なのである。
今日は朝からあいにくの雨であるが、これですべて散ってしまうことはないだろう。ぜひいちど足をお運びいただきたい。
高田川に絶えて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし
(高田川に一切桜というものがなかったら、春をのどかな気持ちで過ごせるだろうに)
大和高田市の高田川沿い、大中公園周辺に名所「高田千本桜」がある。「奈良県観光情報」(大和路アーカイブ)によると《昭和23年(1948年)、市制施行時に名倉市長が進駐軍に寄付を頼んで植樹した1200本の桜が高田川沿い大中公園1kmを埋める。夕闇とともにぼんぼりが灯り、ほのかなあかりに美しく浮かぶ夜桜に、見物の人の波は絶えることがありません》。

一昨日(4/9)、大和高田市へ出張した帰りに高田川の桜を見物した。幸運なことに、桜はこの日から満開であった。ソメイヨシノばかりではなく、ヤマザクラなど、白やピンクの花びらが川を蔽っていた。これだけ咲くと、もう花に酔いそうである。春の心はのどけからまし…。
戦後植えられた桜だから、という理由からか『奈良まほろばソムリエ検定 公式テキストブック』(山と渓谷社)に載っていないのは、かえすがえすも残念である。「進駐軍に寄付を頼んで植樹」という事実も、案外知られていない。「千本桜の秘話」(大和高田市の公式HP)に、名倉仙蔵氏(第2・4・5・6代 大和高田市長)の著書『人間をめぐる断想』からの引用文が載っていたので紹介する。

「市制施行」(昭和23年1月)を記念して、その年の冬に、延長2キロメートルの堤防にサクラ並木をつくる計画を立てた。サクラ苗木は、市内の町内会から、数本ずつの寄贈をうけることになってその数は千本を少し越えた。文字どおり市民のサクラ、ということになる。サクラ苗木は、吉野山保勝会へ斡旋を依頼して昭和23年12月に植樹することになった。このまま植樹ができたらなんの問題もなかったのだが、ひとつの挫折があった。河川の堤防にサクラを植える交渉を、長いあいだかかって県とやってきたがどうしても許可できないという。

従来は河川の堤防にサクラを植樹すると堤防を弱くするといわれてきたが、サクラの根の張り方からみて、植樹の位置、間隔が適当であればむしろ堤防を強くする、この論文を、知事と土木部長に提示して強く許可を求めたが、許可できないという。奈良軍政府司令官ヘンダーソン大佐に話してサクラの植樹に協力を求め。将校食堂でヘンダーソン大佐と私の趣旨説明が終わると、軍曹がボール箱でつくった寄付箱を持って食卓をまわってくれた。当時、サクラ苗木の価格は7年生、8年生、といったもので80円だった。


まず、ヘンダーソン大佐が自分と夫人の名前を書いて6本を寄贈してくれた。将校連中は、つぎつぎに自分と夫人や子どもの名前を書いて軍曹に渡してくれた。30分ほどで250本の寄贈をうけることになった。将校とその夫人、子どもの名前を書いた小さな名札をつくって苗木につけ、一挙に、250本を堤防の安全な位置へ植樹した。…250本の苗木に右へならって千本サクラの苗木を植えてしまった。枯れたもの、折れたもの、の補植に100本程度根気よくつづけてきた。…高田川畔は、いま(昭和46年)、ヤマザクラ、ヒガンザクラ、ソメイヨシノ、サトザクラなどの多くの品種が集められて、声のない陽春の音楽をたたえているように思える。

毎年3月にはいると、「サクラの国のサクラの名所」、というポスターの中ヅリが近鉄電車の電車内に出る。吉野山の美しいみごとなサクラのカラー写真がポスターの半分を占め、あとの半分には、沿線のサクラの名所が書き出されるのが恒例になっている。ここ数年、さまざまな思いを込めて、このポスターに、興味とも注意ともつかないような私なりの関心をもってきた。
「高田川畔のサクラ」が、いつになったら「サクラの国のサクラの名所」にのるのだろうか。そんな期待感をもっていた。「サクラの国のサクラの名所」のポスターに、本年(昭和46)になって初めて「高田川畔のサクラ」が載せられるようになった。

「大中公園で花見をしよう」と、現地でOH先輩(大和高田市出身・在住)と待ち合わせた。合流したあと先輩に連れられて、大中池の東側(大中公園内)にある「静御前記念碑」を訪ねた。Wikipedia「大和高田市」によると《静御前は源義経との別れの後、母・礒野禅尼の里である大和高田市礒野(いその)に身を寄せたと伝えられる。確たる文献証拠はないが、礒野の地には静御前の墓と伝える塚が残る。(中略) 付近の磐園(いわその)は「いその」の古名と考えられ、石園、礒野も同じ名に由来していると考えられる》とある。

碑の表には「しずやしず 賤(しづ)のおだまきくりかえし 昔を今になすよしもがな」という静御前の歌が彫られていた。「倭文(しづ=織物の名)や倭文、倭文の織物の麻糸をつむいで巻き取った苧環(おだまき=糸玉)から糸を繰り出すように繰り返しながら(義経様が「静や、静」と呼んでくれた)昔を今に戻す方法があればなあ」という意味だ。「賤(しづ)」は身分の低い人のことで、麻糸紡ぎを仕事にしているような人。「静御前」をかけている。

裏面には《静御前は大和高田の宿の長者磯禅師の娘といわれる。京に遊んで歌舞の名手となり、烏帽子に水干鞘巻を帯びたる麗姿は都人の称賛を浴びた。かくて源義経と結ばれたが頼朝に追われ吉野山に義経と別れ捕らえられた。鎌倉鶴岡八幡宮の社頭、頼朝政子の前に夫を想う曲を舞い、後許されて大和に帰り母子とも磯野の里におわるという。ここに静御前の遺跡を示す村絵図により記念碑を建つ 昭和五十三年七月 高田川を美しくする会 堀江彦三郎撰 玉泉米田壽夫書》とある。
それにしても、よくこれだけの桜を植えられたものである。「補植に100本程度根気よくつづけてきた」とあるとおり、陰には相当の努力が払われてきたのだ。桜が咲くのはほんの5日程度だが、桜守(さくらもり)・佐野藤右衛門氏は「残りの360日が桜にとってはたいせつなんです」という。地元・大和高田市民の支えがあって、1200本もの桜が守られてきたのである。高田川の桜がなければ、大和高田市のイメージというものはよほど違ったものになっただろうし、高田川はこんなにきれいに保たれることもなかったことだろう。何しろ大和高田市は、奈良県で最も人口密度の高い市町村なのである。
今日は朝からあいにくの雨であるが、これですべて散ってしまうことはないだろう。ぜひいちど足をお運びいただきたい。










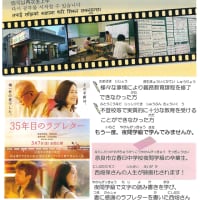
















> 市民も殆ど知らない?逸話も含め紹介頂き深謝
> です。おかげで郷土への愛着がましてきました。
大和高田市には、たくさんの見どころがありますね。あの日は美味しいお店も発見しました。高田川は、地域を愛する市民の力で、美観が保たれています。
> ヘンダーソン大佐のなされ様は、勧進帳の富樫奉行を思い起こします。
進駐軍も、なかなかやりますね。それにしても、名倉元市長の慧眼には脱帽です。
花の命は儚いですが、これからの新緑も
素敵です。
コメントのおいしい店も気になります(^^♪
お勤めの支店の近くですかね~
> 花の命は儚いですが、これからの新緑も素敵です。
なるほど、これはいいですね。吉野山も、桜が散ったあとのムンムンする青葉若葉が良いですし。
> コメントのおいしい店も気になります お勤めの支店の近くですかね~
JR高田駅近くのビル1階にある「串活 薩摩」というお店です。串カツ以外の居酒屋メニューも、とても美味しいです。いつか、当ブログでも紹介したいと思っています。