★ラルフ124C 41+
1911年、ガーンズバックは「モダンエレクトリック」誌に、未来を舞台にした技術冒険物語の執筆を開始した。最初は誌面の穴埋めのつもりだったが、読者の熱心な要望に応えて書き継がれ、完結までに全12回に及ぶ長期連載となった。
作中には、科学好きの読者をわくわくさせる未来的な発明が数々紹介されていた。たとえば蛍光照明、テレビ、ラジオ、プラスチック、野球の夜間ゲーム、立体映写機、ジュークボックス、液体肥料、自動販売機、睡眠学習、無線電力送信、ガラス繊維、ナイロン等(?)……。蛍光照明やラジオはいうにおよばず、その多くが尊敬するテスラの発明やアイデアに触発されたものだった。
作品は最終的に「ラルフ124C 41+」という題名で出版され、科学冒険小説の代表作のひとつとなった。
ガーンズバックは、読者の反響によって「ラルフ─」のような作品に需要があることに気付かされた。そこで、その手の作品を積極的に雑誌に掲載するようになった。この傾向は、彼が次に創刊した雑誌によってさらに顕著になる。
アマチュア無線家の数は急増し、無線のマーケットはさらに拡大していた。それを見越して、ガーンズバックは1913年、二番目の雑誌となる「エレクトリカル・エクスペリメンター」誌(「モダーン・エレクトリック」誌を改題)を発刊した。
この雑誌でガーンズバックはコラムニスト、エッセイスト、作家として、未来冒険物語「ミュンヒハウゼン男爵の新しい科学的冒険」を含む多くの文章を発表し、未来技術がもたらす社会的インパクトについて探求した。
さらにA・A・メリットやレイ・カミングスといった人気作家の科学冒険小説で誌面を飾ったほか、ウェルズやヴェルヌの復刻作品も登場させた。後者はもっぱら著作権料節約のためだった。
ガーンズバックはこの雑誌を通して、「ラルフ─」のような作品にふさわしい名称を採用しようとした。
ウェルズに代表される空想的な科学小説は従来、「サイエンティフィック・ロマンス」と呼ばれてきた。それらは社会批判・文明批判を旨とし、描かれる未来も悲観的で暗いものが多かった。
これに対して、彼が求めたのはジュール・ヴェルヌ風の明るい未来小説だった。
二〇世紀初頭の西欧世界は、科学技術が開く新世紀への期待に満ちあふれていた。電力システム、電話、電信、無線、鉄道、汽船、自動車、航空機、合成化学、アルミニウム精錬。人々は次々と生まれる新技術・新発明に熱狂し、それらが普及した未来の姿を熱烈に知りたがった。こうした期待に沿って楽観的な未来社会を描くのが彼が求める新しい科学小説だった。それだけに従来の用語は捨てられなければならなかったのである。
考えた末、彼が提案したのは「サイエンティフィクションscienti-fiction」という名称だった。
「サイエンティフィクション」とはなにか?
彼の定義によれば、それは「ジュール・ヴェルヌ、H・G・ウェルズ、エドガー・アラン・ポーのタイプの物語……科学的事実と予言的ヴィジョンをないまぜにした魅力あるロマンス」である。
これだけでは旧来の科学ロマンスと大差ないように思えるが、注意すべきはここで彼が強調したかったのは後半部だということである。彼の関心は科学的事実と予見技術社会の未来像そのものにあり、前半部に挙げたヴェルヌ、ウェルズ、ポーの三人彼らの小説の文学性や思想性にほとんど興味がなかった。言い換えれば、彼の「サイエンティフィクション」は、科学技術に特化した通俗小説だった。これは文学的洗練などに興味のない彼の読者の嗜好にも合致していた。
この新語づくりにあたって大きな刺激を与えたのはやはりテスラだった。彼の未来的な発明やアイデア、ビジョンは、まさにサイエンティフィクションそのものだったからである。
ガーンズバックはその「生きたサイエンティフィクション」に新しい文学のイメージを重ねようとして、テスラに関する情報ならなんでも載せようとした。1917年8月号には、「電気学と戦争に関するテスラの見解」と題するインタビュー記事を掲載、その中で軍事レーダーに関するもっとも早い予言を語らせている。
原稿の執筆も依頼、これに応じて、テスラは新発明やそれに基づく予言的ビジョンを披瀝していった。とりわけ1919年の活躍はめざましかった。
2月号には「有名な科学的幻想」、4月号と6月号には「月の回転」、5月号には「無線の真実」と立て続けに論考を発表、さらに自伝執筆の求めに応じて、同年2月号からは、唯一の自伝となる『わが発明』の不定期連載を開始した。誌面にはのちに高名なSFイラストレーターとなるフランク・R・ポールによる無線送電塔、無線動力の飛翔体などのイラストが華々しく添えられていた。
世紀の予言者の誌面登場は、雑誌の権威を高めるとともに、無線の通販という新興ビジネスのイメージづくりにも貢献した。まさに一石二鳥だった。一方、テスラにとっても、ガーンズバックという賛美者の出現はありがたかった。
無線送電の挫折以来、投資家の信頼を大きく損ねた発明家は、この頃、慢性的な資金不足に悩まされていた。再起の思いは強かったが、予備的な実験すらままならない状況が続いていた。そこへきて、1917年には完成目前で工事が中断していた無線送電塔が、新しい所有者の手で破壊されるという憂き目にもあった。
それだけに、専門的意見から未来のビジョンまで、自由に意見を発表できるメディアの存在は貴重だったのである。
★サイエンス・フィクションの誕生
自作の自雑誌掲載を機に、ガーンズバックのサイエンティフィクションへの思いはますます募っていった。その思いは、一九二三年の「サイエンス・アンド・インベンション」誌の”サイエンティフィクション特集”につながった。特集の反響は上々だったので、勢いに乗って今度は「サイエンティフィクション」というタイトルの新雑誌創刊を読者に提案した。しかしこちらの反応は余り芳しくなかった。
そこでいったん仕切り直しをして構想を練り直すことにし、1926年、まったく別のタイトルで新雑誌創刊に踏み切った。「アメージング・ストーリィズ」。アメリカ最初の商業SF誌の誕生である。
アメージング・ストーリイズは順調に部数を伸ばし、10年来採用してきたサイエンティフィクションという用語もようやく定着しかけた。
だが天性のアイデアマンはそれに飽きたらず、新しい呼び名を次々に読者に提案していく。そして最終的に「サイエンス・フィクション」という名称で落ち着いたのである。もっとも何と呼ぼうと、彼が意図していた技術主体の未来小説だったことに変わりはなかったが。
「アメージング・ストーリィズ」誌創刊時、テスラはすでに七〇歳になっていた。ガーンズバックがSFに足場を移してからも、ふたりの親密な関係は続いた。そしてテスラの発明的想像力は、SF的想像力の源泉であり続けた。
ガーンズバックにとってテスラはまたとない支援者だったが、逆に、テスラにとって彼との関わりはプラスばかりではなかった。
エジソンやテスラを生んだ発明の英雄時代は19世紀末に終焉を迎える。20世紀、独立独歩の発明家に代わって台頭したのは大学や研究所に所属する高学歴の専門家たちだった。それによりかつて世界を震撼させた発明家たちの栄光も次第に色褪せていったのである。
そんな中、彼らに新たな活躍の場を用意したのがサイエンス・フィクションだった。科学的想像力を重視するこの新興の文芸ジャンルの中に、彼らは天才的でアウトローな科学者──「マッドサイエンティスト」として再生したのである。
世界を一変させる大発明を成し、時に世界征服すら夢見る異端の天才科学者。彼らの発明を軸に、次々登場する狡猾で獰猛な宇宙怪物(BEM)、必ず窮地におちいる薄着の金髪美女、それを救う力強い正義のヒーローなどが、大宇宙せましと駆けめぐる。これがスペース・オペラと呼ばれる初期サイエンス・フィクションの定番だった。
この場合、主役のヒーローやお相手の美女は、たいてい類型的で無個性な大根役者と決まっていた。それに比べて、宇宙怪物やマッドサイエンティストなどの脇役たちは、個性がきわだつ演技派だった。中でも人間的な弱さを抱えたマッドサイエンティストは、ともすれば平板になりがちな物語に深い陰影を与える役割を果たした。
拙著『逆立ちしたフランケンシュタイン』でも指摘したように、彼らのモデルは中世の魔術師や錬金術師であり、直接には19世紀の発明家たちだった。とりわけテスラの天才性、カリスマ性、異端性、悲劇性などは最高のモデルにふさわしかっただろう。
しかし、こうしたイメージの浸透はテスラにとって痛しかゆしだった。通俗SFにおいては、マッドサイエンティストのイメージも通俗化せざるをえない。それによってテスラの発明もまた、殺人光線や超破壊兵器に特化され、俗化されていったからである。このことが後世、テスラの過小評価を招く一因になったことは否めない。
まさかガーンズバックも、おのれが心血を注いだメディアが「自分の神」を貶る結果を招くとは思いもよらなかっただろう。
とはいえそれは結果論であり、テスラはガーンズバックの存在に大いに慰められたし、ガーンズバックのテスラに対する尊敬も終生変わらなかった。
一九四三年に発明家が亡くなると、ガーンズバックは遺骸を受け取った葬儀屋にデスマスクの制作を委託した。完成したデスマスクは、「プラクチカル・エレクトロニクス」誌に発表され、その後、ガーンズバックの事務所内に保存された。
そして現在はベオグラードのテスラ博物館の収蔵品となっている。
★ガーンズバックの贈り物
未来を鏡とする現代批判を旨としてきた「科学ロマンス」は、未来の国アメリカで、未来の技術風景そのものを描く「サイエンス・フィクション」へと変貌を遂げた。それを牽引したのは、移民でありながら、きわめてアメリカ的な個性をもった一人の編集者だった。
しかし彼のアイデンティティは1930年代末には早くも崩壊してしまう。それを促したのは、MITで学んだインテリ編集者、J・W・キャンベルだった。
文学指向の強いこの敏腕編集者のもとで、サイエンス・フィクションは、ガーンズバック的な技術楽観主義や通俗性を脱して、洗練された〈文学〉へと変貌していった。それはたしかにSFの進化ではあったが、一面では科学ロマンスへの回帰でもあっただろう。
その後もサイエンス・フィクションは、J・バラードの「スペキュレイティヴ・フィクション」、ウィリアム・ギブスンやブルース・スターリングの「サイバーパンク」、「スティームパンク」などの衝撃を受けとめ、変貌を重ねながら、より重層的な文学ジャンルへと成長を遂げていった。
興味深いことにギブスンは1980年代に、「ガーンズバック連続体」というメタフィクション的なSF短編を著して、ガーンズバックへの多大な負債を認めた。
むろん、サイバーパンクの旗手は、現代SFの内実が名付け親の定義から遠く隔たったことは充分に認識していた。その上で、彼の技術小説が持つ荒々しい想像力や廃墟のイメージ、人工性、神秘性などに、ハイテク時代の文学の可能性を見ようとしたのだった。
反科学・反技術主義的な風潮に支配されていた1970年代が終わり、80年代にはコンピュータや新素材などの科学技術に再び期待と関心が集まった。その技術の行く末を見据えて、コンピュータを介して人と機械が融合する先端的で、異端的なマッドサイエンスを扱ったのがサイバーパンクの小説群だった。これとニコラ・テスラという真正マッドサイエンティストの同時代的復権は偶然ではないだろう。
挫折した発明家ガーンズバックは、テスラを通して発明家の時代の終わりをさとった。だからこそ文学の発明を通して神々の時代の再興を夢見たのではないだろうか。私には「サイエンスティフィクション」がガーンズバックからテスラへの私的な贈り物だったように思えてならない。
〈参考文献〉
*Tesla, Nikola, My Inventions, Hart Brothers, 1982.
*Tesla,Nikola, Famous Scientific Illusions, Electrical Experimenter, February 1919
*Tesla,Nikola, The Moon's Lotation, Electrical Experimenter, April,June 1919
*Tesla,Nikola, The True Wireless, Electrical Experimenter, May 1919
1911年、ガーンズバックは「モダンエレクトリック」誌に、未来を舞台にした技術冒険物語の執筆を開始した。最初は誌面の穴埋めのつもりだったが、読者の熱心な要望に応えて書き継がれ、完結までに全12回に及ぶ長期連載となった。
作中には、科学好きの読者をわくわくさせる未来的な発明が数々紹介されていた。たとえば蛍光照明、テレビ、ラジオ、プラスチック、野球の夜間ゲーム、立体映写機、ジュークボックス、液体肥料、自動販売機、睡眠学習、無線電力送信、ガラス繊維、ナイロン等(?)……。蛍光照明やラジオはいうにおよばず、その多くが尊敬するテスラの発明やアイデアに触発されたものだった。
作品は最終的に「ラルフ124C 41+」という題名で出版され、科学冒険小説の代表作のひとつとなった。
ガーンズバックは、読者の反響によって「ラルフ─」のような作品に需要があることに気付かされた。そこで、その手の作品を積極的に雑誌に掲載するようになった。この傾向は、彼が次に創刊した雑誌によってさらに顕著になる。
アマチュア無線家の数は急増し、無線のマーケットはさらに拡大していた。それを見越して、ガーンズバックは1913年、二番目の雑誌となる「エレクトリカル・エクスペリメンター」誌(「モダーン・エレクトリック」誌を改題)を発刊した。
この雑誌でガーンズバックはコラムニスト、エッセイスト、作家として、未来冒険物語「ミュンヒハウゼン男爵の新しい科学的冒険」を含む多くの文章を発表し、未来技術がもたらす社会的インパクトについて探求した。
さらにA・A・メリットやレイ・カミングスといった人気作家の科学冒険小説で誌面を飾ったほか、ウェルズやヴェルヌの復刻作品も登場させた。後者はもっぱら著作権料節約のためだった。
ガーンズバックはこの雑誌を通して、「ラルフ─」のような作品にふさわしい名称を採用しようとした。
ウェルズに代表される空想的な科学小説は従来、「サイエンティフィック・ロマンス」と呼ばれてきた。それらは社会批判・文明批判を旨とし、描かれる未来も悲観的で暗いものが多かった。
これに対して、彼が求めたのはジュール・ヴェルヌ風の明るい未来小説だった。
二〇世紀初頭の西欧世界は、科学技術が開く新世紀への期待に満ちあふれていた。電力システム、電話、電信、無線、鉄道、汽船、自動車、航空機、合成化学、アルミニウム精錬。人々は次々と生まれる新技術・新発明に熱狂し、それらが普及した未来の姿を熱烈に知りたがった。こうした期待に沿って楽観的な未来社会を描くのが彼が求める新しい科学小説だった。それだけに従来の用語は捨てられなければならなかったのである。
考えた末、彼が提案したのは「サイエンティフィクションscienti-fiction」という名称だった。
「サイエンティフィクション」とはなにか?
彼の定義によれば、それは「ジュール・ヴェルヌ、H・G・ウェルズ、エドガー・アラン・ポーのタイプの物語……科学的事実と予言的ヴィジョンをないまぜにした魅力あるロマンス」である。
これだけでは旧来の科学ロマンスと大差ないように思えるが、注意すべきはここで彼が強調したかったのは後半部だということである。彼の関心は科学的事実と予見技術社会の未来像そのものにあり、前半部に挙げたヴェルヌ、ウェルズ、ポーの三人彼らの小説の文学性や思想性にほとんど興味がなかった。言い換えれば、彼の「サイエンティフィクション」は、科学技術に特化した通俗小説だった。これは文学的洗練などに興味のない彼の読者の嗜好にも合致していた。
この新語づくりにあたって大きな刺激を与えたのはやはりテスラだった。彼の未来的な発明やアイデア、ビジョンは、まさにサイエンティフィクションそのものだったからである。
ガーンズバックはその「生きたサイエンティフィクション」に新しい文学のイメージを重ねようとして、テスラに関する情報ならなんでも載せようとした。1917年8月号には、「電気学と戦争に関するテスラの見解」と題するインタビュー記事を掲載、その中で軍事レーダーに関するもっとも早い予言を語らせている。
原稿の執筆も依頼、これに応じて、テスラは新発明やそれに基づく予言的ビジョンを披瀝していった。とりわけ1919年の活躍はめざましかった。
2月号には「有名な科学的幻想」、4月号と6月号には「月の回転」、5月号には「無線の真実」と立て続けに論考を発表、さらに自伝執筆の求めに応じて、同年2月号からは、唯一の自伝となる『わが発明』の不定期連載を開始した。誌面にはのちに高名なSFイラストレーターとなるフランク・R・ポールによる無線送電塔、無線動力の飛翔体などのイラストが華々しく添えられていた。
世紀の予言者の誌面登場は、雑誌の権威を高めるとともに、無線の通販という新興ビジネスのイメージづくりにも貢献した。まさに一石二鳥だった。一方、テスラにとっても、ガーンズバックという賛美者の出現はありがたかった。
無線送電の挫折以来、投資家の信頼を大きく損ねた発明家は、この頃、慢性的な資金不足に悩まされていた。再起の思いは強かったが、予備的な実験すらままならない状況が続いていた。そこへきて、1917年には完成目前で工事が中断していた無線送電塔が、新しい所有者の手で破壊されるという憂き目にもあった。
それだけに、専門的意見から未来のビジョンまで、自由に意見を発表できるメディアの存在は貴重だったのである。
★サイエンス・フィクションの誕生
自作の自雑誌掲載を機に、ガーンズバックのサイエンティフィクションへの思いはますます募っていった。その思いは、一九二三年の「サイエンス・アンド・インベンション」誌の”サイエンティフィクション特集”につながった。特集の反響は上々だったので、勢いに乗って今度は「サイエンティフィクション」というタイトルの新雑誌創刊を読者に提案した。しかしこちらの反応は余り芳しくなかった。
そこでいったん仕切り直しをして構想を練り直すことにし、1926年、まったく別のタイトルで新雑誌創刊に踏み切った。「アメージング・ストーリィズ」。アメリカ最初の商業SF誌の誕生である。
アメージング・ストーリイズは順調に部数を伸ばし、10年来採用してきたサイエンティフィクションという用語もようやく定着しかけた。
だが天性のアイデアマンはそれに飽きたらず、新しい呼び名を次々に読者に提案していく。そして最終的に「サイエンス・フィクション」という名称で落ち着いたのである。もっとも何と呼ぼうと、彼が意図していた技術主体の未来小説だったことに変わりはなかったが。
「アメージング・ストーリィズ」誌創刊時、テスラはすでに七〇歳になっていた。ガーンズバックがSFに足場を移してからも、ふたりの親密な関係は続いた。そしてテスラの発明的想像力は、SF的想像力の源泉であり続けた。
ガーンズバックにとってテスラはまたとない支援者だったが、逆に、テスラにとって彼との関わりはプラスばかりではなかった。
エジソンやテスラを生んだ発明の英雄時代は19世紀末に終焉を迎える。20世紀、独立独歩の発明家に代わって台頭したのは大学や研究所に所属する高学歴の専門家たちだった。それによりかつて世界を震撼させた発明家たちの栄光も次第に色褪せていったのである。
そんな中、彼らに新たな活躍の場を用意したのがサイエンス・フィクションだった。科学的想像力を重視するこの新興の文芸ジャンルの中に、彼らは天才的でアウトローな科学者──「マッドサイエンティスト」として再生したのである。
世界を一変させる大発明を成し、時に世界征服すら夢見る異端の天才科学者。彼らの発明を軸に、次々登場する狡猾で獰猛な宇宙怪物(BEM)、必ず窮地におちいる薄着の金髪美女、それを救う力強い正義のヒーローなどが、大宇宙せましと駆けめぐる。これがスペース・オペラと呼ばれる初期サイエンス・フィクションの定番だった。
この場合、主役のヒーローやお相手の美女は、たいてい類型的で無個性な大根役者と決まっていた。それに比べて、宇宙怪物やマッドサイエンティストなどの脇役たちは、個性がきわだつ演技派だった。中でも人間的な弱さを抱えたマッドサイエンティストは、ともすれば平板になりがちな物語に深い陰影を与える役割を果たした。
拙著『逆立ちしたフランケンシュタイン』でも指摘したように、彼らのモデルは中世の魔術師や錬金術師であり、直接には19世紀の発明家たちだった。とりわけテスラの天才性、カリスマ性、異端性、悲劇性などは最高のモデルにふさわしかっただろう。
しかし、こうしたイメージの浸透はテスラにとって痛しかゆしだった。通俗SFにおいては、マッドサイエンティストのイメージも通俗化せざるをえない。それによってテスラの発明もまた、殺人光線や超破壊兵器に特化され、俗化されていったからである。このことが後世、テスラの過小評価を招く一因になったことは否めない。
まさかガーンズバックも、おのれが心血を注いだメディアが「自分の神」を貶る結果を招くとは思いもよらなかっただろう。
とはいえそれは結果論であり、テスラはガーンズバックの存在に大いに慰められたし、ガーンズバックのテスラに対する尊敬も終生変わらなかった。
一九四三年に発明家が亡くなると、ガーンズバックは遺骸を受け取った葬儀屋にデスマスクの制作を委託した。完成したデスマスクは、「プラクチカル・エレクトロニクス」誌に発表され、その後、ガーンズバックの事務所内に保存された。
そして現在はベオグラードのテスラ博物館の収蔵品となっている。
★ガーンズバックの贈り物
未来を鏡とする現代批判を旨としてきた「科学ロマンス」は、未来の国アメリカで、未来の技術風景そのものを描く「サイエンス・フィクション」へと変貌を遂げた。それを牽引したのは、移民でありながら、きわめてアメリカ的な個性をもった一人の編集者だった。
しかし彼のアイデンティティは1930年代末には早くも崩壊してしまう。それを促したのは、MITで学んだインテリ編集者、J・W・キャンベルだった。
文学指向の強いこの敏腕編集者のもとで、サイエンス・フィクションは、ガーンズバック的な技術楽観主義や通俗性を脱して、洗練された〈文学〉へと変貌していった。それはたしかにSFの進化ではあったが、一面では科学ロマンスへの回帰でもあっただろう。
その後もサイエンス・フィクションは、J・バラードの「スペキュレイティヴ・フィクション」、ウィリアム・ギブスンやブルース・スターリングの「サイバーパンク」、「スティームパンク」などの衝撃を受けとめ、変貌を重ねながら、より重層的な文学ジャンルへと成長を遂げていった。
興味深いことにギブスンは1980年代に、「ガーンズバック連続体」というメタフィクション的なSF短編を著して、ガーンズバックへの多大な負債を認めた。
むろん、サイバーパンクの旗手は、現代SFの内実が名付け親の定義から遠く隔たったことは充分に認識していた。その上で、彼の技術小説が持つ荒々しい想像力や廃墟のイメージ、人工性、神秘性などに、ハイテク時代の文学の可能性を見ようとしたのだった。
反科学・反技術主義的な風潮に支配されていた1970年代が終わり、80年代にはコンピュータや新素材などの科学技術に再び期待と関心が集まった。その技術の行く末を見据えて、コンピュータを介して人と機械が融合する先端的で、異端的なマッドサイエンスを扱ったのがサイバーパンクの小説群だった。これとニコラ・テスラという真正マッドサイエンティストの同時代的復権は偶然ではないだろう。
挫折した発明家ガーンズバックは、テスラを通して発明家の時代の終わりをさとった。だからこそ文学の発明を通して神々の時代の再興を夢見たのではないだろうか。私には「サイエンスティフィクション」がガーンズバックからテスラへの私的な贈り物だったように思えてならない。
〈参考文献〉
*Tesla, Nikola, My Inventions, Hart Brothers, 1982.
*Tesla,Nikola, Famous Scientific Illusions, Electrical Experimenter, February 1919
*Tesla,Nikola, The Moon's Lotation, Electrical Experimenter, April,June 1919
*Tesla,Nikola, The True Wireless, Electrical Experimenter, May 1919















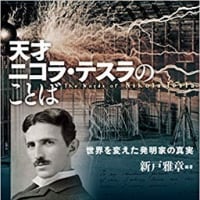



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます