今朝は午前8時に起床。
ヘミングウェイ『日はまた昇る』(新潮文庫、高見浩氏訳)の残りを一気に読む。
その後、朝食、洗濯等と一日の過ごし方は休日のお決まりコース。夕方、銀座の画廊にでかけ、ある作家の個展のオープニングを見て帰った。
☆ ☆ ☆
さて、ヘミングウェイの作品は、現在の自分の関心とはなんの関連もなく、手元にあったからというのでアトランダムに読んでみたのだが、実際に読んでみると、1920年代後半のパリとスペインを舞台としており、偶然ではあるが、日頃クレンペラーの演奏を聴きながら考えている「1920年代のヨーロッパ(ベルリン)は、どのような空間であったのか。そこでどのような文化が展開していたのか」という問題ともぴたりオーバーラップしている。『日はまた昇る』が出版されたとき、ベルリンでは、クレンペラーが次々とセンセーショナルな演奏を行っていたのだ。
それと、私にはヘミングウェイの文体(高見氏の訳文)そのものが、とても新鮮で心地よいのだが、これをクラシック音楽の演奏に比較するならば、やはりクレンペラーのキビキビした演奏が、この文体に通ずるのではないだろうか。すくなくともこれは、フルトヴェングラーやクナッパーツブッシュの演奏の背景にある文化意識とは、まったく別種のものだ。
ちょっと、映画のシナリオを読んでいるような気もしてくる。
それは、ヘミングウェイの文体が映像を思い浮かばせるというよりも、セリフの連続と行動の描写だけで成り立っている文章の構造そのものが、映画のシナリオによく似ているのだ。適当に例をひいてみよう。
★ ★ ★
ブレットがショールをまとってもどってきた。伯爵とキスを交わし、彼が立ちあがろうとすると肩をおさえて止めた。外に出しなに振り返ると、伯爵のテーブルには若い女が三人集まっていた。ぼくらは大きな車に乗り込み、ブレットが自分のホテルの住所を運転手に告げた。
「だめ、あがってこないで」ホテルに着くと、ブレットは言った。すでにベルを鳴らしていたので、ドアのロックは解除されていた。
「本当に?」
「ええ。おねがい」
「じゃあ、おやすみ、ブレット」ぼくは言った。「残念だよ、きみがそんなみじめな気分で」
「おやすみ、ジェイク。おやすみ、ダーリン。もう二度と会わないわ」ドアの前で、ぼくらはキスした。彼女はぼくを押しのけた。もう一度キスした。「だめ、おねがい!」
素速く背後を向いて、彼女はホテルの中に消えた。ぼくは自分のフラットまで伯爵の運転手に送ってもらった。20フラン渡すと、運転手は帽子に手を添えて言った。「おやすみなさい」彼は走り去った。ぼくはベルを鳴らした。ドアがひらいた。ぼくは自分の部屋まであがって、ベッドにもぐりこんだ。(同書126~7頁)
★ ★ ★
文学の世界では、この文体を「ハードボイルド」というのだとおもうが、この文体が指向しているものは、文学という現象を突き抜けているように、私には感じられる。
また、この作品は物語そのものも、とてもおもしろい。
19歳の闘牛士に恋した34歳のブレットが身をひくラストは、特に秀逸。もし自分が若い男に恋をしたら、自分から身を引くことなんてできるだろうかと、おもわず作品世界にのめり混んでしまった。
ヘミングウェイ『日はまた昇る』(新潮文庫、高見浩氏訳)の残りを一気に読む。
その後、朝食、洗濯等と一日の過ごし方は休日のお決まりコース。夕方、銀座の画廊にでかけ、ある作家の個展のオープニングを見て帰った。
☆ ☆ ☆
さて、ヘミングウェイの作品は、現在の自分の関心とはなんの関連もなく、手元にあったからというのでアトランダムに読んでみたのだが、実際に読んでみると、1920年代後半のパリとスペインを舞台としており、偶然ではあるが、日頃クレンペラーの演奏を聴きながら考えている「1920年代のヨーロッパ(ベルリン)は、どのような空間であったのか。そこでどのような文化が展開していたのか」という問題ともぴたりオーバーラップしている。『日はまた昇る』が出版されたとき、ベルリンでは、クレンペラーが次々とセンセーショナルな演奏を行っていたのだ。
それと、私にはヘミングウェイの文体(高見氏の訳文)そのものが、とても新鮮で心地よいのだが、これをクラシック音楽の演奏に比較するならば、やはりクレンペラーのキビキビした演奏が、この文体に通ずるのではないだろうか。すくなくともこれは、フルトヴェングラーやクナッパーツブッシュの演奏の背景にある文化意識とは、まったく別種のものだ。
ちょっと、映画のシナリオを読んでいるような気もしてくる。
それは、ヘミングウェイの文体が映像を思い浮かばせるというよりも、セリフの連続と行動の描写だけで成り立っている文章の構造そのものが、映画のシナリオによく似ているのだ。適当に例をひいてみよう。
★ ★ ★
ブレットがショールをまとってもどってきた。伯爵とキスを交わし、彼が立ちあがろうとすると肩をおさえて止めた。外に出しなに振り返ると、伯爵のテーブルには若い女が三人集まっていた。ぼくらは大きな車に乗り込み、ブレットが自分のホテルの住所を運転手に告げた。
「だめ、あがってこないで」ホテルに着くと、ブレットは言った。すでにベルを鳴らしていたので、ドアのロックは解除されていた。
「本当に?」
「ええ。おねがい」
「じゃあ、おやすみ、ブレット」ぼくは言った。「残念だよ、きみがそんなみじめな気分で」
「おやすみ、ジェイク。おやすみ、ダーリン。もう二度と会わないわ」ドアの前で、ぼくらはキスした。彼女はぼくを押しのけた。もう一度キスした。「だめ、おねがい!」
素速く背後を向いて、彼女はホテルの中に消えた。ぼくは自分のフラットまで伯爵の運転手に送ってもらった。20フラン渡すと、運転手は帽子に手を添えて言った。「おやすみなさい」彼は走り去った。ぼくはベルを鳴らした。ドアがひらいた。ぼくは自分の部屋まであがって、ベッドにもぐりこんだ。(同書126~7頁)
★ ★ ★
文学の世界では、この文体を「ハードボイルド」というのだとおもうが、この文体が指向しているものは、文学という現象を突き抜けているように、私には感じられる。
また、この作品は物語そのものも、とてもおもしろい。
19歳の闘牛士に恋した34歳のブレットが身をひくラストは、特に秀逸。もし自分が若い男に恋をしたら、自分から身を引くことなんてできるだろうかと、おもわず作品世界にのめり混んでしまった。











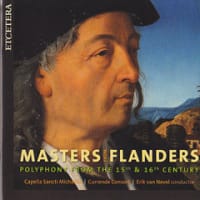


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます