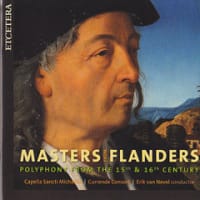まずは『<性>と日本語ーーことばがつくる女と男』の第1章「ことばとアイデンティティ」を詳細に読んでみることにしよう。
☆ ☆ ☆
中村桃子さんは、冒頭で朝日新聞の記事「DO科学」に出てくるののちゃんと藤原先生の会話を例に引いて、日本語には文末に使われる「ね・わね・わ・よ」などの典型的「女ことば」と「男ことば」が存在することに簡単にふれたのち、ことばとアイデンテイティに関して「本質主義」と「構築主義」の二つの考え方が存在することを紹介する。
ことばとアイデンティティに関する本質主義とは、「アイデンティティをその人にあらかじめ備わっている属性のようにとらえて、人はそれぞれの属性にもとづいて言語行為を行なうという考え方」(本書26頁)である。「たとえば、アイデンティティのうちでジェンダーにかかわる側面を本質主義にもとづいて表現すると、人は<女/男>というジェンダーを「持っている」、あるいは、<女/男>というジェンダーに「属している」と理解される」(本書26頁)。しかし実際には、女性も男性もそれぞれの状況に応じてさまざまに異なる言葉づかいをしており、とりわけ、実際の場面で女性たちが用いている言葉づかいは、さまざまな要因によって多様に変化している(すべての女性がつねに藤原先生のように話すとはかぎらない)。したがって、「多様に変化する女性の言語行為から、自然に「女ことば」という一つの言葉づかいが形成されたとは考えられない」(本書27頁)というのが中村さんの見方だ。
それでは構築主義とはどのような考え方、捉え方であるのか。「そこで提案されたのが、アイデンティティを言語行為の原因ではなく結果ととらえる考え方である。私たちは、あらかじめ備わっている<日本人・男・中年>という属性にもとづいて言語行為を行なうのではなく、言語行為によって自分のアイデンティティをつくりあげている。(中略)ジェンダーでいえば、<女/男>というジェンダーを、その人が持っている属性とみなすのではなく、言語行為によってつくりあげるアイデンティティ、つまり、「ジェンダーする」行為の結果だとみなすのである。そして、私たちは、繰り返し習慣的に特定のアイデンティティを表現しつづけることで、そのアイデンティティが自分の「核」であるかのような幻想をもつ」(本書27頁)。このブログの記事でいえば、ベルイマンの映画作法はまさに本質主義的であり、ブレッソンの作法は構築主義的であるといえるとおもう(ブレッソンは、「幻想」でしかないアイデンティティの問題にほとんど拘泥しない)。この二つの考え方の違いがあらわれてくるのは、実は、言語行為という局面には限らないのだ。ゆえにそれはジェンダー(社会的性役割)にも、あるいはジェンダーにこそ強く反映される。中村さんは続ける。「哲学者ジュディス・バトラーは、「ジェンダーとは、身体をくりかえし様式化していくことであり、きわめて厳密な規則的枠組みのなかでくりかえされる一連の行為であって、その行為は、長い年月の間に凝固して、実態とか自然な存在という見せかけを生み出していく」(『ジェンダートラブル』竹村和子訳)と指摘している」(本書27-8頁)と。
ところで直前に、「とりわけ、実際の場面で女性たちが用いている言葉づかいは、さまざまな要因によって多様に変化している」と書いたが、それがなぜ女性たちが用いている言葉づかいに典型的にあらわれてくるかというと、中村さんによれば、「女ことば」と「男ことば」は非対称的な構造をもっているからだ。つまり、「「女ことば」は大人の女性一般のアイデンティティを表現するために利用することができる標準的な言語資源であるが、「男ことば」は特定の<男性性>と結びついているようだ。その結果、「女ことば」は、女性が実際に使っている言葉づかいだと考えられがちなのに、「男ことば」は、実際の男性でもスポーツなどの特別な場面で使う言葉づかいだとみなされるという違いが生まれる」(本書39頁)。さらには、「私たちが、「女ことば」を「女が話している言葉づかい」だとみなすのは、「女ことば」が、たんに女性の言葉づかいであるばかりでなく、女性の言葉づかいの規範、「女はこのように話さなければならない」というルールのようなものとして認識されているからである。「女ことば」は女らしさに不可欠な規範とみなされているが、男性はつねに「男ことば」を守らなければいけないとはみなされていない。その証拠に、女子は「女の子なんだから、もっとていねいな言葉づかいをしなさい」と注意されることがあるが、男子は「男の子なんだから、もっと乱暴な言葉づかいをしなさい」とは注意されない。不思議なことに、「女ことば」という言語資源には、「女はこのような言葉づかいをしている」という知識だけでなく、「女はこのように話さなければならない」という規範が含まれているのである」(本書38-40頁)。
そこで中村さんは、ミッシェル・フーコーが『知の考古学』に記している、言説とは、「言説によって語られる諸対象を体系的に形成=編成する実践」であるという指摘を手がかりにして、言語資源を「知識」としてとらえ直すべきであるとする。
すると、「標準語」には隠れた男性性が付与されており、「女ことば」は、「標準語」の女版、「標準語」の亜種として位置づけられていることが明らかとなり、(一種の丁寧語である)「女ことば」に対応するのは、「(男の)標準語」であることがわかってくる。また、「「男ことば」は、「標準語」の中でも特別な<男性性>を表現する資源として機能する」(本書45頁)ことも理解されてくる。
またこのように、一種の知識である「言語資源」という視点から言語行為をみていくと、「私たちの言語行為は言語資源と結びついているカテゴリーからのずれを生じており、この「ずれた行為」が画一的なカテゴリーと結びついた言語資源を変革する可能性を前提としている。日本語を言語資源という視点からながめることは、言語資源と言語行為がお互いに影響しあいながら変化していくダイナミズムを明らかにする道を開く」(本書47頁)という。
☆ ☆ ☆
中村桃子さんは、冒頭で朝日新聞の記事「DO科学」に出てくるののちゃんと藤原先生の会話を例に引いて、日本語には文末に使われる「ね・わね・わ・よ」などの典型的「女ことば」と「男ことば」が存在することに簡単にふれたのち、ことばとアイデンテイティに関して「本質主義」と「構築主義」の二つの考え方が存在することを紹介する。
ことばとアイデンティティに関する本質主義とは、「アイデンティティをその人にあらかじめ備わっている属性のようにとらえて、人はそれぞれの属性にもとづいて言語行為を行なうという考え方」(本書26頁)である。「たとえば、アイデンティティのうちでジェンダーにかかわる側面を本質主義にもとづいて表現すると、人は<女/男>というジェンダーを「持っている」、あるいは、<女/男>というジェンダーに「属している」と理解される」(本書26頁)。しかし実際には、女性も男性もそれぞれの状況に応じてさまざまに異なる言葉づかいをしており、とりわけ、実際の場面で女性たちが用いている言葉づかいは、さまざまな要因によって多様に変化している(すべての女性がつねに藤原先生のように話すとはかぎらない)。したがって、「多様に変化する女性の言語行為から、自然に「女ことば」という一つの言葉づかいが形成されたとは考えられない」(本書27頁)というのが中村さんの見方だ。
それでは構築主義とはどのような考え方、捉え方であるのか。「そこで提案されたのが、アイデンティティを言語行為の原因ではなく結果ととらえる考え方である。私たちは、あらかじめ備わっている<日本人・男・中年>という属性にもとづいて言語行為を行なうのではなく、言語行為によって自分のアイデンティティをつくりあげている。(中略)ジェンダーでいえば、<女/男>というジェンダーを、その人が持っている属性とみなすのではなく、言語行為によってつくりあげるアイデンティティ、つまり、「ジェンダーする」行為の結果だとみなすのである。そして、私たちは、繰り返し習慣的に特定のアイデンティティを表現しつづけることで、そのアイデンティティが自分の「核」であるかのような幻想をもつ」(本書27頁)。このブログの記事でいえば、ベルイマンの映画作法はまさに本質主義的であり、ブレッソンの作法は構築主義的であるといえるとおもう(ブレッソンは、「幻想」でしかないアイデンティティの問題にほとんど拘泥しない)。この二つの考え方の違いがあらわれてくるのは、実は、言語行為という局面には限らないのだ。ゆえにそれはジェンダー(社会的性役割)にも、あるいはジェンダーにこそ強く反映される。中村さんは続ける。「哲学者ジュディス・バトラーは、「ジェンダーとは、身体をくりかえし様式化していくことであり、きわめて厳密な規則的枠組みのなかでくりかえされる一連の行為であって、その行為は、長い年月の間に凝固して、実態とか自然な存在という見せかけを生み出していく」(『ジェンダートラブル』竹村和子訳)と指摘している」(本書27-8頁)と。
ところで直前に、「とりわけ、実際の場面で女性たちが用いている言葉づかいは、さまざまな要因によって多様に変化している」と書いたが、それがなぜ女性たちが用いている言葉づかいに典型的にあらわれてくるかというと、中村さんによれば、「女ことば」と「男ことば」は非対称的な構造をもっているからだ。つまり、「「女ことば」は大人の女性一般のアイデンティティを表現するために利用することができる標準的な言語資源であるが、「男ことば」は特定の<男性性>と結びついているようだ。その結果、「女ことば」は、女性が実際に使っている言葉づかいだと考えられがちなのに、「男ことば」は、実際の男性でもスポーツなどの特別な場面で使う言葉づかいだとみなされるという違いが生まれる」(本書39頁)。さらには、「私たちが、「女ことば」を「女が話している言葉づかい」だとみなすのは、「女ことば」が、たんに女性の言葉づかいであるばかりでなく、女性の言葉づかいの規範、「女はこのように話さなければならない」というルールのようなものとして認識されているからである。「女ことば」は女らしさに不可欠な規範とみなされているが、男性はつねに「男ことば」を守らなければいけないとはみなされていない。その証拠に、女子は「女の子なんだから、もっとていねいな言葉づかいをしなさい」と注意されることがあるが、男子は「男の子なんだから、もっと乱暴な言葉づかいをしなさい」とは注意されない。不思議なことに、「女ことば」という言語資源には、「女はこのような言葉づかいをしている」という知識だけでなく、「女はこのように話さなければならない」という規範が含まれているのである」(本書38-40頁)。
そこで中村さんは、ミッシェル・フーコーが『知の考古学』に記している、言説とは、「言説によって語られる諸対象を体系的に形成=編成する実践」であるという指摘を手がかりにして、言語資源を「知識」としてとらえ直すべきであるとする。
すると、「標準語」には隠れた男性性が付与されており、「女ことば」は、「標準語」の女版、「標準語」の亜種として位置づけられていることが明らかとなり、(一種の丁寧語である)「女ことば」に対応するのは、「(男の)標準語」であることがわかってくる。また、「「男ことば」は、「標準語」の中でも特別な<男性性>を表現する資源として機能する」(本書45頁)ことも理解されてくる。
またこのように、一種の知識である「言語資源」という視点から言語行為をみていくと、「私たちの言語行為は言語資源と結びついているカテゴリーからのずれを生じており、この「ずれた行為」が画一的なカテゴリーと結びついた言語資源を変革する可能性を前提としている。日本語を言語資源という視点からながめることは、言語資源と言語行為がお互いに影響しあいながら変化していくダイナミズムを明らかにする道を開く」(本書47頁)という。