
本日、 。
。
最高気温3℃、最低気温-8℃。とずいぶん冷え込んだ日が続いております。
久々の投稿で申し訳ございません。
改めまして、明けましてお 出とうございます。
出とうございます。
友人の一斉メールでご存じの方も多いかと思いますが、去年年末に男の子を授かり、
正月は初めての、育メンをやっており、事務的な仕事が滞ってしまったのでご迷惑おかけして申し訳ございませんでした。
これから、今年の菜園教室の案内、申込み事務手続きを復活させて、順次行っていこうと思います。
本年もよろしくお願いいたします。

去年の8月に出版させていただいた拙著『これならできる!自然菜園』(農文協)を手にとっていただけた方が予想以上に多く、
出版社共々、感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。
自然菜園を執筆させていただいたことで、今までまとまっているようで、まとまっていなかった事柄が整理整頓され、
今年は今までと異なったアプローチでより分かりやすく、菜園教室ができるように思えます。
内容一新したリニューアル菜園教室2013楽しみにしていてください。
 菜園教室のご案内は、
菜園教室のご案内は、
@自給自足Lifeホームページに掲載されます。
先日、以下のようなご質問をコメント欄にいただきました。
コメント欄に返すには重要な内容だったので、ブログでご返信とさせていただきます。
※このブログのコメント欄では、菜園に関するご質問が無料でできます。
自給自足の生活のため個人的なご質問はお仕事の依頼以外、現在すべてお断りさせていただいております。
詳細なご質問は、菜園教室にご参加いただきその際、お願いたします。
*****************************
ところで、この場を借りて、たけさんに質問です。
畑の土に苦戦しています。
①水はけが極端に悪く、日照りの日はカチカチに固まり、雨が続くと海苔のような苔が生えてきてしまう、
いわゆる重粘土質です。
昨年、自然農にチャレンジしましたが、②作物の成長はすこぶる悪く、麦と大豆だけ辛うじて育ったような状態でした。
畑の現状を整理すると、以下のような状態です。
・重粘土質
③・10年程前から耕すのみで作付けはしていない
・それ以前は、農薬除草剤化学肥料をバリバリ使用
④春に向けて少しでも土を良くしたいと考えていますが、
今からできることはありますでしょうか。
以前のたけさんの記事を参考に、④一部の畑で麦類とレンゲとクローバーをばらまいています。
*****************************
1)そうですね。①のような重粘土質では、畑が難しい一方、元々は田んぼであればお米は野菜に比べ無農薬栽培で育てやすいので、
無理をせず、畑に向いた場所以外では無農薬栽培での稲作にするのも一つの手です。
また、水抜きができる暗渠(あんきょ)付きの畑であれば、稲作→大豆→麦の輪作体系を組んで村全体で有機農業に転換に成功した埼玉県小川町のように、稲と穀物、そこに野菜を組み込んで行う方法も考えられます。
粘土土といっても専門的には種類があり、特性がありますので、それを知っておくのも大切です。
土壌情報閲覧システムから全国の土質が調べることができます。
2)②作物の生長が悪い理由は、いくつか考えられますが、
③からも無農薬で野菜そのものが育つ環境が調っていない可能性が高いですね。
まずは、養分があるか、塩基バランスがどうか、PHはいくつか、EC値は?が一目でわかる簡易土壌分析などを行って、
目で観ることができない、化学成分を調べてみることをお奨めします。
いわば、人間でいえば健康診断で、血圧、尿酸値など現在の健康状態を数値で確認する作業です。
簡易土壌分析は、1サンプル500~5,000円位で、ホームセンター(カインズホームなど)、農協さんなどいろいろなところで行っており、レーダーチャートで一目でわかるグラフで出してくれます。
※畑の深さ10cmのところの土を5か所とり、5つを混ぜたものが1サンプルにするのが一般的です。
3)②からも粘土でも割と育てやすい野菜を選んで栽培するのも手です。
粘土土でも肥えていれば、よく育つ順に書くと、レンコン、マコモ、クワイ、稲、サトイモ、ショウガ、ダイズ、エダマメ、タマネギ、ニンニク、ラッキョウ、アサツキ、ネギといった感じです。
私の場合、マコモ、サトイモ、ショウガ、黒豆などは、田んぼの畦(あぜ)など粘土で水はけが悪いことを利用して育てています。
来年からは、田んぼを半分に分け、半分稲、半分畑にし、その間で、サトイモ、ショウガなど育てようと思っております。
4)④ですが、その後順調に緑肥作物が育っていますか?
緑肥作物を栽培することで、土を肥やしたり、水はけを改善したりする方法はとても有効です。
しかし、適当に行ってもなかなか緑肥作物そのものが育たなく、その効果が半減してしまっているケースが多いものです。
水はけが悪いのであれば、水はけに強い緑肥作物を選び、
痩せているのであれば、痩せ地に向いてもの、もしくは堆肥などを入れて土壌改良してから、
適期に、種を充分必要量播いてから耕し、土を覆土する必要があります。
幸い、以前に書いたブログにその要点を紹介させていただいておりますので、ご参照ください。
ブログ「緑肥作物で元田んぼの粘土土質を改良」シリーズ
5)④の春からの対策ですが、
雪が降り地面が凍っている現在は特に畑でする野良仕事はありませんが、
現在使っている畑のすべてで簡易土壌診断をする、結果が1カ月位先になりますので、前もってサンプルを採ってすぐに提出する。
また、土壌分析の結果を受けて抜本的に土壌改良する菜園計画を立てて、1~3年は、主に土づくりを軸に栽培計画した方がいいかと思います。
最初の1、2年はしっかり土づくりした方がいいと思います。
水はけ・肥持ちを良くするために、堆肥や緑肥作物の投入、明渠の設置、高畝対策など、
まずは耕し有機農業ではじめ、団粒構造も発達し、腐植もできてきたら(畑になってきたら)、順次自然農に切り替えていく方が無難だと思います。
自然農の創立者川口由一さんも、戦前まで伝統農法=有機農業でやっていた田畑で、伝統的な農法で栽培しており、
その後数年農薬・化学肥料を使い中毒したの結果、自然農に3年かかって転化していった経緯があります。
まずは、野菜が育つ畑にし、地域風土を活かした栽培歴、栽培法を学びながら、移行していくことが無難ですよ。
日本中、元水田を畑として使いたい要望は多くなってくると思います。
稲を栽培するのが最適ですが、畑にしたい場合、恵まれている場合を除きある程度覚悟して取り組む必要があると思います。
粘土の強い土は、最初は「水はけが極端に悪く、日照りの日はカチカチに固まり、雨が続くと海苔のような苔が生えてきてしまう」大変な土かもしれませんが、
上手に畑化すると「水持ちが良く、肥料も流失しにくく、美味しい野菜が育つ土」になってくれます。
また何かご質問があれば、コメント欄からご質問ください。
もし、菜園コンサルが必要な場合は、別にご相談ください。
今年も実り多い年になりますように~
2013年度の自然菜園講座の一つ「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!(12/25~2月末)

2012年12月の講座での集合写真
「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!(12/25~2月末)
先着24名。耕さず、草と虫を敵としない川口由一さんのはじめた自然農に特化したシャロムヒュッテに1泊2日しながら、全10回の体験型ワークショップです。
耕さない田んぼに、畑で実際に、自然の理を学び、実践できます。
しかも、自分の小さな菜園区画が付いているので、3~12月の間自然農で野菜を育てることができます。
半農半Xの暮らし、自然農にご興味がある方にお奨めの講座です。
只今準備中ですが、
自然農法で自給自足の農園が学べる「Azumino自給農スクール2013」
穂高養生園で、日帰りも食事、宿泊もできる自然菜園入門講座も間もなく募集がはじまります。
お好みでお選びください。
【お迷いの方へ】
・耕さない自然農を学びたいなら→「あずみの自然農塾2013(第7期)」
・無農薬栽培の基本から応用を学び、我が家の自給率をアップしたいなら→「Azumino自給農スクール2013」

1月23日(水)は長野、9日(水)松本で、
無農薬ずくなし家庭菜園教室の菜園プランと土づくりをテーマに、「春準備号」がはじまります。
長野メルパルク教室
長野城山公民館教室
松本教室
【拙著のご紹介】
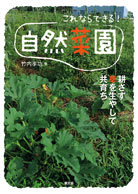
『これならできる!自然菜園』

『コンパニオンプランツで失敗しらずのコンテナ菜園』
好評発売中~
 。
。最高気温3℃、最低気温-8℃。とずいぶん冷え込んだ日が続いております。
久々の投稿で申し訳ございません。
改めまして、明けましてお
 出とうございます。
出とうございます。友人の一斉メールでご存じの方も多いかと思いますが、去年年末に男の子を授かり、
正月は初めての、育メンをやっており、事務的な仕事が滞ってしまったのでご迷惑おかけして申し訳ございませんでした。
これから、今年の菜園教室の案内、申込み事務手続きを復活させて、順次行っていこうと思います。
本年もよろしくお願いいたします。

去年の8月に出版させていただいた拙著『これならできる!自然菜園』(農文協)を手にとっていただけた方が予想以上に多く、
出版社共々、感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。
自然菜園を執筆させていただいたことで、今までまとまっているようで、まとまっていなかった事柄が整理整頓され、
今年は今までと異なったアプローチでより分かりやすく、菜園教室ができるように思えます。
内容一新したリニューアル菜園教室2013楽しみにしていてください。
 菜園教室のご案内は、
菜園教室のご案内は、@自給自足Lifeホームページに掲載されます。
先日、以下のようなご質問をコメント欄にいただきました。
コメント欄に返すには重要な内容だったので、ブログでご返信とさせていただきます。
※このブログのコメント欄では、菜園に関するご質問が無料でできます。
自給自足の生活のため個人的なご質問はお仕事の依頼以外、現在すべてお断りさせていただいております。
詳細なご質問は、菜園教室にご参加いただきその際、お願いたします。
*****************************
ところで、この場を借りて、たけさんに質問です。
畑の土に苦戦しています。
①水はけが極端に悪く、日照りの日はカチカチに固まり、雨が続くと海苔のような苔が生えてきてしまう、
いわゆる重粘土質です。
昨年、自然農にチャレンジしましたが、②作物の成長はすこぶる悪く、麦と大豆だけ辛うじて育ったような状態でした。
畑の現状を整理すると、以下のような状態です。
・重粘土質
③・10年程前から耕すのみで作付けはしていない
・それ以前は、農薬除草剤化学肥料をバリバリ使用
④春に向けて少しでも土を良くしたいと考えていますが、
今からできることはありますでしょうか。
以前のたけさんの記事を参考に、④一部の畑で麦類とレンゲとクローバーをばらまいています。
*****************************
1)そうですね。①のような重粘土質では、畑が難しい一方、元々は田んぼであればお米は野菜に比べ無農薬栽培で育てやすいので、
無理をせず、畑に向いた場所以外では無農薬栽培での稲作にするのも一つの手です。
また、水抜きができる暗渠(あんきょ)付きの畑であれば、稲作→大豆→麦の輪作体系を組んで村全体で有機農業に転換に成功した埼玉県小川町のように、稲と穀物、そこに野菜を組み込んで行う方法も考えられます。
粘土土といっても専門的には種類があり、特性がありますので、それを知っておくのも大切です。
土壌情報閲覧システムから全国の土質が調べることができます。
2)②作物の生長が悪い理由は、いくつか考えられますが、
③からも無農薬で野菜そのものが育つ環境が調っていない可能性が高いですね。
まずは、養分があるか、塩基バランスがどうか、PHはいくつか、EC値は?が一目でわかる簡易土壌分析などを行って、
目で観ることができない、化学成分を調べてみることをお奨めします。
いわば、人間でいえば健康診断で、血圧、尿酸値など現在の健康状態を数値で確認する作業です。
簡易土壌分析は、1サンプル500~5,000円位で、ホームセンター(カインズホームなど)、農協さんなどいろいろなところで行っており、レーダーチャートで一目でわかるグラフで出してくれます。
※畑の深さ10cmのところの土を5か所とり、5つを混ぜたものが1サンプルにするのが一般的です。
3)②からも粘土でも割と育てやすい野菜を選んで栽培するのも手です。
粘土土でも肥えていれば、よく育つ順に書くと、レンコン、マコモ、クワイ、稲、サトイモ、ショウガ、ダイズ、エダマメ、タマネギ、ニンニク、ラッキョウ、アサツキ、ネギといった感じです。
私の場合、マコモ、サトイモ、ショウガ、黒豆などは、田んぼの畦(あぜ)など粘土で水はけが悪いことを利用して育てています。
来年からは、田んぼを半分に分け、半分稲、半分畑にし、その間で、サトイモ、ショウガなど育てようと思っております。
4)④ですが、その後順調に緑肥作物が育っていますか?
緑肥作物を栽培することで、土を肥やしたり、水はけを改善したりする方法はとても有効です。
しかし、適当に行ってもなかなか緑肥作物そのものが育たなく、その効果が半減してしまっているケースが多いものです。
水はけが悪いのであれば、水はけに強い緑肥作物を選び、
痩せているのであれば、痩せ地に向いてもの、もしくは堆肥などを入れて土壌改良してから、
適期に、種を充分必要量播いてから耕し、土を覆土する必要があります。
幸い、以前に書いたブログにその要点を紹介させていただいておりますので、ご参照ください。
ブログ「緑肥作物で元田んぼの粘土土質を改良」シリーズ
5)④の春からの対策ですが、
雪が降り地面が凍っている現在は特に畑でする野良仕事はありませんが、
現在使っている畑のすべてで簡易土壌診断をする、結果が1カ月位先になりますので、前もってサンプルを採ってすぐに提出する。
また、土壌分析の結果を受けて抜本的に土壌改良する菜園計画を立てて、1~3年は、主に土づくりを軸に栽培計画した方がいいかと思います。
最初の1、2年はしっかり土づくりした方がいいと思います。
水はけ・肥持ちを良くするために、堆肥や緑肥作物の投入、明渠の設置、高畝対策など、
まずは耕し有機農業ではじめ、団粒構造も発達し、腐植もできてきたら(畑になってきたら)、順次自然農に切り替えていく方が無難だと思います。
自然農の創立者川口由一さんも、戦前まで伝統農法=有機農業でやっていた田畑で、伝統的な農法で栽培しており、
その後数年農薬・化学肥料を使い中毒したの結果、自然農に3年かかって転化していった経緯があります。
まずは、野菜が育つ畑にし、地域風土を活かした栽培歴、栽培法を学びながら、移行していくことが無難ですよ。
日本中、元水田を畑として使いたい要望は多くなってくると思います。
稲を栽培するのが最適ですが、畑にしたい場合、恵まれている場合を除きある程度覚悟して取り組む必要があると思います。
粘土の強い土は、最初は「水はけが極端に悪く、日照りの日はカチカチに固まり、雨が続くと海苔のような苔が生えてきてしまう」大変な土かもしれませんが、
上手に畑化すると「水持ちが良く、肥料も流失しにくく、美味しい野菜が育つ土」になってくれます。
また何かご質問があれば、コメント欄からご質問ください。
もし、菜園コンサルが必要な場合は、別にご相談ください。
今年も実り多い年になりますように~
2013年度の自然菜園講座の一つ「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!(12/25~2月末)

2012年12月の講座での集合写真
「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!(12/25~2月末)
先着24名。耕さず、草と虫を敵としない川口由一さんのはじめた自然農に特化したシャロムヒュッテに1泊2日しながら、全10回の体験型ワークショップです。
耕さない田んぼに、畑で実際に、自然の理を学び、実践できます。
しかも、自分の小さな菜園区画が付いているので、3~12月の間自然農で野菜を育てることができます。
半農半Xの暮らし、自然農にご興味がある方にお奨めの講座です。
只今準備中ですが、
自然農法で自給自足の農園が学べる「Azumino自給農スクール2013」
穂高養生園で、日帰りも食事、宿泊もできる自然菜園入門講座も間もなく募集がはじまります。
お好みでお選びください。
【お迷いの方へ】
・耕さない自然農を学びたいなら→「あずみの自然農塾2013(第7期)」
・無農薬栽培の基本から応用を学び、我が家の自給率をアップしたいなら→「Azumino自給農スクール2013」

1月23日(水)は長野、9日(水)松本で、
無農薬ずくなし家庭菜園教室の菜園プランと土づくりをテーマに、「春準備号」がはじまります。
長野メルパルク教室
長野城山公民館教室
松本教室
【拙著のご紹介】
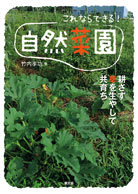
『これならできる!自然菜園』

『コンパニオンプランツで失敗しらずのコンテナ菜園』
好評発売中~



























そうですね。小さな砂漠化は日本でも起こっております。自分の敷地が緑化され、パラダイス(自然豊かな環境)を再生したいと思います。
堆肥化は、いろいろな方法がありますが、私の堆肥の師匠(橋本力男先生)の本をお勧めしますので、是非手に取ってみてください。
『畑でおいしい水をつくる 自家製有機堆肥のすすめ』http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_93914530/
土の中に有機物が多いとそれを分解する生物が増えるのですね、なるほどです。
雑草を積んでいる所と、栽培している所、草が茂っている所では虫の種類が違うなあと草刈りをしている時に感じたことがありました。
土も草も生き物にもそれぞれのバランスというものがあるのですね、余計なことをして砂漠のようにならないよう気を付けます。
堆肥の作り方のご指導ありがとうございます。
①の堆肥の作り方としては間違ってはいなかったようですが、とても時間がかかるものなのですね。
②の材料のバランスや技術、ノウハウが必要な作り方だと、病気も少なく、時間が半分程になり魅力的です。
②の技術の必要な堆肥の作り方も勉強してみたいですが、こちらから長野までは距離的に難しいです。
今回色々教えて頂いたことを活かして少しずつ取り組んでいきたいと思います、長々とありがとうございました。
そうですね。タキイ種苗さんから直接ネットで買うよりも、同じ商品なのに、町の種苗やさんの方が緑肥作物だけでなく、いろいろな種苗が安いのは不思議ですね。
1)緑肥作物を鋤き込み、大地で堆肥化刷ることで微生物を殖やし有機物を腐植化し、団粒構造を発達させることによって、野菜という特殊な植物は、よく育つようになります。
ところが、有機物が分解する生き物が中心になり、分解が終わると、土になった後は、何もしなけれな、風雨にさらされ、砂漠になって行きます。
生きた緑肥作物が根が張っていることは、水を吸い上げ大地を潤し、地上部の草の中には、クモやカエルを頂点とした食物連鎖が発達し、土の中でも、ミミズやヤスデが少しずつ枯れた植物などを分解しながら分解者以外の微生物、菌根菌、根粒菌などがネットワークを張り、微生物の森が構築されていきます。
生きた草や緑肥作物は、自然豊かな「小さな森」で、刈り取られ根の切り株だけが残った大地は、一時的に豊かになっても砂漠への一歩を踏み出したとも言えます。残念ながら、かつての四大文明も耕して、文明を誇りましたが、今は砂漠です。
そのため、「生きた緑肥が一番」と申し上げた感じです。
2)草堆肥(雑草堆肥)には、2つ作り方があります。
①一つは、野積法です。積み上げておく方法で、
ねこじゃらしさんの方法もその一つで、窒素系の油粕で分解を早め、土を乗せることで、分解を早めています。
この方法では、材料によりますが、草の場合は最低1年以上放置し、土になるまで(土になった部分から)使用することができます。
ちなみに、材料が落ち葉主体の場合、3~5年。麦わらの場合、5~8年、カヤやススキの場合10年以上かかります。
②堆肥づくりの発酵には、水、空気、窒素炭素比のバランス、積み上げ方に法則があり、それを満たすと材料の種類にかかわらず、わずか3~4日で45℃以上発酵が進み、最初の1週間で60~75℃に達し、その後切り返しを行うことで、草堆肥の場合半年~1年で完熟(熟成)堆肥になります。
落ち葉主体だと1年~1年半くらいなど炭素比が高い資材が多いほど熟成に時間がかかります。
②の方法の場合、ここでは説明しきらないので、11~12月に安曇野校で実際に自然堆肥づくりを行うので,見にきてください。の方が早いと思いました。http://www.shizensaien.net/azumino_basic-w/index.html
②の方は手間がかかりますが(技術が必要ですが)①に比べ短期間で、高温発酵により病虫害が少なく、草のタネが発芽能力をなくし、高品質で、養分に富んだ堆肥にできる特長があります。
①の作り方は、草が枯れていくに従い水分を失い、枯れたものは時間がかかり、作る量が少ないと発酵熱のロスが多くなりやすいので、特に間違っているというよりも②の発酵(分解)条件を満たしていない可能性が高いので、その分時間がかかるものです。
とても強い台風で、各地で被害がありましたが大丈夫でしたでしょうか?
多年草の緑肥や混ぜた状態で販売している緑肥もあるのですね、種の代金が思ったよりも高かったので助かります。
アドレス貼って下さったつる新さんもタキイより安いので、種代が安くなりそうです。
耕した後種を蒔き、草を上に乗せると好光性の種が発芽しやすく、草のない状態で種まき後に5~15㎝耕すのが一般的なのですね。
教えて頂いた草の生えている上からの種まきも、緑肥が生えていない所があれば試してみようと思います。
昨日どうにか種まきが終わり、種まき後に3~5㎝耕して、草を隙間を開けながらうっすら乗せて軽く水を撒いたのですが、今日見たら土が乾燥して固くなってしまっていて、これで大丈夫なんでしょうか?
鋤き込むのは野菜を栽培するのに適した方法なのですね。
また緑肥の効果は生きている状態が一番高いのですか、素人の私には根が腐らなければ地中の有機物が増えないのでは?と思ったりもするのですが、
生きた根が年中張っている状態の方が良いのでしょうか?
あと後出しで申し訳ないですが、6月から作っている雑草堆肥があまり分解が進まないのですが、雑草や緑肥での堆肥の作り方も教えて頂けませんでしょうか?
私がやった方法は刈った雑草を50㎝程積み上げて、草に粒の油粕を混ぜて、市販の園芸用の土を上から乗せていたんですが、何か間違っていたのでしょうか?
ご返信大変遅くなりました。台風19号対策で、前倒しでいろいろやっていたものですから。
さてご質問・コメントから内容から目的が「広過ぎるのでひとまずは土を柔らかく生き返らせたい」のであれば、来年菜園を行わない場所には、これから播ける緑肥作物の中に、多年草の緑肥をmixし、来年以降、15㎝残して草刈りして、多年草の緑肥(赤クローバー、イタリアンライグラス ペレニアルライグラス オーチャードグラスなど)毎年生えてくる緑肥も一緒に育てた方が、毎回種まきをせずいいと思います。
ただし、トラクターをお持ちでない場合は、ほふくして増えるシロクローバーなどでは広がってしまい、菜園に戻すとき大変なので控えた方がいい緑肥作物もありますので、今後を考えて、地域に合った多年草緑肥のブレンドがお奨めです。
ちなみに、つる新種苗さんでは、自然菜園緑肥mixレギュラーリョクヒミックス(1年生と多年生ミックス)といったブレンドされたものも市販しております。http://tane.jp/haruyasai/bokusou/hinshu/ryukuhimix.html
1)「蓮華の播種時期は9~11月と農協のHPに書いていたので、今頃が適期ではないかと思うのですがどうでしょうか?」幅が広いところ見ると暖地のようですね。特にレンゲは、適期に地域風土に合わせて蒔いてください。
2)「土を耕した後に普通に覆土鎮圧するのと、
耕した土に上からバラマキその上に雑草の枯れ草を載せるのとでは生育に違いがありますでしょうか?」
①そうですね。耕した場合はいずれもたくさんの草(有機物)があると温かい時期発酵して、発芽発根障害が出やすいので、1~2度耕してから、草が土に還ってから播種する必要があります。
②通常の種まきに対して、耕してからタネを蒔き、草を乗せると、好光性種子が発芽しやすく、敷いた草が多すぎたり、草が固まっていると発芽ムラがあるので、草が均一にまんべんなく敷くことができ、草の間から緑肥が生えやすいように敷くのポイントです。
また、その場合、耕して乾く前に当日種まきすることも大切なポイントです。
③耕して草がなくなってから、全体に種を蒔き5~15㎝耕すことで、一斉発芽する蒔き方が緑肥作物では一般的です。
④私の場合、自然農のやり方で、草ぼうぼうの中、昼間草が乾いているときに、草の上から緑肥作物のmixを蒔いて、地際で草を刈って敷き詰めて、草の間から発芽させることもよくやっております。
春や秋に緑肥の禿げたところに追い蒔きする場合、そのようにやるのがお奨めです。
2)「体力、面積的に鋤き込みが厳しく、上部を根元で刈り敷し、根を残しておこうと思っていたのですが、効果を最大限に生かすのなら、やはり緑肥は米ぬか、もみ殻、クン炭と鋤き込まねばならないのでしょうか?」
それは、緑肥作物を鋤き込んで、野菜が育つために行う方法で、緑肥の効果を最大限に活かすのであれば、生きた緑肥が一番なので、
①一年草の緑肥作物の場合、種をつけたら、種ごと鋤き込む、もしくは地上部を刈って敷くと再び生えてきます。
②①よりは、前もって1年草のタネの中に、多年草の緑肥作物のタネも混ぜておくと、花が咲くたびに、種をつける前に15㎝残して刈って、刈ったものを持ち出すと(菜園の草マルチに利用すると)また多年草緑肥が生えてくるので、それは楽でいいですよ。
ご回答にあった3年後ですが今は栽培プランはなく、栽培するにも私には広過ぎるのでひとまずは土を柔らかく生き返らせたいです。
今の状態では畝立ても植え付けも極々少数しかできそうにないです。
固い土ですが、昨日また耕してみたところ、雨のおかげか幾分柔らかく、それまで2cmだったのが1回で5cmほど掘れたので、どうにか1畝分(平地ですが)終わらせれました。
水を吸わせると柔らかくなるようなので、昨日帰る前まだ耕していない所に水を撒いておきました。
地域は中国地方なので暖地になると思います。昨日耕した所もそうですが、今大豆が豆をつけている所も土に腐食が少なく、
春から半年間草を刈り敷いていも地表の数ミリが柔らかいだけで、少し掘るのにも想像以上に体力を使ってしまいます。
ただ生き物は種類も数もだいぶ増えたと思います。(ミミズは少ないですが)
ですので、竹内さんがせっかく考えて頂いたプランですが、まず栽培をしていない半分に今月緑肥を、
残りの半分に来月緑肥を蒔き1年間育て、野菜の栽培は少数に留めようかと思っています。
緑肥の蒔き方ですが、この辺りの蓮華の播種時期は9~11月と農協のHPに書いていたので、今頃が適期ではないかと思うのですがどうでしょうか。
ライ麦、エン麦、クリムソンクローバー、蓮華を、土を耕した後に普通に覆土鎮圧するのと、
耕した土に上からバラマキその上に雑草の枯れ草を載せるのとでは生育に違いがありますでしょうか?
緑肥の鋤き込みのご指導ありがとうございます。
体力、面積的に鋤き込みが厳しく、上部を根元で刈り敷し、根を残しておこうと思っていたのですが、
効果を最大限に生かすのなら、やはり緑肥は米ぬか、もみ殻、クン炭と鋤き込まねばならないのでしょうか?
そうですか。クズは大変なので、一度思い切って取っておいて正解だったと思います。
現状「植えた大豆、きゅうり、ミニトマトの生育は無肥料でも悪くない」のであれば、
元畑なので、後は、ダイズ、夏野菜(根を張ってもらい、半年以上草マルチ)や緑肥作物(根で耕してもらい、刈って鋤き込んで堆肥にして)で土づくりしていけばいいと思います。
1)今年試験栽培した半分は、
①来年大豆跡地は、ミニトマト、シシトウ、オクラなどを育て、ナスや、キュウリ、カボチャ、ズッキーニには、クラツキをしてから育てるといいと思います。
②夏野菜の草マルチとして、トマト、ナス、カボチャを植える場所から30㎝話したところに、春先にエン麦を蒔くと、夏野菜を植えた後、1か月後刈って草マルチ活用できます。
③今年キュウリやミニトマトを育てた跡地では、ダイズを育てて、直根で耕してもらい来年の夏野菜の土づくりにしたいですね。
④来年以降は、夏野菜の跡地(半年間以上夏野菜に草マルチをしながら育てた場所)に冬野菜(春・秋・越冬野菜)を育てることができます。
2)地域風土(いつライ麦の蒔き時かなど)情報がないので何とも言えませんが、
私なら手を付けていない半分(50㎡)は、今年、ライ麦、エン麦、クリムソン、クリムソンクローバーをレンゲの蒔き時期に蒔いて育てます。
翌年5~7月にライ麦が50㎝以上育った段階で、30㎝以下に刈り敷き、米ぬか、もみ殻、クン炭と共に鋤き込んで1か月以上しっかり分解するまで数回耕してから、
秋に畝立てし、通路に緑肥mixを蒔き、越冬野菜(ソラマメ、エンドウ、越冬キャベツ)から育てると思います。
3)一番大切なのは、とりあえず育てるのは今年限りで、来年から3年後にどのような菜園にしたいのかしっかりプランを立てて行うことが大切です。
家庭菜園では、少量多品目で連作して畑が空くことがないので、最初のプランが肝心です。
自然菜園では、連作できるした方がいい野菜の「連作区」と1年おきに夏野菜と冬野菜たちを交互に育てる「夏畝&冬畝」に分けてプランします。各書籍にご紹介しているの参考にしてみてください。
重粘土の20年ほどの元畑の耕作放棄地で、3年前に草刈り、その後に重機にて大量の葛を撤去し、春にスギナ、夏はツユクサ、メヒシバ、スベリヒユ、当時は無恥ゆえにハコベやオオイヌノフグリまでをも、葛撤去後から昨年末まで除草剤で枯らしていました。
今年春からは土が死んでいる気がして除草剤の使用をやめ使っていません。
このブログを参考に土を生き返らせたいと思い、今回初めてタキイで燕麦、ライ麦、クリムソンクローバー、蓮華を買いました。
メヒシバ、オヒシバ、ヒメムカシヨモギなどの草刈りまでは進んだのですが、土が固く種をまいて雑草を刈り敷きしただけでは発芽や成長しないのではと思い、耕そうとしたのですが固すぎてほとんど耕せません。
2cm程度ずつ同じ場所を何度も耕して、ようやく10cm耕せたかなという感じです。
固い原因は葛を取り除くときに重機で何度も往復したのと、2,3年の除草剤の使用だと思うのですが、このような場合はどのようにすればよいのでしょうか?
半分の面積に試験的に植えた大豆、きゅうり、ミニトマトの生育は無肥料でも悪くないと思います。
広さですが10m×10m程度で作業はすべて手作業になります、突然の質問ではありますがよろしくお願いします。
そうですか。お役に立てて良かったです。
田畑共に、良かれと思ってやったことが、本当は(悪くなる)原因で、失敗される方も多いものです。
個人的には、田んぼでは、無肥料で育つチャンス(タイミング)になってから無肥料栽培に切り替えた方が無難だと思っております。
まだそのタイミング出ない場合は、それまでは、無肥料でも稲が良く育つ環境づくりをした方が無難だと思っております。参考にしてみてください。
無肥料栽培で持続可能なタイミング
・稲の力が最大限にでる育苗
・稲の根がしっかり張れる水管理
・田んぼに草が生えにくくなる環境づくり
・生えてしまった草を抑える技術
・無肥料栽培で力を発揮する品種
・無農薬でよく育つ選抜された自家採種の種子
・無肥料でもしっかり稲が育つ土づくり(育土)
稲作はとてもシンプルですが、奥が深いので、
原因と結果はわかりやすいものです。
よい結果を産む原因を増やし、
悪い結果をもたらす原因を排除できるか。
その田んぼと風土とご自身に合った方法が見つかるといいですね。
そうですね。
1)田んぼと畑では全く違います。
というのは、田んぼは水を張り、酸素があまりない還元の世界。
畑は、如何に根に酸素を与え、保湿できるかと全く逆の世界だからです。
田んぼの場合も畑の場合もいずれも有機物が如何に土にするのかが大切です。有機物はそれらのものが土の中で悪さをすることもあるので、完熟+土に馴染むまで夏場2週間、冬場1カ月馴染ませるのが基本になります。
田んぼは、水を張るので(酸欠になるので)、春前に如何にワラなど未熟な有機物を土に還すかがポイントです。
2)ピートモスは稲作の育苗には使いますが、田んぼに大量に入れることはめったにありません。
というのもピートモスは乾燥した未熟な水苔類などの総称で、いったん乾燥してしまったものは、水に馴染みにくく、かなり丁寧にあらかじめ水分調整をしてからでないと畑(ブルーベリーなど)でも水と分離してしまうからです。
また、水を吸うようになったピートモスは、畑で水持ちをよくすることからも、田んぼで大量につかうことによって、水はけが悪くなりすぎると問題がでます。
3)無農薬栽培で一番後々トラブルになるのは、身近にある無料の有機物に安易に手を出して、田畑と相性が悪いのに使用してしまい、後々悪影響をもたらすことです。
自然栽培にもいろいろありますが、自然栽培の基本は、稲がしっかり根を張れることにあります。そのために、ワラは分解にしくいので全部持ち出す方や、無肥料にする方も多いです。
田んぼは、水を張る特性から、よほど水持ちが悪すぎる砂地の田んぼや、ピートモスを前もって完熟堆肥などに入れて発酵させて分解を促進させて、田んぼの状況を見ながらでないと安易に使用するのは、懸念されます。
それよりも、田植えするまでに、如何に草の発芽スイッチをオフにしておく、稲のやる気になる状態にしておくなど基本的なことがとても大切です。
これは入れても肥培効果は期待出来ませんか。よろしくお願いします。
だいたいが思い込みの栽培方法です。
なぜそれが定番になったか、理由の経緯が想像できるようになると、オリジナルの定番ができるようになっていく傾向があります。
自然を学ぶことは楽しいものです。
エダマメは移植を嫌い、初生葉展開期が移植適期と考えていたので大苗は全く考えていませんでしたが、この手がありました。
これから、錦秋など、感光性のエダマメを播種する予定なので、それまでに高畝にして、トラップをしかけたりして大切に育ててみたいと思います。
(お返事のコメントは、いただかなくても構いません)
そうですか。ナメクジですか。
確かに畑によって、できやすいもの不可能に近いものはありますので、難しい質問ですね。
ブログも拝見し、いろいろ実験していて勉強になりました。
もし私であれば、ナメクジが発生しにくい環境にした上で、ナメクジ対策をして、何回か試した後、駄目ならそこで育つ他の野菜を育てると思います。
例えば、
1)高畝にして、風通しを良くし、日が良く当たるようにする。
2)前作に、エンバク、クロタラリア、セスバニア、ソルゴーなど夏の緑肥作物の種を混播し、土に穴を空けて排水性を高める。そして、秋にエンバク、ライムギを混播しエダマメが育ちやすい土を育土する。
3)早生のエダマメを大苗に育てる。(ポット9cmで本葉3~4枚まで育ててから定植。
4)定植したら、1m離して飲み残しのビール缶を雨がはいらないように設置し、ナメクジトラップを仕掛ける。
5)草マルチの代わりに、土寄せする。
そんな感じにしてみながら、幾層にも対策を重ねて様子を見てみると思います。
後はやってみて、自然観察しながら工夫します。
万策尽き果てて、竹内さんにもとを訪ねました。
粘土質の休耕田でエダマメを栽培しても、ほぼ全滅します。
まず、ナメクジが子葉を食べます。
海藻等を使ったり、育苗後の定植によりナメクジ被害を逃れても、その後、虫だったり、原因不明で枯れていきます。
同時期に播種し、家の裏に定植したエダマメはすくすく育っています。
長い間、この休耕田を無農薬栽培している方は、「畑によって出来るもの、出来ないものがある。」とおっしゃっています。
竹内さんならどうされますか。
自然栽培への過渡期ということで、もう少し我慢でしょうか。
そうですね。
一番大切なのは、生命を育む場を調えてあげる手助けをし、その後野菜を中心に勝手に自然循環ができていくのを支える手助けをすることです。
森を観ながら、樹も観る姿勢と実践での失敗からの学びが一番ですので、私の言ったことは細かい話なのであまり気にしないでくださいね。
たつきさんへ
そうですか。是非やってみて、何かあればコメントください。
緑肥作物は、政治でいえば官僚のような存在です。どんなに優秀でも、政治家(園芸家)の手腕が問われます。
上手に緑肥作物を活かした栽培に心をくだいてくださいね。
「これなら出来る自然菜園」のサポートされる、嬉しい記事です。
今年は緑肥:野菜が1:1になるくらい、緑肥を増やして、まずは土を育てたいと思います。
本で紹介されている、2月の、緑肥混播の準備が出来ました。土がどう変わるか楽しみです。
引き続き、竹内さんの経過レポートも楽しみにしています。
土壌分析をお願いできる機関があること知りませんでした。
御教授ありがとうございます。
今年から再来年までは、粘土に向いた作物を植えつつ、
微生物を増やす土作りをテーマに野良仕事に勤しみます。
そうですね。勉強になります。
あくまで、目安として簡易土壌分析を役立ててみてください。
微生物が増え、安定してきたら腐植も増え、団粒構造も発達し、水はけ、水持ち、肥持ちも良くなります。
いかに、微生物増やし、それを栽培と結びつけて土を育てていくのかが重要です。
理由は、ECはイオン化している肥料分を測っているので、微生物に蓄えられている肥料分が計れるていない場合があるからです(特に簡易計)
今回の場合、土壌微生物バランスが完全に狂っている(慣行栽培と耕運で微生物が少ない)ので、微生物を増やす土作りから始めてみてはどうでしょうか?
土壌に腐植やカルボキシル基を増やせば、微生物が安定しますし。
ちなみに、腐植やカルボキシル基関係のpH調整は、検査方法によっては出ない可能性が考えられます。
腐植は、リグニンやタンパク質
カルボキシル基は、有機酸
を使えばいいと思います。