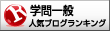今回、TOEFLの受験のための勉強をしてつくづく思いましたが、論文を読んだり書いたりするための英語については自分としてもこもらない程度の英語力はあると思っていたのですが、反面、一歩専門から離れると自分のボキャブラリーってものすごく少ないですね。
TOEFLのキクタン(頻出編)というので英単語を学び直しましたが、やはり科学技術系で使わない単語はほとんど知りませんでしたし、科学技術系でも普段使わないような単語は知らないものが多く、この年になって新たな発見でした。
ということで、TOEFLキクタン(頻出編)についてはある程度マスターしたので、次は別のキクタンを使ってボキャブラリーの増強を図ろうと思っています。
車通勤なので、とりあえず音声を流しておくだけである程度は単語を覚えることができるので、それほど負担にならないのもいいところです。
TOEFLの試験はもう受けることはないと思いますが、もしかするとTOEICの試験に関しては高専の教員も定期的な受験が必要になってくるかもしれないので、その時にあまりに悪い点数を取っても恥ずかしいので、そういう意味でも単語量を増やしておくのはいいことですね。
考えてみると、高専の学生の時に編入試験のために英語の勉強を始めてしましたが、その際には英単語ターゲット1900という、高校生が覚える基本的な単語をまず覚え、その後は編入試験に工学系の英語が多いということで工学系の英語に注力しました。私のボキャブラリーもその流れで工学系に偏っていますので、幅を持たせる意味でも別の分野の英単語を覚えるというのは楽しいですね。
ただ、TOEFLの試験でも文学の問題が出てきまして、内容的には50%分かるかどうかという感じだったので、単語だけ覚えても内容を知らないと英語を聞いても全く分からない感じです。ま、これは日本語も同じで、今の知識量で文学部の講義を聞いてもちんぷんかんぷんなので、英語の問題ではないのかもしれませんが。
久しぶりに英語の勉強を始めましたが、知らなかったことが自分の頭の中に定着してくるという感覚はいいものですね。
もしも学生の皆さんで編入試験の勉強を始めようという学生がいましたら、しばらくしたらこの感覚を感じて楽しくなると思いますので、ぜひ、早めに始めてもらいたいですね。