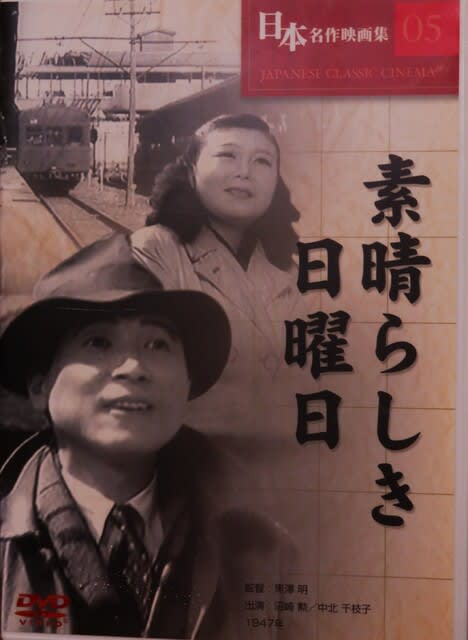世界文学全集でよく目にした「ジェーンエア」だけど、読んだことも観たこともない。日中は炎暑のさなかだったので、扇風機を浴びながらそのDVDのお世話になる。小説家のシャーロット・ブロンテが『ジェーン・エア』を発表したのは、1847年。産業革命が進行し、イギリスが「世界の工場」とか「世界の銀行」と言われたヴィクトリア朝時代である。イタリア・フランスに遅れをとっていたイギリスが世界のNo.1となったころが舞台となる。
 イギリスの産業革命は資本主義の急速な進行を産み出し、街には労働者階級が集まり、貧富の格差が増大するとともに、貴族の従来の基盤が崩れていく時代背景が読み取れる。そんな中、孤児院で育ったヒロインは既成のルールを飛び出し、自分の意思や考え方を少女時代から固辞していく。そこに、当時の女性の自立を貫く困難さがよく出ている。したがって、著者の当初の小説のペンネームも男性名だった。
イギリスの産業革命は資本主義の急速な進行を産み出し、街には労働者階級が集まり、貧富の格差が増大するとともに、貴族の従来の基盤が崩れていく時代背景が読み取れる。そんな中、孤児院で育ったヒロインは既成のルールを飛び出し、自分の意思や考え方を少女時代から固辞していく。そこに、当時の女性の自立を貫く困難さがよく出ている。したがって、著者の当初の小説のペンネームも男性名だった。

いっぽう、精神障碍者の妻を持つロチェスター家の貴族の夫がもう一人の主人公だ。しかし、彼の複雑でミステリアスな性格に最後までハラハラする。それに翻弄されるヒロインだったが、その原因を踏まえた知性を持つ女性として心ひそかに彼に思いを寄せていく主人公の心の揺らぎを重厚に描いている。ロチェスター家の貴族は、オーソン・ウェルズが演じた。彼は監督として「市民ケーン」、俳優としては「第三の男」主演が有名。
 19世紀中葉の大英帝国の光と影をバックとしながら、作者が経験した学校の不衛生でいじめ・校則への告発は現代でも通用する普遍性がある。また、女性の自立を阻む社会や労働、さらには精神障碍者への偏見なども現代性がある。
19世紀中葉の大英帝国の光と影をバックとしながら、作者が経験した学校の不衛生でいじめ・校則への告発は現代でも通用する普遍性がある。また、女性の自立を阻む社会や労働、さらには精神障碍者への偏見なども現代性がある。
当時、イギリスを覆った霧の街は大英帝国の光と影の矛盾が随所に出てくる。繁栄の副産物として、「ドラキュラ」「ジキル博士とハイド氏」らの怪物たちの登場をはじめ、実際にあった「切り裂きジャック」事件などが社会の不安感を煽る。規律やモラルを重視する従来の社会・学校の体制との矛盾がいよいよ桎梏となっていく。ロチェスター家の主人の怪しさやヒロインの自立的な生き方の貫徹が、本映画の主軸となり、時代背景となってもいる。まさに、世界文学に成長していく中身を作品は用意していったというわけだ。













 四代目市川小団次(1812~1866)が演じた鬼薊清吉が見上げた空に何かを持った野鳥が飛んでいる。「十六夜」の小袖の一部を野鳥が運び清吉を励ます場面かもしれない。象徴的な場面なのだろうが、その意味は実際に観劇していないのでわからない。
四代目市川小団次(1812~1866)が演じた鬼薊清吉が見上げた空に何かを持った野鳥が飛んでいる。「十六夜」の小袖の一部を野鳥が運び清吉を励ます場面かもしれない。象徴的な場面なのだろうが、その意味は実際に観劇していないのでわからない。
 三代目豊国の画号はいっぱいあるが、この絵の「紀好豊国」というのは聞いたことがない。ひょっとすると、破天荒な「奇行国芳」を意識したのかもしれないと、勝手に想像している。また、彫刻師は「横川彫竹」と、個人名を明示しているのは珍しい。本名は「横川竹二郎」だが、当時の一流の彫師だった。とくに、髪の毛の生え際やほつれ毛は世界的にも評価が高い。今回の絵でももちろんだが、難しい刺青の表現は超絶技巧ではないかと思う。
三代目豊国の画号はいっぱいあるが、この絵の「紀好豊国」というのは聞いたことがない。ひょっとすると、破天荒な「奇行国芳」を意識したのかもしれないと、勝手に想像している。また、彫刻師は「横川彫竹」と、個人名を明示しているのは珍しい。本名は「横川竹二郎」だが、当時の一流の彫師だった。とくに、髪の毛の生え際やほつれ毛は世界的にも評価が高い。今回の絵でももちろんだが、難しい刺青の表現は超絶技巧ではないかと思う。
 版元(保永堂)の竹内孫八は、広重の「東海道53次」を出版したことで大手版元となった。版元の所在地は、江戸霊岸島塩町だったので、「霊鹽」が印字されている。今回注目したのは、その役者絵の隅に、「仙女香」という粉白粉のCMがあることだった。京橋で販売された「仙女香」は、三世瀬川菊之丞の俳名「仙女」にちなんで命名され、浮世絵とタイアップして宣伝を行った最初の商品だった。
版元(保永堂)の竹内孫八は、広重の「東海道53次」を出版したことで大手版元となった。版元の所在地は、江戸霊岸島塩町だったので、「霊鹽」が印字されている。今回注目したのは、その役者絵の隅に、「仙女香」という粉白粉のCMがあることだった。京橋で販売された「仙女香」は、三世瀬川菊之丞の俳名「仙女」にちなんで命名され、浮世絵とタイアップして宣伝を行った最初の商品だった。
 菊五郎の背景は「白髭神社」のようで、
菊五郎の背景は「白髭神社」のようで、








 役者絵の着物の両脇あたりに、「大」の漢字を三点つなげた「大和屋」の家紋がさりげなく描かれている。それで、当時の庶民はこの「女形」は三代目坂東三津五郎であることを了承する。この頃から、坂東家は女形が十八番となっていく。
役者絵の着物の両脇あたりに、「大」の漢字を三点つなげた「大和屋」の家紋がさりげなく描かれている。それで、当時の庶民はこの「女形」は三代目坂東三津五郎であることを了承する。この頃から、坂東家は女形が十八番となっていく。 この坂東三津五郎の着物の柄は、流水に流れ散っていく桜のデザインが凝っていると同時に艶やかだ。鹿の子模様もちらりと内輪に散らしている。さらには、黒い帯にはいろいろな家紋のようなロゴを6個も描いている。ひょっとすると判じ絵のような暗示的なデザインかといろいろ考えてみたが、結論は出ず。なぜこの模様なのか、意味があるはずだろうがわからない。
この坂東三津五郎の着物の柄は、流水に流れ散っていく桜のデザインが凝っていると同時に艶やかだ。鹿の子模様もちらりと内輪に散らしている。さらには、黒い帯にはいろいろな家紋のようなロゴを6個も描いている。ひょっとすると判じ絵のような暗示的なデザインかといろいろ考えてみたが、結論は出ず。なぜこの模様なのか、意味があるはずだろうがわからない。 なお、版元は、川口屋宇兵衛(福川堂)。検閲印の「極」は1個のみで、文化文政時代であることが判る。寛政の改革で蔦屋重三郎や山東京伝が逮捕されて間もなく、町人の経済力から町人文化が活発になることで、江戸歌舞伎も頂点に達する。そのことで、女流の演奏家・アーティストも多く登場していく。
なお、版元は、川口屋宇兵衛(福川堂)。検閲印の「極」は1個のみで、文化文政時代であることが判る。寛政の改革で蔦屋重三郎や山東京伝が逮捕されて間もなく、町人の経済力から町人文化が活発になることで、江戸歌舞伎も頂点に達する。そのことで、女流の演奏家・アーティストも多く登場していく。