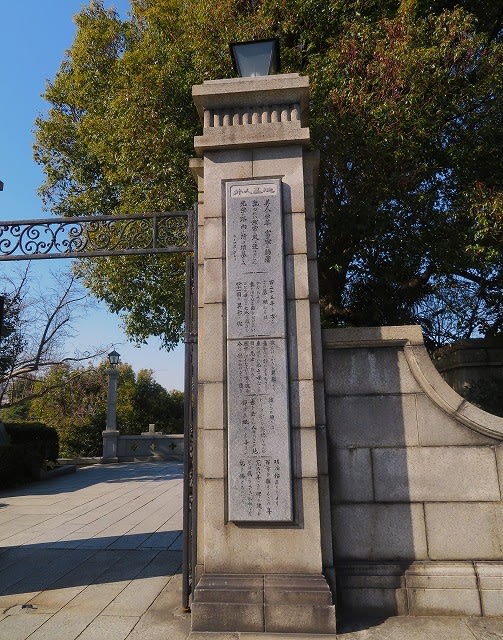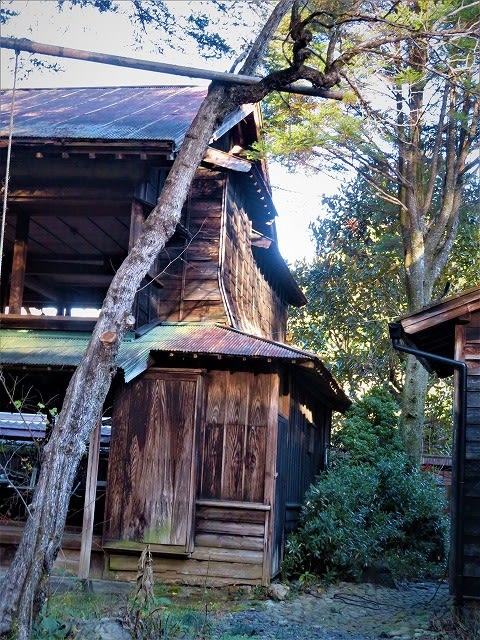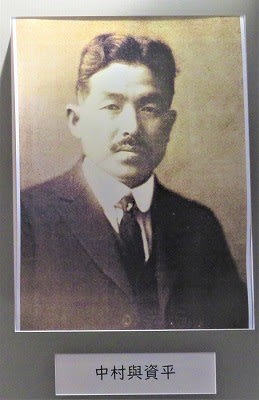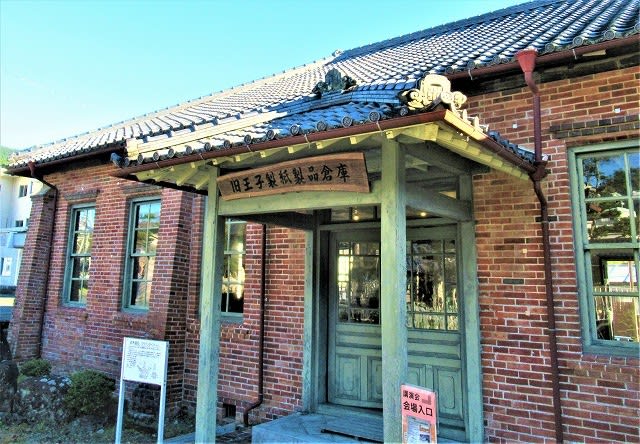本堂の屋根にあってもおかしくない立派な鬼瓦が山門にあった。「鬼瓦」はもともと厄除けの飾りとしての瓦だが、同時に雨漏りしやすい棟の先端を補強した実用的な防水機能を担う。この瓦のてっぺんに巻物のお経の形をした「経の巻」が三巻乗せてあった。もともとは宮中で使用され、寺社のみが使用を許されていたものだ。
「経の巻」の下にある2本の平行線は「綾筋」というが、その由来を調べたが記述したものはほとんどなかった。鬼面の抽象的なものという説明がひとつだけあったがよくわからない。私見では京都でよく見る土塀のラインで見られるように皇室に関係してるよというメッセージとみた。その「綾筋」の下には菊花の寺紋があったが、それも皇室に関係があるように思われる。とにかく、鬼瓦のそれぞれの名称にはほとんどがそもそもの意味がスルーしている。建築家や瓦職人の説明は平板になっている気がする。

庭に片隅に置いてあった鬼瓦は長楽寺のものなのだろうか。鬼瓦にも雄雌があるそうだ。口を閉じているのはメスだそうだ。鬼瓦制作の基本は、職人による個人技なので同じデザインの瓦を探すのは難しい。瓦が新しいので江戸以降のものに違いない。かなりデフォルメされていて個性的だ。

庭には県指定文化財となった梵鐘が静かに置かれていた。静岡県内では二番目に古いそうだ。というのも、梵鐘の銘に、鎌倉時代後期の嘉元3年(1305年)に作られた由が刻まれている。

山門の棟端の瓦には、「松に鷹」の飾り瓦が見える。「松」は、千年の緑を保ち、無病・長寿を祈願するとともに、「鷹」は鋭い爪で幸運をつかみ、邪気を追い払う意味があり、両方で最強の縁起物を置く。隅先の瓦には「菊花文」の軒瓦が堂々と使われている。

さて、講演の会場は本堂の広間だった。この廊下から庭を鑑賞できる。講師の山本義孝さんは、「カミ」とはそれぞれ火・水を表し、特定の名をもたないミタマを言い、「神」とは名前や人格をもち社や祠で祀られるという。また、「ホトケ」とは死霊や霊魂など抽象的なものを表し、「仏」とは如来・菩薩などの具体的な名前があると紹介する。

本図は、山岳宗教の権威・鈴木正崇氏によるとのことだが、あらためてこれだけの意味合いがあるのを初めて知る。また、寺には、「山号(サンゴウ)」・「院号」「寺号」の三つがある。「山号」は、寺が山に創建された例が多いことと同名の寺が多くなってきたので、その所在地の山の名の「姓」をつけた。禅宗が広まるのを機に広まり、それ以前の寺には「山号」がない寺もある。「院号」は地名、「寺号」は「名」を表す、というが…。

 長楽寺の「山号」は「光岩山」である。古代の日本人は自然が作った巨大な岩に畏怖し信仰の場としていた。そこに、天台僧の経典埋納や山伏の祭祀・修行などがあり、12世紀ごろになって観音堂や奥の院が形成される。山本氏は、丹念なフィールドワークの結果、僧侶と山伏らとの祭祀のやり方の違いを明らかにし、「光岩」の巨大な一枚岩の下方に左右対称の自然石による石組み・祭壇を確認している。そこに「結界」を示す石が配列されているという。長楽寺の歴史は自然崇拝・アニミズムに始まり「神仏習合」の経過をたどっている。次回6月の講義が待たれる。
長楽寺の「山号」は「光岩山」である。古代の日本人は自然が作った巨大な岩に畏怖し信仰の場としていた。そこに、天台僧の経典埋納や山伏の祭祀・修行などがあり、12世紀ごろになって観音堂や奥の院が形成される。山本氏は、丹念なフィールドワークの結果、僧侶と山伏らとの祭祀のやり方の違いを明らかにし、「光岩」の巨大な一枚岩の下方に左右対称の自然石による石組み・祭壇を確認している。そこに「結界」を示す石が配列されているという。長楽寺の歴史は自然崇拝・アニミズムに始まり「神仏習合」の経過をたどっている。次回6月の講義が待たれる。