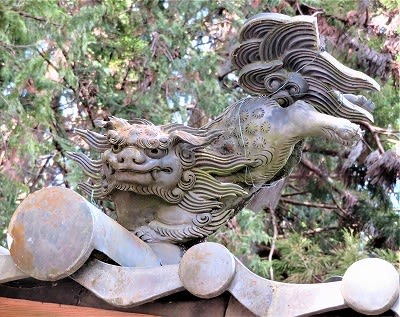久しぶりの街中にでかけたとき、ほんの少しの空き時間ができたので近くの鳥羽山城に行くことになった。以前、散策会で訪れたこともあったが山城の地味な魅力はわからなかったころだ。時間がないのでまずは山城の玄関である「大手道」から一気に突入する。この先に本丸がある。
桜と紅葉の名所でもあるここは今ではハイキングにも人気があり公園にもなっている。久しぶりのしっとりとした雨に濡れた階段には赤い落葉の絨毯が迎えてくれた。家康が隣の武田軍が居座る「二俣城」を奪還・攻略するためここに本陣を築いたところでもある。

ところどころに「野面積み」の石垣が見られる。山城ファンにとっては城の遺構がたまらないほどの箇所が発見できそうだが、不勉強のオイラには足早にスルーするしかない。浜松市も並みなみならぬ調査で発掘と保存を手掛けたのがわかる。それほどきれいに整備されている。
二俣城は甲斐を南下する武田軍と駿府側の防御の徳川軍との軍事的拠点だったが、この鳥羽山城は城主や家老の住まいとしても利用されたようだ。また同時に、迎賓館のような外交施設だったらしく、本丸のそばには枯山水の庭園もあった。その遺構の存在は山城としては稀であるという。そして天目茶碗などが発掘されていることからもそれはうかがえる。

天守閣らしき建物からの眺望は見事だった。目の前に天竜川が悠々と流れており、遠くは浜松の街並みを展望できる。この地域の「二俣」は、山間部と平野を結ぶ流通の拠点でもあった。とくに山林運搬の基地として昭和の時代まで栄えていた。二俣を歩くと古風な蔵にたびたび出会う。芸者をあげてどんちゃん騒ぎしたという山林地主や関係者の話もよく耳にする。今は往時の勢いがなく商店街もシャッター通りとなってしまっている。

二俣は同時に信仰の交通路にあった。秋葉神社や近くの光明寺への道すがらには、貴重な文化財の跡があるのに、なかなか発掘・活用されていない。地域の宝を共有・発掘していく人材がいないのだろうか。もったいないことだ。オイラの住んでいる中山間地にはこうした名所旧跡なるものは皆無と言っていいのに。そんなことをブツブツ言いながら城跡を駆け巡ったが、つぎはもう少し時間をかけて「国破れて山河在り」や栄華のあれこれを満喫してみたいものだ。



















 (愛知県美術館から)
(愛知県美術館から)








 洞門内は蛍光灯がともっており壁もクリーム色にしてあり明るかった。もともとはレンガ造りのようだ。想像以上に距離がある。高さは2.3mというがもっと高いように見える。出口の光をめざす。このトンネルのおかげで浜松との交通とがスムーズになる。太平洋戦争中は、通行止めとなり戦車壕に転用された。
洞門内は蛍光灯がともっており壁もクリーム色にしてあり明るかった。もともとはレンガ造りのようだ。想像以上に距離がある。高さは2.3mというがもっと高いように見える。出口の光をめざす。このトンネルのおかげで浜松との交通とがスムーズになる。太平洋戦争中は、通行止めとなり戦車壕に転用された。