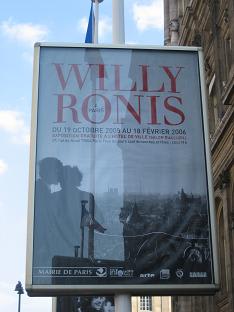11月2日から、パリ日本文化会館で『成瀬巳喜男監督特集』が始まっています。

(フランスの映画専門誌『カイエ・デュ・シネマ』で紹介された成瀬特集です)
上映されるのは31作品。学生時代、岩波ホールや燃えてしまった京橋のフィルムセンターで溝口や黒澤はよく観たのですが、成瀬は『めし』・『浮き雲』・『山の音』くらいしか観ていません。今回は是非できるだけ多くの作品を、パリで観たいと思っています。
まず最初に観てきたのが、『夜ごとの夢』。成瀬初期の傑作といわれている1933年の作品です。

玄関受付に、ポスターや上映時間などの案内が出ています。

上映会場のある地下3階のホールには、かつてフランスで上映された日本映画のポスターがパネル展示されていました。

会場は、大ホール。上映が始まると、スクリーンの下に細長いサブ・スクリーンのようなものが現れました。この作品、無声映画なのですが、今回の上映用の素材は英語バージョン。日本語字幕の上に、英語訳が大きく出ているので、フランス語訳はサブスクリーンのほうに控えめに出すことになったようです。でも、きちんと読めます。実は一番読みにくいのが、日本語字幕! 細く読みにくい書体の上、黒バックに茶色ですから、見難い。しかもその下半分くらいが、白抜きのはっきりとした英語に覆われていますから、ついつい英語を読むことになってしまいます。でも、十分にストーリーは分かります、問題なしです。
観に来ていたのは9割方フランス人。若干年配の方が多かったですね。マンガやアニメを通して日本への関心をもっている若い人が多いのですが、昔の映画ともなると、興味をもつ層も世代が上になってしまうようです。でも、“やるせ泣き男”とも呼ばれ、庶民の心の機微を紡ぎだすのに秀でた成瀬監督。その作品に描かれた庶民の歴史があってこその今日の日本です。日本に関心のあるフランスの若い人たちにもぜひ観てほしいと思います。

これがプログラムです。12月2日まで、断続的に上映されます。14時、16時半、19時半の1日三回上映で、それぞれ異なった作品を上映しています。
↓アクセスランキングへ「励みの一票」をお願いします!
日記アクセスランキング

(フランスの映画専門誌『カイエ・デュ・シネマ』で紹介された成瀬特集です)
上映されるのは31作品。学生時代、岩波ホールや燃えてしまった京橋のフィルムセンターで溝口や黒澤はよく観たのですが、成瀬は『めし』・『浮き雲』・『山の音』くらいしか観ていません。今回は是非できるだけ多くの作品を、パリで観たいと思っています。
まず最初に観てきたのが、『夜ごとの夢』。成瀬初期の傑作といわれている1933年の作品です。

玄関受付に、ポスターや上映時間などの案内が出ています。

上映会場のある地下3階のホールには、かつてフランスで上映された日本映画のポスターがパネル展示されていました。

会場は、大ホール。上映が始まると、スクリーンの下に細長いサブ・スクリーンのようなものが現れました。この作品、無声映画なのですが、今回の上映用の素材は英語バージョン。日本語字幕の上に、英語訳が大きく出ているので、フランス語訳はサブスクリーンのほうに控えめに出すことになったようです。でも、きちんと読めます。実は一番読みにくいのが、日本語字幕! 細く読みにくい書体の上、黒バックに茶色ですから、見難い。しかもその下半分くらいが、白抜きのはっきりとした英語に覆われていますから、ついつい英語を読むことになってしまいます。でも、十分にストーリーは分かります、問題なしです。
観に来ていたのは9割方フランス人。若干年配の方が多かったですね。マンガやアニメを通して日本への関心をもっている若い人が多いのですが、昔の映画ともなると、興味をもつ層も世代が上になってしまうようです。でも、“やるせ泣き男”とも呼ばれ、庶民の心の機微を紡ぎだすのに秀でた成瀬監督。その作品に描かれた庶民の歴史があってこその今日の日本です。日本に関心のあるフランスの若い人たちにもぜひ観てほしいと思います。

これがプログラムです。12月2日まで、断続的に上映されます。14時、16時半、19時半の1日三回上映で、それぞれ異なった作品を上映しています。
↓アクセスランキングへ「励みの一票」をお願いします!
日記アクセスランキング