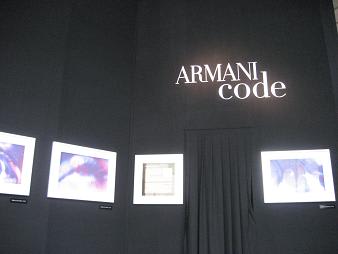国立図書館のリシュリュー館で、“La Photographie Humaniste 1945-1968”(ユマニストの写真・1945~68年展)という展示会が行われています。

以前ご紹介したことのある写真家たちの作品が並んでいます。ドワノー(Doisneau)、ロニス(Ronis)、ブラッサイ(Brassai)、ニエプス(Niepce)、ブレッソン(Bresson)、そしてウェイス(Weiss)、ボヴィス(Bovis)・・・第二次大戦の前後から70年代、80年代までに活躍した写真家たち。パリとそこに生きる人々を愛情いっぱいにレンズで捉えたカメラマンたちで、ユマニスト派(l’ecole humaniste)といわれています。

会場入り口ですが、作品にぴったりの雰囲気で、期待させてくれます。

細長いスペースにうまく展示されています。ぐる~っと一周すると全部見れるようになっています。

説明にも記されているように、古きよき時代へのノスタルジーと来たるべき新しい時代への楽観的な気持ちが一体となった戦後のパリ、そこに生きる市井の人々をモノクロで捉えた写真の数々です。

右は、逆光の中を駆け出した男性、有名なWeissの1点です。そしてポスターにも使われている霧の煙る早朝のパリを職場へ向かう人々。

これは、ドワノーの写真を基に、『枯葉』などでおなじみの詩人・ジャック・プレヴェールが作ったコラージュです。人の頭がみな奇怪な動物になっています。フランスの芸術史を振り返ると、いつの時代にも、同時代の芸術家同士のジャンルを越えた交流が盛んだったことに驚かされます。画家、作家、音楽家、写真家・・・日本ではコラボなどといって共同制作がちょっと前から流行っているようですが、フランスではロマン派をはじめ昔から盛んであり、今も続いているようです。

ドワノーの写真でパリを特集した“Life”(ライフ誌)です。戦後に出版された号ですが、見出しがいいですね。“In Paris, young lovers kiss wherever they want to and nobody seems to care”(パリでは、若い恋人たちはどこであろうとキスをし、誰も気に留めないようだ)・・・アメリカ人から見ても、やはりこう思えるようです。フランスの伝統ですね。

ここには、アンリ・カルティエ=ブレッソンの言葉が記されています。“La photographie, une petite arme pour changer le monde”(写真、世界を変えるための小さな武器)・・・写真、それ自体は小さいけれど、世界を変えることができる。
会場に展示されている写真を眺めていると、世界を変えるまでは無理にしろ、見た人にほんの少しでも感動を与えられるような写真を撮りたいと思えてきます。
↓「励みの一票」をお願いします!
日記アクセスランキング

以前ご紹介したことのある写真家たちの作品が並んでいます。ドワノー(Doisneau)、ロニス(Ronis)、ブラッサイ(Brassai)、ニエプス(Niepce)、ブレッソン(Bresson)、そしてウェイス(Weiss)、ボヴィス(Bovis)・・・第二次大戦の前後から70年代、80年代までに活躍した写真家たち。パリとそこに生きる人々を愛情いっぱいにレンズで捉えたカメラマンたちで、ユマニスト派(l’ecole humaniste)といわれています。

会場入り口ですが、作品にぴったりの雰囲気で、期待させてくれます。

細長いスペースにうまく展示されています。ぐる~っと一周すると全部見れるようになっています。

説明にも記されているように、古きよき時代へのノスタルジーと来たるべき新しい時代への楽観的な気持ちが一体となった戦後のパリ、そこに生きる市井の人々をモノクロで捉えた写真の数々です。

右は、逆光の中を駆け出した男性、有名なWeissの1点です。そしてポスターにも使われている霧の煙る早朝のパリを職場へ向かう人々。

これは、ドワノーの写真を基に、『枯葉』などでおなじみの詩人・ジャック・プレヴェールが作ったコラージュです。人の頭がみな奇怪な動物になっています。フランスの芸術史を振り返ると、いつの時代にも、同時代の芸術家同士のジャンルを越えた交流が盛んだったことに驚かされます。画家、作家、音楽家、写真家・・・日本ではコラボなどといって共同制作がちょっと前から流行っているようですが、フランスではロマン派をはじめ昔から盛んであり、今も続いているようです。

ドワノーの写真でパリを特集した“Life”(ライフ誌)です。戦後に出版された号ですが、見出しがいいですね。“In Paris, young lovers kiss wherever they want to and nobody seems to care”(パリでは、若い恋人たちはどこであろうとキスをし、誰も気に留めないようだ)・・・アメリカ人から見ても、やはりこう思えるようです。フランスの伝統ですね。

ここには、アンリ・カルティエ=ブレッソンの言葉が記されています。“La photographie, une petite arme pour changer le monde”(写真、世界を変えるための小さな武器)・・・写真、それ自体は小さいけれど、世界を変えることができる。
会場に展示されている写真を眺めていると、世界を変えるまでは無理にしろ、見た人にほんの少しでも感動を与えられるような写真を撮りたいと思えてきます。
↓「励みの一票」をお願いします!
日記アクセスランキング