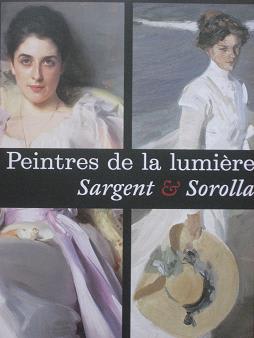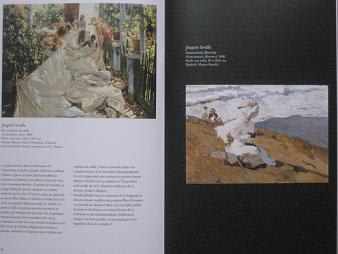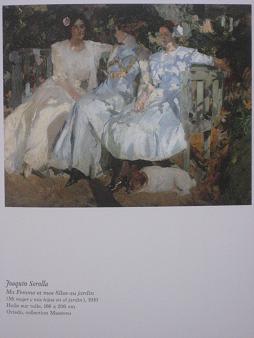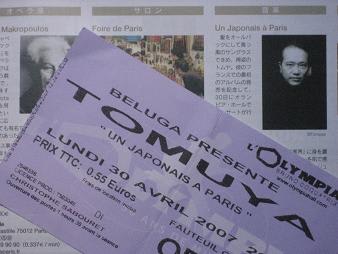21世紀の今でも、奴隷がいる・・・そんなショッキングな写真展が行われています。

このイベントに気付いたのは、メトロの駅に貼ってある大型ポスター。“Esclaves au Paradis~L'esclavage contemporain en Republique Dominicaine”(天国の奴隷たち~ドミニカ共和国における今日の奴隷制度)。地上の楽園としてヨーロッパの観光客に人気のカリブ海。そこに浮かぶイスパニョーラ島。1492年にコロンブスが到着したこの島の東側三分の二を占めるのがドミニカ共和国。そして残りの西側がハイチ共和国。この島で、今でも奴隷制度を髣髴とさせる状況が続いている・・・

会場は、かつての工場を改修したようなアート・スペース。主催には、人権擁護団体・アムネスティ・インターナショナルやパリ市、リベラシオン紙などが名を連ねています。

写真の点数はそれほど多くはないのですが、タイトル・スローガンにもなっている「血と砂糖と汗と」に現されたサトウキビ農場労働者の悲惨な暮らしぶりが見事に写し出されています。奴隷のような状況に置かれているのは、ドミニカ共和国のサトウキビ農場で働くハイチ出身者・・・。
このカリブ海の島にコロンブス一行がやってきたときは、先住民族が平和に暮らしていました。しかし、この島で金鉱が発見されるや、スペイン人たちは先住民たちを金の採掘で酷使。あまりの酷使に、彼らはほぼ死滅してしまいました。そこで、必要な労働力として、アフリカから多くの黒人奴隷をつれてくる。金の生産が減ると、サトウキビやコーヒーなどのプランテーションで酷使する。その間に、スペイン領のこの島は、西側がフランス領になったり、すべてが仏領になったり、再び東側がスペイン領に戻ったりしましたが、19世紀初頭、フランス領がハイチ共和国として独立。世界初の黒人による共和国で、またラテン・アメリカ最初の独立国でした。こうした快挙にもかかわらず、このハイチは島の東にあるスペイン領を占領したり、南北に分かれての内戦があったり、非常に不安定な状況だったようです。東側の地域も、ハイチの支配の後はスペイン領に戻り、その後アメリカの占領を経て、独立。このように、元は一つの島であったところに、アフリカの人たちが奴隷として連れてこられ、しかもスペインとフランスの力関係で境界線が引かれ、その後独立しても、反目しあう二カ国関係になってしまったようです。
また、ハイチは独立の際、フランス人入植者たちの農園などを接収しましたが、その補償と引き換えに独立を認めてもらったため、後々までその莫大な補償の支払いが大きな足枷となってしまいました。その支払いのため、国民経済が一向によくならない、その不満から政治が不安定になり、独裁、内紛、暗殺などが続き、国は疲弊しきって、世界最貧国の一つに数えられています。

(上の地図、左のクリーム色の部分がハイチ、右側グリーン系の部分がドミニカ)
ドミニカ共和国として独立した東側のほうが、状況はまだましなようで、その結果、職を求めて多くのハイチ人がドミニカ共和国へ出稼ぎに。そのまま居つく人もいますが、その待遇たるや、まさに奴隷並み。かつて互いに敵同士で闘った歴史もあり、ドミニカ人のハイチ人に対する扱いは、かつての奴隷を髣髴とさせるものだそうです。
プランテーションで1日15時間働き、サトウキビを1トン収穫して得られる賃金が1ユーロちょっと(160~170円)。体格がよく、慣れている人でも、1.5トンの収穫、1.6ユーロの賃金が限度だそうです。しかも払われるのは兌換券のようなもので、それで買い物をすると手数料まで引かれてしまうとか。

このような収入では食べて行けず、子どもたちも働くことに。しかし、基本的には子どもの就労は違法なため、支払われる額は、非常に少ないものに。もちろん、衛生・医療制度などは、あってなきに等しい状態。また長年ドミニカで暮らしていても、正式な滞在許可証を出してもらえず、いわば不法滞在状況。その結果、子どもたちには就学の機会も与えられない。

アムネスティがこの問題を告発するレポートを公にし、また今回の会場でも配布しています。名前だけはよくニュース等で聞いたり、見たりしていましたが、そのレポートを手にするのは初めてです。今年の4月に出されたもので、フランス語版はA4・32ページ。その中には、ハイチ人への聞き取り調査の抜粋も載っていますが、まるで犬並みの扱いだとか、上手い口車に乗せられてここに来たら、待っていたのは家畜のようにこき使われる日々だったとか、現状を訴える声が多く紹介されています。
こうした現状に、かつての宗主国、フランスとスペインは何か策を講じているのでしょうか。それとも、見て見ぬふりなのでしょうか・・・ハイチの惨状は、数年まえ日本のテレビでも見た記憶があります。しかし、ドミニカへ働きに行った人たちの奴隷並みの生活は知りませんでした。ヨーロッパの奴隷商人に連れられアフリカからイスパニョーラ島へ。その島は、ヨーロッパ二カ国の思惑と力関係で分断され、相争い、憎しみあう関係に。そして、より悲惨なほうから、まだましなほうへ働きに来ている人たちは、人ではなく奴隷のような日々を送る・・・常に虐げられ、悲惨な人生を送るのは、アフリカ系の人たち。こうした現状を、ヨーロッパの人たちはどう思っているのでしょうか・・・。
イベント紹介雑誌にも載っていないこのイベント、しかも分かりにくい会場(あ、ここだ、やっと見つけた、と言って入ってきた人たちもいました)、しかし、それでも会場にはそれなりの数の白人が訪れていました。完全には、見捨てられていないようです。それが、せめてもの救いです―――。

・“Esclaves au Paradis~L’esclavage contemporain en Republique Dominicaine”
(天国の奴隷たち~ドミニカ共和国における今日の奴隷制度)
・L'Usine Spring Court
5 passage Piver
(11区、メトロのBelleville駅から徒歩5分)
・6月15日までの開催
↓アクセスランキングへ「励みの一票」をお願いします!
人気blogランキングへ

このイベントに気付いたのは、メトロの駅に貼ってある大型ポスター。“Esclaves au Paradis~L'esclavage contemporain en Republique Dominicaine”(天国の奴隷たち~ドミニカ共和国における今日の奴隷制度)。地上の楽園としてヨーロッパの観光客に人気のカリブ海。そこに浮かぶイスパニョーラ島。1492年にコロンブスが到着したこの島の東側三分の二を占めるのがドミニカ共和国。そして残りの西側がハイチ共和国。この島で、今でも奴隷制度を髣髴とさせる状況が続いている・・・

会場は、かつての工場を改修したようなアート・スペース。主催には、人権擁護団体・アムネスティ・インターナショナルやパリ市、リベラシオン紙などが名を連ねています。

写真の点数はそれほど多くはないのですが、タイトル・スローガンにもなっている「血と砂糖と汗と」に現されたサトウキビ農場労働者の悲惨な暮らしぶりが見事に写し出されています。奴隷のような状況に置かれているのは、ドミニカ共和国のサトウキビ農場で働くハイチ出身者・・・。
このカリブ海の島にコロンブス一行がやってきたときは、先住民族が平和に暮らしていました。しかし、この島で金鉱が発見されるや、スペイン人たちは先住民たちを金の採掘で酷使。あまりの酷使に、彼らはほぼ死滅してしまいました。そこで、必要な労働力として、アフリカから多くの黒人奴隷をつれてくる。金の生産が減ると、サトウキビやコーヒーなどのプランテーションで酷使する。その間に、スペイン領のこの島は、西側がフランス領になったり、すべてが仏領になったり、再び東側がスペイン領に戻ったりしましたが、19世紀初頭、フランス領がハイチ共和国として独立。世界初の黒人による共和国で、またラテン・アメリカ最初の独立国でした。こうした快挙にもかかわらず、このハイチは島の東にあるスペイン領を占領したり、南北に分かれての内戦があったり、非常に不安定な状況だったようです。東側の地域も、ハイチの支配の後はスペイン領に戻り、その後アメリカの占領を経て、独立。このように、元は一つの島であったところに、アフリカの人たちが奴隷として連れてこられ、しかもスペインとフランスの力関係で境界線が引かれ、その後独立しても、反目しあう二カ国関係になってしまったようです。
また、ハイチは独立の際、フランス人入植者たちの農園などを接収しましたが、その補償と引き換えに独立を認めてもらったため、後々までその莫大な補償の支払いが大きな足枷となってしまいました。その支払いのため、国民経済が一向によくならない、その不満から政治が不安定になり、独裁、内紛、暗殺などが続き、国は疲弊しきって、世界最貧国の一つに数えられています。

(上の地図、左のクリーム色の部分がハイチ、右側グリーン系の部分がドミニカ)
ドミニカ共和国として独立した東側のほうが、状況はまだましなようで、その結果、職を求めて多くのハイチ人がドミニカ共和国へ出稼ぎに。そのまま居つく人もいますが、その待遇たるや、まさに奴隷並み。かつて互いに敵同士で闘った歴史もあり、ドミニカ人のハイチ人に対する扱いは、かつての奴隷を髣髴とさせるものだそうです。
プランテーションで1日15時間働き、サトウキビを1トン収穫して得られる賃金が1ユーロちょっと(160~170円)。体格がよく、慣れている人でも、1.5トンの収穫、1.6ユーロの賃金が限度だそうです。しかも払われるのは兌換券のようなもので、それで買い物をすると手数料まで引かれてしまうとか。

このような収入では食べて行けず、子どもたちも働くことに。しかし、基本的には子どもの就労は違法なため、支払われる額は、非常に少ないものに。もちろん、衛生・医療制度などは、あってなきに等しい状態。また長年ドミニカで暮らしていても、正式な滞在許可証を出してもらえず、いわば不法滞在状況。その結果、子どもたちには就学の機会も与えられない。

アムネスティがこの問題を告発するレポートを公にし、また今回の会場でも配布しています。名前だけはよくニュース等で聞いたり、見たりしていましたが、そのレポートを手にするのは初めてです。今年の4月に出されたもので、フランス語版はA4・32ページ。その中には、ハイチ人への聞き取り調査の抜粋も載っていますが、まるで犬並みの扱いだとか、上手い口車に乗せられてここに来たら、待っていたのは家畜のようにこき使われる日々だったとか、現状を訴える声が多く紹介されています。
こうした現状に、かつての宗主国、フランスとスペインは何か策を講じているのでしょうか。それとも、見て見ぬふりなのでしょうか・・・ハイチの惨状は、数年まえ日本のテレビでも見た記憶があります。しかし、ドミニカへ働きに行った人たちの奴隷並みの生活は知りませんでした。ヨーロッパの奴隷商人に連れられアフリカからイスパニョーラ島へ。その島は、ヨーロッパ二カ国の思惑と力関係で分断され、相争い、憎しみあう関係に。そして、より悲惨なほうから、まだましなほうへ働きに来ている人たちは、人ではなく奴隷のような日々を送る・・・常に虐げられ、悲惨な人生を送るのは、アフリカ系の人たち。こうした現状を、ヨーロッパの人たちはどう思っているのでしょうか・・・。
イベント紹介雑誌にも載っていないこのイベント、しかも分かりにくい会場(あ、ここだ、やっと見つけた、と言って入ってきた人たちもいました)、しかし、それでも会場にはそれなりの数の白人が訪れていました。完全には、見捨てられていないようです。それが、せめてもの救いです―――。

・“Esclaves au Paradis~L’esclavage contemporain en Republique Dominicaine”
(天国の奴隷たち~ドミニカ共和国における今日の奴隷制度)
・L'Usine Spring Court
5 passage Piver
(11区、メトロのBelleville駅から徒歩5分)
・6月15日までの開催
↓アクセスランキングへ「励みの一票」をお願いします!
人気blogランキングへ