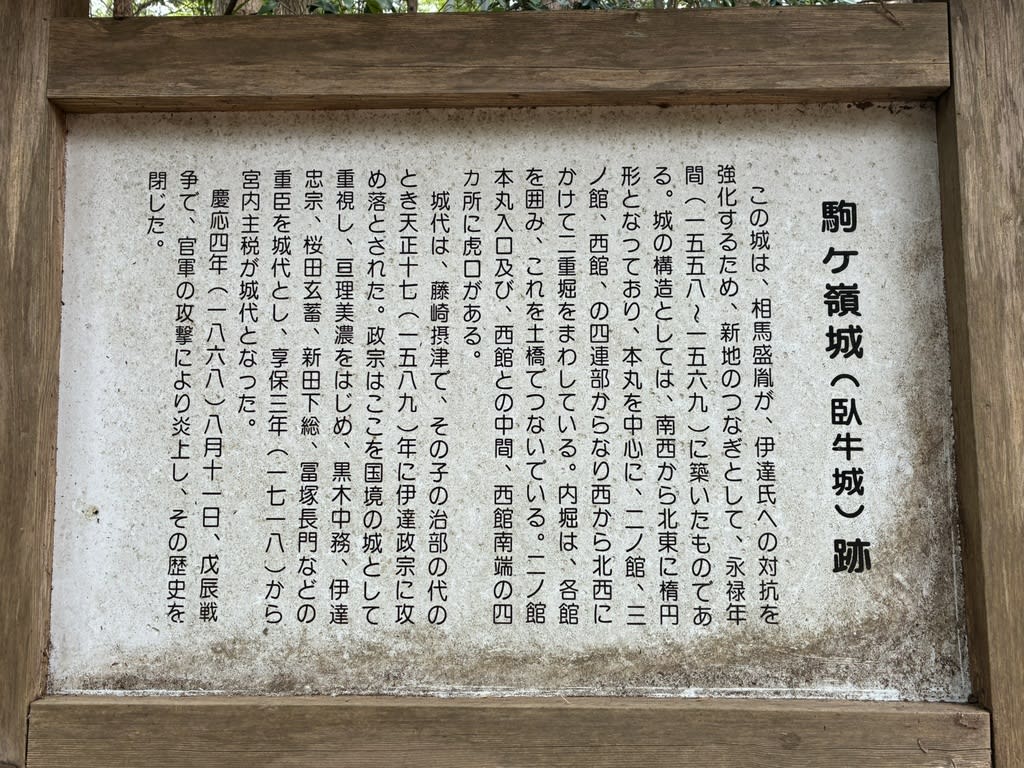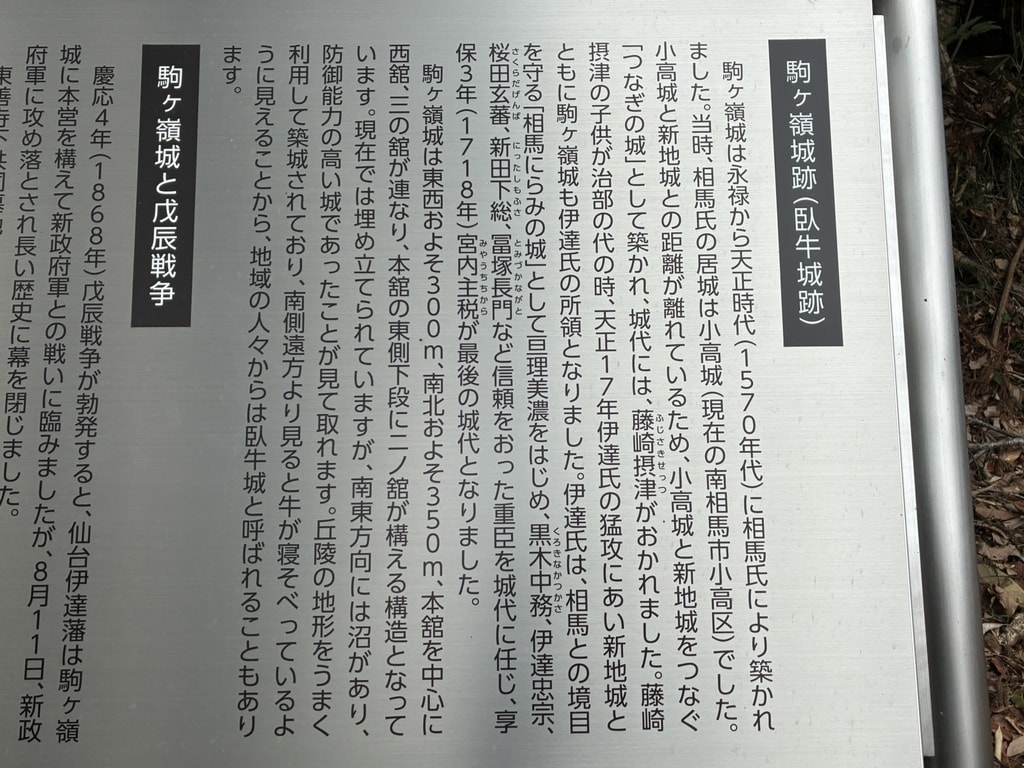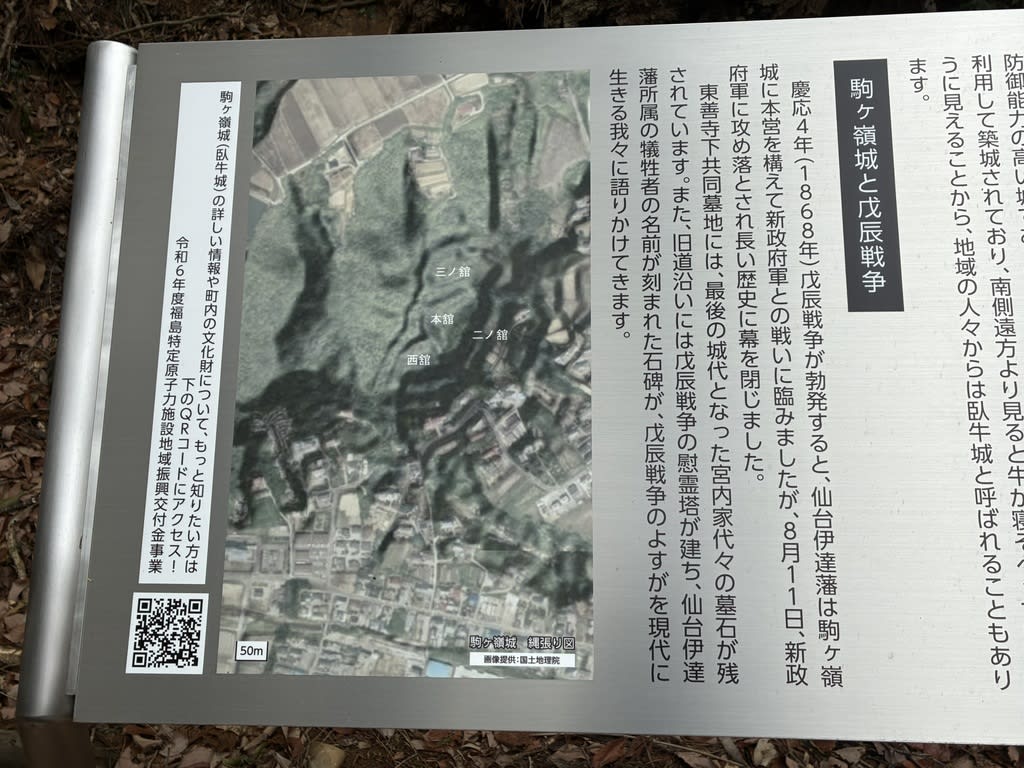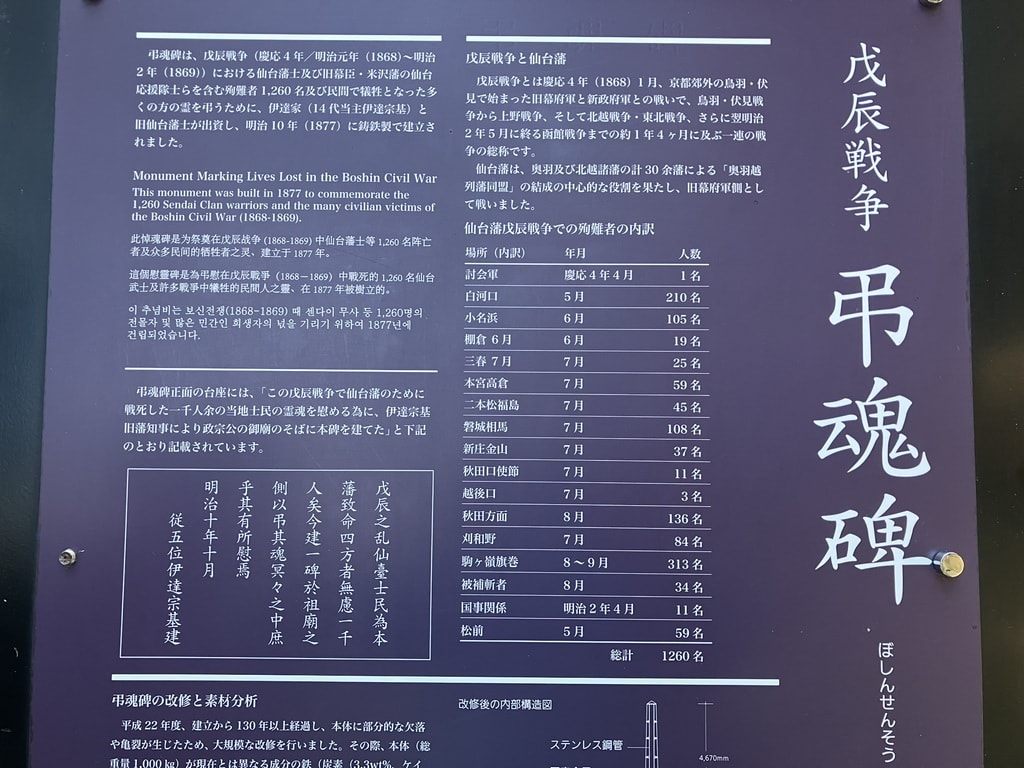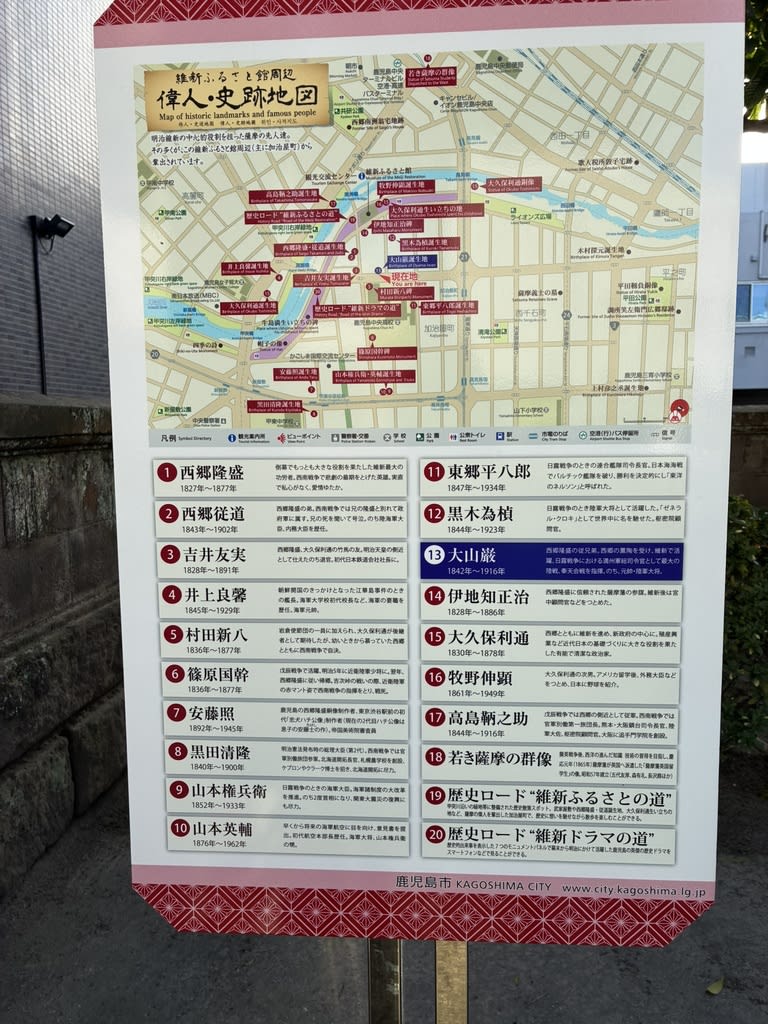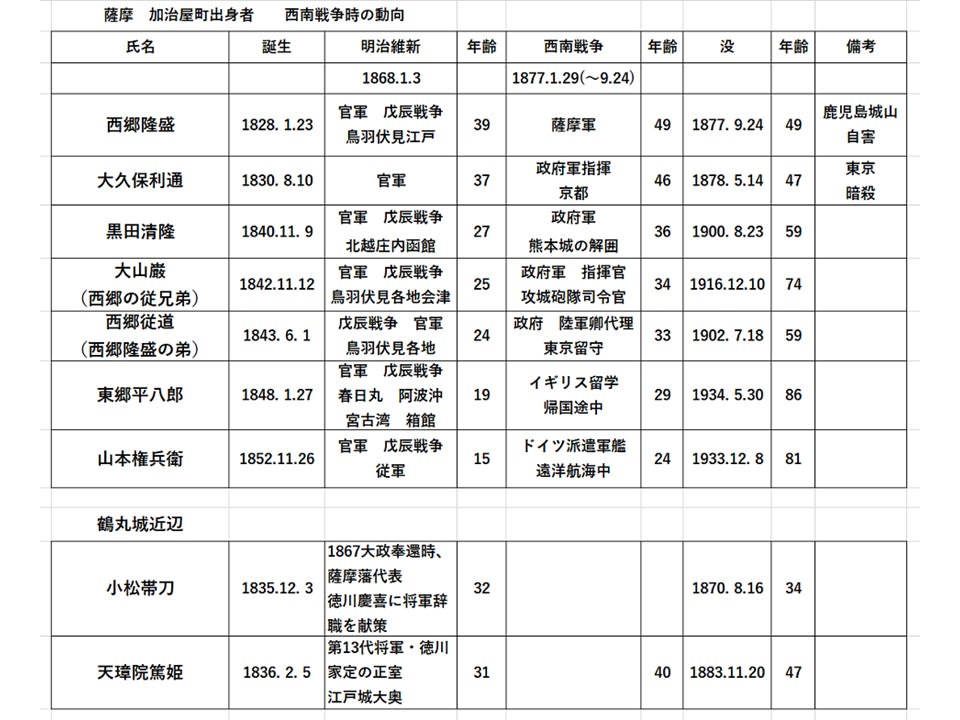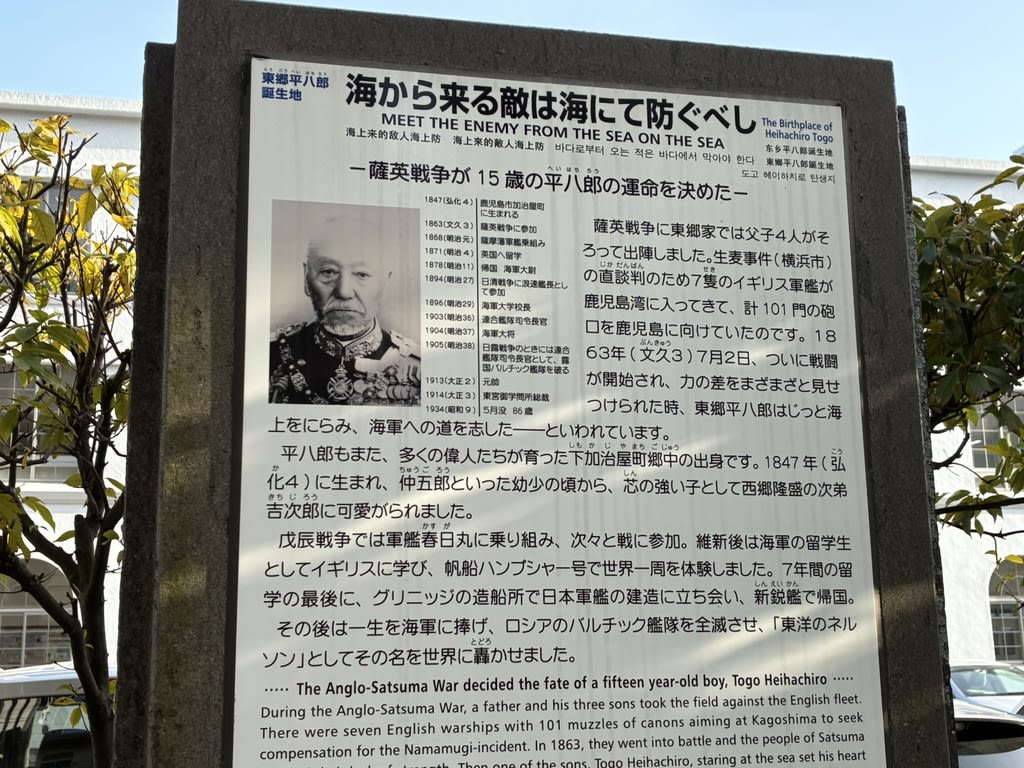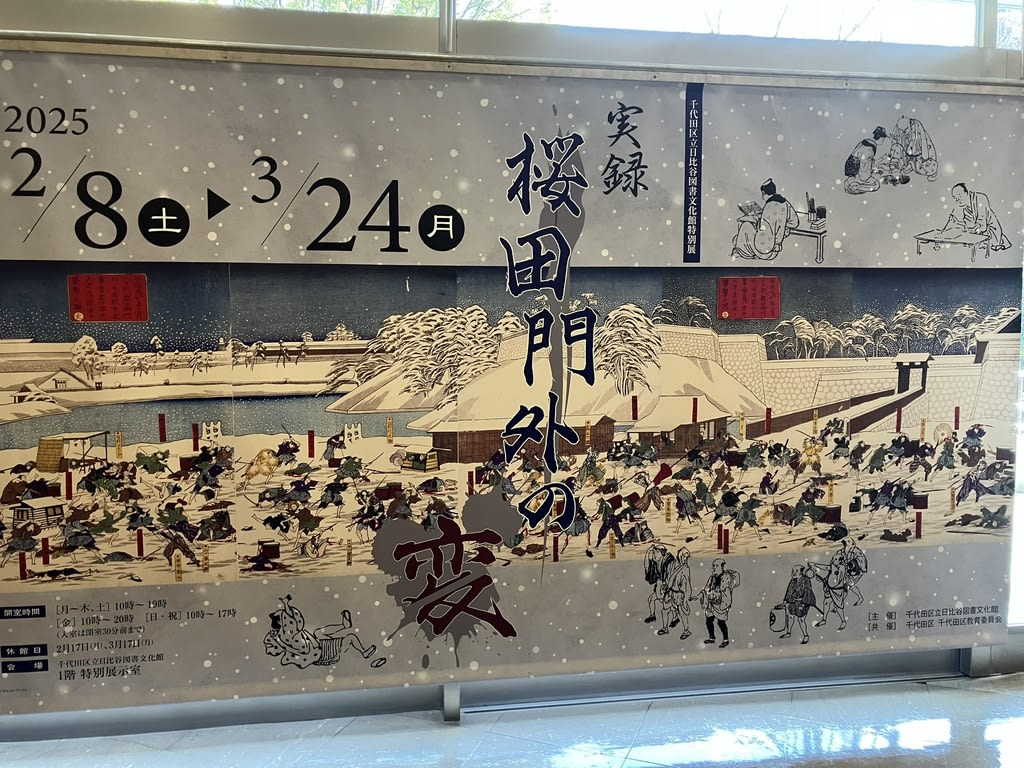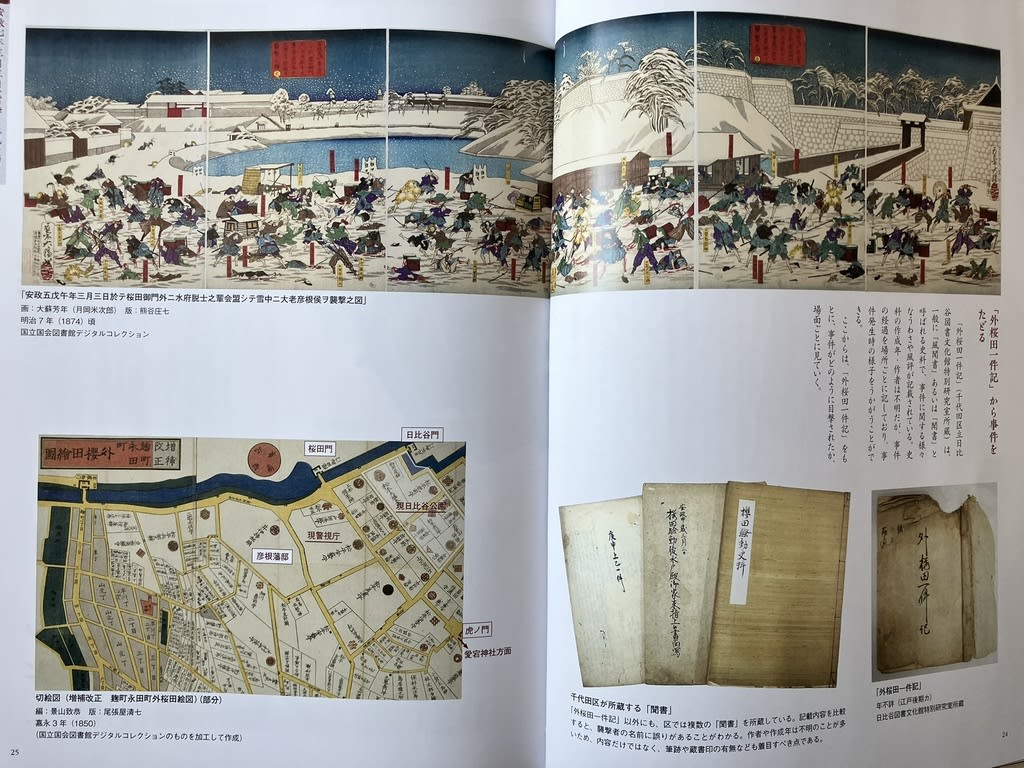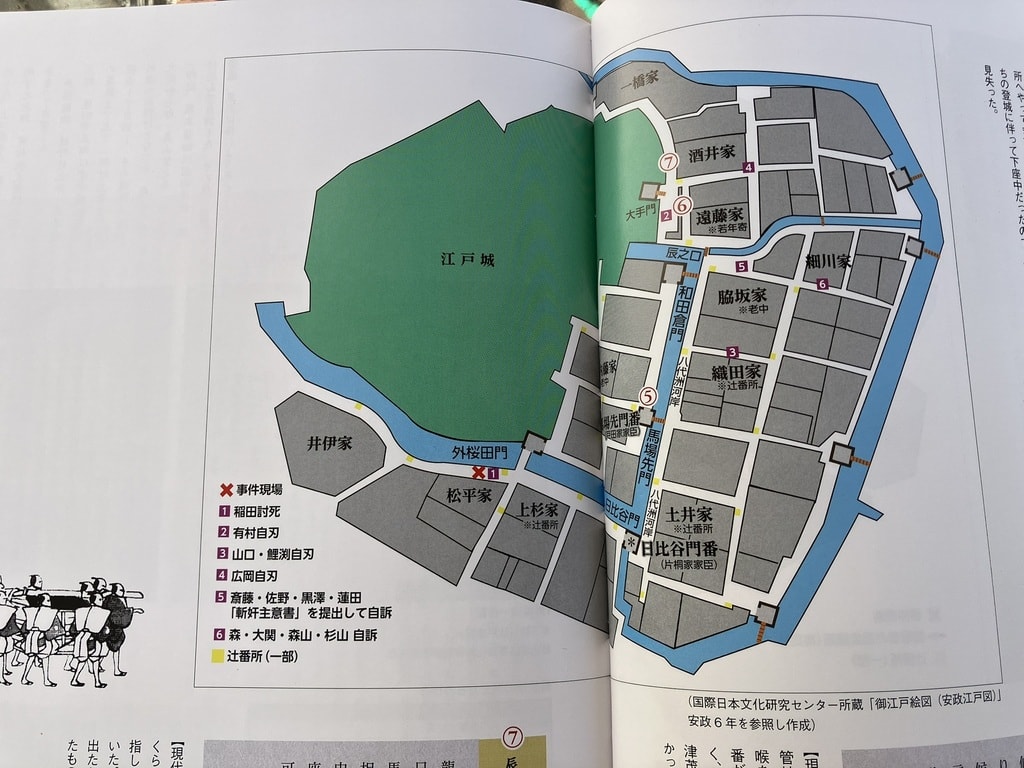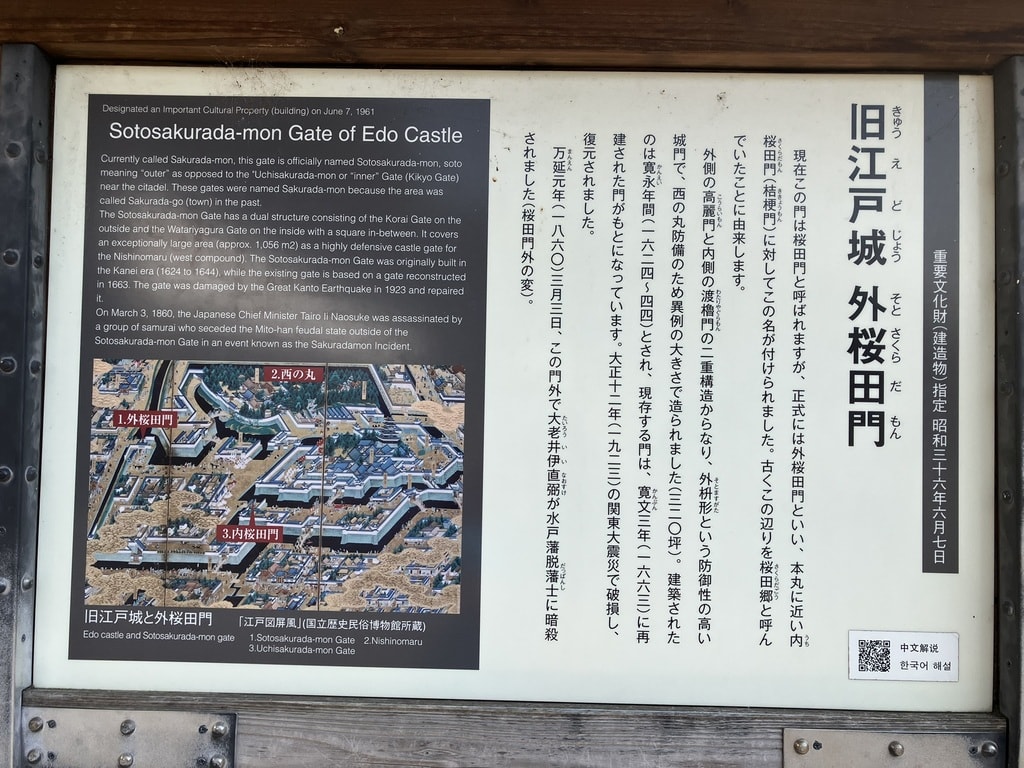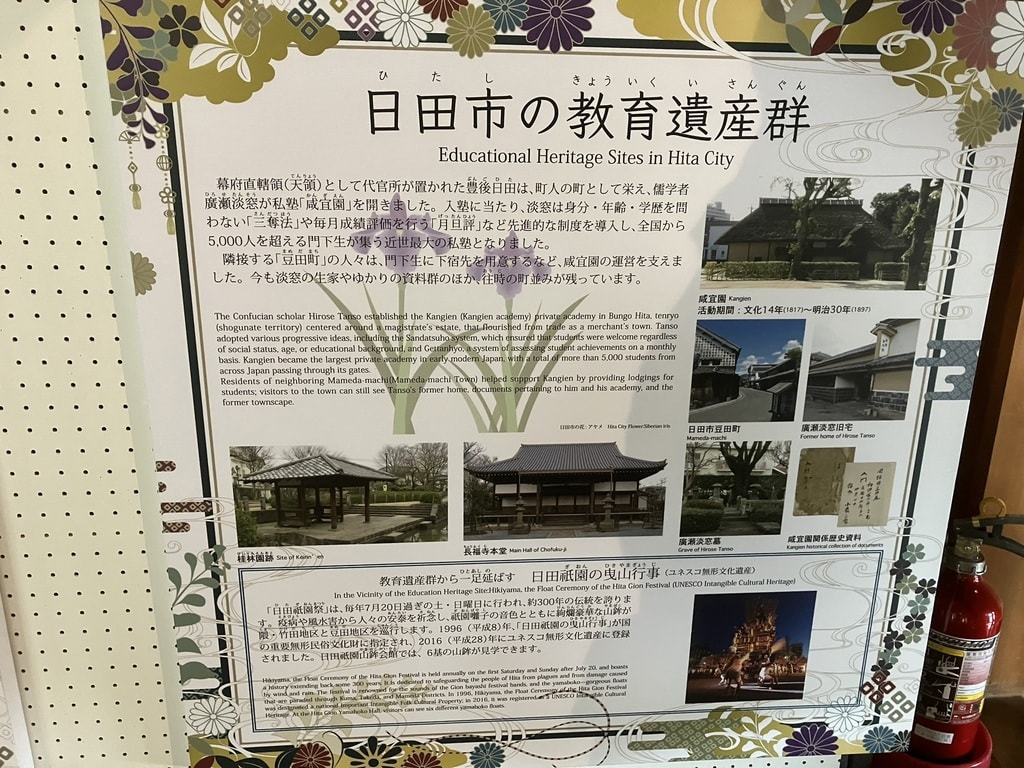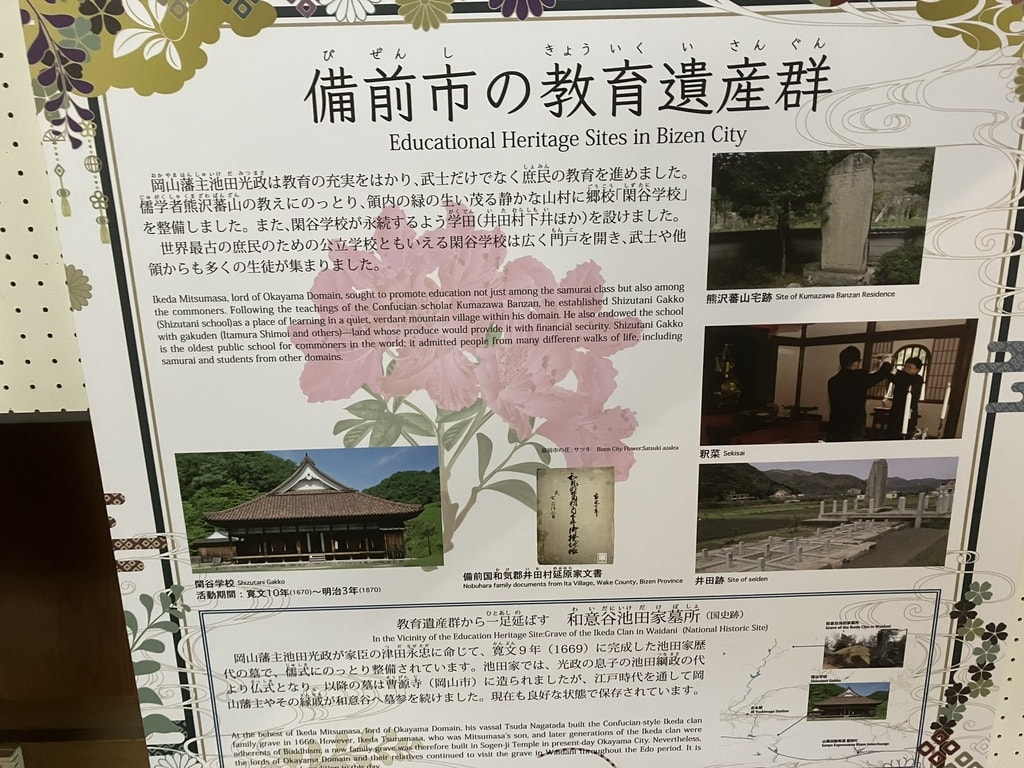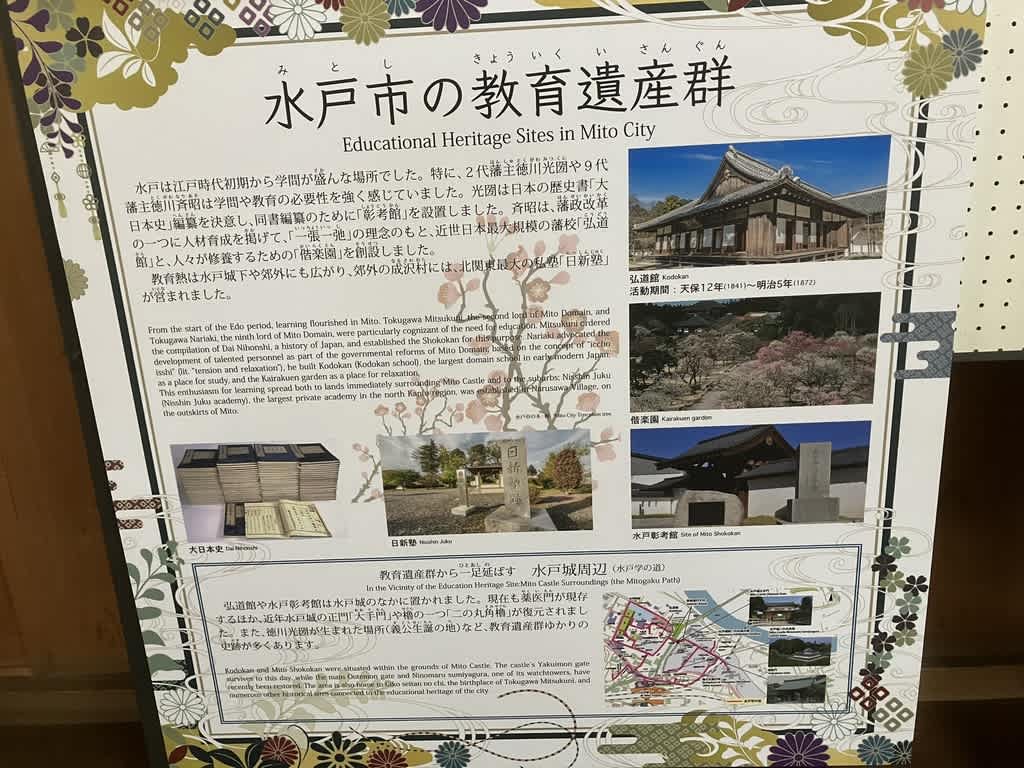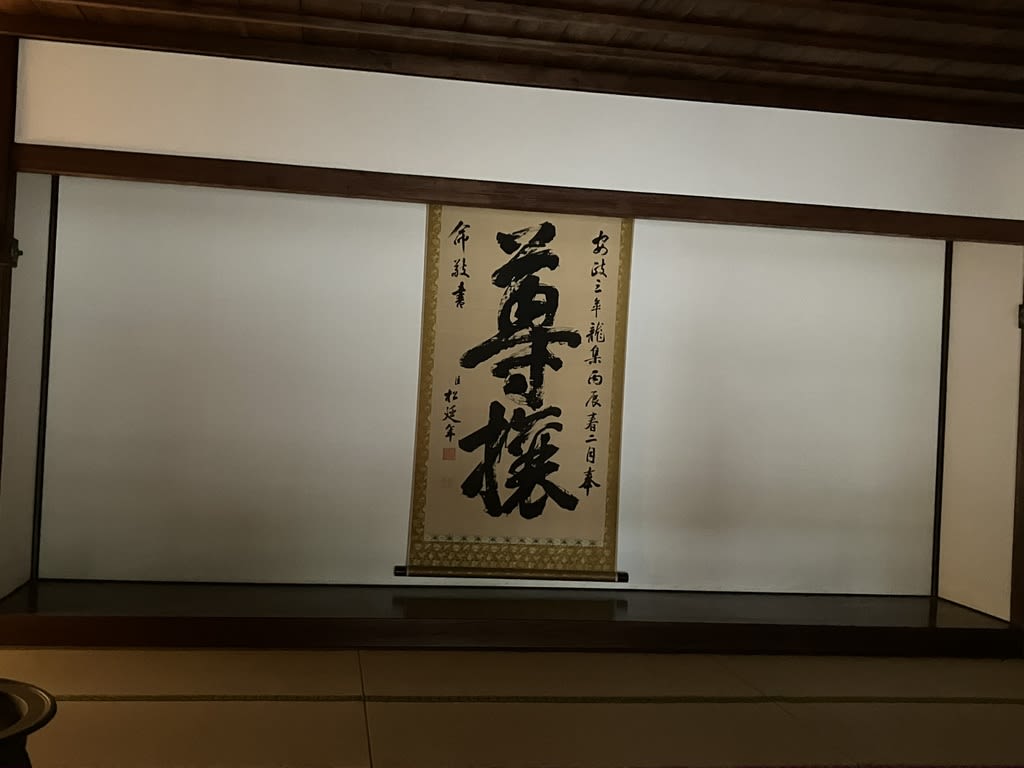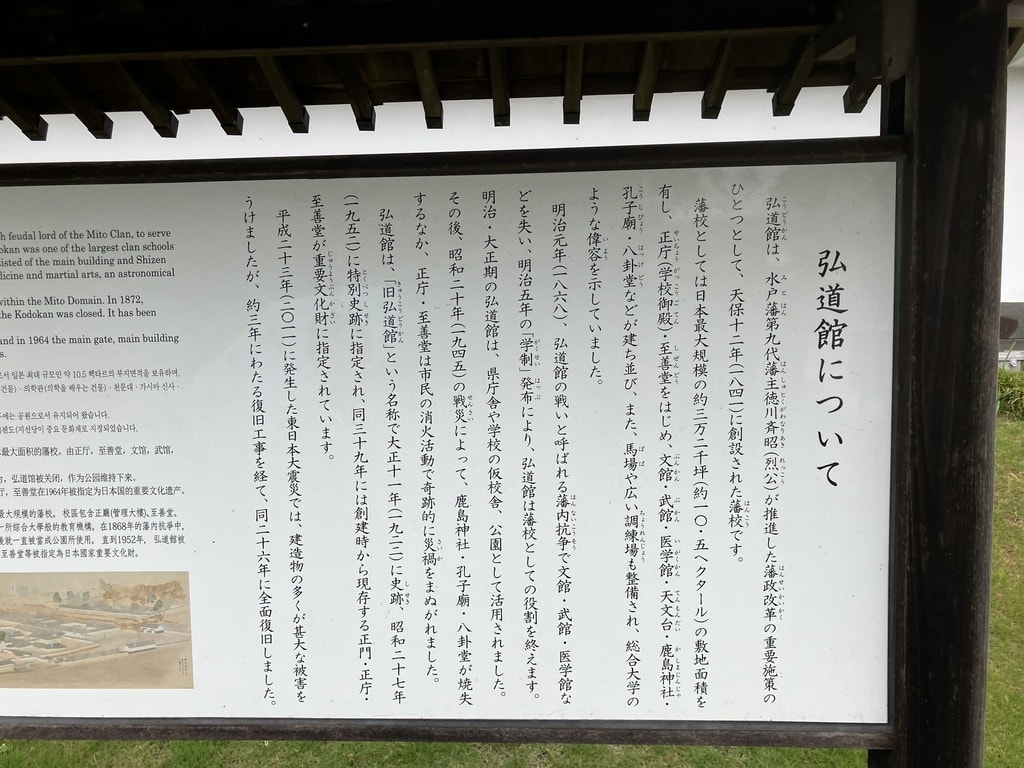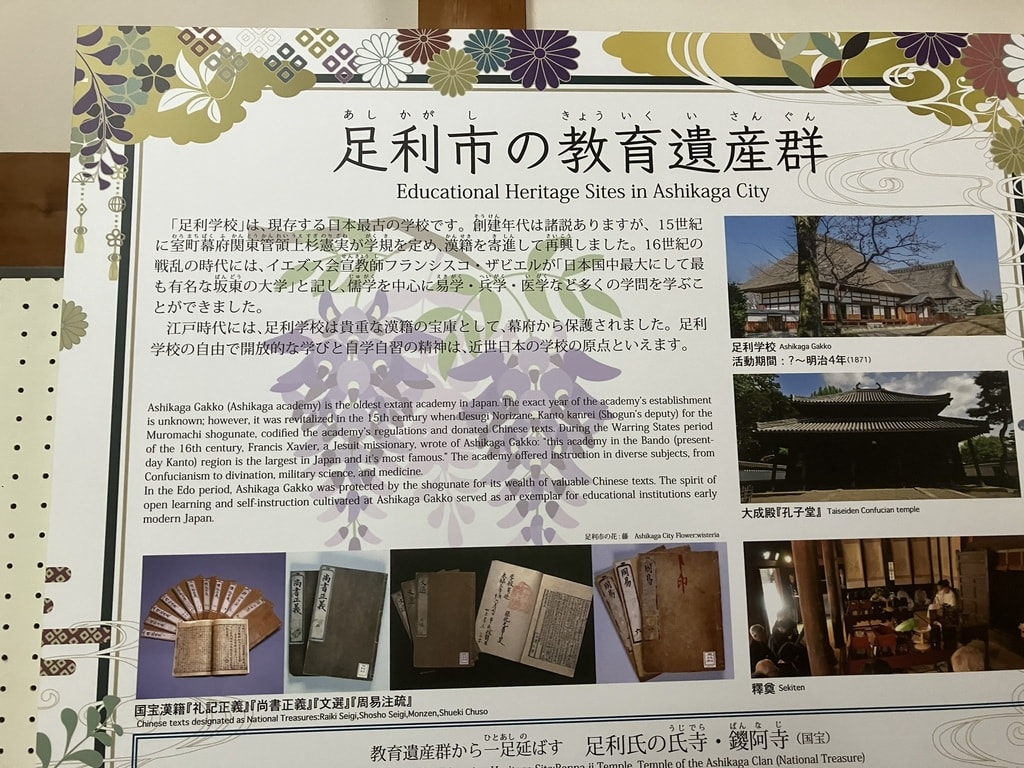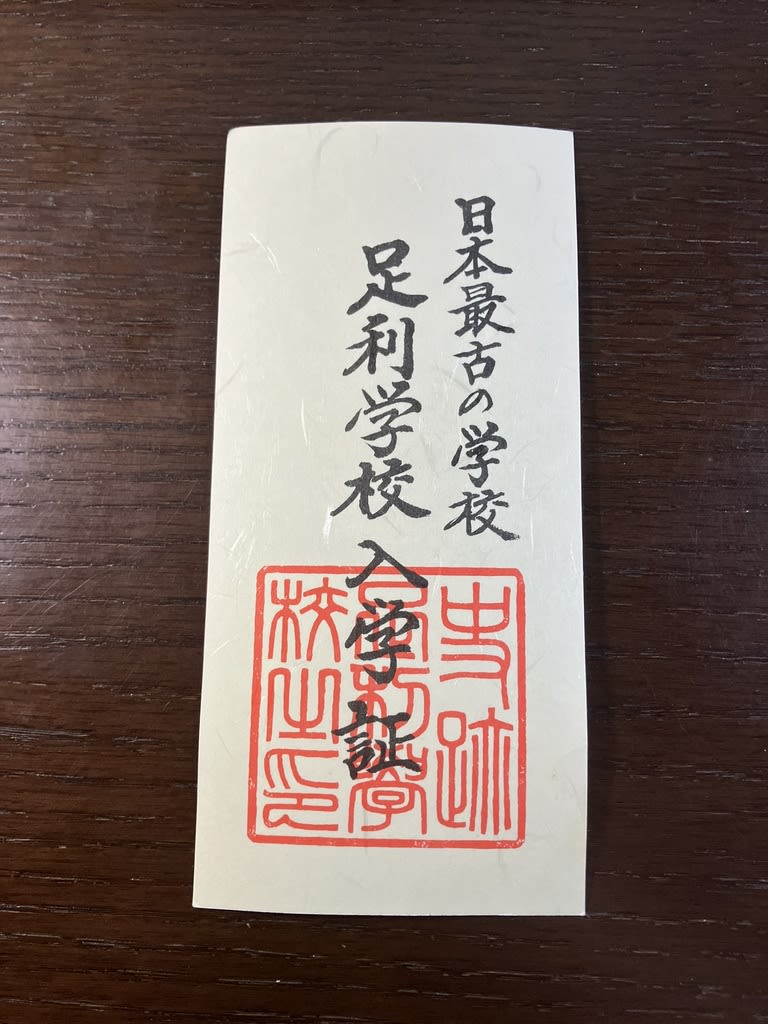シドニー
サーキュラー・キー
連絡船が多数発着する中心地
神戸のメリケン波止場付近と雰囲気が似ている
親近感があって初めて来たとは思えない
シドニー サーキュラー・キー
波止場の連絡船
セントラル駅の列車
ブルーマウンテン行き
片道2時間
オパールカード
シドニー付近の列車、バスとフェリー共通
1週間の乗降自由でオーストラリアドルで約50ドル
空港から市内往復
市内観光用 バス 電車
フェリー乗降全て
ブルーマウンテン往復
タクシー利用なしで交通はすべてこのカード一枚でOKだった
ブルーマウンテン 原生林
ブルーマウンテン三姉妹
有名なスポットらしい
オペラハウス
オーストラリア博物館
ゴールドラッシュ
約90kgの金塊
現在金の価格は1グラムあたり16,698円
90kgでは15億円
こういう金塊を発見発掘できれば最高な気分!
現実に戻って1兆円企業とは売上この金塊を666個
赤字1000億円とは90kgの金塊66個
赤字が続けば詰んでしまう
いけない、いけない!
90kgの金塊を掘り当てる夢を見なくては!
コッカトゥー島
たぶん、世界遺産
マンリー海岸
リゾート地
ここからは備忘録
オーストラリアの歴史
"5万年前 石器時代後期" "現生人類(ホモ・サピエンス)がアフリカからユーラシア大陸に渡来し、狩猟・採集生活を送っていた アボリジニの祖先がジャワボルネオを含むスンダランドからサフールランド(オーストラリア)に移住した"
その後16世紀まで オーストラリア大陸はオーストラリア先住民、いわゆるアボリジナル(日本ではアボリジニと呼ぶ)が住んでいた
1606年 ヨーロッパ人によるオーストラリア「発見」
1770年 英国ジェームス・クック エンデバー号でシドニー付近に上陸
1788年1月26日 "シドニー入植 フィリップ英海軍大佐一行がシドニー付近に初めて移民 オーストラリアの新しい歴史が始まった 流刑囚780人と海兵隊関係者1,200人
先住民アボリジニはオーストラリア大陸に25から30万人
1788年-1900年 ニュー・サウス・ウェールズ植民地
1788年-1934年 オーストラリア開拓戦争:オーストラリアの開拓時代、イギリスの入植者と先住民族との間に起きた100年以上に渡る激しい対立
1794年-1816年 ホークスベリー・ネピアン戦争
1828年–1832年 ブラック・ウォー 入植者との戦いでタスマニアン島のアボリジニーは殆ど絶滅し、入植者によるアボリジニーのフリンダーズ島への強制移住で終わる
1851年 ゴールドラッシュ 人口 1851年で437,665人から1861年に1,168,149人
1854年 ユリーカ砦の反乱 1856年労働者が抵抗 8時間労働制
1858年 シドニー、メルボルン、アデレード間の電信が開通 ニューサウスウェールズ州やビクトリア州議会選挙 この頃、オーストラリアの人口は100万人
1901年1月1日-現在 オーストラリア連邦の成立
1914年7月 第一次世界大戦 オーストラリアはイギリスと共に連合国側に付いて参戦
1939年9月1日ー1945年8月15日 "1939年9月1日ドイツがポーランドに侵攻 第二次世界大戦が始まった オーストラリアはイギリス側に立って参戦、まず中東・地中海沿岸に、次いで北アフリカ地域に志願兵を派遣した
1941年12月に日本軍が真珠湾攻撃を行うと、日本に対する宣戦を布告した。日本軍は 1942年の2月から7月にかけてダーウィン、ブルーム、タウンズビルなどオーストラリア大陸北部の爆撃を繰り返す
5月には特殊潜航艇を用いてシドニー港を攻撃した
1901年-1973年 白豪主義時代 中国人などのアジア系の移民を排斥、制限し、白人主体のオーストラリアを建設・維持しようとする政策
人口 1949年 800万人 1959年 1,000万人
1981年 1,500万人 大量の難民 インドシナ半島から到着したボートピープル
2004年 2,000万人国内マーケットの活性化移民政策
2025年 2,700万人超
2030年 3,000万人見込"
現状 オーストラリア
名目GDP(国内総生産) 2024年 世界第14位 1兆8千億ドル USD
1人当りGNI(総所得) 2023年 世界第18位 5.6万ドル
主な産業 畜産業や小麦を中心とする農業 鉄鉱石、石炭、ボーキサイトも主要な輸出品
人口 オーストラリア総人口は2666万人
10大都市に70%、東海岸に80%の国民が住む
シドニー 531万人 メルボルン507万人 ブリスベン251万人 パース 208万人 アデレード135万人 ゴールドコースト69万人 ニューカッスル49万人 キャンベラ46万人 サンシャインコースト34万人 ウロンゴン30万人
以上の10大都市の人口合計1864万人
オーストラリアの人種構成 ヨーロッパ系約92%、アジア系約7%、先住民アボリジニが約1%
宗教 キリスト教約61%、無宗教約22%