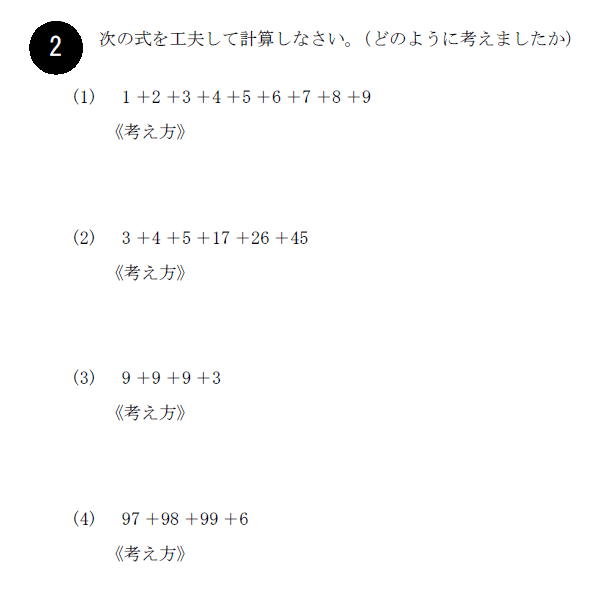

オープンキャンパスがあちこちの大学で開催されていたが、私立大学入試はこの1、2年急激に難化している。一方で、中学入試では私立大学付属校が大人気となっている。この2つがどうつながっているのか。
* * *
教育改革再生実行会議から大学入試改革の構想が公表されたのが2013年である。2021年1月から実施される大学入試からセンター試験がなくなるなど、大きな改革が行われると発表された。が、構想が大胆なだけに、当初から実行は可能なのか、疑問視する専門家も大勢いた。
わが子が当事者となる保護者の中には「どうなるかわからないから、中学から付属校に入れたほうが安全」と判断し、2014年度入試から受験校として付属校を選ぶケースは徐々に増えていた。
それが一段と強まったのは、政府が地方創生政策の一環で、23区内の私立大学の「定員厳格化」を打ち出したことからである。2015年から徐々に定員の1.2倍→1.17倍→1.14倍→1.10倍以上を入学させた場合、経常費補助金を不交付にすると打ち出したのである。
私立大学はどこも中退者が出ることを考え、定員より多く入学させていたから大変である。定員をキチンと守るには合格発表数を絞るしかない。その結果、東京の私立大学入試はとんでもないことになった。
ではどのくらい絞られたのだろうか。「定員厳格化」の動きがまだなかった2015年度入試と今年2018年度入試の合格発表数を比べてみよう(一般入試の数字)。
【青山学院大学】9277人→6708人(72.3%)
【立教大学】1万3198人→1万452人(79.2%)
【早稲田大学】1万8281人→1万4532人(79.5%)
【上智大学】5532人→4422人(79.9%)
【明治大学】2万4909人→2万1216人(85.2%)
【法政大学】1万9549人→1万7548人(89.8%)
20%以上も減らした大学が4校もあるのである。このほか減少数が少ないところでも慶応義塾大学は92.4%と7.6%ほどは減らしている。中央大学を除く大規模私立大学が軒並み減らしたのだから、大学受験生には悲劇が起きたわけである。
2017年度入試以降、「予備校の模試でA判定だったのに落ちた」という話をあちこちで聞くようになった。となれば、「どこか合格大学を確保しなければ」と受験生は多数の大学に願書を出す。合格発表数が減っているところに志望者が増えたのであるから、倍率が上昇する一方となった。私立大学入試が急激に「狭き門」となったのは、こうした理由からである。
◆付属校人気って本当なの?
先にも述べた「不合格」の話は、親戚の子、近所の子の話として、リアルな現実として中学受験の保護者の耳にも入ってくる。親たちは先回りして心配するのが常だから、「有名私立大学の入試がそんなに難しくなっているのなら中学から付属校に入れたほうが安心」となって、ある意味当然と言える。
2018年度入試の受験者数の状況からそれを見てみよう。前年対比の増減。
【早稲田系】早稲田、早稲田大学高等学院、早稲田実業/3校とも増
【慶應系】慶應普通部、慶應中等部、慶応湘南藤沢/3校とも増
【明治系】明治大学付属中野、明治大学付属中野八王子、明治大学付属明治/3校とも増
【立教系】立教池袋、立教新座、香蘭女学校、立教女学院/立教新座、香蘭女学校が増。立教池袋、立教女学院の減はほんのわずか
【中央系】中央大附、中央大附横浜/2校とも増
【法政系】法政大学、法政大学第二/2校とも増
【学習院系】学習院、学習院女子/2校とも増
【日大系】日本大学豊山、日本大学豊山女子、日本大学第一、日本大学、日本大学藤沢、千葉日本大学第一/日本大学、日本大学藤沢を除く4校が増
※日本大学第二、日本大学第三は他大学進学者が多いので入れていない
【東海大系】東海大学附属高輪台、東海大学附属相模、東海大学附属浦安/東海大学附属高輪台を除く2校が増
このほか日本女子大学附属、青山学院、明治学院など、軒並み増えていて、減ったところを探すことが難しいほどだ。
このように難関大学の付属校だけではなく、いまや普通の学校からでも十分受かるであろう中堅大学の付属校も志望者が増えているのが実情だ。ここまで心配しなくてもいいだろうと思うが、保護者が危惧している要因はもう2つある。
・私立大学が付属校、系属校との接続を今後さらに強化するのではないか
・AO入試、推薦入試はそれぞれ「総合型選抜」「学校推薦型選抜」と名称が変わるが、これらの募集定員が拡大されるのではないか
いずれも一般入試の定員減につながるものだけに、神経質にならざるを得ないのである。今の時代、大学入試はストレートに中学入試につながるものになっている。

医学部合格校の常連ではない、それも商業高校から合格者を2年連続で輩出した高校がある。香川県の高松商業高校だ。進路指導教諭に学校の特色について聞いてみた。
* * *
今年の医学部の合格状況は、西日本の名門私立が相変わらずの強さを見せた。全国の医学部に毎年多くの合格者を出す東海(愛知)、ラ・サール(鹿児島)、洛南(京都)、灘(兵庫)、東大寺学園(奈良)の5強が上位を占めた。
東海は国公立大医学部の合格者総数で、5年連続の首位である。同校学習指導部長の内藤俊一教諭は「医学部受験の対策どころか、特別な指導は一切していない」と話す。元々、親が医師であるなどの理由で、医学部を目指す生徒が多い。「医学部以外の選択肢もある」と思うこともあるというが、志望について指示することはまったくないという。
とはいえ、毎年多数の合格者を出しているが、その背景についてこう話す。
「本校の生徒は、浪人を恐れずに高い目標に向かっていく傾向があります。また、中学3年のときに、自分の進路について卒業リポートをまとめます。実際に仕事をしている人に質問し、将来像を具体化させることで、目標が明確になるようです。身近な医師である親に聞いてくる生徒も多いです」(内藤教諭)
一方、医学部合格校の常連ではない、それも商業高校から合格者を2年連続で輩出する高校がある。香川県の高松商だ。香川大学医学部に、今年は浪人生1人、昨年は現役1人が合格している。進路指導主事の道久和紀教諭はこう話す。
「本校は就職も進学もできるとアピールしていますが、昔から4年制大学への進学率は高かったのです。学科別にいえば、実践的な英語教育に注力する英語実務科(1クラス)は75%(過去4年の現役のみの平均)の生徒が進学します。6クラスある商業科でも約半数強(同)の生徒がやはり4年制大学に進学します」
1900年創立の伝統ある高校だが、同校の資料によると、52年には東大合格者がおり、60年代後半ごろには全国の商業高校で国公立大学進学率が日本一になったこともあるという。
