@現代無名の江戸幕府の立役者・脇役『伊奈備前守忠次』。歴史上、立身した多くの人物の裏にはそれを導いた立役者がいた。その一人が徳川家康に仕え、家臣として小田原城攻め、関ヶ原の戦いを戦い抜き、徳川幕府の基盤、検知・土木治水、砦・御殿・城・橋建築、新田開発などの能力(知識と経験)を発揮、さらに代官頭としての力量で様々な江戸幕府全体の構築・政策を普請・実行した人物、伊奈忠次である。 家康との信頼関係が第一、様々な普請に対する指示の正確性と着実に実績に繋げる周りとの信頼、精密な計算された段取り、完成した諸々の完成度合いなど、上司を満足させ、周りからも信頼される人材は貴重である。 上司から見れば、如何に、何を持って信頼し、どこまで仕事・役割を任せれるかである。信頼を築くための行動は一夜ではできない。忠次の忠誠普請は農民(幕府を根底から支える)の暮らしを優先にしたことではないかと思う。(一生懸命)
『伊奈備前守忠次』和泉清司
- 徳川家康の関東入国以来、土木治水や新田開発を通して農村経営の安定化に取り組み、徳川幕府260年の基礎を築いた伊奈忠次。関東だけでなく東海地方にまで及んだ幅広い業績を、従来の研究の枠を超えて忠次研究の第一人者が解説。利根川や荒川の付け替えといった河川改修で知られる伊奈忠次。その功績は土木治水にとどまらず、新田開発や検地、寺社政策など幅広く、多岐にわたります。戦乱の時代を経て民衆の暮らしに安定をもたらすことで、徳川幕府の基盤を築くのに重要な役割を果たした伊奈忠次の生涯を詳しく紹介
- 「伊奈備前守忠次」
- 1550年三河国に織田信康に仕えた父忠家の長男として出生
- 1582年家康の伊賀越えに従い、小牧長久手の戦いに参戦
- 1589年徳川領5カ国の総検知、郷中定書を出す
- 1590年小田原城ぜめでは東海道の道路・川整備普請
- 1590年小田原城内の倉庫・在庫計算で秀吉の信頼
- 家康の代官として伊奈忠次、大久保長安、彦坂元正、長谷川長綱ら4名が指名を受け関東領国での農政、検知、土木治水、新田開発等を行う。
- 1591年武蔵小室・鴻巣等で1万3千石、陣屋を敷く
- 1591年大宮氷川神社検知(1596年造営)
- 1592年江戸千住に橋を設置、奥州道の起点とする
- 利根川整備・寺社領証文
- 1596年伊奈駿河守、その後備前守となる
- 1600年家康の近習、関ヶ原の戦いでの小荷駄奉行
- 徳川直轄領を監修・伝馬定書・制度・手形を設ける
- 1604年武蔵各地の新田開発・綾瀬川にて備前提を築く
- 1605年利根川・天竜川など治山治水・土木工事を着工
- 1608年尾張の総地検、木曽川整備
- 永楽銭使用禁止、新たな銭を鋳造
- 1609年富士川、利根川に備前堤
- 1610年享年61歳、江戸で死去する
- 「忠次の業績」
- 五カ国領の時代遠江国中泉にて 家康の御殿、検分の精密さ
- 年貢・陣夫役・農民権・竹財堤(7か条郷中定書)を整備
- 小田原攻めでの天竜川渡り中止を秀吉に提言、損害を最小限
- 小田原城内の兵糧・倉庫の詳細整理(一旦封印させ後日調査)
- 家康に対し関東全体支配拠点は小田原ではなく江戸に提言
- 関東領国の農村の復興と生産力を掌握(検知)と直轄領確保
- 年貢収取・割符(過去年貢免率平均による収方)
- 利根川治水・防災、新田開発、寺社政策
- 家康の鷹狩り(御殿増設)・家康の領主の声を聞く
- 代官頭(4名)として検知・新田開発・寺社政策など
- 伊奈:三河・遠江・駿河(東海地域)
- 大久保:甲斐・佐渡島・石見国大森・奈良・大津
- 彦坂:相模・伊豆・鎌倉
- 長谷川および彦坂は農民からの訴えにより脱落
- 大久保も銀山等からの隠匿で失脚する・大久保家断絶
- 関東地区の用水偃・溜井増設(奈良偃・玉井偃・大麻生偃)
- 1594年千住橋(120mx7m)架ける
- 江戸城普請・木材石運搬請負(26家・530万国割り当て)
- 3千船、大金150枚(10万石に対し巨石1120個)
- 伊豆・三崎地方から江戸湾(芝浦)への積み出し
- 日本自前の銭発行(鋳造の采配)今まで永楽銭が一般的普及
- 「関ヶ原の戦い」石田三成・小西行長の分治派vs福島正則・黒田長政の武断派の争い
- 家康の好物「1富士、2鷹、3茄子」
- 家康の三貨制度(小判・丁銀・銅銭)京都金工師後藤庄三郎
- 駿府城は大久保長安による普請で信州・木曽から木材調達
- 秀吉の大名間での領土紛争禁止令「惣無事令」の確立
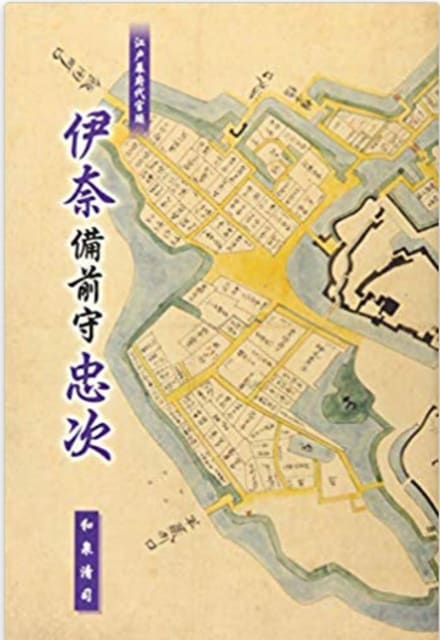












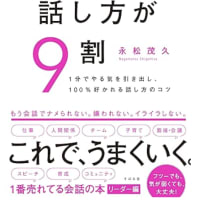
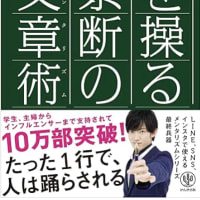
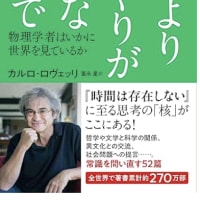


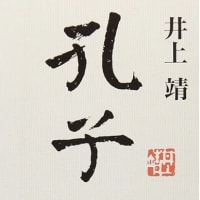

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます