@ダライ・ラマ、第14代チベット法王。だがチベットには今も残る問題・遺産・悲劇が多い。チベットに置ける強大な中国占領軍により過去30年に渡り大量殺戮によって125万人が餓死、強姦、処刑、拷問、自殺などで死亡し、数万人が強制収用所に閉じ込められた。中国は東北部に2〜3百万の満州人に対し7千5百万人の中国人が移り住み、東トルキスタンでは1949年に現地人20万人に対し中国人が7百万人、内モンゴルの植民地化によりモンゴルにはモンゴル人250万人に対し850万人の中国人が住む。チベットでは6百万人のチベット人に対し2500万人の中国人が移り住んでいる。(2001年現在)チベットも1949年以降(中華人民共和国成立後)中国による領土拡大政策により領土に侵略され、昔中国の首都も領土だった大国チベットは無残にも「武力による脅し」で中国自治区と化した。最初中国は「平和・協力協定」として接近も、全て見せ掛けで侵入するキッカケを工作し、次々と略奪、配下にしていった様は現代の中国の動きを見ても頷ける。問題は中国の「武力・脅し」に対応できる仏教の国チベットの武力に勝る?「話し合い」で双方が妥協することはあるのだろうか? チベットは世界でも優質の大量鉱物地であることから中国の手は引き下がるどころか、徐々に侵入、掠奪することは歴史的にも分かる。日本人の多くが知らない異国(特にチベットと近隣諸国)の出来事を知ることは重要で、さらにその国々の長たる人物の動きを知ることで対日本への動きも見える。インドの諺「一度ベビに噛まれたものは、縄にも用心する」
『ダライ・ラマ自伝』ダライ・ラマ 2001年初版
- チベットの宗教的、政治的最高指導者として精力的に平和活動を続け、ノーベル平和賞を受賞した第14世ダライ・ラマが観音菩薩の生まれ変わりとしての生い方ちから、長きに渡る亡命生活の苦悩、司教指導者たちの交流、世界平和への願いなどを、波乱の半生を振り返りつつ語る。チベットとダライ・ラマをしる格好の書。
- 「チベット仏教の歴史」
- 仏教の教祖は仏陀釈迦牟尼。2千5百年前に生まれた釈迦の教え「ダルマ(正法・仏教)は紀元4世紀にチベットに紹介された。それまではボン教でチベット人は生来攻撃的な性格なのだが、宗教的習慣に深く染まるようになってしまった。」それ以前チベットは広大な帝国を築いており、北インドの大きな部分、ネパール、ブータンも合わせ中央アジア全土に君臨していた。紀元763年にはチベット軍は中国の首都を事実上攻略し、貢物その他の特権を勝ち取り大きな領土を支配していた。だが、仏教に熱心に帰依することで中国清朝(1636〜1912年)満州族歴代の皇帝は仏教徒でありダライ・ラマ「仏教を説く王」として深く尊敬した。
- 仏教の根本的教理は物事の相互依存性、因果の法則(縁起論)
- 人が経験する一切のものは行為に導かれた起因に基づく
- 生前動物を虐待してきた人間は来世には動物を労る心を持たない人に飼われる犬になって生まれる説・生前の善行は来世に幸せな再生をもたらす一助となる
- 「ダライ・ラマ」
- 現存の第14代ダライ・ラマは第13世ダライ・ラマの1933年57歳で亡くなったツブテン・ギャッツオのお告げにより民衆から選ばれた。そのお告げは「Ah Ka Ma」という文字で地域・場所等を言った。3歳のダライ・ラマ(1935年7月6日生まれ)ラモ・トンヅップが選ばれた。その後ポタラ宮殿で正式に即位、勉学と修行が始まった。子供の頃の思出の一つ、友達を作るには力ではなく思いやりだと悟る
- 「中国との関係と侵略」
- 中国皇帝穆宗の時代には恒久的幸せを全て分け隔てなく慈愛の手を差し伸べ、平和に尽くそうと相互尊重、古き良き憂苦的隣人関係を実現する条約もあった。1949年、中国兵による襲撃が開始されチベット駐屯地の責任者が殺された。当時チベット軍は総員8500人に対し、中国人民解放軍が前面に出没した。中国は中国解放記念日に「チベットの平和解放」としてチベット領内(チャムドの東リチュ河を越え)に8万の兵で侵入開始した。その後ラサが陥没、国連に訴えたが連合メンバーではないこともありインドを除いてイギリス・アメリカは支持しなかった。当時、ダライ・ラマは当時15歳、6百万人の国民指導者としての役はまだなかった。その為二人の首相を任命し交渉させたが、中国軍侵入は止まらなかった。1951年中国側は17か条協定を提案、無理やり承認させる。軍への穀物提供に対価を払うとしていたが実際は支払いはなされず制度は見かけだけの中国固有優先で侵入・街の陥落(無対価で食料の提供、宿泊施設の強制的占領、張将軍の贅沢三昧と横柄で野蛮な行動)へとつながった。民衆との衝突が相次いで起り首相も中国の強制で辞職させられ、チベット全土に対し中国当局の改革政策を無理やり強制させ農村に飢餓、栄養不足で多数が亡くなった。1954年中国政府はダライ・ラマ等を北京に中国的平和交渉をするべく招聘しダライ・ラマを監視、チベット自治区として中国共産党配下に置いた。当時毛沢東・周恩来が中心の政府であったが外交事例的な言葉を残しただけで実際は侵略支配を意味した。毛沢東のダライ・ラマに話した言葉「宗教は毒だ。僧侶と尼僧は独身だから人口が増えない。また宗教は物質的神秘を無視する」だるまの破壊者だと悟る。1955年以降チベットの多方面から中国軍・政府「改革」での悲惨事件・出来事を聞くようになり「人民に対する罪」として処刑されるものが多数、土地・家屋・家畜等を略奪し、新しい課税を強制するなど自国のように支配するようになる。毛沢東は少なくとも向こう6年はいかなる改革も強制しないと言っていたが、1959年には15万人の中国軍の侵略・攻防は収まらず、虐殺的行動になり民衆は爆発寸前で、ダライ・ラマの言葉させ通じない事態になり、ノルブリンカ宮殿・ポタラ宮殿を中国軍が実力行使、砲撃が始まり撤退・亡命することを決意する。ラサを脱してから3週間でインドに亡命する。当時の侵略で約150万人のチベット人民が集団虐殺された。 中国の書記長が変わり視察団を数回送るがチベット人に対する援助、支援は変わりなく賃貸料等課し無残な仕打ちを受け続けていた。チベットには約30万人の中共軍隊が配置され放射性廃棄物の汚染、核兵器の基地を少なくとも中国の3分の1配置している。またアムドには約1千万人の強制労働収容を確保している。1987年には数千人のチベット人に対する無差別銃撃する事件が起こった。「殺人、強姦、恣意的投獄、拷問、非人間的な卑劣な取り扱いの行動」を世界に指摘された。
- 「インドとの関係」
- ネール首相・マハトマ・ガンディーは心から支援・協力をするようになる。が、ダライ・ラマに対しては中国との関係はインドが介入することではなくチベット独自の問題だと突き放された。その後80人を伴ったダライ・ラマの亡命時には土地等含め難民支援を積極的にした。またインド政府として教育等にも支援し、学校、寺院の建設、チベット文化を保持するための施策を施した。北のダラムサラ(3万人)、および南のマイソール地域(3千人)での膨大な土地(3000エーカー)を与えた。その後内外の記者130名が出席した会場で中国の提案した「17か条」は中国自ら協定を破り違反をし、残虐行為の具体的な説明なども発表した。インドの諺「一度ベビに噛まれたものは、縄にも用心する」中国への警戒心
- 「ブータンとの関係」
- 亡命チベット人を暖かく受け入れ土地や交通手段を提供し、農業建設を援助した。一時チベット人の不幸な事件が起きたが真実が解き明かされることはなかった。
- 「中国の対応」
- 亡命時の中国新華社通信は「反逆者」としてダライ・ラマ等を罵り、「チベットの愛国的僧侶や民間人の協力で、人民解放軍は反逆者を完膚なきまでに叩き潰した。」それは宮殿・学1校・寺院に集まった多くの民衆8万7千人が虐殺されたという事だった。だがこれらの数値は自殺者、拷問による死者、餓死者は含まれていない。鄧小平の警句として有名なものは「鼠をとるなら猫の色は黒でも白でもいい」「顔が醜かったらそうではない振りを装うっても意味がない」
- 「日本との関係」
- 1967年日本訪問。日本人の感性・人間性の良い面にふれ、都市が整理整頓されていたことに驚いたが、伝統的な文化や価値観を失わず維持していることに心を魅かれた。
- 「ダライ・ラマの信念」
- 31年間の亡命生活で最も大切な要素の一つはあらゆる種類の人々との邂逅だった。誰でも逢い話を聞き何かを学ぼうと心がけてきた。常に熱意を持って接した。宗教は愛と慈悲の教えによって良き人間を育むものだと認識。西欧社会は物事を「黒か白か」と考え、相互依存性、相対性を無視する傾向があると感じ「灰色」もあるという事が欠けていると思った。日課として祈りと瞑想を最低5時間。それは3つの理由がある。
- 日々の務めを全うするための心構え
- 時間を充実させるのに役立つ
- 恐怖を和らげる
- 「意識の集中」
- 行者の修行での座禅は1分間に酸素呼吸は7回、寒いところでも体温を温存できると認知した。「お告げ師」は預言者ではないが自然と精神領域間の媒体として行動する守護神である。人間の輪廻(化身)は死んだ年から18ヶ月から遅くとも2年以内に生まれる。チベット医学の驚異は病の根源は無知、欲望、憎しみだとする。中国は17か条で「中国はチベット人から針一本、糸一本も勝手に取り上げることはない」と提唱していたが全く裏返しとなる。が人間の問題は人間同士の付き合いで付き合いによってのみ解決しうるという信念である。
- 趣味はカメラと時計の修理













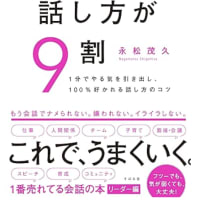
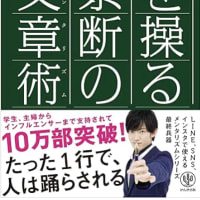
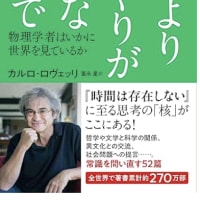


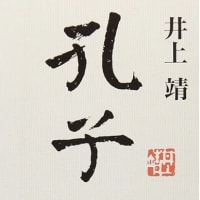

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます