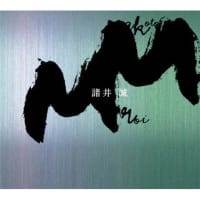■Venice GR Digital (C)Ryo
ベルリン・フィルの首席オーボエ奏者、アルブレヒト・マイヤーのCDアルバムが出たので聞いてみました。
Albrecht Mayer in Venice というタイトルで、文字どおりビバルディやマルチェッロなど、17-18世紀のイタリア・ヴェネツィアを中心に活躍した作曲家たちの作品を集めたものです。
全部で17あるトラックのうち、私はとりわけ11番目のトラック、ベネデット・マルチェッロ (Benedetto Marcello)の Canzona:Se morto mi brami perche non m'uccidiに心を動かされました。
夏休みのあいだ外で騒いでいた近所の子供たちの声が鎮まり、大掛かりなスポーツの祭典が終わり、折からの長雨に蝉の声も聞こえない…、夏の強烈な光が去る間際、祭りが去った後の心の隙間にそっと忍び込むような旋律、それがマルチェッロの作品から聞こえてきました。
それは同時に、17世紀から18世紀にかけて、ヴェネツィアのオペラ劇場を中心に連夜繰り広げられていた喧騒と享楽の日々を、緞帳の後ろに立って静かに見つめていたマルチェッロ自身の心の声のようにも聞こえました。
ベネデット・マルチェッロ=1686年ー1739年、イタリアの貴族にして作曲家、兄のアレッサンドロ・マルチェッロは、映画「ベニスの愛」で有名になったオーボエ協奏曲を書いた人です。ベネデット・マルチェッロには、1720年頃に出版した「当世流行劇場=Il Teatro Alla Monda」という著作があり、これは小田切慎平さん、小野田香織さんの二人によって翻訳され、日本語で読むことができます(未来社刊行)。
この本の内容を、訳者の小田切さんが書いた解説から抜粋してみましょう。
『ベネデット・マルチェッロは、由緒あるヴェネツィアの貴族として生まれ、二十一才でヴェネツィア共和国大委員会委員、二十五才で弁護士、三十才でヴェネツィア共和国で財政を主として受け持つ四十人委員会委員となるなど、政府の要職を歴任した政治家です。最後は五十二才で、ヴェネツィアの西一七〇キロに位置し、ミラノにほど近いプレシアの司教座聖聖堂参事会の議長として赴任し、結局ヴェネツィアに帰ることなく、翌年その地で死去しました。』
(中略)
『その、ベネデット・マルチェッロが、一七二〇年、三四才の時に出版したのが、この「当世流行劇場」という小冊子でした。匿名で出版されたこの小冊子の値段は、当時としては手頃な三〇ソルディ(二〇ソルディ=一リラ)。オペラの台本と同じ大きさの安っぽい紙に印刷され、値段は、ヴェネツィアでも、大衆的な劇場であったサンタンジェロ劇場の入場券とだいたい同じくらいでした。そして、その内容は、当時の百鬼夜行ともいうべきオペラ業界の姿を辛辣に暴き立て、そこに巣食っている、台本作家、作曲家、カストラート、男性歌手、女性歌手、劇場支配人、演奏家、舞台装置家、背景画家、踊り手、ブッファ役、衣装係、写譜係、女性歌手のパトロンや母上、などありとあらゆる人々が、いかにオペラで手抜きをして、成り行き任せで、ずる賢く、名誉や利益を求めて、うまく立ち回ろうとしているかを描き出しているのです。』
『そして、その最大の矛先は、当時サンタンジェロ劇場を活動の中心とし、作曲家、劇場支配人、興行師として辣腕をふるい、何本もの自作のオペラを上演していた、アントニオ・ヴィヴァルディに、そうあの「四季」で有名な作曲家のヴィヴァルディに向けられていたのでした。』
(つづく)
ベルリン・フィルの首席オーボエ奏者、アルブレヒト・マイヤーのCDアルバムが出たので聞いてみました。
Albrecht Mayer in Venice というタイトルで、文字どおりビバルディやマルチェッロなど、17-18世紀のイタリア・ヴェネツィアを中心に活躍した作曲家たちの作品を集めたものです。
全部で17あるトラックのうち、私はとりわけ11番目のトラック、ベネデット・マルチェッロ (Benedetto Marcello)の Canzona:Se morto mi brami perche non m'uccidiに心を動かされました。
夏休みのあいだ外で騒いでいた近所の子供たちの声が鎮まり、大掛かりなスポーツの祭典が終わり、折からの長雨に蝉の声も聞こえない…、夏の強烈な光が去る間際、祭りが去った後の心の隙間にそっと忍び込むような旋律、それがマルチェッロの作品から聞こえてきました。
それは同時に、17世紀から18世紀にかけて、ヴェネツィアのオペラ劇場を中心に連夜繰り広げられていた喧騒と享楽の日々を、緞帳の後ろに立って静かに見つめていたマルチェッロ自身の心の声のようにも聞こえました。
ベネデット・マルチェッロ=1686年ー1739年、イタリアの貴族にして作曲家、兄のアレッサンドロ・マルチェッロは、映画「ベニスの愛」で有名になったオーボエ協奏曲を書いた人です。ベネデット・マルチェッロには、1720年頃に出版した「当世流行劇場=Il Teatro Alla Monda」という著作があり、これは小田切慎平さん、小野田香織さんの二人によって翻訳され、日本語で読むことができます(未来社刊行)。
この本の内容を、訳者の小田切さんが書いた解説から抜粋してみましょう。
『ベネデット・マルチェッロは、由緒あるヴェネツィアの貴族として生まれ、二十一才でヴェネツィア共和国大委員会委員、二十五才で弁護士、三十才でヴェネツィア共和国で財政を主として受け持つ四十人委員会委員となるなど、政府の要職を歴任した政治家です。最後は五十二才で、ヴェネツィアの西一七〇キロに位置し、ミラノにほど近いプレシアの司教座聖聖堂参事会の議長として赴任し、結局ヴェネツィアに帰ることなく、翌年その地で死去しました。』
(中略)
『その、ベネデット・マルチェッロが、一七二〇年、三四才の時に出版したのが、この「当世流行劇場」という小冊子でした。匿名で出版されたこの小冊子の値段は、当時としては手頃な三〇ソルディ(二〇ソルディ=一リラ)。オペラの台本と同じ大きさの安っぽい紙に印刷され、値段は、ヴェネツィアでも、大衆的な劇場であったサンタンジェロ劇場の入場券とだいたい同じくらいでした。そして、その内容は、当時の百鬼夜行ともいうべきオペラ業界の姿を辛辣に暴き立て、そこに巣食っている、台本作家、作曲家、カストラート、男性歌手、女性歌手、劇場支配人、演奏家、舞台装置家、背景画家、踊り手、ブッファ役、衣装係、写譜係、女性歌手のパトロンや母上、などありとあらゆる人々が、いかにオペラで手抜きをして、成り行き任せで、ずる賢く、名誉や利益を求めて、うまく立ち回ろうとしているかを描き出しているのです。』
『そして、その最大の矛先は、当時サンタンジェロ劇場を活動の中心とし、作曲家、劇場支配人、興行師として辣腕をふるい、何本もの自作のオペラを上演していた、アントニオ・ヴィヴァルディに、そうあの「四季」で有名な作曲家のヴィヴァルディに向けられていたのでした。』
(つづく)