「世に倦む」選書15冊の続きを。⑨の日高六郎編『1960年 5月19日』。1960年10月に出版の岩波新書。60年安保闘争とは何だったかを知る最良の入門書。1960年5月19日の強行採決、6月10日の羽田ハガチー事件、6月15日のデモと樺美智子の死、6月17日の七社共同宣言、6月18日の自然承認、6月23日の岸信介の退陣表明と、怒濤の1か月間が綴られている。戦後民主主義が運動のレベルで爆発した沸点の日本人のドラマ。この政治の激動を通じて、日本国憲法の理念は体制として確立し、いわゆる平和と繁栄の戦後日本ができた。ダワーが言うところの、憲法の理想を日本人が地上に引き降ろした市民革命の瞬間である。SEALDs選書にこの一冊が入ってないことも、どうにも不自然で不可解でならない。運動としての民主主義の意義にコミットするならば、60年安保の歴史を基礎知識として持とうとするのは当然のことだろう。除外された理由は何なのか。われわれは、日本国憲法について、東京裁判について、60年安保について知らなくてはいけない。基本を押さえないといけない。これらは学校教育では教わらないことが多く、正確な知識を持った教師が少ない。この書で歴史の概要を掴んだ上で、丸山真男集第8巻に所収されている「選択のとき」と「復初の説」の2論文を読み、世織書房『同時代人丸山真男について』での日高六郎の回顧を参考にして欲しい。 ⑩の樋口陽一の『個人と国家』。立憲主義について知る適当な教材は何だろうということは、誰もが思案して思い悩む問題だろう。SEALDs選書には、立憲主義を概説したテキストのセレクトが特にない。これも不具合に感じる点だ。私は、この本とは別に、同じ樋口陽一の『憲法と国家』と長谷部恭男の『憲法とは何か』の3冊を読んでみた。立憲主義とは何かを学ぶためである。その上で、推薦する一冊として集英社新書を選んだ。最も分かりやすく説明されていると感じたからであり、樋口陽一らしい社会科学的な百花繚乱の関心が書かれ、立憲主義の意味が歴史的に説かれているからだ。社会科学的な視角からの立憲主義論という点で、他の2冊は物足りない。最近、社会科学をジェネラルに語れるオーソリティが本当にいなくなった。そうした大型で豊穣な知性と説得力を持った学者は、81歳の樋口陽一くらいのものだ。その意味で、今は樋口陽一の時代だと言える。今年の憲法学者の活躍はめざましく、憲法学者だけがアカデミーで唯一信頼できる存在であることをつくづく思い知らされた。立憲主義の学説とは樋口陽一の代名詞でもある。しかしながら、残念なことに、今年の立憲主義のブームは、決して立憲主義が市民に学習され議論された理性的なムーブメントではなかった。
⑩の樋口陽一の『個人と国家』。立憲主義について知る適当な教材は何だろうということは、誰もが思案して思い悩む問題だろう。SEALDs選書には、立憲主義を概説したテキストのセレクトが特にない。これも不具合に感じる点だ。私は、この本とは別に、同じ樋口陽一の『憲法と国家』と長谷部恭男の『憲法とは何か』の3冊を読んでみた。立憲主義とは何かを学ぶためである。その上で、推薦する一冊として集英社新書を選んだ。最も分かりやすく説明されていると感じたからであり、樋口陽一らしい社会科学的な百花繚乱の関心が書かれ、立憲主義の意味が歴史的に説かれているからだ。社会科学的な視角からの立憲主義論という点で、他の2冊は物足りない。最近、社会科学をジェネラルに語れるオーソリティが本当にいなくなった。そうした大型で豊穣な知性と説得力を持った学者は、81歳の樋口陽一くらいのものだ。その意味で、今は樋口陽一の時代だと言える。今年の憲法学者の活躍はめざましく、憲法学者だけがアカデミーで唯一信頼できる存在であることをつくづく思い知らされた。立憲主義の学説とは樋口陽一の代名詞でもある。しかしながら、残念なことに、今年の立憲主義のブームは、決して立憲主義が市民に学習され議論された理性的なムーブメントではなかった。 1946年の民主主義のようには真摯に学ばれず、反問と相克と陶冶の中で定着するという知的過程にはならなかった。本当なら、樋口陽一の本を、明治の国民が福沢諭吉の「学問のすすめ」を読んだようにして熟読し、庶民のレベルであれこれと論議をしなくてはいけなかった。立憲主義は民主主義とは緊張関係にある原理であり、二つは対立的で矛盾的でもあるという問題は、樋口陽一も言い、この間ずっと言われてきたが、その中身について、あるいはそれをどう捉えるかについては、掘り下げて突っ込んだ議論がなかった。立憲主義のお勉強が低調だった。本来なら、まだ一般に定着してない理論であり概念なのだから、終戦直後の民主主義のように、これが立憲主義だ、否それは立憲主義ではないというような、侃々諤々の討論が国民の中に巻き起こり、論争を通じて各自が言葉を錬磨する思想的展開こそがあるべきだった。ところが、SEALDs運動はそれをせず、最初は「民主主義って何だぁ」と、米国流デモの直輸入をモノマネでやっていたのを、後から「立憲主義って何だぁ」とフレーズだけ付け加えるだけというお粗末さで終わり、立憲主義の学習と議論を促す知的運動は全く提起されることがなかった。SEALDs運動は、「なんだぁ」に「これだぁ」がセットになって、民主主義も立憲主義も、すでに獲得され確定された安直な与件(既成概念)であり、一人一人が思考し格闘する課題ではなかった。
1946年の民主主義のようには真摯に学ばれず、反問と相克と陶冶の中で定着するという知的過程にはならなかった。本当なら、樋口陽一の本を、明治の国民が福沢諭吉の「学問のすすめ」を読んだようにして熟読し、庶民のレベルであれこれと論議をしなくてはいけなかった。立憲主義は民主主義とは緊張関係にある原理であり、二つは対立的で矛盾的でもあるという問題は、樋口陽一も言い、この間ずっと言われてきたが、その中身について、あるいはそれをどう捉えるかについては、掘り下げて突っ込んだ議論がなかった。立憲主義のお勉強が低調だった。本来なら、まだ一般に定着してない理論であり概念なのだから、終戦直後の民主主義のように、これが立憲主義だ、否それは立憲主義ではないというような、侃々諤々の討論が国民の中に巻き起こり、論争を通じて各自が言葉を錬磨する思想的展開こそがあるべきだった。ところが、SEALDs運動はそれをせず、最初は「民主主義って何だぁ」と、米国流デモの直輸入をモノマネでやっていたのを、後から「立憲主義って何だぁ」とフレーズだけ付け加えるだけというお粗末さで終わり、立憲主義の学習と議論を促す知的運動は全く提起されることがなかった。SEALDs運動は、「なんだぁ」に「これだぁ」がセットになって、民主主義も立憲主義も、すでに獲得され確定された安直な与件(既成概念)であり、一人一人が思考し格闘する課題ではなかった。 ⑪の大塚久雄の『国民経済 - その歴史的考察』。学生諸君にはどうしてもこの本を読んでもらいたい。高度経済成長の基本思想が何だったかを知ってもらうためである。戦後、1950年代から1960年代の東大(法・経)の学問と教育の基調がどこにあり、どういうエリートを育てて霞ヶ関や各界指導部に送り出し、どのような国家と経済を建設しようとしていたのか。どのような経世済民の理念だったのか。誰がその指導者だったのか。それを知るために⑪を読んで欲しい。今、新自由主義が当然の空気の中に生きている君たちは、GDPが大きくなればなるほど格差は開くものだという常識を持っている。それが間違った固定観念だということは、日本の高度成長の事実が証示している。戦前の日本は現在よりも厳しい格差社会であり、格差社会というよりも身分制社会だったこと、橋田壽賀子のドラマで歴然だろう。その、一部が富み大半が貧しい暮らしだった社会を、日本は高度成長によって一億総中流社会に変えた。誰でも平等に教育を受けられ、平等に医療を受けられ、年金がもらえる社会に変えた。終身雇用と年功序列の企業に就職し(非正規などあり得ない)、現場で自分の力を存分に発揮して満足な会社人生を全うできる社会に変えた。世界から、地上で唯一成功した社会主義国と言われ、その絶倫の生産力と技術力を欧米に恐れられ、新興国のモデルとなった日本。その秘密を、この社会科学の古典がベーシックに教えている。
⑪の大塚久雄の『国民経済 - その歴史的考察』。学生諸君にはどうしてもこの本を読んでもらいたい。高度経済成長の基本思想が何だったかを知ってもらうためである。戦後、1950年代から1960年代の東大(法・経)の学問と教育の基調がどこにあり、どういうエリートを育てて霞ヶ関や各界指導部に送り出し、どのような国家と経済を建設しようとしていたのか。どのような経世済民の理念だったのか。誰がその指導者だったのか。それを知るために⑪を読んで欲しい。今、新自由主義が当然の空気の中に生きている君たちは、GDPが大きくなればなるほど格差は開くものだという常識を持っている。それが間違った固定観念だということは、日本の高度成長の事実が証示している。戦前の日本は現在よりも厳しい格差社会であり、格差社会というよりも身分制社会だったこと、橋田壽賀子のドラマで歴然だろう。その、一部が富み大半が貧しい暮らしだった社会を、日本は高度成長によって一億総中流社会に変えた。誰でも平等に教育を受けられ、平等に医療を受けられ、年金がもらえる社会に変えた。終身雇用と年功序列の企業に就職し(非正規などあり得ない)、現場で自分の力を存分に発揮して満足な会社人生を全うできる社会に変えた。世界から、地上で唯一成功した社会主義国と言われ、その絶倫の生産力と技術力を欧米に恐れられ、新興国のモデルとなった日本。その秘密を、この社会科学の古典がベーシックに教えている。 ⑫のオーウェルの『1984年』。前回、政治学は丸山真男の『現代政治の思想と行動』の一冊だけでよいと断言したが、オーウェルのこの作品だけは例外だ。この本は、まさに政治学の本である。これを読まないと、今の政治の談議についていけない。例えば、「二重思考」とか「ニュースピーク」とか、オーウェルが物語の中で登場させた概念は、今では普通に眼前の政治を語る言葉として使われている。そして、その意味を理解して誰もが使わないといけない状況になっている。まさに日常の政治用語になっている。そういう思想家と著作が他にあるだろうか。ロールズの正義論がどうのとか、アレントの「悪の凡庸」がどうのとか、そうした議論はよく見かけるが、オーウェルの「二重思考」や「ニュースピーク」を凌駕する程度と迫力ではないことは言うまでもない。オーウェルが架空の国の政治を語る上で開発した言語は、それなしに今の日本の政治とイデオロギーを分析できないものになった。「ビッグブラザー」も「2分間憎悪」も、今の政治の現実そのものである。10年前はそうではなかった。間もなく、人はあの「テレスクリーン」がインターネットであることを知るだろう。オーウェルは21世紀の日本を予見してこの小説を書いたかのごとくであり、私は慄然としながら「1984年」の世界に夢中になっている。ウィンストンはどうなったのか、オセアニア国はどうなるのか、それを考えることは、自分自身と日本の運命を考えることと同じなのだ。
⑫のオーウェルの『1984年』。前回、政治学は丸山真男の『現代政治の思想と行動』の一冊だけでよいと断言したが、オーウェルのこの作品だけは例外だ。この本は、まさに政治学の本である。これを読まないと、今の政治の談議についていけない。例えば、「二重思考」とか「ニュースピーク」とか、オーウェルが物語の中で登場させた概念は、今では普通に眼前の政治を語る言葉として使われている。そして、その意味を理解して誰もが使わないといけない状況になっている。まさに日常の政治用語になっている。そういう思想家と著作が他にあるだろうか。ロールズの正義論がどうのとか、アレントの「悪の凡庸」がどうのとか、そうした議論はよく見かけるが、オーウェルの「二重思考」や「ニュースピーク」を凌駕する程度と迫力ではないことは言うまでもない。オーウェルが架空の国の政治を語る上で開発した言語は、それなしに今の日本の政治とイデオロギーを分析できないものになった。「ビッグブラザー」も「2分間憎悪」も、今の政治の現実そのものである。10年前はそうではなかった。間もなく、人はあの「テレスクリーン」がインターネットであることを知るだろう。オーウェルは21世紀の日本を予見してこの小説を書いたかのごとくであり、私は慄然としながら「1984年」の世界に夢中になっている。ウィンストンはどうなったのか、オセアニア国はどうなるのか、それを考えることは、自分自身と日本の運命を考えることと同じなのだ。 ⑬の立花隆の『天皇と東大』。文春文庫で4分冊の大書。東大(帝国大学)を通して日本の近現代史を描いた渾身の歴史ノンフィクション。この本はもっと評価されていいし、話題になって議論されてよく、学生に推薦されてもよいと思うが、内田樹だの、東大岩波系の、業界マッチメイクな売らんかな本(マーケティング商品)ばかりにスポットが当たっている。そのことが私は不満だ。血盟団事件、美濃部達吉と天皇機関説事件、蓑田胸喜と滝川事件、平泉澄の皇国史観、矢内原忠雄事件、津田左右吉事件、平賀粛学、河合栄治郎事件、等々、重要な知識界の事件史が説明されている。どれも、生半可に知っている程度で、詳しくは知らないことが多く、この本は勉強になった。この文庫4冊の歴史情報群は、まるで丸山真男集のサブテキストそのものだ。日本の近現代史の主役は二人いて、一人は天皇であり、もう一人は共産党である。国体思想と共産主義。この二つの鬩ぎ合いこそ日本の近現代の政治思想史の真相に他ならず、立花隆の方法的視角は当を得ている。それこそが、敗戦して国家を再出発させるときのギブン(所与・前提)だった。この国で自由と民主主義を考える者は、近現代史の歴史の知識を確実にしなくてはいけない。侵略戦争へと進む天皇制ファシズムの思想と、アンチテーゼとしての日本マルクス主義を知らなくてはいけない。こうした骨太の歴史認識の方法は、最近では流行らなくて、ジェンダーだの何だのと脱構築の社会学の方向に簡単に流れてしまう。
⑬の立花隆の『天皇と東大』。文春文庫で4分冊の大書。東大(帝国大学)を通して日本の近現代史を描いた渾身の歴史ノンフィクション。この本はもっと評価されていいし、話題になって議論されてよく、学生に推薦されてもよいと思うが、内田樹だの、東大岩波系の、業界マッチメイクな売らんかな本(マーケティング商品)ばかりにスポットが当たっている。そのことが私は不満だ。血盟団事件、美濃部達吉と天皇機関説事件、蓑田胸喜と滝川事件、平泉澄の皇国史観、矢内原忠雄事件、津田左右吉事件、平賀粛学、河合栄治郎事件、等々、重要な知識界の事件史が説明されている。どれも、生半可に知っている程度で、詳しくは知らないことが多く、この本は勉強になった。この文庫4冊の歴史情報群は、まるで丸山真男集のサブテキストそのものだ。日本の近現代史の主役は二人いて、一人は天皇であり、もう一人は共産党である。国体思想と共産主義。この二つの鬩ぎ合いこそ日本の近現代の政治思想史の真相に他ならず、立花隆の方法的視角は当を得ている。それこそが、敗戦して国家を再出発させるときのギブン(所与・前提)だった。この国で自由と民主主義を考える者は、近現代史の歴史の知識を確実にしなくてはいけない。侵略戦争へと進む天皇制ファシズムの思想と、アンチテーゼとしての日本マルクス主義を知らなくてはいけない。こうした骨太の歴史認識の方法は、最近では流行らなくて、ジェンダーだの何だのと脱構築の社会学の方向に簡単に流れてしまう。 ⑭のオリバーストーンとピーター・カズニックの『もうひとつのアメリカ史』。これは、NHKで10回分のドキュメンタリー番組として放送された。特に解説の必要もないと思われるが、世界と日本を見る上での基本的知識を提供する傑作である。米国の戦後史が、共産主義(ソ連)との戦いの歴史であったことが示されている。マッカーシズムの説明は手薄な感じがあるが、第二次大戦の総括と原爆の真実を語る部分は秀逸で、特にキューバ危機の描写は圧巻だ。ベトナム戦争も過不足なく描かれている。軍産複合体こそが米国政治の主役であり、影の支配者であることが結論され、オバマ政権でもそれに変わりがないことが分かる。⑮のエドワード・サイードの『戦争とプロパガンダ』。これは、2001年の同時多発テロからイラク戦争までの間の米国で、戦争反対の論陣を果敢に張り、ネオコンのイデオロギーを暴露して戦ったサイードの言論をシリーズにしたものだ。白血病と闘いながら、サイードは孤独にこれを書き、絶筆となった。21世紀、「テロとの戦争」が始まったときの政治思想史のテキストとして、そして知識人の言論のお手本として、自由と民主主義を考える皆さんにお薦めしたい。以上、自由と民主主義を考えようとする学生諸君を想定して、推薦書15冊を紹介した。本は何のために読むのか。学生は何のために学問するのか。知識人になるためである。知識人とは何か。ウォルフレンはこう言っている。
⑭のオリバーストーンとピーター・カズニックの『もうひとつのアメリカ史』。これは、NHKで10回分のドキュメンタリー番組として放送された。特に解説の必要もないと思われるが、世界と日本を見る上での基本的知識を提供する傑作である。米国の戦後史が、共産主義(ソ連)との戦いの歴史であったことが示されている。マッカーシズムの説明は手薄な感じがあるが、第二次大戦の総括と原爆の真実を語る部分は秀逸で、特にキューバ危機の描写は圧巻だ。ベトナム戦争も過不足なく描かれている。軍産複合体こそが米国政治の主役であり、影の支配者であることが結論され、オバマ政権でもそれに変わりがないことが分かる。⑮のエドワード・サイードの『戦争とプロパガンダ』。これは、2001年の同時多発テロからイラク戦争までの間の米国で、戦争反対の論陣を果敢に張り、ネオコンのイデオロギーを暴露して戦ったサイードの言論をシリーズにしたものだ。白血病と闘いながら、サイードは孤独にこれを書き、絶筆となった。21世紀、「テロとの戦争」が始まったときの政治思想史のテキストとして、そして知識人の言論のお手本として、自由と民主主義を考える皆さんにお薦めしたい。以上、自由と民主主義を考えようとする学生諸君を想定して、推薦書15冊を紹介した。本は何のために読むのか。学生は何のために学問するのか。知識人になるためである。知識人とは何か。ウォルフレンはこう言っている。 「知識人というのは、博識である人とか、硬派ものの記事を書く人とか、大変な学識のある人とかとは違う。こうした人もおそらく知識人ではあろうが、所詮は役人、もしくはジャーナリスト、もしくは学者でしかないのもしれない。別の言い方をすれば、これらは真実の追求、あるいは客観的な理解の追究を、金銭とか安全保障とか相互扶助とかの追求より大切であると考えるとはかぎらない人々なのである。知的な誠実さを何よりも尊しとする姿勢こそ、知識人のきわだった特徴である。人が知識人であるがためには、独立不羈の思索家でなくてはならない。役人、ジャーナリスト、学者など、自分の頭を使って仕事をする人々も『知識人』たりえようけれど、これらの人はしばしば、この名称に値するほど知的に誠実ではないのが普通だ。わが身にどんな結果が振りかかろうとも、あくまで、筋をとおして考えることを自分の責務とする人々の意見は、これが権力の行使のされ方に関連する問題を取り上げたものである場合、もっとも価値が高くなる。権力行使のあり方こそ、日常の社会生活面で我々に影響を与える、他のすべての事柄を決定づけるからだ。言いかえれば、知識人は、政治問題を詳しく説いてもらうために最も必要とされるのである。我々の自由が無用に縮小されたり、権力を保持する者がその支配下にある万人を災難に追い込んだりしないよう取り計らう上で、知識人こそ我々の持てる最大の希望である」(窓社 『日本の知識人へ』 P.4)。
「知識人というのは、博識である人とか、硬派ものの記事を書く人とか、大変な学識のある人とかとは違う。こうした人もおそらく知識人ではあろうが、所詮は役人、もしくはジャーナリスト、もしくは学者でしかないのもしれない。別の言い方をすれば、これらは真実の追求、あるいは客観的な理解の追究を、金銭とか安全保障とか相互扶助とかの追求より大切であると考えるとはかぎらない人々なのである。知的な誠実さを何よりも尊しとする姿勢こそ、知識人のきわだった特徴である。人が知識人であるがためには、独立不羈の思索家でなくてはならない。役人、ジャーナリスト、学者など、自分の頭を使って仕事をする人々も『知識人』たりえようけれど、これらの人はしばしば、この名称に値するほど知的に誠実ではないのが普通だ。わが身にどんな結果が振りかかろうとも、あくまで、筋をとおして考えることを自分の責務とする人々の意見は、これが権力の行使のされ方に関連する問題を取り上げたものである場合、もっとも価値が高くなる。権力行使のあり方こそ、日常の社会生活面で我々に影響を与える、他のすべての事柄を決定づけるからだ。言いかえれば、知識人は、政治問題を詳しく説いてもらうために最も必要とされるのである。我々の自由が無用に縮小されたり、権力を保持する者がその支配下にある万人を災難に追い込んだりしないよう取り計らう上で、知識人こそ我々の持てる最大の希望である」(窓社 『日本の知識人へ』 P.4)。


















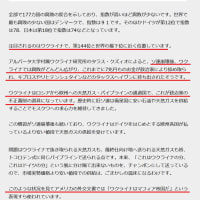



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます