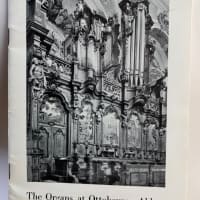“Auf wiedersehen, Fatherland”
EUの基軸国であるドイツにおける移民問題は、フランスやイギリスほど大きな注目を集めてこなかった。しかし、ドイツに移民をめぐる問題がないわけではない。実は別の問題が静かに進行していた。
これまでドイツは、トルコなどからの移民受け入れ国というイメージが強かった。しかし、改めてドイツの受け入れ数と送り出し数の差を見ると、ネットでは送り出しが多くなっているという記事*が目にとまった。
北海に面したドイツの港町ブレーマーハーフェンBremerhaven から19世紀には、ドイツ、ロシア、スカンディナビアなどから、7百万人近くが新大陸アメリカなどへ移民していった。私は訪れたことがないが、この港町にある「ドイツ移民センター」には、当時の出港時を体験させるコーナーや移民が目指したアメリカ、ニューヨーク港外のエリス島移民管理事務所などの展示があるらしい。当時、出港は移民にとってドイツ国籍を捨てることであり、祖国との永遠の決別を意味していた。
しかし、その後かなり長い間、ドイツはトルコなどを中心に移民を磁石のように引きつける国であった。とりわけ「ガストアルバイター」プログラムが機能していた1970年代半ばまでは、多くのトルコ人労働者がドイツへやってきた。その後、移民へのドアは閉じられていったが、ドイツはEU諸国の中でも圧倒的な移民受け入れ国であった。そして1989年のベルリンの壁崩壊は、東西ドイツ間の人の移動を増加させた。荒廃した東ドイツから豊かな西ドイツへ、エスニック・ジャーマンの帰国、ソヴィエットからのユダヤ人の移住などが進んだ。
だが、今や流れは逆転している。外国人やエスニック・ジャーマンの入国数は大きく減少し、逆に故国を離れるドイツ人が加速している。2004年だけでも15万人以上のドイツ人が、海外出国の届けを提出した。1884年以降、最大の数である。流出・流入の差でみると、ネットで流出の国となっている。今は出国も航空機や列車になり、かつてのような移民や家族が悲しむ光景もみられない。高い熟練・技能を持った人には、ベルリンだろうが、ミュンヘン、ロンドン、ニューヨーク、どこでも違和感がない。
ドイツの政治家はしばらく前まで移民労働者の流入を問題としていたが、いまは流出問題にひそかに悩んでいる。ドイツに魅力を失った若い人が出国する動きが強まっているからである。2006年前半6ヶ月に69,000人のドイツ人が出国、47,000人が戻ってきた。ネットの流出は22,000人である。 心配のし過ぎかもしれないのだが、これから長く続く国力衰退の一歩かもしれない。
確かに8200万人の国民からみれば取るに足らない小さな数だが、その背後に「頭脳流出」brain drain という深刻な問題が隠れている。優秀な頭脳の持ち主が海外へ流出する問題である。正確な実態は不明だが、アメリカやスエーデンなどで brain gain の方が多いというのに、うわさではドイツは流出の方が多いらしい。
ひとつの例が挙げられている。ドイツ医師会によると、12,000人のドイツ人医師が海外、特にイギリス、スイスなどで働いているとのこと。イギリスの医師不足が深刻なことは以前に記したこともある。昨年、アメリカで働くドイツ人医師の数を上回った。そして、同じドイツ語圏のオーストリアが、ドイツ人医師にとって第3位の出稼ぎ先に浮上している。
スイスではドイツ人医師が良い仕事を奪っているとの苦情も生まれている。オーストリアでは大学医学部が外国人学生受け入れについて、割り当て枠を導入した。というのも、ドイツ人学生が特にメディカルスクールの入試でよい成績で、オーストリア人学生を抜いてしまうからだ。
しかし、ドイツにとって最も深刻な問題は失業が10%を越え、成長率も他のEU諸国より低下してくると、優秀な若者が自国が機会を提供してくれないと思い海外へ流出してしまうことである。若い世代が自国の将来に夢を失うことほど暗いことはない。
最近はドイツも日本も高度な熟練や専門性を持った人材については、積極的受け入れの方向に動いているが、来て欲しい人材はアメリカなどへ行ってしまう。ドイツの悩みは日本にも共通するところがある。魅力ある国造りはそう簡単ではない。
Reference
“Auf wiedersehen, Fatherland”, The Economist October 28th 2006.