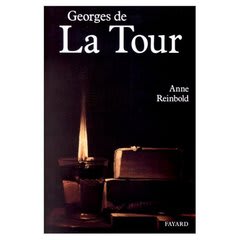- ペトルス・クリストゥス(1410/20ー1475・76)
『若い女の肖像』
1470年頃
ベルリン絵画館
Petrus Christus
Portrait of a Lady
About 1470, Oil on oak, 28 x 21cm
Provenanve: Solly collection, London, Staatliche Museen
Preussischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie, Berlin, 1821
絵画には「肖像画」というジャンルがあるように、古来実に多くの人間の顔が描かれてきた。写真が発明されるまでは、肖像画は写真の代わりを果たしてきた部分もある。
人間ならほとんど当然のことだが、今日でもひと目見てきわめて強く印象に残る顔と、すぐに忘れてしまう顔があることは、写真も絵画もあまり変わりはない。一目惚れというように一度見たら、直ぐに好きになってしまう場合もあるが、好き嫌いを問わず、一度見たら忘れないほど強い印象を残す顔もある。
ラ・トゥールの『いかさま師』に描かれた女性(いかさまの場を取り仕切る女性、彼女の召使い)あるいは『占い師』に描かれている女性たち(卵形の不思議な目をした人物、ひどく醜く描かれた占い師)などは、恐らく好き嫌いという次元を超えて、網膜に焼き付いてしまうタイプではないか。これらの人物は、画家の想像の産物という見方もあるようだが、モデルを最大限重視した画家の性格からも、当時画家の周辺にこれらの人物のモデルがいたと考える方が自然である。
印象に残るタイプは、描かれた肖像あるいは見る側の性別でも多分差異が生まれるだろう。しかし、見る側の性別によって、肖像画の好き嫌いに有意な差異が生まれるかを実験した成果を管理人は残念ながら見たことはない。小さな標本でテストしたことはあるのだが、標本数が小さく統計的検証に耐えない。
ペトルス・クリストゥスの名作
今回、取り上げた作品は、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールから、さらに時代を遡る15世紀中期にブルッヘで活動したペトルス・クリストゥス(Petrus Christus, 1410/1420-1475/1476)という初期フランドル派に分類されるオランダの画家である。画家の後期の作品で、フランドル絵画の傑作の一枚といわれている。
上掲の作品は現在ベルリンの国立絵画館が所蔵するが、来歴には謎めいた部分があり、1821年に王室コレクションを経てベルリン絵画館に移るまでは、ロンドンのSally Collectionに隠れるように含まれていた。
何度か訪れたベルリン絵画館で、対面したことがある筆者には長年にわたるおなじみの作品である。多くの場合、ほとんど観客のいない部屋で見たので、名画の多いベルリンでもながらく印象に残る一枚として脳裏に刻まれてきた。小品なので、知らない人は見逃しかねない。ある時など、どういうわけか、数室にわたり展示室に誰も観客がいなかったこともあった。巡回に当たっていた学芸員が、見どころまで丁寧に説明してくれた。この時はルーカス・クラナッハの作品まで、説明してくれた。日本ではほとんど起こりえないことだった。
1994年にニューヨークのメトロポリタン美術館で、PETRUS CHRISTUS: Renaissance Master of Bruges と題して、特別展が開催された。管理人はながらく専門とは全く関係ない趣味の領域で、17世紀美術の源流にかかわることに興味を抱いてきた。その流れで、この画家には不思議に惹かれるものがあった。その内容はとても短くブログには書き切れないため、今回は省略するが、このクリストゥスの『若い女性の肖像』も、最初に対面した後、今日にいたるまで、ながらく残像が消えずにいる作品だ。有名な作品なので、日本でもご存知の方は多いと思う。
謎を秘めた美女
全体の雰囲気が非常に謎めいている。一見して古典的で貴族の子女と思われる面立ちを見せているが、その表情はかなり硬く、無表情というに近い。陶器の人形のような硬質さも感じる。初めて自分の容貌を画家に描かせるという緊張からか、少なからず人間離れしたような印象も受ける。緊張の極みなのかもしれない。当然、あの『モナリザ』のようなゆとりはまったく感じられず、かすかな笑みも浮かべていない。なんとなく不機嫌な表情との評もある。
彼女はいったい、なにを考えているのだろうか。年齢も10歳代か20歳代か、判然としない。来歴にも謎がある。身につけている衣装、装身具などがフランスに由来するらしいことは指摘されてきた。しかし、彼女がだれであるかについては、イングランドの貴族タルボット卿 第二代シュルーズベリー伯(Lord Talbot, second earl of Shrewsbury, d.1453) の2人の娘のひとりなど諸説があるようだが、いまだに確定されていない。しかし、彼女が当時の高貴な家に関係しているとは、ほぼ間違いない。
一時期、この作品がイタリアのフィレンツェ・メディチ家の1292年の美術品目録に記されていた ”Pietro Cresti da Brggia”ではないかとの推定もあるが、これも確証はない。ペトルス・クリストゥスがどこで、いかなる修業をしたかは明らかではないが、急速に有名になり、ヤン・ファン・アイクの死後、代表的画家の地位を占めていた。およそ30点近い作品が今日まで、継承されている。
作品は木材のoak (カシ、ナラの類)の板を貼り合わせたものに描かれている。背景を見ると、木製の壁あるいは衝立のようなもので、画面中央部が二分されていて、特別の空間であることを思わせる。肖像を描くために、こうした場を設定したのだろう。
こうして一人の若い女性は、自らにまつわる謎を明かすことなく、5世紀近い年月を超えて、われわれの目前に不思議な容貌のままに生きている。
所蔵美術館のブックマークから
Reference
PETRUS CHRISTUS: Renaissance Master of Bruges, The Metropolitan Museum of Art,New York
追悼 ピート・シーガー氏逝去 2014年1月27日(94歳)
1月18日の記事にサイモン&ガーファンクル、そしてジョン・バエズ、ボブ・ディランなどのことを記したばかりだった。ピート・シーガー氏が亡くなるとは、「花はどこへ行った」、「We shall over come」などがいたるところで聞こえていた時代に20代を過ごした筆者には、ことのほか思い出深い。謹んでご冥福を祈りたい。