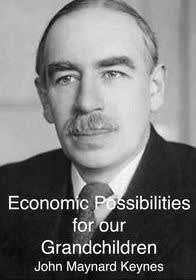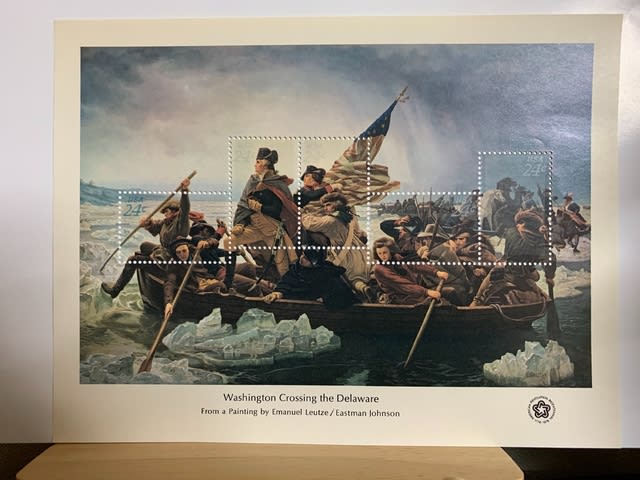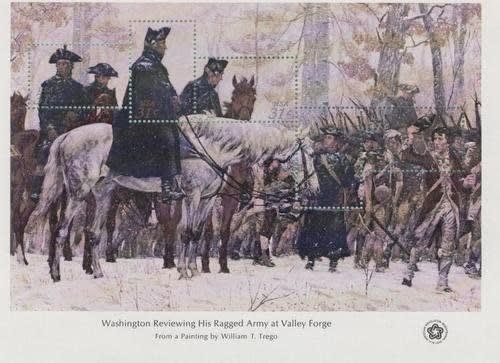前回の記事を掲載した直後、オードリー・タン(唐鳳)さんのインタビューに基づく新著『オードリー・タン 自由への手紙』(講談社、2020年11月17日刊行)を書店で目にした。早速購入し、読んでみた。改めてオードリーさんの考えに感動するとともに、優れた人材は年令、性別などに影響されることなく登用する台湾(中華民国)という国の自由、闊達さに驚かされた。
台湾:暖かな国民性
これまでの人生で台湾はかなりの回数、訪れているが、そのつど、この国の人々の暖かな人間性、親切な応対にはいつも驚かされてきた。政治的立場のいかんにかかわらず、日本では到底会うことのできないような方々も、インタビューなどの時間を割いてくれた。中国本土(中華人民共和国)にも、それに比肩する友人、知人がいないわけではないが、近年国家的統制の色が次第に個人レヴェルまで浸透しているように感じられる。それまでは大変開かれた発言をしていた知人が、習近平政権が成立したころから、香港と台湾の問題はすでに解決済だとの断定的な発言をするにいたって、返す言葉を失ったようなことがあった。それから数年、香港と台湾を取り巻く状況は大きく変わってしまった。
とはいっても、台湾の人々の国民性が最初からこのように暖かな人間性に溢れたものであったというわけでは必ずしもない。この国が経験した厳しい歴史の中から生まれたものだ。親しい友人から1945年連合国軍への日本の降伏後、1949年から1987年までの38年間に及んだ戒厳令下の時代、苛酷な日々の話を聞いたこともあった。とてつもない苦難な日々を克服した結果の間に培われた今日なのだった。友人の中にはアメリカ、カナダなどへ移住した人たちもいた。米中冷戦の間で、国際社会での居場所を狭められ、国名表記すらままならない日々があった。友人から母国の国名すら思うように記せず、勝手に書き換えられてしまう話を涙ながらに聞かされたこともあった。
オードリーさんの新著の基調となる「誰かが決めた「正しさ」には、もう、合わせなくていい」という言葉の意味は大変深く大きい。
スマホを使わない自由
冒頭、オードリーさんがスマホを使っていないということを知って驚かされた。逆のイメージを抱いていたからだ。
オードリーさんがタッチペンやキーボードがあるPCを主に使い、スマホを使わない理由は、「アンチ・ソーシャルメディア」を標榜しているからと記されていた。テクノロジーの支配から自由になるためにあえてそうしているとのこと。指ですぐに操作できるとなると、常にスマホをスクロールしてしまう。そして、ついには依存症になってしまう。スマホに触れないことでSNSに過剰に注意を払わずにすんでいるとの興味深い指摘に出会った(5ページ)。
筆者もPCはテープカセットの時代からなんとか使ってきたが、スマホには長年なじめずにいた。今年年初、新型コロナ感染で万一入院するなどの場合を考え購入はしたが、未だなじめないでいる。小さな画面を見つめていると、思考範囲が狭くなってしまうように感じることもある。電車内で人々が一斉に小さな画面に見入り、歩きながらも読みふける光景には今でも強い違和感がある。しかし、世界はすでにこのテクノロジーにかなり支配されており、それなしに生きることはかなり困難を感じる。
自由が脅かされる今
本書は下記の4部門 Chapter* 毎にに分類された17通の手紙「ーーーーーから自由になる」という構成になっている。それぞれがきわめて重い意味を持っているが、台湾にとってとりわけ重要なのはやはりCHAPTER3に分類されている「13 支配から自由になる」だろうか。その自由が今脅かされているからだ。
CHAPTERS:
*1 格差から自由になる
*2 ジェンダーから自由になる
*3 デフォルトから自由になる
*4 仕事から自由になる
「絶望の切れ間に光がある」(124ページ)
台湾は、現在大きな危機のさなかにある香港を支援するという立場をとっている。1980年代、戒厳令が解除されたばかり、報道の自由もなかった当時の台湾を香港に多数いた国際ジャーナリストが援助したことに、台湾が今恩返しをするというスタンスが強調されている。そして台湾がもっとも長期に及んだ戒厳令時代に苦しんだ国民であり、「すべての希望がついえた」と思われる時こそ、希望を持ち続ける術(すべ)を知っているとの自負の思いが記されている(124 ページ)。
かつて、この国の指導者は教育水準が高くバイリンガルな人たちが多いことに驚かされたが、オードリーさんも台湾語の他に標準中国語、英語、日本語、フランス語などを含む多文化に通じた人のようだ。たくさんの原住民がいる台湾には20を越える言語があるという。そのためもあって「2030年バイリンガルカントリー・プロジェクト」がすでに発足している。
中国とアメリカ、ヨーロッパの間にあって独自の立場を維持するには、言語の点でも格別の努力が必要だ。オードリーさんに代表される台湾の指導者層は、その点でも大きな研鑽を続けてきたことがうかがわれる。
自由への道のりは想像を絶する苦難に満ちている。しかし、オードリーさんの『自由への手紙』には、苦難を克服する多くの処方箋が示されている。それぞれが深い意味を持つが、オードリーさんを含めて、今日の政治家に求められる次の要件がとりわけ頭に残る。優れた政治家は施政方針や現状についての透明性と説明責任能力をすべてネット上に開示し、それをもって「風上へジグザクに進む」という思考法だ。日本ではどれだけ現実化しているといえるだろうか。納得できる説明なしに次々と過去に追いやられ、無理やり風化させれてゆく問題に考え込むばかりだ。