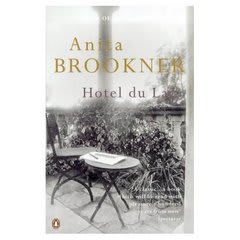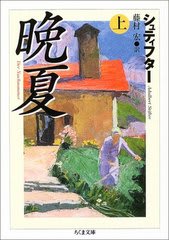いつの間にかあたりに増殖した書籍、資料を整理している中に、Anita Brookner. Hotel du Lac (邦訳:アニータ・ブルックナー、小野寺健訳『秋のホテル』)があった。イギリス文壇最高の栄誉といわれるブッカー賞の受賞作(1984年)である。実際に読んだのは、かなり後の1995年頃であった。カズオ・イシグロの『日の名残り』を読み、映画を見た前後である。
あることから心の傷を負った主人公が、友人が手配してくれたジュネーブ、レマン湖畔のホテルで過ごす間の出来事として、話は展開する。鬱屈したストーリーでありながら、静謐な爽やかさと叙情性をもって描かれている。主人公の女性イーディス・ホウプは、ヴァージニア・ウルフに似た容貌であることになっているが、小説自体も『ダロウエイ夫人』を思わせるようなかすかな陰影を感じさせる。
美術史家としてのブルックナー
小説の内容に立ち入ることが目的ではないが、別の点で気になっていたことがあった。そのひとつは、ブルックナーが小説家になる前から18-19世紀のフランス美術史家としてコートルード美術研究所 Courtauld Institute of Art の教授であり、1967年にケンブリッジ大学のスレード・プロフェッサーに任じられていたことである。ちなみに、初代はジョン・ラスキンだった。ブルックナーはこの分野ですでに立派な業績を残していた。Watteau, Greuze, Jacque-Louis Davidなどの著書がある。美術史家としての背景がおそらく小説にも反映するのだろう。淡々としていながらも描写に陰翳があり大変美しい。なぜ、小説を書くようになったか、その背景を知りたくなった。
もうひとつ気になっていたことは、『秋のホテル』という邦訳名であった。原著の英文タイトルは Hotel du Lac であり、邦訳が出てもしばらく気づかなかった。その後、邦訳を手にして「あとがき」を見ると、訳者は名手の小野寺健氏だが、「デュ・ラック」という言葉が読者に分かりやすいものではあるまいとの編集部の考えもあって、『秋のホテル』になったと記されていた。『湖畔のホテル』では平凡すぎる、あるいは軽薄な印象を与えるということだろうか。今日まで気になっていた。
原著と翻訳の間
原題を知らずに邦訳を読んだ場合には、おそらくほとんど違和感なく受け入れているのだろう。確かに人生の秋を思わせるような印象もないではない。しかし、同時に、ジュネーブのレマン湖に近い、特別の設定をされたホテルで静かに繰り広げられるストーリーには、必ずしも「秋」という設定にしない方がよいように思われた。
こうした感想を抱きながら、その後これもふとしたことから読むことになったカズオ・イシグロのA Pale View of Hills (1982)も、小野寺氏の訳で、最初筑摩書房から刊行された時は『女たちの遠い夏』という題名で、なんとなく生硬な感じがしていたが、2001年に早川書房から文庫版となった時には『遠い山なみの光』に改題されている。
小説のホテルとはまったく関係ないと思われるが*、Hotel du Lacという同名のホテルが、ジュネーブ、レマン湖畔に存在する。この小説が刊行される前のことだが、偶然にもこのホテルの美しい屋外レストランで夕焼けに映える湖面のヨットや遊覧船を眺めながら、ひと時を過ごしたことがあった。表題を見るたびに思い浮かべる記憶の底の情景である。
Reference
Anita Brookner. Hotel du Lac. London: Granada, 1985.(『秋のホテル』小野寺健訳、晶文社、1988年)
*かなり知られているホテルであり、もしかするとブルックナーはなにかのヒントを得たのかもしれない。知りたいところではある。
近着の季刊誌『考える人』(2006年夏号)を手にする。このブログが「変なブログ」であることは、自他共に認めるところだが、この雑誌もかなり「変な雑誌」である。
ふとしたことで創刊号を手にして以来、なんとなく今日まで読んできた。率直に言って、あまり強い存在感がある雑誌ではない。体裁も地味である。今回は創刊4周年記念特集というタイトルを見て、もう4年も経ったのかという思いがした。
読み手が気になる
創刊号の時から、編集者はいったいどのあたりを守備範囲にするつもりだろうと思い続けてきた。かなり茫漠としたところがあり、頼りない感じがするが、目の前にあるとなんとなく手にしている。哲学、文学から写真、イラスト、料理の領域までカヴァーされており、どんな人が読み手なのだろうかと思ったりする。書き手より読み手の方が気になるのも変である。
過去に類似の雑誌がなかったわけではない。しかし、いつの間にか消えてしまったので、この雑誌もいつまで続くかなと思わないでもない。他方で、なんとかがんばって存続してほしいという思いもかなり強い。
仕事に疲れた時や就寝前などに、何の気なしに手に取っている。アフタヌーン・ティのような存在かもしれない。作品ひとつひとつは短いものであり、密度もさほど濃くない。毛色の変わったエッセイ集と考えられなくもない。このどこからでも入り込めて、さまざまな空間をさまよえるところが良いのかもしれない。
ヴェルヌの世界を追う
このところ、比較的楽しみに読んでいるのは、椎名誠「黄金の15人と謎の島」という連載である。ジュール・ヴェルヌ『15少年漂流記』のモデルとされるマゼラン海峡の無人島を目指す旅のドキュメントである。
原作は1880年に書かれた純然たるフィクションなのだが、多くの謎や仕掛けが含まれているらしい。どういうわけか、子供の頃から漂流記が好きであった。デフォー『ロビンソン・クルーソー』はいうまでもないがウイース『スイスのロビンソン』、ヘイエルダール『コン・ティキ号漂流記』など、次々と愛読してきた。 「ロビンソン・クルーソー」は、経済学その他のモデルにも使われ、一時はかなりのめりこんで読んだこともあった。その他の漂流記もそれぞれに楽しみがあり、同じ本を何度も読んだ。
ジュール・ヴェルヌの『15少年漂流記』 (原題はDeux ans de Vacances、二年間の休暇、1880年)は、大人も子供もあきさせない面白さを持っている。多数の訳書があるが新潮文庫版は、心理学者波多野完治氏の翻訳であることに気づいて、不思議な縁に思い及んだ。いずれ書くことがあるかもしれない。
しばらく忘れていたが、この連載を目にして再び興味が湧き上がってきた。ヴェルヌを近く引っ張り出してまた読んでみよう。こんなことでつながっているこの雑誌、私にとってやはり変な存在である。
1冊の本をめぐり買うべきか、買わざるべきか迷っている。ご存じのダ・ヴィンチ物である。しかし、あのダン・ブラウンの『ダ・ヴィンチ・コード』ではない。これはすでに読んでしまった。
悩みの種は、2003年にドイツの著名な美術出版社「タッシェン」TASCHENが刊行した
Leonardo da Vinci - The Complete Paintings and Drawings
Zöllner, Prof. Dr. Frank / Nathan, Dr. Johannes
Hardcover, 29 x 44 cm (11.4 x 17.3 in.), 696 pages
という大変な作品集である。ブームに便乗した安易な作品紹介や解説本ではまったくない。とにかく、これがよく書籍の体裁に収まったものだと思わせるすごい出来栄えである。現代に再現されたダ・ヴィンチの完璧な作品集である。最初、予約見本をロンドンの書店の店頭で見た時に驚嘆した。その後日本語版も出版された。とにかく、その圧倒的な迫力に押される。(今回にかぎらず、「タッシェン」の出版物は、大作が多い。)
内容はいうまでもないが、まず書籍としての大きさがすごい。特大LLX版のハードカバーでサイズは、29 x 44 cm、696 pages という驚くべきものだ。これが書籍かと思わせる圧倒的なヴォリュームである。この迫力は実物を目前にしないと伝わってこない。手持ちの書籍で匹敵するものはないかと見回したが、一冊本では、The Random House Encyclopedia, 1993 が目についたくらいである。しかし、これとても、このダ・ヴィンチ作品集には到底及ばない。厚さはかなりあるが、体積では半分以下といってもよい。The Random House がこの一冊本の百科事典をやめてしまった理由の一つに、書籍としてこれ以上大きくできないという判断があったといわれているから、とにかくすごい。
陋屋のやわな書架では到底大きさ、重量ともに耐えられず、この天才の作品集に適した置き所がない(重さは10kgあるからうっかり足の上にでも落としたら、骨折は疑いない重さである)。机の上に置いたらそれだけで大きな空間を占めてしまい、仕事にならない。体裁はこの通りだが、内容はいうまでもなく、圧倒的にすごい。十分ベネフィットがコストを上回るお買い得であることは明らかである。ダ・ヴィンチの愛好者にとっては、一生あきることのない得難い伴侶となることは間違いない。
3部構成で編集されており、第1部は10章から成り、手紙、日記、契約書、書類を通したダ・ヴィンチの生涯と仕事の詳述、第2部は画家の全絵画作品を掲載している。それも現存する作品ばかりでなく、消滅した作品まですべて網羅している。それぞれの作品の保存状態まで記されており、天才の世界をゆっくりと見ることができる。第3部は素描、ドローイング、スケッチなどを掲載している。ドローイングの半数近くは、ウインザー城が所蔵する作品で、初めて印刷・公刊を認めたきわめて貴重なものである。アマチュアにとっても、見ているだけで大変楽しいし、あきることはない。
結局、魅力にひかれて近く入手することになりそうだが、さてどこに置こうか。
「ドルトムントの奇跡」もついに起きなかったが、この機会にドイツについての記憶を取り戻そうと、書棚から引っ張り出し、少し前から読んでいた本があった。アンドレーア・シュタインガルト(田口建治・南直人・北村昌史・進藤修一・為政雅代訳)『ベルリン<記憶の場所>をたどる旅』(昭和堂、2006年、218ページ)(Andrea Steingart. Schauplätze Berliner Geschite. Berlin: 2004)である。
過去に幾多の悲惨で壊滅的とも思える経験をしながらも、ベルリンは都市としての美しさを維持し続けてきた。個人的にも思い出の多い都市である。緑の多い美しいベルリンだが、過去における幾多の深い傷跡を包み込んでいる。その傷跡の在りかに通りすがりの旅人は気づくことは少ないないだろう。一部を除き、その多くが所在を積極的に主張していないからだ。たまたま乗ったタクシーの運転手から、しばらく前まではここにあった「壁」の近くに住んでいたという話を聞かされ、突然頭の中でフィルムが巻き戻されるような思いがする。
本書に取り上げられた場所は、ほとんどがドイツ現代史の影の部分に関わっている。序文を書いた「ツアイト」誌のベルリン支局長クラウス・ハルトゥングは、次のように結んでいる。「これらの物語には、歪み、矛盾し、そしてしばしば悲劇的であるベルリンの根本的性格が反映されています。さらにこれらの物語は、この都市の宿命を共有するよう求めるのです。この共有なしには、------それもまたこの都市の特殊性の一つですが------私たちがベルリンを理解することはまったく不可能でしょう。」
ベルリンという都市は確かに美しいのだが、ある種の陰影を感じさせる。いかに空が抜けるように青く晴れ渡っていても、そこに形容しがたい翳のようなものを見てしまう。過去を意識してしまうためだろうか。ヨーロッパの他の都市では感じない独特のものである。
本書では、ドイツの現代史にかかわる「皇帝と革命家のベル「リン」、「ナチスのベルリン」、「社会主義統一党のベルリン」、「分割されたベルリン----壁に囲まれた西側----」、「再び統一されたベルリン」の5グループに区分された43ヶ所が写真とともに紹介されている。冒頭には、池澤夏樹氏による「日本語版によせて:新しいホロコースト記念碑のこと」と題した、ベルリンのもうひとつの「記憶の場所」について、本書にふさわしいエッセイが掲載されている。この記念碑もドイツ現代史の最も深い暗部に根ざす出来事を後世に伝えるものだ。
本書で取り上げられた場所は、総じてベルリンが経験した、どちらかといえば影の部分に関連している。このいくつかは私も訪れたことがあり、大きな関心をもって読んだ。ベルリンに必ずしもくわしくない日本の読者のために、訳者たちが現地を訪れて、「日本人のためのガイド」として補足説明や地図が付されている。総体として、読者に対して丁寧な編集がなされている。ぜひ再版の折には、関連年表を付けていただければと思う。ここに取り上げられた「記憶の場所」は、ドイツの若い世代でも知らない歴史的出来事になりつつあるからだ。風化は容赦なく続く。
私の記憶に残る場所からひとつとりあげてみると、「国境地帯に生まれたトルコ人のタマネギ畑」Turkische Zwiebeln im Grengebiet であろうか。1980年代初め、ベルリンのカルテル・オフイスにつとめていた友人に連れて行ってもらった記憶がよみがえってきた。当時、クロイツベルクのトルコ人住宅地域を調査に行ったときに案内してもらった。その荒廃ぶりには言葉を失った。移民問題にのめり込むひとつの契機ともなった。最近訪れてみて、クロイツベルクもずいぶん変わったという思いがした。この「タマネギ畑」もきれいに維持されているようだ。
ベルリンを訪れたことのない人々でも、現代ドイツ史に関心を寄せる方々には一読をお勧めしたい。ワールド・カップのどよめきの裏側にひっそりと存在する、これらの場所を確かに記憶にとどめるために。
「物事をよく知るためには、細部を知らなければならない。そして細部はほとんど無限であるから、われわれの知識はつねに皮相で不完全なのだ。」(M106)
堀田善衛『ラ・ロシュフーコー公爵傳説』集英社、2005年
デュマの『三銃士』*を再読した時にも感じたが、17世紀も今日でも人間の愚かさには変わりがないようだ。時代が変わっても世の中にいさかい、争乱は絶えることがない。堀田善衛の長編三部作『ミシェル城館の人』は以前読んだことがあったが、この『ラ・ロシュフーコー公爵傳説』は初めて手にした。
元来、金言集とか名言集というものはあまり好みではない。というのは、金言や名言は多くの場合短文であり、読む人が置かれた状況次第で受け取る意味も変わってくるからだ。しかし、この作品は、別の点で興味を惹かれた。堀田善衛というきわめて強い個性、ユニークな思想を持った作家が、独特の文体をもって、この17世紀のモラリスト、ラ・ロシュフーコーなる人物を描き出している点である。「箴言集」が生まれる背景の物語といってもよい。ただし、あくまで創作である。ちなみに、堀田善衛はラ・ロシュフーコーの著作マキシムは、わが国ではしばしば「箴言集」と訳されているが、箴言という言葉はなじみがないので、原語のMaximesをそのまま採用するとしている。
たまたま、以前取り上げたリシリューの生涯について、少し立ち入って関連した文献を読んでいる間に、この作品に出会った。前半はリシリューの時代であり、後半にはマザランが登場する。マザランについては、肖像画などから受ける印象では、人当たりの良い穏健な人物であるかに見えるが、リシリューが推薦しただけに、かなり似たところも持ち合わせていたようだ。当時、巷に流行した小唄に次のような「生まれ変わったリシリュー」というのがあったという(本書、p.238)。
彼(リシリュー)は死んだのではない。
年齢を変えただけなのだ。
この枢機卿(マザラン)は誰も彼もを怒らせる。
堀田善衛がラ・ロシュフーコーというモラリストの生涯と思想の根源に迫った作品は、読み出すと止められない独特の面白さがある。この創作が現実とどのくらいの距離があったかについては、語ることができない。しかし、17世紀フランスという時空を理解するについて、多くのヒントが散りばめられていることは確かである。
著者は作中で、ラ・ロシュフーコーに17世紀を「女の世紀」と呼ばせている。デュマの『三銃士』でもそうであったが、王妃を始めとしてさまざまな女性が、縦横無人に活躍しているのは大変印象的であった。離れて見ると、実に面白い時代であったことに改めて気づく。
冒頭に記したマキシムについて、一言。このブログ、お気づきの通り、「断片」ばかりである。それが集まると、なにかが見えてくるだろうか。
本ブログ内関連記事
*
http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/d/20060418
ラ・ロシェルの攻防戦におけるリシリュー*
Courtesy of:
Henri Motte 1846-1922
Richelieu at the siege of La Rochelle, 1881
Oil on canvas, 112.2x190.5 cm
La Rochelle, Musée des Beaux-Arts
『三銃士』再読
ある会議出席のため、列車と航空機でかなりの時間を過ごさねばならないことが分かった。そこで機内の退屈しのぎに、2,3の書籍を選んで持ってゆくことにした。たまたま最近のブログで話題としたフランス宰相・枢機卿リシリューに関連して、この際、あのアレクサンドル・デュマの名作『三銃士』を読み直してみようと思いついた。中学生の頃だったろうか、一度読んだことは覚えているのだが、翻訳者も誰であったかまでは記憶していない。当時はヨーロッパの歴史についての知識も十分でなく、フランスにも行ったことがなかったのだから、強い印象が残らなかったのも当然なのだが。
時間を忘れられる書物
そこで、携帯に便利で入手しやすい岩波文庫版『三銃士』上下(生島遼一訳、1970年改訳)*を持ってゆくことにした。 機内で読み始めてみると、これが想像していたよりはるかに面白い。訳文はちょっと古めかしい感じもするが、ほとんど気にならない。昔読んだ時も面白かったという記憶は残っているが、これほど巧みにストーリー展開が考えられていたとは思わなかった。
特に複雑なプロットや思想などが込められているわけではない。リシリューの時代の出来事を虚実を含めて描いているのだが、最後まで読者を倦ませることがない。あらためて、デュマの力量に感嘆する。最初は新聞小説の体裁をとったといわれるから、読者はさぞや次が待ち遠しかっただろう。しかし、日本人としてこの作品を読むについては、やはりヨーロッパ、とりわけ17世紀のフランス史について知識がないと面白みは半減してしまう。
お読みになった方はご存じの通りだが、三銃士とダルタニャンにとって、リシリュー枢機卿(生島訳では枢機官になっている)はいわば不倶戴天の敵役である。本書では枢機官の名で、頻繁に登場する。政治的にも、軍略の上でも際だった辣腕の持ち主として描かれている。王に忠誠を誓いながらも、実は王とも対立しており、王と王妃も反目していた。さまざまな策略が渦巻き、リシリューは多数の密偵を放ち、あらゆる情報を集めていた。いわば、今日のCIA長官のような役割も果たしていた。
リシリューはルイXIII世と並び、あるいは王を凌ぐ権力の持ち主であったといわれるが、それだけに敵も多かった。暗殺者も横行し、日夜を通して、油断できない毎日を過ごしていたようだ。ひどい不眠症であったといわれるが、こうした緊張感が生み出したものだろう。もしリシリューの日常がこのデュマが描いたものに近かったならば、とても落ち着いて寝られるような人生ではなかったに違いない。
リシリューの実像は?
さて、『三銃士』の中で、リシリューがうわさではなく、実際に姿を現すのはダルタニャンが一時、部屋を借りていたボナシュウという小間物商が捕らえられて、尋問のためにリシリューの部屋につれて行かれた場面である。ちなみに、この男の妻ボナシュー夫人は身分に比して才たけて、密かに王妃の絶大な手助けとなっており、われらがダルタニャンと愛人関係にもなっていた。
ボナシュウがまさか枢機官とも知らずに連れて行かれた部屋での状景は次のように描かれている:
「暖炉の前には、尊大な容貌をした中背の男が立っている。広い額に鋭い眼、口髭のほかに唇の下にのばした髭が痩せた顔を一層細面に見せていた。この男はまだせいぜい36、7の年齢だったのに、髪も髭ももうごま塩になりかけているのだった。剣はつっていなくとも、十分武人と見える面魂があったし、まだ埃の少し残っている長靴は、その日のうちに馬上どこかに出かけたことを語っていた。 この人こそ、アルマン=ジャン=ヂュブレシ、すなわりリシリュー枢機官だったのである。」 (上巻216ページ)
リシリューについては、肖像画などを通して、表面的にはあるイメージを再現することができるが、実際にはいかなる人物であったか、さまざまな風説もあり、本当のところは不明な点が多い。敵とすればこれほど怖い存在はないが、忠誠を誓って部下となれば徹底して庇護したともいわれる。しかし、波乱万丈、一時も気を許せない環境に生きたために、心身の疲労も一通りではなかったのだろう。椅子に深く腰掛けた小柄な老人のような姿を描いた作品もある。
後年、デュマの時代に形成されていた一般的イメージを推し量る意味で、この『3銃士』で描かれているリシリュー像はきわめて興味深い。そこで長くなるが、続けて引用してみよう。
「この人物の姿として我々がよく教えられている、老朽して殉教者のように苦しみ、体躯は折れ屈み、声は衰えて、この世ながらの墓のように深い肘掛け椅子に身をうずめている老人、ただ精神力だけで生きており、知力だけで全欧州を向こうに闘っていた人、そんなのではなく───いま眼の前にいるのは、この時代に実際にそうであったままのこの人の姿なのである。つまり、俊敏で風雅な武人、すでに体力は衰えかけているが前代未聞の傑物たらしめている精神力に張り切って、マントゥア公領でヌヴェール公を援助し、ニームを攻略し、カストル、ユゼスを奪取した後、いよいよイギリス軍をレ島から追い払い、ラ・ロシェルを攻囲しようと意気込んでいる人なのであった。」(217ページ)
文人としての側面
さらに、その後、プロテスタントの拠点として著名なラ・ロシェルの戦いを前に、ダルタニャンが対面した時のリシリューは、自室で書類を調べている裁判官のような男に見えたが、実際には机に向かって指で韻を数えながら、詩を書いていた。その表紙には『ミラーム5幕悲劇』と書かれていた(118ページ)。こうして、リシリューには多忙な日々の中にも、詩作にふける文人としての一面があったことが伝わっていた。
デュマのこの描写から推察できるように、当時リシリューについて行き渡っていたイメージは、権謀術数にたけた武人でありながらも寸暇を惜しんで詩作にふける文人でもあった。しかし、心身の疲労も急速に進んでいたのだろう。年齢よりも老人に見えたに違いない。彼の日常がこのデュマが描いたようなものに近かったとしたら、とても神経が休まる時などなかったろう。なにしろ、身辺にいる者の誰が敵方のスパイや暗殺者であるか分からなかったほど、複雑怪奇な実態が展開していた。
さらに、デュマの『三銃士』には王妃をはじめとして、あのミレディーなる妖艶にして恐ろしい貴婦人も登場し、ストーリーが展開する。当時の読者ならずも、次に何が起こるか胸をときめかせて読みふけることは疑いない。途中で筋が割れてしまうようなことがないのは、さすがである。
かくして、出かける時はいささか憂鬱であった長旅も、始めてみると、あっという間に終わってしまった。こうした書物にはワインに熟成の時があるように、読む側にもそれにふさわしい準備が必要なことを痛感させられた。
*イギリスの軍船を港に近づかせぬよう、リシリューの創意でプロテスタントの拠点であるラ・ロシェルの港に築いた大防波堤。
* デュマ(生島遼一訳)『三銃士』 1970年改訳版、岩波書店
「17世紀のデルフトでは、生活に秩序があった。富める者も貧しい者も、カトリックもプロテスタントも、主人も召使いも、それぞれの場所をわきまえていた。」
Tracy Chevalier. Girl with a Pearl Earing, Limited Edition, 2005.
この小説の著者トレイシー・シェヴァリエについては、このブログでも何度かとりあげたことがある。2000年に刊行された直後に読み、大変印象が深かった。その後、この作家のスタイルを確認したいと思って、 『貴婦人と一角獣』も読んでみた。
「お気に入り」リストに入ったシュヴァリエ
ご存じの方も多いはずだが、オランダ17世紀の画家フェルメールを題材とした小説である。映画化もされた。なぜ、もう一度読むことになったのかというと、最近、ふとしたことで、この原作で「限定版」(Limited Edition with new material and illustrations)と銘打ったハードカヴァーを手にしたことによる。以前読んだのは同じ出版社ハーパー・コリンズ社のペーパーバック版であった。
この「限定版」は大変表紙も美しい。そして、著者の「あとがき」や小説に出てくるフェルメールの作品、年譜、デルフトの地図なども掲載されていて、読者にとっては便利でもあり、大変魅力的な書籍に出来上がっている。それでもう一度、読んでみたくなった。
デルフトの記憶
小説の舞台デルフトには10年ほど前、1995年に一度だけ訪れたことがある。実は、毎日愛用しているデルフト焼きのマグも、その時買い求めたものだ。静かな落ち着いた感じの町であった。当時はアムステルダムのティンバーゲン研究所のヴィジティング・フェローとして短期間受け入れてもらっていたこともあり、たまたま体験できたオランダの美術環境には、さまざまな関心を呼び起こされた。
記録によると、フェルメールは1632年に生まれ、1675年に43歳で突然に世を去っている。このブログでも取り上げているロレーヌの画家ラ・トゥールよりは少し後の生まれだが、美術史上はほとんど同時代の画家といってよい。ラ・トゥールが「赤の画家」とすれば、フェルメールは「青の画家」である。
この限定版で特に興味を惹かれたのは、ペーパーバックにはない著者「あとがき」Afterword である。それによると、この作品は1999年の刊行だが、シュバリエが小説とする発想を抱いたのは、97年11月であったとのことである。ある朝、自宅の壁に長らく掲げられていたフェルメールのこの作品のポスターを眺めていて、小説への発想が生まれた。19歳の時に購入し、その後16年近く見ていたと記されているから、まさに突如として気づいたようだ。
少女の表情が生んだ小説
作品のプロットが展開するきっかけになったのは、やはりこの少女の表情らしい。それまでずっと眺めていて気づかなかった不思議な表情に突然閃いたものがあるようだ。世間を知らない少女のようでありながら、成熟した女性のようでもある。画家フェルメールはいかなる背景の下で、この少女をモデルとしたのだろうか。この点がシュヴァリエの発想の原点となる。
シュヴァリエはデルフトにも行き、フェルメールの作品や生涯についても調査を行った。世界中に多数のファンがいるフェルメールだが、この画家もラ・トゥールに似て、その生涯がいかなるものであったか、あまり良く分からない。年譜によると、1653年には富裕な家の出自でカトリック教徒の妻を迎え、プロテスタントであった自分はカトリックに改宗したようだ。11人の子供が生まれた。当時のデルフトでは、市民のおよそ20%がカトリックであった。新教国オランダでは、この時期にプロテスタントが圧倒していたのだ。そして、画家は結婚した年に、画家のギルドGuild of St. Lukeに親方画家master painter として加入している。
シュヴァリエは、この限定版のアイディアを大変喜んでいる。その最大の理由は、読者にフェルメールのファンが多いとはいえ、小説に出てくる作品のイメージを思い浮かべる人はそう多くないからだ。作家は「あとがき」に、この絵を言葉で説明するには「7500語を費やしても難しい」と記している。そのために、シュヴァリエは小説技法として、仕事中の事故で視力を失った少女の父親に、奉公先の画家や作品の説明をする形で、詳しい記述をしたと記している。最初から限定版のアイディアがあれば、良かったのにと思うのは素人考えだろうか。いずれにせよ、フェルメールの作品が挿入されたことで、大変リッチな一冊となった。フェルメールについては、世界的にも多数のすばらしい研究サイトがあるが、最小限必要な資料などが本書の中に含まれることになったのは、読者にとっては大変有り難い。
不思議なつながり
さらに、興味があることが記されている。シュヴァリエはこの小説でフェルメールについての既成観念を創り出してしまうことを懸念したと述べている。しかし、この小説を書いてから1年くらいして、小説の方向として多分間違っていなかった(perhaps I was on the right track)という奇妙な形の確認ができたとの感想を記している。それは、最初主人公であるこの少女の名前をGriet(Margrietを短くしたもの、英語ではMargaret、日本語邦訳では「フリート」と表記されている)とした。短くて、はっきりしていて、すべてを尽くしており、彼女の名前として最適と思ったからだという。ところが、もっと学のある人がその後知らせてくれたことによると、この名前が彼女にふさわしいもっと良い理由があるという。それは、Margrietはラテン語で「真珠」を意味する 'margarita' に由来するからだとのことであった。
原著
Tracy Chevalier. Girl With a Pearl Earing. London: Harper Collins, 2000.
邦訳
トレイシー・シュヴァリエ、木下哲夫訳『真珠の耳飾の少女』白水社、2004年。
______.Girl With a Pearl Earing. Limited Edition with new material and illustrations. London: Harper Collins, 2005.
Homepage of Tracy Chevalier:
http://www.tchevalier.com/gwape/inspiration/index.html
References
フェルメールはファンが多いだけに、世界中に多数の関連サイトがある。その中で、今回シュヴァリエが参考になったと記しているサイトを紹介しておこう。ちなみにこのサイトは質量ともにきわめて充実している:
http://www.essentialvermeer.com/index.htm
フィリピンに関するある文献を探索する過程で出会った一冊である。春江一也氏の作品は、「プラハの春」、「ウイーンの冬」そして最近の「ベルリンの秋」まですべて読んでいるつもりだったから、一瞬とまどった。これまでの作品の印象から、次の舞台も東欧か中欧という思いこみがあった。そのためもあって、今回手にした文庫版*に先だって、この作品が2002年に刊行されていたことをうかつにも知らなかった。
しかし、本書を取り寄せてみて、直ちに納得した。春江氏はフィリピン、ダバオの総領事館に勤務した経験もあったのだ。同氏の作品は、いずれも外交官時代の経験に基づいて、事実面での考証がしっかりしており、その上に組み立てられるストーリー展開は大変巧妙であり、いつも一気に読んでしまった。最近の妙な日本語では、「読まされてしまった」といえようか。読み出すと、他の仕事を放り出してしまうので、「プラハの春」に出会った時から、春江氏は私にとって「危ない」作家だった。エンターテイニングな作品でありながら、しっかりと調べられた時代的背景などにも惹かれてのめり込んでしまう。
いまやほとんど知る人がいなくなった、20世紀初めフィリピンへの日本人出稼ぎ労働者のその後が本書で展開する。フィリピンへ出稼ぎに行くが、志を果たせず、マニラなどで貧困にあえぐ生活をしていた日本人出稼ぎ労働者が、ある実業家に連れられて、ダバオに移住した。
彼らは文字通り艱難辛苦の時を経て、1930年代にマニラ麻の原料アバカの栽培に成功した。ダバオは日本人が発展の素地を築いた地であった。カリナンはダバオの郊外に現存する小さな町Calinanのことである。しかし、第二次大戦によって状況は一転、荒涼たる光景へと変わる。
そして、戦後を舞台とした同じ場面において、この小説の主人公柏木雪雄が登場する。柏木は日本の一流銀行の経営幹部の一人であった。しかし、バブル期の放漫経営の結果、破綻する。特別背任の罪を背負った主人公は責任感も強く、服役する。そして、刑期満了後、自らが背負った個人としての遠くなった記憶の糸をたどり、ダバオを訪ねる旅に出る。
彼の背景には読者があっと思うような過去が存在し、そのための自らの再生の旅もまた思いもかけない展開となる。フィリピンと日本の関係は、単に複雑だという表現はそぐわないほどである。大変長く深く屈折した過去につながっている。日本人で、その全体像が見通せる世代の人々はきわめて少なくなった。一時、大きな話題となった「山下財宝」が重要な道具立てとして登場してくる。といっても、ご存じない世代の方が圧倒的に多い時代になりました。
フィリピンと日本の関係は、戦前、戦後を含めて、容易に説明しえないほど入り組んだ経緯をたどってきた。サスペンス・ドラマの形をとりながらも、巧みに歴史的事実をふまえた着実なストーリー展開に思わず引き込まれて読みふけってしまう。 あとがきでは、重要な登場人物のひとりである女性医師も、アメリカに行っている。フィリピンの医師、看護婦が海外へ多数働きにいっている問題は、このブログでもとりあげたことがある。半ば楽しみながらも、フィリピンという国と日本との関わり合いを改めて考えさせられてしまう。
*
春江一也『カリナン』集英社文庫、2005年(2002年に同社から刊行された作品の文庫化)。
本ブログ内の関連記事
http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/e/637b174a6bdab08bf5d9038d061e20b6
W・G・ゼーバルト(鈴木仁子訳)『目眩まし』白水社、2005年
息抜きのつもりで読み始めたのだったが、やはりしっかりと読まされてしまった。この作家の作品は『アウステルリッツ』『移民たち』*を読んで、かなりスタイルには慣れていたつもりであったが、前作以上に手強かった。
なにしろ、スタンダールの旅、カフカの旅と、自分の旅を重ね合わせる構成となっている。『移民たち』ときわめて似た構成ではある。しかしながら、今回は文豪の旅と重なり、一段と重厚味を増している。スタンダール、カフカはあまり読んだことがない。文学専攻の友人の話に出てきた時などをきっかけに、いくつか読んだきりだ。
作家が自ら楽しみ、読者を翻弄するかのように技巧のかぎりを尽くして編み込んだ虚構の世界と作家の実体験とが、文字通り虚実の隔てなく次々と展開する。時の流れを縦糸に、空間を横糸にした織物に作家が思うがままにストーリーを編み込んでいる。文学カテゴリーとしても、小説なのか、回想なのかも分からない。ぜーベルト独特の世界というほかはない。
題名につられて読んだ『移民たち』もそうであったが、この作家のとりあげる舞台は、不思議となじみのある土地が多いのも、ひきつけられて読んでしまう源である。インスブルックからブレンナー峠を越えて北イタリアにいたる地方は、生涯の友人となったドクターK(インスブルック大教授)夫妻と旅したことがあり、位置関係が浮かんでくるので迫真力を持ち込んでくれる。ある年の夏、ガルミッシュ・パルテンキルヘンからインスブルックを通り、ブレンナー峠を越えてボルツアーノ、ベローナへ抜けた記憶がよみがえってきた。
第二話「異国へ」に出てくるイタリア、リモーネのホテルで、パスポートをとりちがえられて紛失する事件など、警察署の証明の写真などが出てくる。これもゼーベルトの作品の特徴ではあるが、果たして本物なのだろうかと思わせるのは例のごとくである。すっかり、作家の術中にはまった感じがする。
四つの物語というのが、『移民たち』に続き、不思議なプロットである。なぜ四つでなければならないのか。これ以上少なくとも、多くとも成立しないという微妙な数である。
ゼーバルトは人生の後半をイギリス、イーストアングリア大学での教員をしながら、作家活動を続けていた。ここのクリエイティブ・ライティング・コースは、あのカズオ・イシグロ**やトレーシー・シュヴァリエ***が学んだところでもあった。どんな教育をしているのだろうかと興味が尽きない。
本ブログ内関連記事
*
http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/e/7cf3df99ccfd335c17c8134302da6a7c
**
http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/e/481ff293f2a1eaf4f1957dfb7b353827
***
http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/e/b67799fe64fc5e88cc35ff7ea57b5daf
インターネット社会といわれ、情報は溢れるばかりに存在するが、信頼できる情報は必ずしも十分ではない。昨日のヒーローも今日は落ちた偶像、移ろいやすい世の中。物質的豊かさという意味では歴史上の最高水準に達したともいえるが、不安や危機感はかえって増幅している。現代社会に生きる人々の抱く不安や幸福感はどこから生まれるのだろうか。このブログでもとりあげているジョルジュ・ド・ラ・トゥールが生きた16-17世紀の人々と比較して、どんな違いがあるのだろうか。こんなことをとりとめなく考えながら、小さな(しかしきわめて濃密な)本を読んだ。現代イギリス文壇の第一人者ともいわれるイアン・マキューアンの新著『土曜日』*である。
主人公ヘンリー・ペロウニーは48歳、名手といわれる成功した脳神経外科医である。妻は新聞社の法務分野を担当する有能な弁護士、息子と娘二人の子供に恵まれ、物質的にはなんの不足もない豊かな生活を送っている。堅実に富を築いてきた結果を思わせるジョージアン風の家。
2003年2月15日の土曜日夜半3時40分頃、ふと目覚めたヘンリーは、未だ夜の闇に包まれた町並みを寝室の窓から見るともなしに眺めていた。その日に起きたさまざまなことが頭を去来している。窓の外を夜勤帰りの看護婦らしい二人の女性が帰宅の道をいそいでいる。ヘンリーの勤務する病院からの帰途だろうか。交代明けにしては、時間が合わないと彼は思う。すると、まもなく機体から火を噴いているらしい航空機がヒースロー空港に向けて降下して行くのを目にする。最初は流星かと思った光だ。寝ている妻を起こして話そうと思うが、事故であればまもなく大騒ぎになるだろうと思いつつ、脳裏に去来するさまざまなことを考えている。
小説の舞台は、2月15日土曜日という一日だけに設定されている。彼の心のどこかで不安を生んでいたのは世界の状況、とりわけイラクに対する差し迫った戦争であり、17ヶ月ほど前に起きたニューヨーク、ワシントンでの同時多発テロ以来のペシミズムの高まりであった。
この日主人公は、ロンドンの街路を埋め尽くした反戦デモを避けようと同僚の麻酔医とスカッシュ(球技)をプレーするために球技場へ行く途中だった。小さな衝突事故で彼は一人の若者と対決することになる。彼の目からすると、どこか決定的におかしい、正気でない人間に映った。他方、若者はヘンリーが自分を仲間の面前で恥をかかせたと思った。その後、事態は思いもかけない方向へと展開していく・・・・・。
小説の顛末を書くほどおろかなことはない。他方、マッキューアンのこの小説は主人公の外科用メスのように、正確に作家の目指す方向へとプロットを切り裂いて行く。人間のどこかにひそむ恐れ、不安、迷い、さまざまな精神神経症的症状、殺意・・・・・・。そして、人間の求める幸せとはなになのか。
人間の幸せの本質は複雑でとらえがたく、もろく移ろいやすい。それはなまじの小説家が扱うよりも、練達した医師の方がはるかに適している。医師、とりわけ外科医は常に生と死の狭間にある対象を前にして、その行方を追っている。時には、壊れた部分を繕うこともする。幸せを取り戻す役割でもある。彼らにとって小説は不要な存在なのだ。マキューアンはまさに名手の技をもって、この役割を描いている。そこに描かれた現代人の幸せ、そしてあらゆる種類の不安、暴力、そして恐怖の様相は絶妙である。おそらく、この小説家の達した極致的作品のひとつであろう。ブッカー賞(1998)受賞作の「アムステルダム」**よりも、一段と洗練された水準に達していると思われた。
* Ian McEwan. Saturday. London: Vintage, 2005.
本書の邦訳はまもなく新潮社から刊行されるとのこと。
**『アムステルダム』新潮社、1999年
Ian McEwan Homepage
http://www.ianmcewan.com/
見るともなくつけたBSテレビで、あの「ヒトラー最後の12日間」を追体験してしまった。シュピーゲルテレビ(2005年)が制作した「地下壕での死」Death in the Bunkerの放映であった。映画とほぼ同じ光景が目前に展開した。主要な関係者の証言により最後の日々を再現する形になっていた。いつ撮影者の身に危険が及ぶかもしれないすさまじい戦闘の状況をよく撮影したと思う。
映画の短縮版のような印象を受けるが、映画と異なって俳優ではなく実在した人物の映像が現れ、衝撃的である。映画で見たゲッペルスの家族の最後、とりわけ6人の子供に青酸カリのカプセルを与えるゲッペルス夫人がしばらく残像に残って困ったこともあり、演説するゲッペルスの実像が印象に残った。ヒトラーばかりでなく、周囲の指導者を含めて、「狂気の集団」だった。
今回のテレビ版で新たに目にしたことは、4月30日ソビエト軍がヒトラーの地下壕から100メートルの距離へ迫った時にヒトラーと夫人となったエヴァ・ブラウンが自殺した後の状況が示されていたことである。伝えられるように「歴史に名が残る」と、最後の日に結婚したエヴァ・ブラウンの心境とは実際にはいかなるものだったのだろうか。
ヒトラーとヒトラー夫人となったエヴァの遺骨はソビエト軍によって確保され、モスクワKGB公文書館で密かに保管されていた。ゲッペルス夫人の遺骨も含まれていた。60年近い年月を経て公開されたものであった。ベルリン陥落後も長らく謎に包まれていたにもかかわらず、映像で見るかぎり想像したほど厳重な保管状態でないようにも見えた。狂気の歴史の断片がそこにあった。
reference
「ヒトラーの最後:目撃者たちの証言」世界のドキュメンタリー・シリーズ、 2006年1月20日BSテレビ1
本ブログ内関連記事
http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/d/20051125
*The Macclesfield Psalter の海外流出抑止を訴える募金ポスター
中世書籍の制作をめぐって
作家の伊集院 静氏が1月13日付『日本経済新聞』の「読書をする人十選」)で、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの作品「聖母の教育」(「聖母の読書」)を取り上げ、その中に描かれている書籍がなにであるのか興味を持ったが、確認できなかったと記されている。
実は、私もこの書籍はなにを書いたものであるのか関心を持ち、その部分を拡大してみたことがあった。しかし、なにか挿絵のようなものがあることは読み取れたが、書籍の内容についてまでは確認できなかった。このラ・トゥールの作品「聖母の教育」については、真贋論争の渦中の一品でもあり、このブログではまだ取り上げていないが、いずれ話題としてみたい。
中世装飾本の世界
実はラ・トゥールの作品に登場する書籍(いくつかある)は、キリストや使徒たちの時代を想定すれば、画家がイメージしたのは彩色本であったのかもしれない。この彩色本について、イギリス、ケンブリッジ大学のフィッツウイリアム美術館とケンブリッジ大学図書館の共催で、昨年末まで開催されていた『中世西欧における書籍制作の10世紀』と題する特別展**があった。
この特別展は昨年7月から年末まで開催され、フィッツウイリアムズ博物館やケンブリッジ大学の学寮などが所蔵する、金、銀などで彩色した書籍(装飾本)を中心にヨーロッパから集められた展示物であった。 あのラ・トゥールの生涯の探索にも登場するメッスの文書なども含まれていた。現在はある意味で伝統的な印刷書籍の終焉の時を迎えつつあるのかも知れない。電子出版が着実に拡大しつつある。しかし、紙に印刷した書籍もそう簡単になくなって欲しくない。
印刷術の発明者がグーテンベルグか否かは異論があるようだが、15世紀中頃までは、Book というとしばしば「聖書」のことを意味したといわれる。 こうしたことを考えていると、現在我々が日常手にしている印刷書籍に先行した彩色本制作について、新たな興味が湧いてきた。
4世紀にパピルスは現在の書籍の形態によって代替された。最初は羊皮紙だったが、その後紙が取って代わる。15世紀中頃までは羊皮紙に印刷されることもあったらしい。そして、初期ルネッサンス、ダンテ、ペトラルカ、チョーサーなどの作品を今日に伝えてきた。
活版印刷物が出回る前に制作されていた書籍に金銀を含む顔料で彩色した作品が、今回の展示が焦点を当てたものであった。 これらの彩色本の制作は、みるからに複雑な過程を必要とするとともに制作費も高価であり、多大な時間を要したことが分かる。その背後に富裕なパトロンの富、地位、趣味などさまざまな条件が必要となる。
マクレスフィールド・サルター文書
この展示で最大の注目を集めたのは、The Macclesfield Psalterと呼ばれるイギリスの彩色原稿である。宗教戦争、社会的不安、放置などのために多くのフレスコ画やパネルが逸失してしまっている今日、この小さな書(170x108cm)はイギリスの中世絵画の精緻な成果を今日に伝えている。
この書籍はイーストアングリアのシルバーン城 Shirburn Castle のマクレスフィールド伯爵の図書室の棚に何世紀も文字通りたなざらしになっていた。そして、2004年6月22日サザビーのオークションにかけられ、アメリカのポール・ゲッティ美術館が購入した。
しかし、その後、美術品の輸出に関わる委員会などの目にとまり、フィッツウイリアム博物館などが中心になって、イギリスの国家的面子にかけて大規模なキャンペーンを展開し買い戻したものである*。14世紀(1330年代)イーストアングリアにおける最も注目すべき装飾本のひとつといわれている。
興味をそそる内容
この一部分だけを印刷したものに以前出会ったことがあり、今回の特別展を契機に新たな興味がわいてきた。以前から特に記憶に残っていたのは、兎が馬に乗っている場面とか、猿が壺に入れた飲み物を病人らしき人に運んでいる場面とか、深海の「えい」のような魚が描かれていたりして、『鳥獣人物戯画巻』の情景を思わせる部分があったからである。
今回の特別展に展示された文書の挿絵や解説の一部を読んでいると、中世人の不思議な世界の一端が浮かび上がってきて思わず引き込まれて行く。 このマクレスター・サルター文書を展示した特別展には、彩色文書を作成した顔料、絵筆、補修材なども展示され、大変興味深いものであった。「聖母の教育」につながる「書籍」の歴史も追いかけてみたいテーマではある。
Reference
The Macclesfield Psalter. Cambridge: The Fitzwilliam Museum, 2005
**
The Cambridge Illuminations: 26 July-11 December 2005
http://www.cambridgeilluminations.org/
クリスマスが近づき、海外の友人などからのメールが届く。電子メールの時代、カードはめっきり少なくなった。それでも、この時期に友人やその家族が過ごした1年の消息を知るのは率直にうれしい。この時代、決して心の和む話ばかりではないが、それが人生なのだと思う。
ある友人の生き方
オーストリアの古い友人からの長いメールがあった。10年ほど前から長らく専門としていた社会科学の領域から離れ、まったく別の学問領域であるイタリア中世の研究を始めた。以前の専門領域でも立派な成果を残していたのに、蔵書も処分し、あっさり方向転換してしまった。その過程では多くの悩み・煩悶もあったのだと思う。しかし、その転換には共感することも多かった。かなりの部分を共有している。新しい仕事に必要なイタリア語も10年前から個人教師について学び準備していた。中世キリスト教会の世俗的繁栄の陰に隠れていた膨大な貧困の発見などに新たな資料を掘り起こしている。すでにいくつかの著作も生まれた。
『晩夏』との出会い
この友人との交友を通して、不思議と念頭に浮かぶ一冊の本がある。オーストリア領、南ボヘミアに生まれたシュティフター Adalbert Stifter (1805-1868)という作家の『晩夏』(Der Nachsommer, 1857年)という大部の著作である。「晩夏」とは、その言葉の与える印象とは異なり、「冬」、言い換えると死を前にしておくればせに出現したつかの間の夏の幸福、という意味が込められているらしい。
作家はこの作品の時代設定を1830年に設定しながらも、激動する現実とはおよそ隔絶した理想郷、自然と文化、とりわけ芸術との接点を象徴し、人間性実現のための美的教育の場として「薔薇(ばら)の家」を想定・構築した。この「薔薇の家」の主人リーザハ老人が、結ばれるべくして結ばれなかった昔の恋人マティルデとその子供たちと心を通わせつつ、つかの間の幸せに浸っている世界を描いている。
作品の主人公は語り手であるハインリヒという青年だが、実はリーザハの思い描いた姿である。ハインリッヒはマティルデの娘ナターリエと結ばれ、「ばらの家」で「人間が人間となるべき」道を学び、そこで養われた愛と精神を蓄え、混沌と激動の世の中に生きるのであろう。ストーリーは、現実とは遠い世界で、しかも時が進んでいるのか、止まっているのか分からないほどゆっくりと進んでゆく。この梗概を聞いただけで、実際にどれだけ作品を手にする人がいようか。
偶然の不思議さ
実は、私がこの大部で難解で、退屈な作品の一部に出会ったのは、なんと教養ドイツ語課程のテキストとしてであった。こんな作品をテキストに選定した教師の「非常識さ」を恨んだ。実際、テキストは原書から一部分を抜き出しただけで、最後につけられた解説なしには、まったく作品の構成すら把握できなかったのだから。話の展開自体があまりにゆったりとしていることに加えて、文体にもかなり難渋した。しかし、不思議なことに、この作品は私の脳細胞のどこかに残っていた。
10年ほと前に、先述のオーストリア人の友人夫妻と南アルプスの山中深く旅した時にふと思い出し、ひとしきり話題となった。 文学史上、一般的にこの作品の評価は、退屈極まりない(「終わりまで読み通した人にはポーランドの王冠を進呈する」ヘッベル)という意見から、オーストリア文学の宝であり、「繰り返して読むに値する僅かな作品の一つ」といったニーチェまで、両極端に分かれている。 しかし、はるか以前から大勢は「いまさらシュティフターでも」という流れに入っていることだけは間違いない。ドイツ文学を専門とする友人に聞いても、あまり興味を示してくれない。大体、読んだことがある人自体少ないのだから。
友人も私も、この作品の評価はどちらかというと後者に近いのだが、条件づきであった。この長編を読み通し、その世界に共感するには読者の側の時間の熟成など、いくつかの条件が準備されねばならないことも分かったのだ。 シュティフターという作家とは前述のごとき妙な出会いではあったが、いつかこの作品を通して読んでみたいと思っていた。しかし、日本では完訳がなく、といってドイツ語テキストで散々な思いをしただけに、このためにドイツ語の再学習をする気にもなれない。というわけで、折に触れて「石さまざま」(岩波文庫)などの小品だけを読んでいた。
作品との再会も偶然であった。1979年の暮れ、ふと立ち寄った書店で『晩夏』(藤村宏訳、世界文学全集 31巻、集英社)の完訳が出版されていることに気づき、直ちに買い求めた。訳者藤村宏氏の素晴らしい解説も付されており、初めてこの作品の全容に接することができた。その時の感動は忘れられない。多くの人は手に取ることすらしないだろう退屈な、およそ「反時代的」作品である。(2004年には筑摩書房から文庫版としても刊行された。この報われないかもしれない長編の訳業に取り組まれた藤村宏氏と両出版社の見識にはただ脱帽するのみである。装幀は当然ながら集英社版の方が良いが、絶版である。多分あまり売れなかったのだろう。これからお読みになる勇気のある方は、ちくま文庫版をお探しになることをお勧めする)。
「時間」が必要な作品
本書の解説の最後に、訳者藤村宏氏が「時間を持つ」書物という小見出しの下で、本書についてのリルケの深い含蓄に富んだ言葉を引用されている:
この本はアーダーベルド・シュティフターの詳細な小説『晩夏』です。世界でもっとも急ぐことがなく、もっとも均斉がとれた、もっとも平静な書物の一つです。そして、まさに、それ故に、非常に多くの人生の純粋と穏和が働きかける書物です。あなたがまだ ”時間をお持ち”にならなければならない間は、幾時間か、この小説に耳をお傾けになるのがよろしいと思います。・・・・・・*
そして、原著の挿絵銅版画彫刻を担当したアックスマンは次のように記しているという:
我が国の誇るべき作家シュティフターのこの傑作を、三回は読まなくてはいけない。まず初めは、価値ある享受の時間を生むために。
二回目は、素晴らしい作品構成を、その論法と文体について賞賛するために。
そして三度目は、物語にいかなる隠れた意味が潜むかを明らかにするため**
* 文庫版下巻解説:藤村宏、480
**文庫版上巻解説:小名木榮三郎、506
Reference
シュティフターについてもっと知りたいと思う方に、こんな立派なブログもありました。
シュティフターの書庫
http://homepage1.nifty.com/lostchild/stifter/shu_book.htm#banka
Warke シュティフターの紙ばさみ
http://homepage1.nifty.com/lostchild/stifter/shu_f.htm
このブログでも『白い城』、『イスタンブール』などの作品を取り上げてきた現代トルコ文学界の旗手オルハン・パムクの名前が、最近新聞などメディアにしばしば登場している。今年のノーベル文学賞候補の一人でもあったようだ。最初にこのブログに書いた頃は純粋に文学的興味から取り上げたのだが、その後作家が位置する政治的状況などを知るに及んで読み方が深まってきた。
渦中の人となったパムク
最近になってパムクを取り巻く状況は急転した。この12月16日に、イスタンブールで作家を相手取った公判が開かれた。第一次大戦中のクルド人およびアルメニア人大量虐殺に言及することがタブーになっているトルコで、この問題をスイス、ドイツなどのメディアで表立って批判したことが、イスタンブール市の検察官によって「国家侮辱罪」にあたるとして告訴されたのである。
欧州連合EU加盟の条件である「言論の自由」を認めるか否かの試金石として世界の注目を集めたこの裁判だが、対応に苦慮した裁判官は「法務相の判断を仰がねば裁判を進められない」として、開廷直後に中断し、来年2月まで延期するとした。
パムク氏は法廷の出入り口で右翼から卵を投げられたり、わざわざ傍聴にやってきた欧州議会関係者なども殴られたり、蹴られたりという一幕もあったらしい。
友人がいないトルコ?
改めて述べるまでもなく、トルコはEU加盟が実現するか否かの微妙な段階にある。トルコとしては、この問題でEU側からブレーキをかけられることだけは回避したいのだろう。前トルコ駐在アメリカ大使などが繰り返し指摘していたように、「トルコにはPRの遺伝子が欠けている」といわれるほど、自国のイメージづくりがうまくなかった。このような現代のトルコを形容するによく使われるそうだが、「トルコはトルコ以外に友人がいない」といわれてきた。近隣国との関係など確かに円滑ではない。もっともトルコにかぎらず、日本もまったくその通りなのだが。
パムクの指摘した点は、クルド人問題だけでなく1915年のオスマン帝国のアルメニア人移送・殺害問題である。アルメニア人は、キリスト教徒で、オスマン帝国領内に多数居住していた。オスマン陸軍は第一次大戦中、アルメニア人がロシア側につく動きがあったとして、当時アルメニア人の「反乱鎮圧」を行った。スイスのメディアに、パムクは「100万人のアルメニア人が殺された。だが、私以外にだれもそのことを語ろうとしない」と指摘した。
旧ソ連が崩壊し、アルメニアが独立した90年代以降、虐殺を国際的に認知させようとするアルメニア人側の働きかけが活発化した。その結果、オーストリア、フランス、ベルギーなど欧州の多くの国の議会が虐殺だったと認めた。
「言論の自由」は、EU側にトルコとの加盟交渉を中断させる材料となりかねない重要テーマでもある。EUの側にも、これまで加盟国を急速に増やしてきた「拡大疲れ」があるといわれる。
トルコ加盟の前に横たわる最大の障壁は、ヨーロッパの背後に潜む反イスラーム感情だが、トルコの世俗化したイスラームは、キリスト教とイスラーム世界の緩衝材となる可能性もあると指摘する人々もいる。他方で、トルコがそうした役割を果たそうとするならば、アルメニア人問題など、非イスラーム少数者の問題解決に着手すべきだという人々も多い。
作品に流れる思い
パムクの作品には東西文明の衝突、共存の方向を探る糸、イスラームの役割、EU加盟を求めるトルコの現実と苦悩など、多数の脈流が流れている。今回の母国との対立がいかなる帰趨をたどるか。この作家の作品と行方は、一層目が離せなくなった。
Reference
「語る作家、裁くトルコ:渦中のオルハン・パムク氏」『朝日新聞』2005年12月15日
*2004年11月国際交流基金が主催したオルハン・パムク氏の『私の名は紅』(日本語版)出版記念講演会は、当日どうしても抜けられない仕事のために出席できなかった。思い返すと大変残念である。司会をされたNK氏も思いがけず旧知の間柄であった。
本ブログ内の関連記事:
http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/e/43a23038e8fd958bcc550fd34739a5c2
http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/e/563f881a31ee119f65f61e92ba3031c3
ヨアヒム・フェスト(鈴木直訳)『ヒトラー 最後の12日間』岩波書店、2005年, 244ページ+5
(Joachim Fest. Der Untergang, Hitler und das Ende des Dritten Reiches, Berlin: Alexander Fest Verlag, 2002)
読むに覚悟がいるテーマ
第二次大戦後60周年ということもあってか、昨年から今年にかけてナチス・ドイツ、ヒトラーに関する書籍が出版された。これまでも、ヒトラー、第三帝国をテーマとした出版物は比較的多く読んできたつもりだが、近年は膨大な考証、注などが付された大著が増え始め、しばしば読んでいて辟易とするようなことも多くなった。起きた事実を可能な限り客観的に記し、後世に伝えるという役割を背負った歴史家などには当然のプロセスであっても、その結果を手にした読者には、かなりの圧迫感を与える。
特に対象とするテーマ自体がきわめて重く、陰鬱であるだけに、受け取る側にも相当な覚悟が必要となる。読む側の精神的状態が整っていないと、打ちのめされそうな思いがする。そんなことを2-3度経験した後、しばらく書棚に置かれていた本書を手にした。著者のこれまでの大著と比較すると、膨大な考証資料も付されていないのでなんとか読めそうだと思った。久しぶりに「第三帝国」崩壊後、60年近くの年月が経過した今、新たな視点や発見があるならば、もう一度探索してみたいという気分が生まれていた。
書籍と映像から見たヒトラー
折りしも、『ヒトラー 最後の12日間』が映画化されており、書籍と映像というふたつのメディアから、改めてこの人類の経験した最も暗い時代を追体験した。 フェストの「ヒトラー」は、ベルリン陥落、第三帝国崩壊、ヒトラー自殺の最後の12日間に焦点を集中し、「地下要塞」における狂気が支配した世界を克明に描いている(書籍と映画の間には、さまざまな印象の違いがあるが、その点は別の機会にしたい)。
フェストの今回の著作は脚注、文献考証などを意図的に含まず、読者を一気にベルリン「地下要塞」の異様な終末空間へと導く。第三帝国という奇怪かつ非人道的な存在をつくり上げた一人の男とそれに加担した人物たちが、強い迫真力を持って描き出される。もはや誰の目にも狂人としか思われない精神状態の男によって、支配される醜悪かつ異様な空間は、どうしてこんなところまで行ってしまったのかという恐ろしさを改めて痛感させる。人類はこの時期、こうした世界の存在とおぞましい暴力の蹂躙を許容したのだ。
言葉を失う怪奇な状景
この狂気で満たされた空間に登場する人物は、それぞれが精神的に救いがたいまでに苛まれている。ソ連赤軍の戦車が地下要塞数百メートルの距離に迫り、砲弾が降り注ぐ状況においても、もはや存在しない援軍や奇蹟的事態の発生を信じるヒトラーや将軍たちの心理状態には言葉がない。そして、文字通り破滅的状況にありながら、後継者争いに執念を燃やす将軍たちの異様な姿もそこにある。
フェストによれば、ヒトラーを最後の瞬間まで支えていたのは、途切れることなく堅持された、破滅への意志であった。「人間は、人が良すぎたことを、後になってから悔やむものだ」とのヒトラーの言葉は、この文脈に置かれると実に恐ろしい。
ひとつの世界の破滅とその後
1945年4月30日午後、ヒトラーの自殺によって、焦土作戦と滅亡スペクタクルは恐ろしい破滅へと向かう。文字通り人類を敵とした第三帝国の崩壊は、ひとつの壮大な世界の大崩落であった。しかし、なぜこれだけの舞台装置と犠牲を必要としなければならなかったのか。このとてつもない経験を、その後の世界はどう受け止めたのか。
このひとつの世界の破滅の後も、世界には戦火やテロリズムの惨禍が絶え間なく続いてきた。その実態を見るとき、再び恐るべきあの狂気が人々の心に忍び入る可能性を否定できない。なにも知らず眠り薬と青酸カリを飲まされたゲッペルスの子供たちは、なにを象徴しているといえるだろうか。 「戦争を知らない大人たち」が過半数を占める今日の世界でも、新たな狂気は決して死に絶えず、さまざまにその進入口を求め、拡大の場を探していることを思わざるをえない。
「目を開いていれば、分かったのだが・・・・・・」 (エピローグから)
映画公式ブログ
http://ameblo.jp/hitler/