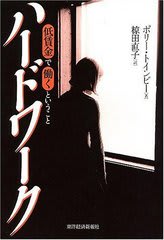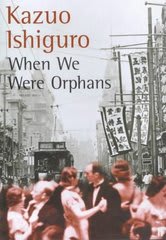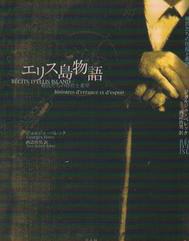The Kite Runner by Khaled Hosseini (London: Bloomsbury, 2003)
気づいてみると、オルハン・パムクに続いて、これもイスラム圏の作者であった。小説:The Kite Runner 『凧を追いかけて』 は、ストーリーの展開が大変巧みでいつの間にか引き込まれ、読まされてしまった。大きな感動を与える作品である。もとはといえば、友人のハリー・カッツ教授に、場所もベルリンのトルコ人移民の多いクロイツベルグのレストランで雑談の折、読後感を聞かされて手にとった一冊である。
著者カーレド・ホッセイニは1980年、政治的な難民としてアフガニスタンからアメリカに移り住み、以来アメリカ西海岸に医師として暮らしているアフガン人である。ちなみに、これは彼の作家としての処女作となる。そしてアメリカで最近までながらくベストセラーの首位を保った。
9.11、イラク戦争、その後に続く同時多発テロなどの過程で明らかになったことは、西欧諸国にとってイスラームの世界は、さまざまな意味で依然として遠い存在であるということであった。そして、多くの日本人にとってもそうであろう。 TVで世界のどこでも実体験できるような感覚になった今日の世界だが、映像と現実の間には、やはり大きな断絶がある。話は著者ホセイニの分身、自画像ともいえる主人公アミールの人生回顧という形で展開する。
1970年代、カブールの町で恵まれた家庭の一人息子として生まれた主人公は、ひとつ年下で忠実な召使いであるハッサンと主従の関係を超えた深い信頼関係を持っていた。だが、古くからの年中行事である凧揚げ競技(日本にもある凧糸にガラスの粉をつけて、相手の凧の糸を切ることで勝敗を競う)で、予想もしないことが二人の関係を断ち切ってしまう。ちなみにkite runnerとは、切り落とされた相手の凧を追いかけて勝利品として手に入れる勝利者のパートナーのことを意味している。
アミールの父親バーバはパシュトン族の成功者として、物心ともに息子が超えがたいと思う大きな存在である。同胞が尊敬する勇気と誠実さを備えている。ともすれば、通俗な郷土の偉人像化しかねないイメージだが、作者はストーリーの展開の巧みさでそれを見事に回避している。話の展開とともに、バーバ自身がかなり複雑な生い立ち、性格を背負っていることも分かってくる。イスラームの世界には、こうした父子の関係が存在するのかと思い、感動する。
父親バーバとポリオにかかり足の不自由な召使いアリ、そしてアリの息子ハッサン、そしてアミールは強い信頼関係で結ばれている。バーバとアリの関係は単なる主従のものではなかった。双方ともに妻を失い、二人の息子であるアミールとハッサンも友情とも異なる強いきずなで心の底で強くつながっている。しかし、アミールは主人と従者、そしてハッサンに対する劣等感のようなものも手伝って、表面的にはハッサンにつとめて冷淡に接してきた。 他方、バーバは従者であるアリ、そして息子のハッサンにも大変人間味あふれる愛情をもって接してきた。時に実の息子アミールにも分からないほどのきずなで結ばれているようだった。そして、どういうわけか、アミールにはあるときまでかなり厳しい対応をした。その理由はかなり後に判明する。
アミールが13歳の時、大きな転機が訪れる。伝統の凧揚げコンテストで、思いもかけないことが二人の関係を冷酷に断ち切る。アミールはハッサンにもはや修復できない精神的な傷を与えてしまう。アミールは父親の勇気を受け継いでいない。父親のような誰をもおそれないような強さがない。そして自らの責任で癒しがたい傷を負い、それはトラウマとしてその後の人生につきまとう。
そして、この時を境に二人の関係、人生も完全に断絶した世界に移ってしまう。アミールとその父親バーバは、ある日ひそかにアメリカへの難民として故国アフガニスタンを捨てる。物語の背景には79年末のソ連のアフガン軍事侵攻、ムジャハディーンとタリバンの対立などの政治的変動が存在する。その状況は、後年アミールがカブールを訪れる後半の部分で生々しく語られる。前半の懐古的な描写と比較して、後半は格段に現実味を帯びる(図らずも、戦乱に明け暮れた時代のロレーヌを思い出してしまう。)
カブールでの豊かな生活とはまったく異なり、アメリカでガソリンスタンドで働き、その後オープンマーケットの露天商となった父の死後、アミールはある電話を機にカブールへ戻る。そこに展開していた状況はなにであったか。 ストーリーはそこから思いもかけない過去を明らかにする。生々流転ともいうべき人々の姿といえようか。
このしっかりと書き込まれた小説(そのかなりの部分は著者の原体験でもあると思われるが)を通して、読者はイスラームの社会や人々の考えの一端に触れる。そこにはわれわれと全く違わない人間としての生き方、考え方が流れている。そのある部分は、日本人がすでに失ってしまったような生き方でもある。読者として、多くのことを考えさせられる。
アフガン人であることは、いかなることであるか。その美しい国は無惨にも破壊され、恐怖の中に生きている人々がいる。 著者はこの複雑な有り様を淡々と、見事に描いている。小説としての洗練さ、技法などの観点からすれば不十分な部分もないわけではない。移民を題材とした特別な小説ジャンルといえるかもしれない。しかし、いずれにせよ読者は間違いなくひとつの大きな感動と満足感を持って読み終えることができる。小説の世界でも、主人公アミールは子供の頃から小説家を目指してきた。ホセイニはアミールに代わってしっかりとその一歩を踏み出した。
Khaled Hosseiniのホームページ
http://www.khaledhosseini.com/