9月13日(日)晴れ
地名研究家である田中先生の案内で網干歴史雑学塾の皆さんと、飾磨区上野田地区に行って来た。
詳しくは田中先生の姫路の地名色模様-夫婦木(めおとぎ)を読んで下さい。
その昔、この場所のすぐ東までが市川だったそうだ。
タイトル写真は夫婦木の地名の由来である二股にわかれた目出度い木と、その北側に祀られている天神さんとお地蔵さん、木の南側には石碑が三基建っている。
訪ねた時は気にかけていなかったが、真ん中の大正14年の石碑に記された寄附金の総額は918円である。
大正14年で918円。そのお金で何をしたのかは調べていないので不明であるが、
ふとある事に気が付いた。
大正6年、興浜にある金刀比羅神社で本殿部分の地上げを行っている。
その時の寄附金は、本殿地上げを言い出したと伝えられる、網干町長もされた山本真蔵氏の200円、当時の興浜惣代であった太田勝治氏の100円、そのあとに80円、70円とつづき総額はまだ計算していない。
しかし918円もあれば相当な仕事ができたように想像できる。
そして、8月14日に掲載した、大覚寺石畳の事を思いだした。
大正4年に今榮儀八郎氏が100円で石畳を寄附したと伝え聞き、その石碑も残るのでそう信じていたが、その当時の100円であれだけの石畳ができたのであろうかと考え、もう一度自分が解読した石碑を見て、思い違いをしていた事に気がついた。
石畳の石の材料は有志がお金を出し合い都合したのだろう。
今榮氏は石工の手間賃として100円を寄附したのではないだろうかとふと思った。
独り言のような記事になりました。


北側の石碑


真ん中の石碑の表


真ん中の石碑の裏


南の石碑の表

南の石碑の裏


お地蔵さんの石でできた花筒には大正14年の文字がある















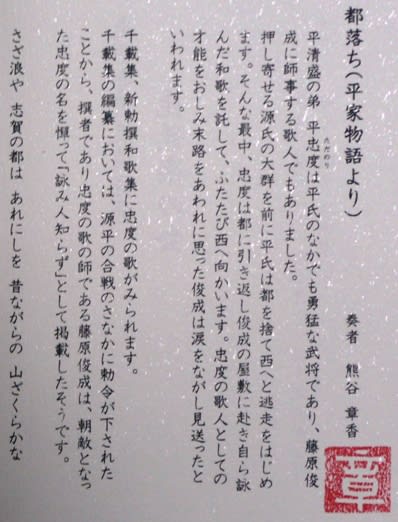















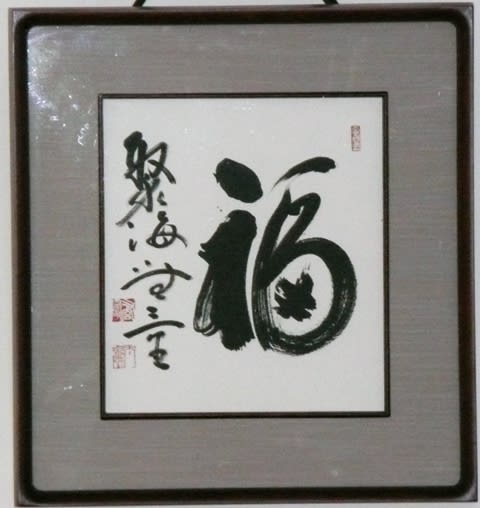









































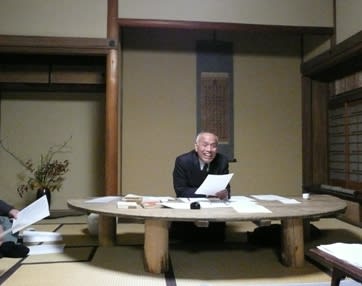





 西釜屋の檀尻も発見。
西釜屋の檀尻も発見。

































































