今朝8月4日の朝日新聞は、新規原発について経産省がエネルギー基本計画に明記しない意向であると伝えた。世耕大臣の話としてである。
今日の金曜ウォークでも話題として取り上げられ、みんなの論議になった。
記事にはこうある。
経済産業省は、原発に対する世論の反発が根強いことなどから、新増設の表現を盛り込むことは時期尚早との判断に傾いている。当面は既存原発の再稼働や運転期間の延長に注力する。
6月9日に日経新聞がエネルギー基本計画に「新設を明記」とリークして、世耕大臣が翌日打ち消して、それ以降、内閣支持率の低下とあいまって、「強硬策」を取り難いという判断も加味されての今回の発表だろうか。
私たちは、以下の3点を確認した。
まず第1に、「新規を明記せず」とは、新規や増設をあきらめたり、今後行わないということではなくて、文章に書かないだけのことで時期をみたり、水面下で潜行して 新設増設の準備と環境整備を行うということである。「時期尚早」、その時期ではないと言っているだけのことである。上関原発についていえば、地元の岸信夫、江島潔ら政治家がそれこそ「新規増設の環境整備」に走り回っている。「もうしばらく待ってください」というサインでしかない。
第2に、にもかかわらず、はっきりと明らかになったのは、原発をめぐっての決定要因は世論であるということだ。福島の過酷事故の記憶は消しされない。原子力安全神話の崩壊はもとに戻せない。ほとんどの国民は、「今度日本列島のどこかで原発事故が起これば列島に住めなくなる」ことを感じている。「まさか、上関原発はもうできないだろう」という声もそんな危機感に支えられている。逆にいえば、原発反対の世論がさらに強く積極的になり、原発推進に賛成する政治家を議席からすべて引きずり下ろし、首長を解任する程になれば、経産省は明記不能どころか、脱原発に舵をきる以外にないということだ。
第3に、経産省の傲慢な独善さである。まだ答申のための諮問委員会もメンバーさえ公表されず、会議さえ開かれていない段階で、「新増設を明記する」とか「明記しない」とかいう方向を出せるものなのか。なんという傲慢さか。
経産省はあくまでも事務局として必要なデータの提供と論議の記録と答申の検討、そして国民からのパブリックコメントの手続きを経て結果が出るのではないか。
はいはい、それは建前であって本当は経産省の官僚が全部仕切っているんですよ、それも知らないのですか?という声が聴こえてくる。そんなことは多くの国民は学習済みだ。むしろ、こりもせず経産官僚の独善的統制で日本列島に住むすべての人、生き物の運命が決められることに震え戦くべきだ。もう責任逃れは許されない。
世界の流れは脱原発だ。
地震と火山の国、福島のレベル7の過酷事故を経験した国、日本こそ、そうならなければ生きていけない。
山口県の私たちは、祝島をはじめ上関原発=新設を止めてきた人たちに本当に感謝したい。
だからこそ、35年間の苦闘に、新設増設、再稼働も含めて、すべての原発は止めると宣言すべきなのだ。中半端な「生殺し状態」のまま、姑息な原発推進をすすめるというのであれば、私たちは、空前の世論の力、県民のほとんどが立ち上がるような運動を準備する以外にはない。決めるのは、人々の声、世論の力なのだ。
参考
朝日新聞 2017/08/04
http://www.asahi.com/articles/ASK815FX0K81ULFA016.html
原発の新増設、明記見送りへ 政府のエネルギー基本計画
政府が3年ぶりに見直すエネルギー基本計画をめぐり、焦点となっている原発の新設や建て替えについて明記を見送る方向になった。安倍政権下で2014年に決めたいまの計画は、原発を「重要なベースロード電源」と位置づける一方、新増設については触れておらず、原発関連業界などから見直しで盛り込むよう求める声が出ていた。
経済産業省は、原発に対する世論の反発が根強いことなどから、新増設の表現を盛り込むことは時期尚早との判断に傾いている。当面は既存原発の再稼働や運転期間の延長に注力する。
世耕弘成経産相は1日の閣議後会見で、エネルギー基本計画の見直しを議論する審議会を9日に開くと発表した。年度内にとりまとめるとしたうえで「骨格を変えるような状況の変化は起こっていない」と話し、計画の主要部分は変えない方針を示した。
政府は2015年、電源に占める原発の割合を30年度時点で20~22%になるよう政策を講じると決めたが、世耕氏は「(既存原発の)再稼働をすれば、新増設を想定しなくても達成可能だ」と強調した。
経産省はまた、50年を見据えたエネルギー政策を話し合う有識者会議の初会合を今月末に開く。地球温暖化対策などの観点から中長期的な原発の必要性についても議論するという。原発推進派にも配慮したとみられ、会議で出た意見をエネルギー基本計画に反映させる可能性がある。(斎藤徳彦、笹井継夫)















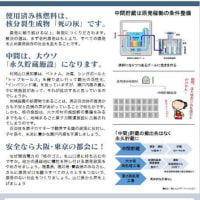
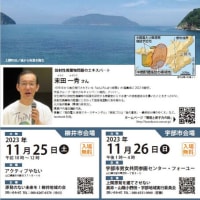
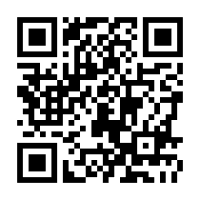
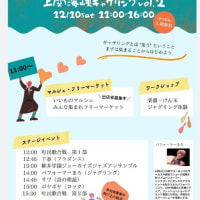





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます