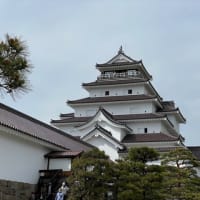今この瞬間の君を抱きしめてあげられたら
遥のことを考えながら駅前にある小さなヘアサロンの前を通りかかった。遥がいつもカットしてもらっていた店だった。理容師のオカマさんが遥のことをとても気に入ってくれていて、毎回、彼が遥の髪をカットしてくれた。普通は、客が理容師を指名するものだけど、遥はオカマさんに逆指名されてしまった。小熊のような丸い顔をしたオカマさんは、遥の透明な魅力をうまく引き出してくれた。
「ねえ、女同士だからさ、今度、遥ちゃんとお茶を飲みに行ったり、お買い物に出かけたりしてもいいでしょ?」
遥をヘアサロンまで送って行った時、オカマさんに許可を求められたことがあった。彼は丸顔をにこにこさせている。
「い、いいですよ。ぜ、全然、かまわないですけど」
突然の申し出に、僕はとまどい気味に答えてしまった。
「きゃっ、やったあ」
しなを作って嬉しそうに小躍りしたオカマさんは、ちゅっと軽く音を立てて遥の頰にキスする。遥はきょとんとして、見るみる間に顔を赤くした。かわいい遥だった。
それから、遥はオカマさんと仲良しになった。
彼は宝塚歌劇団の大ファンで、有楽町の東京宝塚劇場で公演があると必ず足を運び、衛星放送のタカラヅカ専門チャンネルに加入して毎日欠かさず観る。オカマさんは、トップスターやトップ娘役の地位について脚光を浴びているタカラジェンヌには興味がなく、あまり目立たないけど努力している新人を応援するのが好きなのだそうだ。新人の頃から応援しているタカラジェンヌががんばってはいあがり、いい役につくようになるとたまらなくうれしいのだとか。遥も彼に連れられて『ベルサイユのばら』や『エリザベート』を観劇しに行ったことがある。遥は、芝居やショーの内容よりも劇場をつつむファンの熱気に驚いていた。
タカラヅカのほかにも、オカマさんはたびたび遥を遊びに誘った。そんな時、彼は必ず僕に電話して「遥ちゃんを借りるから」と断りを入れてくれたので、僕としても安心だった。なにより、遥は友達を作りにくい性格だから、遥をかわいがってくれる友人ができてよかった。たまに僕も誘われて、三人でいっしょに映画を観たり、飲みに行ったりもした。
一度、オカマさんが遥の手相を観てくれたことがある。
「あなたは最愛の人と一緒に死ぬわ。これ以上ないくらいに愛されて最後を迎えるのよ。あら、変な意味じゃないわよ。愛につつまれるの。わかるかしら? それがあなたの運命よ」
そう言って微笑んだ彼は、遥を愛せるあなたは倖せねと言いた気に僕へ目配せした。
残念ながら、彼の予想ははずれてしまった。でも、遥が最愛の人に愛されるという予言だけは、当たってほしい。それが僕だったら最高だったのだけど、別れるのは運命だとあきらめるよりほかにしかたない。遥が素敵な人を見つけて倖せになってくれたら、それでいいことなのだから。彼女を倖せにするのがほかの男なのなら、僕はそれを受け容れるしかないのだから。
僕は空を見上げた。
クジラのような雲はまだ浮かんでいる。
漂う雲は、僕を見守っていてくれているようだ。
僕なら大丈夫。
今は遥のことをずっと待ち続けていたい気持ちが強いけど、遥のいない暮らしにもそのうちすこしずつ慣れるのだろう。そうなれば、僕なりの倖せを探すから。
今日も元気に働いているオカマさんの姿をガラス窓越しに見て、ヘアサロンの角を曲がった。
駅前通りからはずれたビルの裏手を歩き、文房具屋や花屋や居酒屋がならんだ商店街へ入った。片隅にログハウス風の喫茶店がある。ドアを開けると、バッハの無伴奏チェロ組曲がかかっていた。僕は窓辺の席に腰かけた。
たまにふたりで入った店だった。
丸太造りの内装は素朴なあたたかみがある。高い天井が広々としていて気持ちいい。
バイト代が入ると名物の焼きプリンを一つ頼み、ふたりでわけて食べた。この店の焼きプリンは、オーブンで焼きたてのあつあつが白い陶器のカップに入って出てきた。やわらかいプリンにタピオカが混ざっていて、ぷちぷちした食感を楽しめる。カップの底には僕の大好きな練りサトイモが入っていた。ひつこくない甘さでちょうどいいし、とろりとした舌触りもいい。月に一回の僕たちの贅沢だった。
この店でふたりで向かい合った時、僕は遥を笑わせることばかり考えていた。遥の笑顔を見るのがたまらなく好きだった。遥の笑いのつぼは心得ていたから、どう話せばいいかのは、お茶の子さいさい。遥を笑顔にするのは、僕だけに与えられた特権のように思っていた。まるで、錬金術師《アルケミスト》が手に入れた秘法のように。
メニューを見ながら焼きプリンを食べようかと迷ったけど、一人では味気ないから、やめにした。もうあっさりした上品な味わいの焼きプリンを注文することもないのだろう。こうして一人でぽつねんと坐ってみると、今まで僕の生活は遥を中心にまわっていたんだなとつくづく感じる。僕はブレンドコーヒーだけを頼んだ。
ふと、壁の写真に目がとまる。
むき出しの丸太の壁には、手の届く範囲一面に写真がピンでとめてあった。この店は、客が自由に写真を貼ってもいい。どれも楽しそうな写真ばかり。大勢の人たちの色とりどりの思い出のなかに、僕たちの思い出も混じっていた。
今年の夏、ふたりで花火大会へ出かけた。
中三の時も、高校生の三年間も、去年の夏も、いっしょに花火を観に行ったけど、今年は特別だった。遥が布地を買ってきておそろいの浴衣を縫ってくれたから、僕はうれしくてしょうがなかった。それだけの手間隙《てまひま》をかけてくれた遥に感謝の気持ちでいっぱいだった。写真のなかの僕たちは、紺地に琉球ガラス風鈴の柄をあしらった手製の浴衣を着て微笑んでいる。夏の夜空に、しだれ柳の花火が遠く咲いている。
電車が会場の最寄り駅へ着くと、ホームは浴衣姿の人々であふれた。誰もが浮かれ気味で、祭りの華やかな雰囲気がもう漂っている。僕はほとんどの人が既製の浴衣を買って着ているんだろう、手作りの浴衣を着ている人なんてほとんどいないんだろうなと思うと、すこしばかり誇らしい気分になった。遥のことも、そんな遥を恋人にした僕自身のことも。「押さないでください」と繰り返す駅員の放送を聞きながらゆっくり階段をのぼり、ようやく改札口へたどり着いた。
駅を出た僕たちは人ごみと屋台をすり抜けて川べりへ降り、遊歩道の手すりによりかかって花火を見物した。遥は黒捌《くろさば》きの赤い鼻緒の下駄を履いて、帯に団扇を差している。ピンク色したガラス玉の髪留めがよく似合っている。僕は、遥が両国で買ってきてくれた相撲取り用の桐下駄を履いていた。白い鼻緒が足元を引き締めて見せてくれるから、僕は気に入っていた。コンクリートの上を歩くと、乾いた音が心地良く鳴る。熱帯夜の蒸し暑い夜だったけど、僕はずっと遥の手を握っていた。浴衣の遥はほっそりとしたかげろうのようで、手を離せば迷子になってしまいそうだったから。
次々と花火が打ち上がる。
赤い牡丹。
黄色い嵯峨菊。
薄桃色した八重桜。
紫のあじさい。
白いダリア。
橙色のひまわり。
緑の椰子の木。
青い蝶々。
水色の麦藁帽子。
さまざまな色をしたさまざまな光の模様が暗い空に描かれ、遥の澄んだ頰をぱっと明るく染める。細い首をかしげた遥は、僕の肩にもたれかかり穏やかに微笑む。花火が消えようとする頃、川べりの僕たちに爆音が届いた。
「花火の音は、何秒か前に生まれた音なんだね」
僕はぽつりと言った。
「中三の時、理科の授業で先生が言ってたわね。人間はみんな過去の音を聞いているって。あの時、ゆうちゃんはものすごい発見を聞いたみたいに興奮してたわね」
「だって不思議だよ。今聞いている音が全部昔の音だなんて。音のスピードは秒速三百数十メートルだったよね。あの花火からどれくらい離れているか知らないけど、花火が爆発してからここへ届くまでに数秒かかっているわけだろ。僕たちの耳に聞こえるこの音は、過去からのメッセージなんだよ」
「それじゃ、わたしたちが見ている花火の光も同じね」
「そうだね。光も生まれてから自分の目に届くまでに時間がかかるからね。たしか、太陽の光が地球へ届くまで約八分だったっけ。花火と僕たちの距離だとまばたきもできないくらいのほんの一瞬だけど、あの花火は過去の模様なんだね」
「人はみんな過去を見て生きているのね」
川風が遥の髪を揺らした。
「過ぎ去ったものしか、人は見ることができないんだね」
僕は遥の顔を見つめ、今僕の目に映っている遥の姿も過去のものなのだろうか、とそんなことをぼんやり思った。間近に見ている遥はたしかに今この瞬間の彼女のような気がするし、今握り締めている掌のあたたかさも、今この瞬間のもののはずなのに。
なにげない会話だったけど、今になって振り返ってみれば、僕たちの限界を言い当てた言葉だったのかもしれない。
人は、今この瞬間を見ることができない。
今この瞬間を聴くこともできない。
僕は今見ている風景も人の姿もこの瞬間のものだと思っているけど、実は錯覚で、すべては一瞬前の過去にすぎず、今この瞬間をとらえることができない。刻々と移り変わってゆく過去を眺めるよりほかに、術がない。だからこそ、今この瞬間の遥の心を抱きしめてあげたかった。それができていれば、ほんとうの意味で、遥がなにを思っているのかを理解してあげられたのだろうし、支えにもなってあげられたのだろう。あんなに悲しませることもなかったはずだ。でも、それは目に見えない壁だった。乗り越えることのできない壁だった。
僕は、時の過ぎ行くままに移り変わる遥の心がつけた轍の跡を後から追いかけることしかできなかった。つらい思いをさせてしまった。悔やんでも悔やみきれない。
僕は写真の遥を見つめた。倖せそうだ。
もし、遥の心にも楽しい思い出を残せたのだとしたら、それがせめてものなぐさめだと思うしかないのだろうか。
(続く)