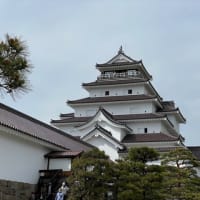その人は丘をのぼって
夏の盛りの丘を歩いた。
舗装していない土道が夏の陽射しを銀色に照り返す。リリィは白いレースの日傘をさし、僕は自転車の籠にリリィが持ってきた花束と墓参りの道具を入れて自転車を押した。白い日傘と白いアオザイの取り合わせはよく似合う。リリィが歩みを進めるたびに、ゆったりとした白いズボンが風をはらんでふくらむ。蝉時雨がシャワーのように降り注ぐから、僕はじっとり汗ばんだ。
「疲れない?」
僕は訊いた。
「平気よ。わたしは農村で育ったんだもの。毎日、野菜だとか山菜だとか柴だとかを背負って山道を歩いていたのよ」
リリィは狭い盆地を見下ろし、
「わたしのふるさとににているわ。山があって、緑があって、鳥がないて、小さな川が流れて、田んぼがあって……。ツヨシもおなじようなところで育ったのね」
とまぶしそうに目を細めた。
村の墓所は南向きの斜面にあった。
山の湧水を引いたホースからバケツへ水を入れ、ひしゃくを突っこんだ。墓地の端の小さな祠にお釈迦様とお地蔵様が祀ってある。僕はお釈迦様へ線香をあげた。僕が拝もうとすると、リリィは手を合わせようかどうか迷った仕草をみせる。
「どうしたの?」
僕は訊いた。
「わたしも昔はお釈迦様を拝んでいたんだけど、今はクリスチャンになったからお祈りしていいものかどうかわからないの。でも、子供の頃は毎月一日にお寺参りしていたんだから、神様も大目に見てくれるわよね」
リリィは首をかしげて微笑む。
「大丈夫だよ」
「そうね」
リリィは僕といっしょに手を合わせた。
いい香りがする。それはリリィが抱いている白い花の匂いでも、線香の匂いでも、香水のそれでもなかった。とても素朴な香りで気分が落ち着く。気持ちがやすらかになる。それでいて、あこがれを誘うようで心がどきどきしてしまう。これがリリィの香りなんだろうか、とぼんやり想った。
先祖代々の墓に水をかけ、リリィの花束を花立てに入れた。僕は墓誌に刻んである父さんの名前を彼女に見せた。
「ほんとうにここにツヨシがいるのかしら?」
リリィは首をかしげる。
「父さんの骨はいちおうこのなかに入れてあるけど。どうして?」
「ツヨシがこのなかにいるような気がぜんぜんしないの。どこかほかのところにいるんじゃないかって」
「父さんはリリィの胸のなかにいるんだよ」
「そうかもしれない」
リリィははっとした顔をして頰を赫(あか)らめる。
「父さん、友達がきてくれたよ」
墓石に声をかけて合掌した。
すすり泣きが聞こえる。
リリィはつややかな褐色の頰に涙を流していた。つらくてたまらなさそうな泣き顔だ。嗚咽はすぐに号泣にかわった。アオザイに透けた肩が震えている。
「入口のところで待っているから、好きなだけ父さんと話をして」
僕はリリィにそう声をかけて墓石から離れた。
墓所の階段に腰掛け、村を見渡した。
黒い屋根瓦が輝き、田んぼの緑の絨毯がどこまでも続く。豆粒ほどに見える軽トラックが村の外れの養鶏場へゆっくり入った。村を取り囲む森は風にそよぐ。いつもと変わらないのどかな風景だ。村には家族や幼馴染みがいる。ここにいればさびしくはない。
祖父の跡を継いで農業をしてもよかったのに、どうして父さんはカメラマンになってベトナムへ行っただろう? 僕はぼんやり考え、
――戦争は残酷だ。だが、戦争のなかにもきらりと光るやさしさがある。戦争だからこそやさしさの貴さがわかるのかもしれない。
と、父さんが日誌のなかに記した言葉を想い起こした。
戦争という極限状態のなかでしかわからない人間性がある。それを探求しようとしたのだろうか? 戦争のなかでほんとうの人間の姿をとらまえようと奮闘していたのだろうか?
――言葉は嘘をつく。しかし、写真は嘘をつかない。事実を写し撮るだけだ。
父さんはこんな言葉も書きつけていた。
混じりけのないはっきりとした時代の証言を残そうとして撮影を続けていたのだろうか? 真実は人の数だけある。真実は案外、頼りないものなのかもしれない。だけど事実はたった一つだけだ。
父さんのことを想っているうちに、やがてリリィが戻ってきた。
リリィの鼻は真っ赤にはれている。彼女が僕の隣に坐ろうとするから、焚きつけ用に持ってきた古新聞の残りを階段に敷いた。
「ごめんなさい、泣いたりして」
「いいんだよ。わざわざ遠くからきてくれて、父さんも喜んでいるよ」
「そうだといいんだけど」
リリィは自信なさそうにうなずく。「ベトナムから来たの?」と訊くと、リリィは首を横に振り、アメリカから来たのだと言った。今はベトナムからアメリカへ移住して、ロサンゼルスでモデルのアルバイトをしながら美術学校に通っているそうだ。
「サイゴンへ行ってからどうしていたのか、よかったら聞かせてもらえないかな。父さんのことも」
「いいわよ。――ツヨシがカフェのウェイトレスの仕事を紹介してくれたの。給料はすごく安かったけど、農村から出てきたばかりの十六歳の娘ができるような仕事はほかにないし、ぜいたくはいってられなかったわ。住み込みで三食付きだから生活には困らなかった。とにかく、サイゴンでサバイバルしなくっちゃいけないんだもの。屋根のしたで眠ることができて御飯が食べられればもうそれでじゅうぶんだった。
サイゴンは華やかだった。農村で育ったわたしにははじめてのものばかだったから、びっくりしてしまったわ。街中にいろんなお店があって市場は品物があふれているものね。お店が終わってからみんなで夜店へ行ってバーベキューや山羊鍋なんかを食べたりしたし、ときどきディスコにも連れて行ってもらったわ。村で暮していた頃は、夕方の六時に夕御飯を食べて、それから囲炉裏のそばで同い年くらいの女の子とちょっとおしゃべりして、九時にはもう眠りにつく生活だったのに、サイゴンでは毎日お祭りのなかにいるようなものよ。でも、わたしはさびしかった。外のにぎやかさを感じればかんじるほど、わたしはひとりぼっちだって思ってしまったの。運命ががらりと変わってしまったことについていけなかった。
ツヨシはいつもわたしをなぐさめたりはげましたりしてくれた。サイゴンには親戚も知り合いもいないし、心細くてしかたなかった。ツヨシがお父さん代わりになってわたしの面倒を看てくれたのよ。わたしが勤めたところは、バドワイザーやハイネケンが置いてあって、ハンバーガーやスパゲティを出す外国人向けの店だった。外国人のお客さんから注文を取るのはなんだか不思議な感じがして面白かったわ。そのうちすこしずつ英語や日本語を覚えてちょっとした世間話ならできるようになって、お客さんと話をするのが楽しかった。
もちろん、嫌なことだってあったわよ。
戦場から還ってきたアメリカ兵は気が立っているから、お酒に酔って暴れだす人がわりといたの。ウェイトレスをむりやりトイレへ連れこんで乱暴しようとする人もいたりして怖かったわ。そんなことがあるたびに、この人たちはわたしの家族を殺したんだって思い出さずにはいられなくて、落ちこんで憂鬱な気分になった。
いちどだけだけど、わたしはお店のなかでアメリカ兵を殺そうとしたことがあったの。へべれけに酔っ払った兵隊が『ベトナム人を皆殺しにしろ』って繰り返し叫びながらお店のなかにいた人を片っ端から殴りつけようとするものだから、わたしは目がくらくらして、村を焼かれたあの日の光景が目の前に甦ってきちゃった。煙を出して燃えるわたしの家、機関銃の音、村人の叫び声、血まみれの死体――思い出したくないことばかり走馬灯のように次からつぎへと目の前に見えるのよ。はっと気がついたら、ツヨシがわたしの手首を掴んでいた。わたしはその人の後ろに立って背中にナイフを突き刺そうとしていたのよ。ツヨシはわたしの手からナイフを奪ったわ。ツヨシがとめてくれて助かった。そうでなかったら、ほんとうに彼を殺していたかもしれない。
そんなことがあってから、わたしはいろいろ考えたわ。わたしがナイフで刺そうとしたのは、やっぱりアメリカ兵が憎いからなのよ。心のおくにとてつもない怒りが渦巻いていて、一度怒りが噴き出してしまったら、わたし自身どうにもとめることができなくなってしまうのよ。あんなことをしようとしたわたし自身が怖かった。わたしはすっかり混乱してしまって、ずっとツヨシに話を聞いてもらったわ。ツヨシにひどいことを言ったり、こぶしで胸をどんどん叩いたりしてしまったけど、ツヨシは辛抱強くわたしを受けとめてくれた。
家族に会いたくてたまらなかった。ひょっとしたら、わたしの家族は生きているんじゃないかって、おとうさんやおかあさんやきょうだいに会えるんじゃないかって、そんなことばかり想うようになったわ。家族が生きていることがわかれば、胸のおくに抱えたつらい憎しみが消えてくれるだろうって、そんなふうに考えたの。
それでツヨシが調べてくれたんだけど、やっぱりわたしの家族はあの日皆殺しにされてしまったみたいなの。でも、わたしはどうしても信じたくなくて、ツヨシに頼みこんでふるさとまで連れて行ってもらったわ。とちゅうで爆撃があったり、銃撃戦をやっているすぐそばをとおったりしてけっこう危なかったんだけど、ツヨシのおかげでなんとかふるさとにたどりつくことができた。
村に着いたのは霧の深い朝だった。あたり一面、ミルクを流したみたいに白く染まっていたわ。ツヨシがいっていたとおり、村は廃墟だった。悪霊がすべてを壊していったのね。家は焼け爛れたまま放置されて誰もいないの。人だけじゃなくって、犬も水牛もにわとりも、みんないなくなっていた。少しずつ霧が晴れて、なんとなく村を見渡すことができるようになった。わたしはぶるっと震えたわ。なんともいえない悲しい雰囲気だった。村人たちの叫び声やうめき声がまだあたりに満ちているの。顔をゆがめながら助けてって叫ぶ声がいつまでも村のなかでこだましているのよ。戦争さえなければ、あのままのんびり過ごせたはずなのに。きれいに暮してゆけたはずなのに。
わたしの家はすっかり焼け落ちていた。真っ黒に焦げた材木があたりに散らばっていたわ。せめて家族の写真だけでも残っていないかなって探したんだけど、どこにもなかった。鍋や釜や鋤は鉄でできているから残っていてもいいはずなんだけど、それもきれいに消えていたわ。おかあさんが嫁入りのときに持ってきたきれいな翡翠の腕輪もなかった。誰かが取っていったのね。村のなかで変わらなかったのは小川くらいかな。村も田んぼも荒れ放題だったけど、村を流れる小川だけは昔とおなじようにきれいな水が流れていたわ。あめんぼが川面で散歩して小さな波紋を作っていた。
それから、近くの村へ行って親戚を訪ねたの。おじさんとおばさんが家族の最期を教えてくれたわ。みんな納屋のなかで折り重なって斃(たお)れていたそうよ。隠れていたところを見つかって銃で皆殺しにされたみたい。わたしの家族はなにもしていないのに、幼い子供まで殺してしまうだなんておかしいわよね。むごいわ。おじさんがわたしの家族の遺体を埋葬してくれたそうよ。
わかっていたといえばわかっていたことなんだけど、わたしが勝手な夢を描いていたといえばそうなんだけど、つらい事実を確認するのはたえがたいことだった。ツヨシに助けてもらったときからその日までずっと涙をがまんしていたけど、とうとうこらえられなくなっちゃった。わたしはおばさんのひざにうずくまって泣いた。おばさんはわたしを抱きしめてやさしく背中をさすってくれたわ。
村育ちのわたしにサイゴンみたいな大都会でずっと暮らしなさいっていわれても、むりよ。村の暮らしなんてほんとにシンプルだけど、都会は複雑だもの。村にいればお金なんてすこししかなくてもちゃんと暮していけるけど、都会はなにをするにもまずお金がいるものね。わたしみたいな田舎娘には、お金がないとなんにもできないというのはなんだか不自由で窮屈な感じがしたわ。人間関係もこみ入っているし、お店であんなことがあって精神的にも参っていたし、わたしはおじさんとおばさんのところに残ろうかと迷ったの。だけど、ふたりはこのあたりは危ないからサイゴンへ戻りなさいっていったわ。わたしの村といつおなじことが起きてもおかしくないって。それに、戦争で働き手が減ってしまって村の生活もたいへんだから残ってもいいことはないだろうって。わたしはおじさんとおばさんがすすめたとおり、サイゴンへ戻ることにしたわ。
最後に家族のお墓をお参りした。土を盛って木の板に名前を書いただけの簡単なお墓だった。『わたしだけ逃げてしまってごめんなさい』ってあやまったわ。みんな死んでしまったのに、わたしだけ生きていることがすまない気がしてしかたなかった。助けてあげられたらよかったのだけど」
「リリィが悪いわけじゃないよ。生き残ってくれて家族の人も嬉しいと思うよ」
「ツヨシもおなじことを言ったわ。でも、ひとりだけ生き残ってしまうとどうしても罪悪感がつきまとうものなのよ。サイゴンへ帰ってからわたしは抜け殻みたいになって、ぼおっとしてしまうことが多かった。お店が忙しいときは、仕事で気がまぎれるからいいんだけど、ひまになって手持ち無沙汰になると心の底から怒りがじわっと湧いてくるの。わたしは自分の心に抱えた憎しみをもてあましたわ。
ツヨシはつらくても現実を受け容れるしかないんだよって繰り返しわたしにいった。わたしもそうするしかないんだって思うようにした。ツヨシのいうことが正しいというのはわかるの。だって、ふるさとへ帰ってこの目で村や家族がどうなってしまったのかを見たんだもの。ツヨシは現実を受け容れなかったら人生が始まらないし、そうしないと結局は自分自身を損なってしまうんだよってさとしてくれた。わたしたちは憎しみについてよく話をしたわ。
『憎しみは心をむしばんでしまう。だから憎しみを克服する道を考えなさい』ってツヨシはなんどもいってくれた。『カフェで暴れる人たちは憎しみで心が腐ってしまったから、あんなことをするんだ。リリィも憎しみに飲みこまれてしまって、もうすこしでとんでもないことをするところだった。でも、そんなふうにはなりたくないだろう』って。ツヨシのいうことはもっともだと思ったわ。
たぶん、ふだんはみんな善良な人なのよね。でも、戦場で暴力にされされて、敵をたおすために暴力を振るって、そんなことを繰り返しているうちにおかしくなってしまうのよね。それに、あのアメリカ兵にしても好きこのんでベトナムへ戦争しにきたわけじゃないんだし。人を傷つけるのは弱いからのなのよ。弱いのはだれもおなじ。そして、みんなおなじ人間なのよ。今はもうアメリカ兵を憎いと思ったりしないわ。ただ悲しいだけ」
「憎しみが消えてよかったね」
「そうね。ツヨシのおかげだわ」
リリィはこくりとうなずいた。
(つづく)