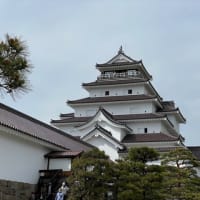これが僕の人生のなかでいちばん古い記憶だと思う。
僕は二歳と十か月だった。とてもおとなしい子供だったらしい。おかっぱみたいな髪型をしていたせいか、女の子とよく間違えられた。
母と手をつなぎ駅前の歩道を歩いていた。クリーム色に青い帯を巻いた乗り合いバスが母と僕を追い越していく。そのバスに乗って川のほとりの団地から駅前まできたのだった。
空は冷たく青く澄み渡り、ここちよい風がそよいでいた。冬の初めのやわらかい陽射しが歩道に降り注ぎ、街路樹の枯葉が散らばっていた。記憶が定かではないのだけど、楓(かえで)の葉だったような気がする。僕は枯葉を踏まないように、ジャンプして飛び越した。なんだか楽しかった。
「ねえ、だっこして」
ふと甘えたくなった僕は母の足にしがみついた。だが、その返事は思いがけもしないものだった。
「お腹の赤ちゃんが大きいからだめやよ」
母は諭すように言う。臨月間近の母はたしかに大きなお腹をしていた。だが、幼い僕はそれがどういうことなのか、いまひとつよくわかっていなかった。
「だっこってば」
僕はだだをこねた。
「あんたのおとうとが生まれるねん。これからはもうだっこできへんのよ。おとうとができるんやで」
「おとうと?」
「そうやよ。お腹の中にはあんたの弟がいるんや」
「おとうとってなに?」
「兄弟やよ。あんたはおにいちゃんになるねん」
「おにいちゃん?」
僕は母の言葉を理解できなかった。それがだっこしてもらえないこととどういうつながりがあるのかとなると、もうさっぱりわけがわからない。ただひたすら悲しかった。もう甘えることができないだなんて。
この世を照らしている陽射しも、僕と遊んでくれた枯葉も、それから大好きな母さえも、急によそよそしく他人行儀になってしまったようだった。
「お父さんがきたで」
母方の祖母の弾んだ声が響いた。
僕は廊下でジェット旅客機の模型を持って遊んでいた。
「さあ、早(は)よ応接間へ行きや」
祖母がせかしにきたから僕は逃げようとしたのだけど、すぐに捕まってしまった。祖母は僕の両脇を抱え、廊下を小走りに歩く。僕はけらけら笑った。
「パパ、ほんまにきたん?」
僕は祖母に訊いた。
「ほんまやで。急がなあかんねん」
応接間にはほんとうに父がいた。僕は意外だった。父が母の実家へくることは滅多になかった。時々、僕は母の実家に預けられたのだが、迎えにくるのはいつも母だった。
母方の祖父は僕を溺愛していた。
僕は初孫だったから可愛くてしかたなかったらしい。しかも男の子だ。大正生まれの祖父は、これで跡取りができたとほっとしたようだ。
祖父は勤めから帰ってくると毎日必ず仏壇を拝んだ。
背広から和服へ着替えた祖父は鐘を鳴らして、
「ナマンダブツ」
と、何度か繰り返す。その後は、念仏を唱えるのでもお経を読むわけでもなく、手を合わせてひたすら祈る。
祖父がなにを祈っていたのか、僕は知らない。
彼を育てた大祖父や大祖母のことも祈っていただろうし、祖父の幼い頃、祖父の弟を死産してすぐに他界してしまった母親のことも祈っていただろう。それから、祖父の幼い頃に結核で亡くなった祖父の父親のことや、戦争で死んだ古い友人たちのことも祈っていただろう。家族の平安も祈っていたかもしれない。
祖父が仏壇と向かい合い始めると、僕は祖父の傍にちょこんと正座して、
「まんまんちゃん、あん」
と言って祖父の真似をして手を合わせる。
しばらくそうして幼いなりにお祈りをしていると祖父は、
「よくお祈りできました」
と僕の頭をなでてくれた。いつもそれを潮に僕は仏間から出た。祖父は祈り続け、仏壇の後は台所に飾ってあるいくつもの神棚を順番に拝み、庭へ出て蛇の神様を拝む。祖父の祈りがすべて済んでから祖父と祖母と三人で食卓を囲んで晩御飯を食べた。
応接間のソファーに坐った父は丸顔に満面の笑みを浮かべた。
「お前の弟が生まれたんや」
「おとうと?」
「そうや。お前はお兄ちゃんになったんや。嬉しいやろ」
「わからへん」
「これからお父さんといっしょに病院へ行こう。ママに会おう」
「うん」
母に会えると言われ僕は元気が出た。
タクシーに乗って大阪市内の病院へ向かった。
病室は汗と消毒薬が混じったむっとむせ返る匂いがする。部屋の雰囲気は明るく、活気がみなぎっていた。
「お母さんを捜すんや」
父は嬉しそうに言った。
「見つけたらお父さんに教えてや」
病室にはずらりとベッドが並び、母と同じくらいの若さの女性が寝巻き姿で並んでいる。幼い僕にはどこまでもはてしなくベッドが続いているような気がした。
一つひとつベッドを確かめた。どの女性も顔を上気させ、頰がつややかだ。今から思えば、おそらく出産を間近に控えた妊婦ばかりを集めた部屋だったのだろう。病室のなかはこれから人生の大仕事をしようとする女の熱気と意気込みで満たされていたのだ。
病室の端から端まで探したが、母の姿は見当たらない。窓の外を見ると、どんよりと曇った空は薄暗くなっていた。真っ直ぐ伸びた大通りには車の赤いテールランプが並んでいる。
「ママ、いいひんで」
僕は父に訴えた。さびしい。
「せやな。おかしいな」
「ママはどこなん?」
「この部屋のはずなんやけど」
父はポケットからメモを出して、
「部屋の番号はおうてるなあ。なんでやろ」
と首を傾げる。
「よそのへやへいったんとちゃう」
「そうかもしれへんな」
父は病室を見渡し、
「ほかの部屋を見てみようか」
と僕の手を牽いた。
廊下へ出たちょうどその時、向かいの部屋のドアが開いた。やつれた母がパジャマ姿で出てきた。
「ママ」
僕は母へ駆け寄った。
父と母はなにごとかを話す。父の声は晴れやかだったのだが、母は疲れきっていて声が小さかった。
おとうとは一か月早産で生まれてきた。
買い物に出かけようとした母は団地の階段から転げ落ち、それで陣痛が始まってしまったのだ。母からの連絡を受けた祖母が急いで団地へ駆けつけて母を病院へ送り、そのまま幼い僕を預かった。
思いがけず出産が始まり、母は身も心もすり減らしてしまったのだろう。僕は母が病人のようなので大丈夫なんだろうかと心配だった。
僕の記憶はここで途切れている。
どう思い出そうとしても、生まれたての赤ん坊の映像は僕の脳裡に甦ってこない。それから父とどこでなにをしたのかも忘れてしまった。生まれたばかりの赤子に会えなかったのかもしれない。
ともかく、おとうとが生まれた。
縁側は陽だまりだった。
モンシロチョウがささやかな庭の植木にとまっては羽ばたく。
僕は空をあおいで目を細めた。こもれ陽がきらきら輝く。風の香りがあたたかかった。
祖父も、祖母も縁側からテラスを眺めて微笑む。テラスでは母がおとうとをベビーバスタブに入れて湯浴みさせていた。
プラスチック製の青いベビーバスタブの横にしゃがんだ母は、赤子が沈んでしまわないように頭と肩を片手で支え、もう片手に持ったタオルでふっくらとした肌をやさしく拭う。
おとうとは、両腕を動かして小さく伸びをする。可愛らしくあくびして、それから、うっとり目を閉じる。
「気持ちよさそうやねえ」
祖母が嬉しそうに言うとみんな笑い声を上げた。おとうとは、風呂につかるだけで家族をのびやかな気分にした。
母はおとうとの頭に石鹸をつけ、湯が耳に流れこまないように気遣いながら丸っこい頭に薄くへばりついた髪をそっと洗った。
みんな楽し気だから、僕も浮かれてしまった。心が歌うようだ。僕はサンダルを履いてコンクリートの叩き台へ降り、ベビーバスの端にしゃがんだ。なんでもないおとうとの仕草を見てははしゃいだ。しあわせな気分でいっぱいだった。
団地の六畳間にベビーベッドを置き、母と僕はその隣で眠った。
母は夜中に起きて授乳しただろうし、弟は夜泣きしたりしたのだろうけど、僕はなにも覚えていない。
ベビーベッドのうえには、レースのフリルやプラスチックの花と葉っぱのついた回転飾りを天井からぶら下げてあった。僕は弟のいない時にこっそりベビーベッドのうえへはい上がり、回転飾りを見上げた。
紐をひっぱるとオルゴールが鳴り、飾りが回転する。メロディーの音階が懐かしさを誘う。なんだか御伽噺のなかにいるようだ。魔法使いがやってきて、不思議の森のなかへ連れていってくれるような、そんな気がした。オルゴールを聴きながらゆっくり回る飾りを眺めているうちにうとうとする。とても安らかな気持ちになれた。
ある晩、ふと目覚めた。
おとうとはベッドのなかでぐっすり眠っている。隣の蒲団に母の姿は見当たらない。僕は台所へ行った。母はエプロンをつけ、流し台で洗い物をしていた。
「あら、起きたの」
母は皿を洗いながら振り返り、
「ミルクティーを飲もうか」
と言った。
寝ぼけまなこだった僕はミルクティーってなんやったやろうと思いながらうなずき、テーブルの椅子に坐った。父はまだ帰ってきていなかった。
母は小さな鍋で牛乳を煮立て、小さなバラ模様のついたティーカップへ注ぐ。カップにはリプトンのティーバックが入れてあった。
「熱いから気いつけや」
母はカップを僕の前に置く。
ミルクティーの表面には牛乳の膜が張っていた。僕はさっそくスプーンでそれをすくい、ふうふう吹いて口へ入れた。僕はホットミルクにできる薄い膜が大好きだった。牛乳の膜をたいらげてから、スプーンでカップをかき混ぜミルクティーをすすった。
「おいしい?」
母もミルクティーを飲む。僕はうなずき、
「正太にものませてあげようや」
と言った。正太はおとうとの名前だ。祖父がつけた。
「正太は眠ってるから起こしたらあかんよ」
「なんであんなにようねるん?」
「赤ちゃんは寝なあかんのよ。あんたもそうやったんやし。――おとうとができてよかったねえ」
「うん。かわいいわ」
「なかよくしいや」
「してるで。きょうもいっぱいあそんだもん」
ミルクティーを飲み終えると母が僕を寝室まで連れていき、掛け布団をかけてくれた。僕はすぐに眠りに落ちた。
この頃の母はまだのんびりしていた。
父との不和も決定的ではなく、それなりにしあわせに暮していた。冷え切った家庭になってしまい、母がなにかに憑かれたみたいにいつも苛立つようになったのはそれから数年後のことだ。僕はこの頃のことを懐かしく思いだせるけど、おとうとにはその記憶がない。もし団地住まいをしていた頃のおだやかな家庭の思い出があれば、彼が思春期を迎えた時、あれほど苦しまずにすんだのかもしれない。
――タンポポみたいやな。
僕は思った。
やんちゃな目をしたおとうとが祖父の家の玄関に立っていた。おとうとの頭はたんぽぽの綿帽子だ。真っ白で、細くて、しゅわしゅわとちぢれた髪の毛が伸びている。おとうとは目をぎらつかせてあたりを見回す。なにかをたくらむちいさな怪獣だった。
白いレースの日傘とケーキの箱を下げた母が玄関へ入ってくる。おとうとは玄関のなかをぐるぐる歩く。母は弟を抱き上げて上(あが)り框(かまち)に坐らせ、小さな靴を脱がせた。僕は縁側でお茶を飲んでいる祖父のもとへ戻った。まだお話の途中だったから、続きを聞きたかった。
「昔、あそこに土俵があったそうや」
祖父は庭の一角を指し、お盆に置いた急須から湯飲みへお茶を注ぐ。
「どひょうっておすもうさんの?」
「そうや。おじいちゃんのおじいちゃんのおとうさんは相撲が大好きやったんや。それで、庭に土俵を作って毎日稽古していたんやそうや。負けず嫌いで強かったらしいわ」
「ぼくもときどきともだちとおすもうするで」
「強いか?」
「ううん。まけてばっかりや」
「そのうち強(つよ)なる」
祖父は僕の頭をなでた。祖父の願いとは裏腹に僕が強くなることはなかった。僕は母に似て、運動神経ゼロのまま育つことになる。
それから祖父は、日本海軍がロシアのバルチック艦隊を撃ち破った日本海海戦の話や戦国時代に織田信長が今川義元の大軍に挑んだ桶狭間の合戦の話をしてくれた。祖父は新聞広告の裏に図を描きながらおもしろおかしく話してくれる。たぶん、祖父が幼い頃に聞いた講談をそのまま僕に話してくれたのだろう。祖父の話はいつも楽しみだった。何度も同じ話をおねだりした。
しばらく話をした後、祖父は昼寝すると言って立ち上がった。僕は台所へ行った。
「あら、あれへんわ」
祖母は、母が買ってきたケーキの箱をのぞきこみながら目を丸くする。
「どないしたん?」
僕は訊いた。
「あんたが食べたがってたいちごケーキなんやけど、いちごがあらへんねん」
「ええっ」
僕はショックだった。母はたしかにいちごショートを二つ買ってきたと言っていた。僕とおとうとがひとつずつ食べるはずだった。
「なんであらへんの?」
悲しくなった僕は泣きそうな声で言った。
「さっきテーブルのうえに置いた時はあったんやけど、どこへ行ったんやろ。おかしいなあ」
祖母はケーキの箱を覗きこみ首をひねる。
ふとベビー椅子に坐っているおとうとを横目で見ると、口のまわりにホワイトクリームがついていた。
「おばあちゃん、あれ」
僕はおとうとの口許を指差した。
「ああ、正太が食べてしもたんやわ。いつのまにやろ」
「そんなあ」
僕はがっかりしてしまった。しかも、スポンジとスポンジの間に薄く切ってはさんであるいちごまでなくなっていた。二重にがっかりだった。
おとうとは祖父が新聞を読む時に使う虫眼鏡を取ろうとして懸命に手を伸ばしている。
「あんた、お兄ちゃんのいちごを食べたんかいな」
祖母は笑いながら正太の頭をなでた。おとうとに言葉がわかるわけもなく、正太は虫眼鏡に夢中だった。
「どうする? チョコレートケーキにしとくか? いちごケーキはおばあちゃんが食べるわ」
祖母が僕にそう訊いたけど、僕は首を横に振った。チョコレートケーキはあまり好きではなかった。
「ほな、いちごケーキを食べとき。いちごはあらへんけど」
祖母はケーキを皿に移し、僕とおとうとの前にそれぞれ置いてくれた。
僕はおとうとが玄関に入ってきた時のなにかをたくらんでいるような目つきを想い起こした。ずる賢いおとうとはいちごを狙っていたに違いない。油断も隙もなかった。
おとうとは目の前のケーキにはまったく興味をしめさない。いちごをふたつも食べてそれで大満足のようだった。それにしても、どうやって箱のなかのケーキからいちごを取り出したのか不思議でしかたなかった。僕は物足りなさを感じながらもケーキを平らげた。
いちごショートの悲劇も忘れてすっかり機嫌を直した僕は、
「ブランコであそぼう」
とおとうとを誘い、縁側から庭へ下りた。テラスのそばに、家庭用の小さなブランコがあった。細い鉄パイプの支柱に小さなベンチが向かい合わせについている。僕は向かいの席におとうとを坐らせた。
「いくで」
立ち上がった僕はブランコを漕ぎ始めた。
おとうとはなにごとが起きたのかとびっくりしてうろたえる。泳いだ目できょろきょろと周囲を見渡し、おろおろする。ちいさな怪獣の面影はどこにもない。僕はそんなおとうとの姿がおかしかった。
「だいじょうぶやで」
僕はスピードを上げず、ごくゆっくり漕いだ。ブランコはきこきこと音を立てる。
夕陽が庭に射す。
ようやく、これは遊びなんだとわかったようで、おとうとははしゃぎ声をあげた。
了