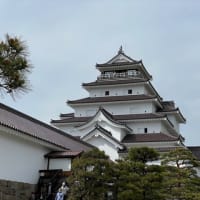「いったい、俺はなにがしたいのだ?」
窓辺に立った隼人《はやと》は、軍用ナイフを力任せに放り投げた。向かいの家の瓦にあたったナイフは甲高い音を立てて跳ね返り、宙を切り裂き垂直落下する。薄汚い飲み屋と売春宿が狭苦しく軒を連ねた細い路地の真ん中にナイフが突き刺さった。驚いた野良犬がけたたましく吠える。荷台にビールケースを積んだ自転車がゆるやかな弧を描き、尾を怒らせた犬を避けて走り抜けた。窓の外は春の陽射しがあふれている。隼人は娼家の二階にいた。
「そんなこと、決まってるじゃない」
珠緒《たまお》が背中から隼人を抱きすくめる。
これが命の息吹だとでも言いた気に生温かい息が耳元に吹きかかる。白粉の匂いが鼻をくすぐる。苛立ちを鎮めようとしてくれたのだと、隼人はすぐにわかった。
「一度でいいから、素顔の君を抱いてみたいものだな」
しばらく考えを巡らせていたかったのだが、珠緒を無視するわけにもいかず、まぜっかえした。
「憎い人」
珠緒は甘えた仕草で隼人の二の腕をつねる。お兄さんのようで甘え甲斐があると珠緒はいつも言っていた。
「それじゃ、白粉を落としてこようか。おっかさんに怒られるかもしれないけど、隼人さんの頼みだっていったら、きっと許してもらえるよ。でもさ――」
「でも、なんだ?」
隼人は素っ気なく訊いた。珠緒は恥ずかしそうにいやいやをして、上目遣いに隼人を見つめる。珠緒の潤んだ瞳を見つめ返した隼人はふと、胸の奥から突き上げる衝動を感じた。
情欲。
そう言ってしまえば身も蓋もない。が、それだけではすまされないなにかだった。川の流れに逆らって跳躍する鮭の姿に似ている。死ぬ日まで、あと幾許《いくばく》もない。せめて子を作り、己の命をつなぎたい。切ない希求が心を突き上げた。
「素顔のあたいなんか見たら、がっかりするかも」
珠緒は、お菓子を貰い損ねた子供がさびしがるように唇を尖らせる。
隼人は痺れるような激情に耐えた。堪《こら》えればこらえるほど、心が逸脱しそうになる。珠緒を泣かせてみたい。思い切り辱めたうえで、孕ませてみたい。
――鬼畜だな。俺も狂ったか。
隼人は己の心をもてあました。
「なにか言ってよ」
珠緒は隼人の腕を叩《はた》く。
「がっかりなんかしないさ」
「ほんと? 隼人さんだけに見せるんだからね」
「わかってるよ」
「わらったりしちゃだめよ」
「しないさ。約束する」
「隼人さんを信じるわ。――ちょっとお風呂に入ってくるわね。ちゃんと待っててよ。帰ったりしちゃ、いやよ」
「どこへも行かない」
「げんまん」
珠緒は曲げた小指を差し出す。隼人は、言われるままに小指をかけた。
「嘘ついたら、針千本飲ます」
珠緒はいそいそと着物の裾をひるがえし、華やいだ様子で障子を引く。障子が閉まる間際、珠緒は一瞬手をとめ、愛しそうに隼人を見つめた。隼人は、純な愛情を己に向ける珠緒の心と、行き場を失ってのたうつ己の心を較べ、口許に微苦笑をにじませた。
隼人の風貌は貴公子のそれだった。明るい瞳は透き通り、高貴な公家の血が流れているような印象を人に与えた。すっと鼻筋の通った高い鼻。ふっくらと整った唇。今は丸刈りにしているが、元々は天然パーマの甘い長髪をしていた。正装をして舞踏会へ出れば、社交界の花形になることは請け合いだ。ただ時折、触れるものをすべて切ってしまいそうな、どこか危うさを秘めたまなざしをのぞかせた。
窓の木枠にもたれ、横丁の向こうを眺めた。桜の花が三分咲きにほころんでいる。
「あの桜が散る頃には、俺も大海原で散華だな」
隼人はひとりごち、顔を顰《しか》めた。指揮官は、己の吐く言葉がどれほど虚しいものかも知りもせずに米海軍のミッチャー機動部隊を叩き潰すのだと息巻いていた。神風攻撃が成功を収めているのであれば、ミッチャーなんぞ、とうの昔に尻尾を巻いてアメリカへ逃げ帰っているはずではないか。
「そんなことはどうでもいい」
隼人は頭を振った。
――俺はなにがしたいのだ?
さっきの言葉が、心のなかでからからと回る。冷たい風が心を吹き荒《すさ》ぶ。心に砂塵が舞い上がる。
なにか一つでいいから、死ぬまでに確かなことを成し遂げたかった。生きた証を現世《うつせみ》に残しておきたかった。が、あと一週間か十日ばかりで、いったいなにができるというのだろう。なにもできないばかりではない。今まで学んできたことも、努力を重ねてきたことも、すべてふいになる。
ドストエフスキーは人間の魂の深淵を見せてくれた。トルストイは理想を掲げて生きることの素晴らしさを説いてくれた。ツルゲーネフは、まだ見たこともないロシアの自然をスケッチしてくれた。レーニンは力強く生きることを教えてくれた。隼人は貪るようにして次からつぎへと彼らの著作を読破し、そうして己の器を広げ、確固たる信念を練り上げようと格闘した。が、今となっては、それがいったい何になるというのだ?
心は空転する。そんな己が情けない。
操縦桿を握り、発進訓練。
標的を探し、急降下訓練。
毎日、訓練に明け暮れた。着地の訓練は要らない。どうせ片道飛行なのだから。
この数か月というもの、己が死ぬことの意味を考え続けた。そして、死ぬことに意味があるのだと、自分自身を説得しようと試みてきた。理屈をこねくりまわしては行き詰まり、また一からやり直し。そんな積み木崩しの繰り返しだった。
一粒の麦、
地に落ちて死なずば、
唯一つにて在らん、
もし死なば、
多くの果《み》を結ぶべし。
新約聖書のヨハネ伝第十二章二十四節に書かれているこの言葉を巡り、思索を繰り返した。
意味のある死であれば、結果として多くの果《み》を結ぶための死ならば、運命を甘受もしよう。が、特別攻撃の死に意味などあるのだろうか。いや、意味など見出せない。体当たりを喰らわす前に撃ち落されるのは目に見えている。米軍は、懲りもせずに阿呆鳥がまた飛んできたと嗤《わら》うことだろう。ただの犬死ではないか。生きてさえいれば、なにごとかを成し遂げられようものを、今まで蓄えてきた力と知識をみすみすどぶに捨てるようなものだ。
「なにが神風特別攻撃隊だ」
隼人は吐き捨てた。憂いが瞳に走る。
学徒動員の特攻隊員たちは、おたがいに死ぬという事実を口にしなかった。予定された死は祟り神だ。ひとたび触れようものなら、どんな騒ぎが持ち上がるか、しれたものではない。汗臭い兵舎のなかでは、それぞれ己の殻に閉じこもり、不条理な死を自分自身に納得させるという孤独で神経質な作業に従事した。見捨てられた淋しさを感じない者はいなかった。心を火焙りの拷問にかけるようなことをしているのだから、当然、誰もが誰にも邪魔されたくはなかった。まれに、お上の宣伝文句を鵜呑みにしてくだらない演説をぶつ輩がいることはいたものの、そのような単細胞は冷笑と憐憫を以て迎えられた。祖国のために自殺攻撃を行なうのではない。戦争の勝負なら、もうついている。敗戦を引き延ばし責任逃れをしたい提督たちのために無謀な自殺攻撃をさせられる――ただそれだけのことだ。とはいえ、無意味な自殺攻撃ほどむなしいものはない。己の死の意味を求めずにはいられなかった。それはすなわち、己の存在の意味を考究《こうきゅう》することでもあった。
特攻機の整備員たちは無表情の仮面を被り、腫れ物にでも触るようにして特攻隊員に接した。ニュース映画は特攻隊員を軍神と持ち上げ、さも出陣を祝うように見送る場面を映しているが、嘘っぱちもいいところだった。整備員はみな黙々と自分の仕事をこなした。もし特攻が一度きりの、国家の命運を決するものであれば、感情もまた高揚したかもしれない。が、特攻は特別なものでもなんでもなく、もはや日常の作戦《オペレーション》だった。理不尽が日常と化してしまった。平時においては邪道と考えられていたことが、耐え難いと思われていたことが、当たり前のことになってしまったのだ。不条理に飼いならされた整備員たちは言葉を奪われた。理不尽に首根っこを摑まれたのでは、自分の気持ちを押し殺し、麻痺するよりほかにどうしようもない。それが唯一の処世術だ。
そのような姿を見るにつけ、隼人は己だけは誤魔化されるまい、己の心を誤魔化すまいと誓った。たとえ、この命を使い捨てにされると識《し》っていても、いや、それを解《わか》っているからこそ、己の心を嘘で塗り固めたくはなかった。もしもこの世が虚空なら、冷ややかな虚ろさをしっかりと抱きしめたまま黄泉へ赴きたかった。たとえ、心に寂しい風が吹き抜けようとも。
珠緒があがってきた。照れ笑いを目元に浮かべ、結った髪に手をやる。
「おっかさんがね、今日は特別だからって、香水をつけてくれたのよ」
はにかんだ珠緒のうなじから甘い匂いがほのかに漂った。
痩せた体。田舎娘の素朴な顔。丸い鼻に愛嬌と人の好さが宿っている。今頃になって、珠緒の頰には小さなほくろが星のように並んでいると気づいた。
「素顔のほうがいいな」
隼人が湯上がりの火照った体をかき抱けば、
「はずかしい」
と、珠緒は隼人の胸に顔を埋める。柔らかい女の香りが凍りついた隼人の心をかすかに溶かす。
戯れというには真剣《シリアス》で、愛と呼ぶにはふざけた営みが終わった。隼人は息苦しさを彼女に預け、どれだけもがいても癒すことのできない無念を紛らわせた。これで最後だと思うとどうにも気持ちが昂《たかぶ》り、立て続けに三度抱いた。最後の交尾を行なう蟷螂《とうろう》の雄は、あるいはこんな風にどうしようもないほど興奮するものなのかもしれないと、果てた後、隼人は天井をぼんやり眺めながら思った。心を吹き荒ぶ風が束の間、凪《な》いだ。隼人は深く息を吸いこんだ。
起き上がった珠緒は襦袢を羽織ろうとする。
「もう少しだけ、そのままでいてくれ」
隼人が珠緒の手を握ると、
「隼人さんのためだよ」
と、珠緒は手にした襦袢を脇へ置いた。
隼人は首筋をそっと眺めた。浅黒い肌に紅い染みが一粒ついている。営みの最中、隼人が残した小さな記念だった。隼人がこの世に生き、珠緒と交わった証だ。珠緒は自分の裸体を見下ろし、
「ちょっとだけ、胸がふくらんだかな」
と、嬉しそうに乳房をなでる。
「ここの食事は栄養がいいと見えるね」
「おっかさんがね、特別配給だっていっていろんなものをくれるのよ。けさはご飯に生卵をかけたし、おやつに羊羹を食べちゃった。あたいらは体が資本だからね」
「パイロットみたいだな」
隼人は朗らかな笑い声を立てた。操縦士には、特別栄養食としてカロリーの高いものが配給された。それだけが、神風特攻隊の唯一の楽しみだった。娼家には軍から闇物資が流れている。やり手の女将ほど、高級将校に物をねだるのがうまい。珠緒が口にしたものは、おそらく女将が将校に頼んで入手した品だろう。
「なんであたいの素顔を見たかったの?」
あどけない瞳になった珠緒は、子猫でもかわいがるように隼人の額をなでる。
「白粉をつけた君は商売女さ。だが、素顔の君は人間だ。それを見たかった」
人間を押し殺してしまう強大な魔性がこの世を覆っている。それは抗うことを許さない圧倒的な暴力だった。本音の自分を見せれば、生きていかれない。人々は人前では思ってもいないことを口にし、陰に隠れてこっそり他人を蹴落とした。すべては生き延びるためだ。それが獣性から離れえない人間の業《カルマ》とはいえ、罪作りには違いない。もしもこの世に純粋な愛や真心があるとすれば、それを裏切る日々だった。
「そんなことをいってくれた人、隼人さんがはじめてだよ」
珠緒は両手で顔を覆う。
「君は人間さ」
隼人は珠緒の乳房に掌を当てた。心臓は確かな鼓動を打っている。それは混じりけのない生成《きな》りのやさしさだった。生きることのせつなさとはかなさが隼人をつつんだ。この温もりを覚えておこう。己にそっと言い聞かせた。
「いやらしいことをいっぱいされて、はずかしい思いをいっぱいさせられて――」
珠緒は肩を震わせる。悪趣味な軍人ややくざにむりやり小便を飲まさせられたと、いつか珠緒が話したことがあった。ほかにも人に言えない思いがたくさんあるのだろう。今がまともな世の中だったなら、珠緒はありふれた倖《しあわ》せを摑み、平凡な農婦として山奥の僻村で一生を送ったはずだった。が、時代がそうはさせてくれなかった。父親がアッツ島で玉砕したために珠緒の家は一家の大黒柱を失い、家計を支えるのは珠緒の役割となった。珠緒はこうして体をひさぎ、残された家族を養っていた。
「隼人さん、ほんとうに死んじゃうの?」
珠緒は小さくつぶやき、隼人の膝に手を置いた。素朴な丸い目から、涙がこぼれ落ちる。
「おいおい、まだ殺してもらっちゃ困るな。俺は生きている」
隼人は右の眉だけ吊り上げてみせた。
「でも、死んじゃうんでしょ」
「まあな」
「あたいの命をあげたいよ」
「俺のことはいい。珠緒はしっかり生きろ」
隼人は彼女の肩を抱いた。想ってくれる人がいる。それがなによりもありがたかった。ふと、ほんとうの恋人のような気がした。一度だけ、休みの日に珠緒を連れ出して河原を散歩したことがあった。隼人は、あの日の夕焼け空を思い出し、あるはずもないふたりの未来を夢想した。
「ねえ、わがままを言っていい?」
珠緒はうつむく。
「なんだ」
「預かってる御本をちょうだい」
「いいさ。やるよ」
隼人は危険な本を珠緒に渡していた。従兄に譲ってもらったロシア語版のレーニン伝記だった。もちろん禁書だ。特高警察に見つかれば、逮捕されて拷問を受けるのは間違いない。刑事に追われていた従兄はこの本を隼人に託し、自ら命を絶った。死ぬ前にもう一度読み返したい本だったので、鞄の底に隠して持ってきたのだが、さすがに兵舎に置いたきりにするのは危ない。そこで珠緒に預かってもらったのだった。珠緒は、押入れの奥からくすんだ緑色の背表紙に金文字でタイトルを記した本を取り出した。手の脂のにじんだ牛皮の表紙が鈍く光っていた。
「一生大切にするわ」
珠緒は、まるで隼人を抱くように愛しそうにレーニン伝記を抱く。
「大切になんかしなくていいさ。だいいち、読めないだろう」
「読めなくてもいいの。お守りにするから」
「この本は土にでも埋めて隠しておくんだ。もし見つかりでもしたら、君は殺される。時がくれば、売ればいい」
「そんな」
「もうすぐこの戦争は終わる」
「そんな噂を聞くけど、ほんとう?」
「この夏には終わる。長くても秋だな。――この国は負ける。そうなれば世の中が変わる。この本は日本ではなかなか手に入らない貴重なものだから、きっといい値段で売れるさ」
「隼人さんの形見をお金にかえるだなんて、できないわ」
珠緒は悲し気に首を振った。
「いいか、よく聞くんだ。戦争が終わったら、日本は大混乱に陥って餓死者が大勢出るだろう。どうしてもお金がなくなったら、この本を売って生活の糧に変えるんだ」
「いやよ。お守りなんですもの」
「本はただの物だから売ってしまっていいのだよ。時々でいいから、俺のことを思い出してくれないか。そうすれば、俺は珠緒の思い出のなかで生き続けることになる」
「わかったわ。隼人さんのいうとおりにする。何度でも思い出すわ。せっぱつまったらこの本は売るわね。ごめんなさい」
「謝らなくていい。珠緒は、どんなことがあっても生き延びろ」
「約束する。あたいが死んだら、隼人さんも死んじゃうもの」
「いい子だ」
隼人は珠緒の頭をなでた。
連合軍の軍艦へ突っこむことで、彼女が生きながらえるための時間稼ぎをできるのなら、己の人生にもすこしは意味があったことになるのかもしれない。なにかの役に立ったことになるのかもしれない。珠緒の人生がなにかの果《み》を結んでくればいい。確信は持てないが、なんとなくそんな気がした。
「隼人さん、どうして特攻なんかに行っちゃうのよ」
拳を握りしめた珠緒は、隼人の胸を叩く。遠い海鳴りを聴くように、隼人は己の胸の響きに耳を傾けた。
「罪を贖《あがな》うのさ」
隼人はぽつりと言った。
「なにそれ? 隼人さんは悪い人じゃないよ」
「今も、こうして君を裏切っている」
「そんなこと、ないったら」
「むずかしいかな。だが、いつかわかるかもしれない」
「全然わからない」
珠緒はどこへも行かせないとばかりに抱きすくめ、隼人の体にしがみつく。ふたりは震える唇を合わせた。
そろそろ兵営へ戻らなければいけない時刻だった。隼人は帰り支度をして階段を降りた。
玄関から路地を見やれば、いつのまにか冷たい雨が降っている。この世という名の流刑地に降る花冷えの雨だった。
「傘を持っていってよ」
彼女は傘立てから店の傘を出そうとした。
「いいよ。もう返しにこられないから」
隼人の言葉に珠緒は黙りこむ。
「元気で」
隼人は手を振った。隼人の瞳にきらりと光ったのは、あるいは涙だったかもしれない。珠緒はこわばったまま目を瞠《みひら》く。迷子の幼な子のようだ。
「いい思い出をくれてありがとう。いつかきっと倖《しあわ》せになってくれ」
隼人は降りしきる雨へ飛び出した。
了
(2011年10月16日発表)
「小説家になろう」サイトでの本作のアドレス↓
http://ncode.syosetu.com/n6444x/