
中年男性の「自己啓発」を描く痛快コメディ
リチャード・リンクレーター監督『ヒットマン』
越川芳明
主人公のゲイリー・ジョンソンは平凡な中年の大学講師だ。ニューオーリンズの郊外にある、学生数七千人弱の小さな州立大学で哲学と心理学を教えている。
結婚歴があるが、いまは独り身のアパートで、鳥や猫を飼い、観葉植物を育てながら静かだが、退屈な日々を過ごす。
電子機器の扱いが得意で、小遣い稼ぎのために地元の警察でパートタイムの仕事を得て、盗聴や盗撮を担当する捜査官でもある。
この講師、大学では若者たちに、ニーチェやフロイトを持ち出してあれこれ説く。
自己とは確固たるものではなく、他者によって「構築」されたものに過ぎないとすれば、未知の自己を発見するためにも、リスクを冒してその殻を破るべきではないか・・・とかなんとか。
だが、実のところ、かれ自身は、変わりばえのしないルーティンを繰り返すばかりの日々を送っている。
ひとりの学生が揶揄するように、かれ自身の日常はリスクを冒すどころか、愛車「シビック」に象徴されるように、中産階級的な小さな安逸に浸っているだけなのだ。
さて、舞台であるメキシコ湾に面したルイジアナ州南部は、合衆国のなかでも得意な歴史と文化を持つ土地である。
もともと先住民たちのものであったが、十七世紀にフランスとスペインが植民地支配するようになる。
しかし、「クレオール」と呼ばれる、植民地のスペイン系やフランス系のカトリック教徒の人たちの他に、先住民やアフリカ黒人のプレゼンスもあり、
そんな多様な人びとによって、ブリキの洗濯板を楽器に応用した「ザディコ音楽」をはじめとして、独自のまぜこぜ文化が培われてきた土地柄である。
英語アングロ文化中心のアメリカ社会のなかで、こうした混淆文化が息づいている土地はめずらしい。
なぜリンクレーターはそうした土地を舞台にして、冴えない中年男性を主人公にした映画を作ろうとしたのだろうか。
思いかえせば、初期の『恋人までの距離(ディスタンス)』(一九九六年)から、この映画監督は移動や旅が人間の精神にもたらす化学変化を描いてきたのだった。
とりわけ、男女関係において、それまでの他人同士が旅の途上で出会い、共通の失敗や事故を経験することで、お互いの心に何か恋心のようなモノが芽生える。
しかし、それは恋心とはっきり言えるモノではないかもしれないが、確実にお互いの内面に変容をおこしていく。
本作でも、若者をけしかけながら、自分は何もできない中年男性が、ふとしたことがきっかけで惰性の生活からの脱却を余儀なくされる。
警察では安全な機械技師をしていたが、おとり捜査のための殺し屋(ヒットマン)を演じる任務へと配置転換される。
名前を変え、毎回あれこれ扮装して別の人間を演じる。
知らず知らずのうちにかれの自身の自己発見の旅が始まっている。
ハリウッド映画特有のハッピーエンドで終わる痛快コメディにもかかわらず、リンクレーター風のひねりが効いている。
アメリカ人好みの「自己啓発」のテーマがそっと隠されているのだ。ミッドクライシス(中年の危機)にある人びとのための教訓が・・・。
合衆国は「自己啓発本」の一大産地である。
その名も『アメリカは自己啓発本でできている』(平凡社刊)という本のなかで、著者の尾崎俊介は、なぜアメリカで自己啓発本が流行るのか、明快に説明している。
ふたつの条件があることが重要であるらしい。
ひとつは、どのような出自であろうと、どこに住んでいようと、男性であろうと女性であろうと社会的な成功(「出世」)を望めば、それが実現できる社会環境・流動性あること。
もうひとつは、そうした成功を望んで努力を惜しまない人たちが大勢いるかどうかということ。
そういうふたつの条件が揃った十八世紀以降のアメリカで、例えばベンジャミン・フランクリンという、貧しい職人の子に生まれながら、アメリカ植民地の代表にまで上り詰めた立志出世の巨人が現われる。
現代にいたるまで、成功への道を歩むにはどうしたらよいかを説く指南書(「自己啓発本」)が続々と生まれている。
確かに、本作では出世というより恋愛成就に重きがあるが、それでも「自己啓発」「自己発見」という中心軸は揺るがない。
これもリンクレーターの思想を背後から支えていると思うので、最後に触れておこう。
ニューオーリンズ文化を彷彿とさせる音楽が満載である。
冒頭から、二十世紀初頭のニューオーリンズ・ジャズを牽引した天才ピアニスト、ジェリー・ロール・モートンのアップテンポな曲が流れてくる。
ラグタイムやブルースなどをフュージョンしたユニークな曲を作ったモートンは、人種差別に異を唱え、アームストロングをはじめ、のちの優れた黒人アーティストのために道を切り開いたといわれる。
さらにバックウィート・ザディコによる「スペース・ザディコ」をはじめとして、ニューオーリンズを本拠地にして活躍したミュージシャンが目白押しである。
リズム・アンド・ブルースのジューン・ガードナーやアルヴィン・ロビンソン、アラン・トゥーサン、ラッパーのロブ49、ジャズトランペッター・キッドのトーマス・ヴァレンタインなど。
とりわけ、白人でありながら、十九世紀の有名なヴードゥ教(ハイチの黒人宗教)の司祭の名前にあやかって演奏活動したドクター・ジョンは、この映画のなかで二曲も採用されている。
ニューオーリンズは合衆国の南の果てであるが、見方を変えれば、カリブ海のフランス語文化圏の北の果てでもある。
マルティニークやハイチなどフランス植民地の「クレオール文化」と強く結びついている。
十八世紀半ばにあった「フレンチ・インディアン戦争」で、イギリス軍によって追放されたカナダ南東部アカディアのフランス系の人々が大挙してこの地に流れてきた。
かれらはここでは「ケイジャン」と呼ばれ、
土地で獲れるザリガニや小エビなどの魚介類にオクラや香味野菜をつかったシンプルなケイジャン料理(ごった煮の「ガンボ」が有名)や、アコーディオンを主楽器にしてフランス語で歌うケージャン音楽など、ユニークな文化を生み出す。
そんなわけで、本作の最後に流れてくるブードゥ教司祭を演じるドクター・ジョンの「サッチ・ア・ナイト」という甘いメロディーは、この中年男性の「自己啓発」をテーマにしたコメディにぴったりである。
こんな夜は こんな夜は
甘い混乱が 月夜の下で
こんな夜は こんな夜は
駆け落ちに ぴったりなとき
君の目が僕の目をとらえ
一瞥で 君は僕に教えてくれた
いまこそ 僕のチャンスだと
だけど 君はここにやってきた
僕の親友のジムと一緒に
で僕はいま必死なんだ
君と駆け落ちしようとして
リチャード・リンクレーター監督『ヒットマン』
越川芳明
主人公のゲイリー・ジョンソンは平凡な中年の大学講師だ。ニューオーリンズの郊外にある、学生数七千人弱の小さな州立大学で哲学と心理学を教えている。
結婚歴があるが、いまは独り身のアパートで、鳥や猫を飼い、観葉植物を育てながら静かだが、退屈な日々を過ごす。
電子機器の扱いが得意で、小遣い稼ぎのために地元の警察でパートタイムの仕事を得て、盗聴や盗撮を担当する捜査官でもある。
この講師、大学では若者たちに、ニーチェやフロイトを持ち出してあれこれ説く。
自己とは確固たるものではなく、他者によって「構築」されたものに過ぎないとすれば、未知の自己を発見するためにも、リスクを冒してその殻を破るべきではないか・・・とかなんとか。
だが、実のところ、かれ自身は、変わりばえのしないルーティンを繰り返すばかりの日々を送っている。
ひとりの学生が揶揄するように、かれ自身の日常はリスクを冒すどころか、愛車「シビック」に象徴されるように、中産階級的な小さな安逸に浸っているだけなのだ。
さて、舞台であるメキシコ湾に面したルイジアナ州南部は、合衆国のなかでも得意な歴史と文化を持つ土地である。
もともと先住民たちのものであったが、十七世紀にフランスとスペインが植民地支配するようになる。
しかし、「クレオール」と呼ばれる、植民地のスペイン系やフランス系のカトリック教徒の人たちの他に、先住民やアフリカ黒人のプレゼンスもあり、
そんな多様な人びとによって、ブリキの洗濯板を楽器に応用した「ザディコ音楽」をはじめとして、独自のまぜこぜ文化が培われてきた土地柄である。
英語アングロ文化中心のアメリカ社会のなかで、こうした混淆文化が息づいている土地はめずらしい。
なぜリンクレーターはそうした土地を舞台にして、冴えない中年男性を主人公にした映画を作ろうとしたのだろうか。
思いかえせば、初期の『恋人までの距離(ディスタンス)』(一九九六年)から、この映画監督は移動や旅が人間の精神にもたらす化学変化を描いてきたのだった。
とりわけ、男女関係において、それまでの他人同士が旅の途上で出会い、共通の失敗や事故を経験することで、お互いの心に何か恋心のようなモノが芽生える。
しかし、それは恋心とはっきり言えるモノではないかもしれないが、確実にお互いの内面に変容をおこしていく。
本作でも、若者をけしかけながら、自分は何もできない中年男性が、ふとしたことがきっかけで惰性の生活からの脱却を余儀なくされる。
警察では安全な機械技師をしていたが、おとり捜査のための殺し屋(ヒットマン)を演じる任務へと配置転換される。
名前を変え、毎回あれこれ扮装して別の人間を演じる。
知らず知らずのうちにかれの自身の自己発見の旅が始まっている。
ハリウッド映画特有のハッピーエンドで終わる痛快コメディにもかかわらず、リンクレーター風のひねりが効いている。
アメリカ人好みの「自己啓発」のテーマがそっと隠されているのだ。ミッドクライシス(中年の危機)にある人びとのための教訓が・・・。
合衆国は「自己啓発本」の一大産地である。
その名も『アメリカは自己啓発本でできている』(平凡社刊)という本のなかで、著者の尾崎俊介は、なぜアメリカで自己啓発本が流行るのか、明快に説明している。
ふたつの条件があることが重要であるらしい。
ひとつは、どのような出自であろうと、どこに住んでいようと、男性であろうと女性であろうと社会的な成功(「出世」)を望めば、それが実現できる社会環境・流動性あること。
もうひとつは、そうした成功を望んで努力を惜しまない人たちが大勢いるかどうかということ。
そういうふたつの条件が揃った十八世紀以降のアメリカで、例えばベンジャミン・フランクリンという、貧しい職人の子に生まれながら、アメリカ植民地の代表にまで上り詰めた立志出世の巨人が現われる。
現代にいたるまで、成功への道を歩むにはどうしたらよいかを説く指南書(「自己啓発本」)が続々と生まれている。
確かに、本作では出世というより恋愛成就に重きがあるが、それでも「自己啓発」「自己発見」という中心軸は揺るがない。
これもリンクレーターの思想を背後から支えていると思うので、最後に触れておこう。
ニューオーリンズ文化を彷彿とさせる音楽が満載である。
冒頭から、二十世紀初頭のニューオーリンズ・ジャズを牽引した天才ピアニスト、ジェリー・ロール・モートンのアップテンポな曲が流れてくる。
ラグタイムやブルースなどをフュージョンしたユニークな曲を作ったモートンは、人種差別に異を唱え、アームストロングをはじめ、のちの優れた黒人アーティストのために道を切り開いたといわれる。
さらにバックウィート・ザディコによる「スペース・ザディコ」をはじめとして、ニューオーリンズを本拠地にして活躍したミュージシャンが目白押しである。
リズム・アンド・ブルースのジューン・ガードナーやアルヴィン・ロビンソン、アラン・トゥーサン、ラッパーのロブ49、ジャズトランペッター・キッドのトーマス・ヴァレンタインなど。
とりわけ、白人でありながら、十九世紀の有名なヴードゥ教(ハイチの黒人宗教)の司祭の名前にあやかって演奏活動したドクター・ジョンは、この映画のなかで二曲も採用されている。
ニューオーリンズは合衆国の南の果てであるが、見方を変えれば、カリブ海のフランス語文化圏の北の果てでもある。
マルティニークやハイチなどフランス植民地の「クレオール文化」と強く結びついている。
十八世紀半ばにあった「フレンチ・インディアン戦争」で、イギリス軍によって追放されたカナダ南東部アカディアのフランス系の人々が大挙してこの地に流れてきた。
かれらはここでは「ケイジャン」と呼ばれ、
土地で獲れるザリガニや小エビなどの魚介類にオクラや香味野菜をつかったシンプルなケイジャン料理(ごった煮の「ガンボ」が有名)や、アコーディオンを主楽器にしてフランス語で歌うケージャン音楽など、ユニークな文化を生み出す。
そんなわけで、本作の最後に流れてくるブードゥ教司祭を演じるドクター・ジョンの「サッチ・ア・ナイト」という甘いメロディーは、この中年男性の「自己啓発」をテーマにしたコメディにぴったりである。
こんな夜は こんな夜は
甘い混乱が 月夜の下で
こんな夜は こんな夜は
駆け落ちに ぴったりなとき
君の目が僕の目をとらえ
一瞥で 君は僕に教えてくれた
いまこそ 僕のチャンスだと
だけど 君はここにやってきた
僕の親友のジムと一緒に
で僕はいま必死なんだ
君と駆け落ちしようとして










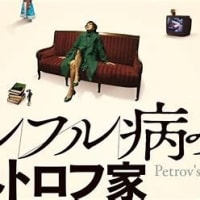
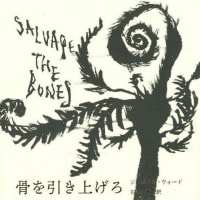

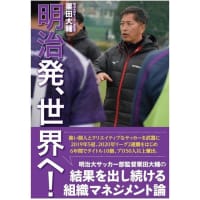











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます