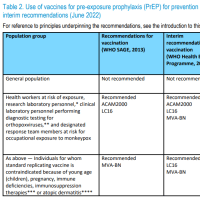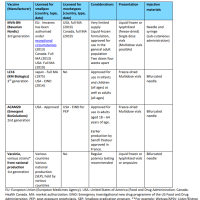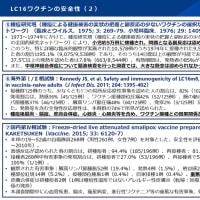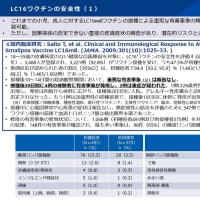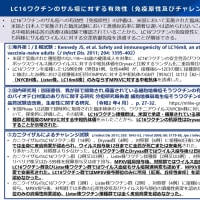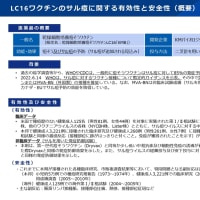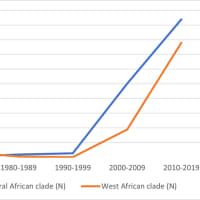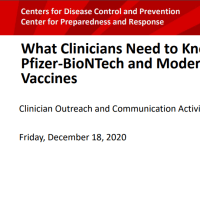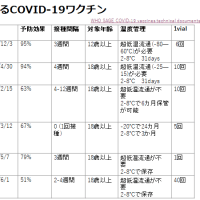感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)における記載
(就業制限)
第十八条 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。
2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。
3 前項の規定の適用を受けている者又はその保護者は、都道府県知事に対し、同項の規定の適用を受けている者について、同項の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による確認の求めがあったときは、当該請求に係る第二項の規定の適用を受けている者について、同項の規定の適用に係る感染症の患者若しくは無症状病原体保有者でないかどうか、又は同項に規定する期間を経過しているかどうかの確認をしなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該患者又は無症状病原体保有者の居住地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
6 前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その通知をした内容について当該協議会に報告しなければならない。
この際、1~3項については、事務の区分により法廷受託事務と整理される。
(事務の区分)
第六十五条の二 第三章(第十二条第四項、同条第五項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十六条並びに第十六条の二を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項から第三項まで、第四十四条の五、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第五項、同条第七項において準用する第三十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項及び第五項並びに第五十一条第四項において準用する同条第一項から第三項までを除く。)並びに第十章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
自治事務と法定受託事務
●国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの
●必ず法律・政令により事務処理が義務付けられる。
● 是正の指示、代執行等、国の強い関与が認められている。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症法施行規則)における記載
(就業制限)
第十一条 法第十八条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容
二 法第十八条第二項 に規定する就業制限及びその期間に関する事項
三 法第十八条第二項 の規定に違反した場合に、法第七十七条第四号 の規定により罰金に処される旨
四 法第十八条第三項 の規定により確認を求めることができる旨
五 その他必要と認める事項
2 法第十八条第二項 の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
一 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務
二 結核 接客業その他の多数の者に接触する業務
三 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、痘そう、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。次項において「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)及びペスト 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務
四 法第六条第二項 から第四項 までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
3 法第十八条第二項 の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 結核、重症急性呼吸器症候群及び鳥インフルエンザ(H五N一) その病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間
二 前号に掲げるもの以外の感染症 その病原体を保有しなくなるまでの期間
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における健康診断、就業制限及び入院の取扱いについて」の一部改正について
(平成19年3月29日)
(健発第0329008号)
(各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)
第3 就業制限に関する事項
1 基本的な考え方
就業制限は、感染症の病原体を保有している者が特定の職業への就業を通じて当該感染症を他人にまん延させるおそれがあるため、当該者に対して就業をしないよう通知するものであり、都道府県等は、感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴いて、特定の職業への就業を通じたまん延のおそれの有無に照らして、通知を行う対象者を客観的に判断することが重要であること。
また、就業制限については、その対象者の自覚に基づく自発的な休暇、就業制限の対象以外の業務に一時的に従事すること等により対応することが基本であり、都道府県等は、対象者その他の関係者に対し、このことの周知等を行うことが重要であること。
2 対象者への周知
法第12条第1項の届出を受けた都道府県知事等は、協議会の意見を聴いて、速やかに一類感染症の患者、二類感染症又は三類感染症の患者又は無症状病原体保有者に対して就業制限の通知をすること。緊急を要する場合で、あらかじめ、協議会の意見を聴くいとまがないときは、その通知をした内容について事後に報告しなければならないこと。
対象者がその管轄する区域外に居住する者である場合には、その者の居住地(住民票の住所地に限られない。以下同じ。)を管轄する都道府県知事等に照会する等、対象者の居所を的確に把握し、就業制限の通知が確実に行われるようにすること。
通知を行うべき対象者が、感染症指定医療機関に入院する等の理由により、事実上業務に従事することが困難な場合や、3の就業制限対象職種に現に従事していない場合であっても、必ず通知を行うこと。
3 就業制限対象職種
就業制限の対象となる職種は、以下のとおりとすること。
(1) エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱等のウイルス性出血熱について、飲食物の製造、販売、調整又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務
(2) 結核について、接客業その他の多数の者に相対して接触する業務
(3) ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下「重症急性呼吸器症候群」という。)、痘そう及びペストについて、飲食物の製造、販売、調整又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に相対して接触する業務
(4) その他の感染症について、飲食物の製造、販売、調整又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
4 就業制限の期間
就業制限の期間は、以下のとおりとし、当該期間を経過しているかどうかの確認のため、法第18条第3項の規定による確認請求ができることの周知を図ること。
(1) 結核及び重症急性呼吸器症候群について、その病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間
(2) その他の感染症について、その病原体を保有しなくなるまでの期間
5 就業制限の通知時の協議会への諮問
(1) 都道府県知事等が法第18条第1項の規定による就業制限の通知について意見を聴く協議会は、診査の対象となる者の居住地を管轄する保健所に置かれたものであること。都道府県知事等は、意見を聴く際には、法第12条第1項の規定による届出の内容に関して記録した書類を含めて必要な書類を協議会に提出すること。
(2) 協議会は、通知の要否を診査し、その結果を法第12条第1項の届出を受けた都道府県知事等に連絡すること。
(3) 連絡を受けた都道府県知事等は、通知が必要な者について、速やかに法第18条第1項の規定による就業制限の通知を行うこと。
なお、対象者がその管轄する区域外に居住する者である場合には、居住地を管轄する保健所に置かれた協議会への諮問の手続について事前に都道府県等間で協定を締結する等、法第18条第1項の規定による就業制限の通知に支障を来すことのないようにすること。
6 就業制限の通知時の協議会への報告
都道府県知事等が法第18条第6項の規定により報告する際には、次に掲げるものを含めて必要な書類を5の協議会に提出すること。
ア 報告の対象となる者に対する就業制限を行う旨の通知の写し
イ 法第12条第1項の規定による届出の内容に関して記録した書類
7 就業制限の終了の確認
対象者又はその保護者が法第18条第3項の規定による確認請求を行った場合には、都道府県知事等は当該対象者が病原体を保有しているかどうかの確認を速やかに行うこと。
厚生省保健医療局結核感染症課長通知 (平成11年3月30日 健医感発第43号)
1 腸管出血性大腸菌感染症
・ 患者については、24時間以上の間隔を置いた連続2回(抗菌剤を投与した場合は服薬中と服薬中止後48時間以上経過した時点での連続2回)の検便によって、いずれも病原体が検出されなければ、病原体を保有していないものと考えてよい。
・ 無症状病原体保有者については、1回の検便によって菌陰性が確認されれば、病原体を保有していないものと考えてよい。
2 コレラ及び細菌性赤痢
・ 患者については、抗菌剤の服薬中止後48時間以上経過した後に24時間以上の間隔を置いた連続2回の検便によって、いずれも病原体が検出されなければ、病原体を保有していないものと考えてよい。
・ 無症状病原体保有者については、無症状病原体保有確認後48時間以上を経過した後に24時間以上の間隔を置いた連続2回(抗菌薬を投与していた場合にあっては服薬中止後48時間以上を経過した後に24時間以上の間隔を置いた連続2回)の検便によって、いずれも病原体が検出されなければ、病原体を保有していないものと考えてよい。
3 腸チフス及びパラチフス
・ 患者については、発症後1ケ月以上を経過していて、抗菌薬の服薬中止後48時間以上を経過した後に24時間以上の間隔を置いた連続3回の検便において、いずれも病原体が検出されなければ、病原体を保有していないものと考えてよい。また、尿中に病原体が検出されている場合にあっては、前記の検便における病原体の陰性確認に加えて、検尿の結果も検便の場合と同様に病原体が検出されなかった場合において、病原体を保有していないものと考えてよい。
・ 無症状病原体保有者については、無症状病原体保有確認後1ケ月以上を経過した後に24時間以上の間隔を置いた連続3回(抗菌薬を投与していた場合にあっては服薬中止後48時間以上を経過した後に24時間以上の間隔を置いた連続3回)の検便によって、病原体が検出されなければ、病原体を保有していないものと考えてよい。また、尿中に病原体が検出されている場合にあっては、前記の検便における病原体の陰性確認に加えて、検尿の結果も検便の場合と同様に病原体が検出されなかった場合において、病原体を保有していないものと考えてよい。
4 ジフテリア及びペスト
・ 患者については、抗菌剤の服薬中止後24時間以上経過した後に24時間以上の間隔を置いた連続2回の検査(ジフテリアの場合は咽頭ぬぐい液、ペストの場合は喀痰(肺ペスト)、分泌液(腺ペスト)又は血液(敗血症ペスト))によって、いずれも病原体が検出されなければ、病原体を保有していないものと考えてよい。
・ 無症状病原体保有者については、無症状病原体保有確認後24時間以上を経過した後に24時間以上の間隔を置いた連続2回(抗菌薬を投与していた場合にあっては服薬中止後24時間以上を経過した後に24時間以上の間隔を置いた連続3回)の検査(ジフテリアの場合は咽頭ぬぐい液、ペストの場合は喀痰(肺ペスト)又は分泌液(腺ペスト))によって、いずれも病原体が検出されなければ、病原体を保有していないものと考えてよい。
5 急性灰白髄炎(ポリオ)
・ 急性期症状消失後、48時間以上の間隔を置いた2回の検査(便及び咽頭ぬぐい液からのウイルス分離)において、強毒(野生株)ポリオウイルスが検出されなければ、病原体を保有していないものと考えてよい。
6 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱
・ 急性期症状消失後、1週間以上の間隔を置いた2回の検査(感染症の種類毎に別表1に定める検体全てにおけるウイルス分離)の結果、病原体が検出されなかった場合に、病原体を保有していないものと考えてよい。但し、検体毎に別表2に定める発病後の期間を超えた後の場合にあっては、1回の検査の結果、病原体が検出されなかった場合に、病原体を保有していないものと考えてよい。
7 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)
・ 検査(咽頭ぬぐい液、喀痰、便、血液からのウイルス分離)の結果、病原体が検出されなかった場合に、病原体を保有していないものと考えてよい。
8 痘そう
・ すべての痂皮が落屑した場合に、病原体を保有していないものと考えてよい。 (ただし、落屑の中には病原体が存在するため、必ず滅菌消毒処理をすること。)
(別表1)
ラッサ熱: 血液、咽頭ぬぐい液、尿、脳脊髄液、胸水
エボラ出血熱: 血液、精液
マールブルグ病: 血液、咽頭ぬぐい液、尿、便、精液、前房水
クリミア・コンゴ出血熱: 血液、咽頭ぬぐい液
(別表2)
ラッサ熱
血液 16日、咽頭ぬぐい液 24日、尿 32日、脳脊髄液 14日、胸水 14日
エボラ出血熱
血液 8日、精液 61日
マールブルグ病
血液 7日、前房液 80日
クリミア・コンゴ出血熱
血液 9日