子檀嶺岳ってルビがふってないと読めないですよね。こまゆみだけと読みます。信州の鎌倉と呼ばれる塩田平にある霊峰です。別所温泉に行く途中に、右側に見えるプリン型の台形の山なので、訪れたことのある方は、あああれかと分かると思います。
古代よりこの地は信濃十六牧の一つ塩原牧(しおばらのまき)に属する馬の産地で、「駒斎(こまい)み」が転訛したという説があります。斎は、「ものいみ」で神仏を祀る時に身を清めることです。子檀嶺神社の祭神は、木俣神(きのまたのかみ)とされていますが、『日本三代実録』では駒弓神(こまゆみのかみ)と記されているので、やはり、牧場の守護神が名の由来なのでしょう。他には胡麻忌みという伝説も残っており、青木村では胡麻を作らないというのですが、今でもそうなのでしょうか。

143号線の「道の駅あおき」から見上げた子檀嶺岳なんですが、どこからどうやって登るのって思いますよね。手前側の南面は、100m以上の崖です。しかもこの山頂は、冠者岳城跡(別名を子檀嶺岳城、火車ヶ岳城、烏帽子形城)の本郭なんです。アンビリーバブル。取材登山に同行した編集者がヒエ~っ!と絶句していました。

当郷管社地区の子檀嶺神社(現在は廃社で下の阿鳥神社に合祀)から見上げた子檀嶺岳。中は少し登って子檀嶺岳登山者休憩所からの子檀嶺岳。裏手にはサフォークやウサギの小さな牧場があります。往路は当郷管社コースを。右は登り始め。思いの外緩やかな登山道が続きます。実は、登山道は、あの山の裏側に緩やかに回って登って行くのです。

最後の登りは急坂ですが、つづら折れで登るので、そう大変ではありません。山頂の主尾根に乗った所は、城跡の堀切の様な所。手前に見張り台の様な小ピークがあります。東側がスパッと切れ落ちていて(最初のカットの右側)、四阿山方面が望めます。戻ってヤセ尾根をひと登りすると山頂。
山頂のベンチで越冬したヒオドシチョウが日向ぼっこをしていました。一番右が山頂なんですが、狭いです。実は、これは団体さんが去った後で、この少し前までは大賑わいでした。山頂には、青木村の田沢、村松、当郷の里宮の奥社があります。

山頂から南には、塩田平のもう一つの霊峰である夫神岳が見えます。左奥には蓼科山、右奥には美ヶ原が見えます。まだかなり残雪があります。実はこの日は黄砂が舞っていて、眺望はもうひとつクリアではありませんでした。上の写真は、コントラストと彩度を補正してあります。

帰路は村松西洞コースへ。こちらは厳しいです。もの凄い急斜面を木に掴まりながら下りました。振り返って山頂を見上げたところ。険しい溶岩の崖です。中は仏岩からの展望。遠くに独鈷山が見えます。これも険しい山で、冬に敗退したことがあります。右は、わずかに咲いていたキジムシロ。

下山後は、麓にある国宝の大法寺三重塔を訪れました。子檀嶺岳登山と必ずといっていいほどセットになる古刹です。「信州の鎌倉」といわれる塩田平は、平安時代までに新田開発が進み、鎌倉時代には米と麦の二毛作が行われ、相当に豊かでした。そして、北条氏の庇護を得てたくさんの寺院や塔が建立されました。子檀嶺岳の山麓にある国保大法寺三重塔は、そんな鎌倉時代の栄華を残す名塔であり、地元の宝です。
塔は、大正9年の解体修理の際に発見された墨書により、鎌倉幕府滅亡の年である1333年(正慶二年)に建立されたことが分かっています。塔のある大法寺は、大宝年間(701~704)藤原鎌足の子上恵が開基し大宝寺と称したといわれ、平安初期の大同年間(801~810)に坂上田村麻呂の祈願で僧義真(初代天台座主)により再興されたと伝わっています。
ここにこのような壮麗な塔が建ったのは、北条氏の庇護とともに、この麓を東山道が通り、浦野駅(うらのうまや)(古代に30里毎に置かれた人馬の施設)があったからなのです。大法寺はその駅寺(うまやでら)でした。

初層には裳階(もこし)(ひさしようなもの。あると四重の塔のように見える)がなく二手先という構造で、初層が大きく安定感があります。軒下には地塗りに用いられた白い胡粉(ごふん)の顔料が、軒を支える肘木(ひじき)には 丹塗(にぬり)の赤い顔料が残っています。いずれも創建当時のものです。つまり往時は、朱色の壮麗豪華な三重塔だったわけです。屋根は檜皮葺(ひわだぶき)です。檜の樹皮を何層にも竹釘で止めていく非常に重厚で耐久性のある屋根です。檜皮を採取する技術者を『原皮師(もとかわし)』といい、樹齢50~60年の檜の樹皮を剥いで使います。その樹木を枯らさないように剥ぐのが高度な技術です。剥がれた樹皮は、8~10年で再生します。
この塔は、いつしかその余りの美しさに誰もが思わず振り返ることから「見返りの塔」と呼ばれるようになりました。
鎌倉時代にこの地で隆盛を誇った塩田北条氏は、鎌倉幕府の滅亡に際し、鎌倉に挙兵し、新田義貞の軍勢に攻略され滅亡しました。そして、時代は南北朝から室町時代、戦国時代へと慌ただしく変貌していきました。この塔がその頃どういう状態であったのかは知る術もありませんが、上田原の合戦などもあった戦国の世を兵火に焼け落ちることもなく残ったというのは、奇跡としかいいようがありません。三十年に一度の檜皮葺の屋根の葺き替えが終わり、さらに美しい姿になりました。

そして、帰路に上田の半過岩鼻の崖地にある絶滅危惧種のモイワナズナの撮影に向かいました。古代には千曲川を塞いでいたという岩鼻。大きな穴は、千曲川の流れが削ったもの。この崖地に咲くのがモイワナズナ。サハリンと北海道、そして本州ではこの上田の半過岩鼻と対岸の下塩尻岩鼻にしか棲息しないという大変貴重な植物なのです。
ただ、この撮影は大変でした。崖上にあるために、落石防止のフェンスを5mほどよじ登り、左手で体を支えて右手で撮影するというもの。これを30分以上繰り返しました。下をバイパスへ向かう車が通るのですが、何をやっているんだ?と思ったことでしょう。普通のナズナより大きく、株立って咲くので目立ちます。絶滅危惧種なので、もちろん採取は禁止です。最後は左手の感覚が無くなるほどでしたが、いいカットが撮れました。

その崖の近くにある半過公園から撮影した太郎山山脈。左の岩鼻から虚空蔵山、上田市民の山・太郎山と続きます。虚空蔵山は、里山とは思えないほど崖だらけの険しい山ですが、地元の人が登山道を整備して、駐車場や標識も整っています。太郎山の様に気軽に登れる山ではありませんが、非常に面白い山です。太郎山からの縦走もできます。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。子檀嶺岳への行き方や写真も載せています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。その山の名前の由来や歴史をまず書いているので、歴史マニアにもお勧めします。
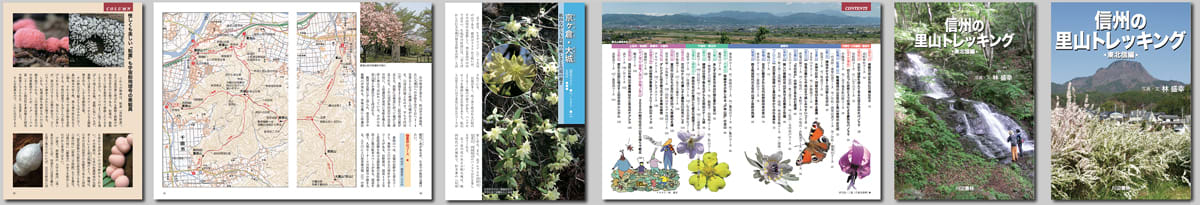
★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。






古代よりこの地は信濃十六牧の一つ塩原牧(しおばらのまき)に属する馬の産地で、「駒斎(こまい)み」が転訛したという説があります。斎は、「ものいみ」で神仏を祀る時に身を清めることです。子檀嶺神社の祭神は、木俣神(きのまたのかみ)とされていますが、『日本三代実録』では駒弓神(こまゆみのかみ)と記されているので、やはり、牧場の守護神が名の由来なのでしょう。他には胡麻忌みという伝説も残っており、青木村では胡麻を作らないというのですが、今でもそうなのでしょうか。

143号線の「道の駅あおき」から見上げた子檀嶺岳なんですが、どこからどうやって登るのって思いますよね。手前側の南面は、100m以上の崖です。しかもこの山頂は、冠者岳城跡(別名を子檀嶺岳城、火車ヶ岳城、烏帽子形城)の本郭なんです。アンビリーバブル。取材登山に同行した編集者がヒエ~っ!と絶句していました。

当郷管社地区の子檀嶺神社(現在は廃社で下の阿鳥神社に合祀)から見上げた子檀嶺岳。中は少し登って子檀嶺岳登山者休憩所からの子檀嶺岳。裏手にはサフォークやウサギの小さな牧場があります。往路は当郷管社コースを。右は登り始め。思いの外緩やかな登山道が続きます。実は、登山道は、あの山の裏側に緩やかに回って登って行くのです。

最後の登りは急坂ですが、つづら折れで登るので、そう大変ではありません。山頂の主尾根に乗った所は、城跡の堀切の様な所。手前に見張り台の様な小ピークがあります。東側がスパッと切れ落ちていて(最初のカットの右側)、四阿山方面が望めます。戻ってヤセ尾根をひと登りすると山頂。
山頂のベンチで越冬したヒオドシチョウが日向ぼっこをしていました。一番右が山頂なんですが、狭いです。実は、これは団体さんが去った後で、この少し前までは大賑わいでした。山頂には、青木村の田沢、村松、当郷の里宮の奥社があります。

山頂から南には、塩田平のもう一つの霊峰である夫神岳が見えます。左奥には蓼科山、右奥には美ヶ原が見えます。まだかなり残雪があります。実はこの日は黄砂が舞っていて、眺望はもうひとつクリアではありませんでした。上の写真は、コントラストと彩度を補正してあります。

帰路は村松西洞コースへ。こちらは厳しいです。もの凄い急斜面を木に掴まりながら下りました。振り返って山頂を見上げたところ。険しい溶岩の崖です。中は仏岩からの展望。遠くに独鈷山が見えます。これも険しい山で、冬に敗退したことがあります。右は、わずかに咲いていたキジムシロ。

下山後は、麓にある国宝の大法寺三重塔を訪れました。子檀嶺岳登山と必ずといっていいほどセットになる古刹です。「信州の鎌倉」といわれる塩田平は、平安時代までに新田開発が進み、鎌倉時代には米と麦の二毛作が行われ、相当に豊かでした。そして、北条氏の庇護を得てたくさんの寺院や塔が建立されました。子檀嶺岳の山麓にある国保大法寺三重塔は、そんな鎌倉時代の栄華を残す名塔であり、地元の宝です。
塔は、大正9年の解体修理の際に発見された墨書により、鎌倉幕府滅亡の年である1333年(正慶二年)に建立されたことが分かっています。塔のある大法寺は、大宝年間(701~704)藤原鎌足の子上恵が開基し大宝寺と称したといわれ、平安初期の大同年間(801~810)に坂上田村麻呂の祈願で僧義真(初代天台座主)により再興されたと伝わっています。
ここにこのような壮麗な塔が建ったのは、北条氏の庇護とともに、この麓を東山道が通り、浦野駅(うらのうまや)(古代に30里毎に置かれた人馬の施設)があったからなのです。大法寺はその駅寺(うまやでら)でした。

初層には裳階(もこし)(ひさしようなもの。あると四重の塔のように見える)がなく二手先という構造で、初層が大きく安定感があります。軒下には地塗りに用いられた白い胡粉(ごふん)の顔料が、軒を支える肘木(ひじき)には 丹塗(にぬり)の赤い顔料が残っています。いずれも創建当時のものです。つまり往時は、朱色の壮麗豪華な三重塔だったわけです。屋根は檜皮葺(ひわだぶき)です。檜の樹皮を何層にも竹釘で止めていく非常に重厚で耐久性のある屋根です。檜皮を採取する技術者を『原皮師(もとかわし)』といい、樹齢50~60年の檜の樹皮を剥いで使います。その樹木を枯らさないように剥ぐのが高度な技術です。剥がれた樹皮は、8~10年で再生します。
この塔は、いつしかその余りの美しさに誰もが思わず振り返ることから「見返りの塔」と呼ばれるようになりました。
鎌倉時代にこの地で隆盛を誇った塩田北条氏は、鎌倉幕府の滅亡に際し、鎌倉に挙兵し、新田義貞の軍勢に攻略され滅亡しました。そして、時代は南北朝から室町時代、戦国時代へと慌ただしく変貌していきました。この塔がその頃どういう状態であったのかは知る術もありませんが、上田原の合戦などもあった戦国の世を兵火に焼け落ちることもなく残ったというのは、奇跡としかいいようがありません。三十年に一度の檜皮葺の屋根の葺き替えが終わり、さらに美しい姿になりました。

そして、帰路に上田の半過岩鼻の崖地にある絶滅危惧種のモイワナズナの撮影に向かいました。古代には千曲川を塞いでいたという岩鼻。大きな穴は、千曲川の流れが削ったもの。この崖地に咲くのがモイワナズナ。サハリンと北海道、そして本州ではこの上田の半過岩鼻と対岸の下塩尻岩鼻にしか棲息しないという大変貴重な植物なのです。
ただ、この撮影は大変でした。崖上にあるために、落石防止のフェンスを5mほどよじ登り、左手で体を支えて右手で撮影するというもの。これを30分以上繰り返しました。下をバイパスへ向かう車が通るのですが、何をやっているんだ?と思ったことでしょう。普通のナズナより大きく、株立って咲くので目立ちます。絶滅危惧種なので、もちろん採取は禁止です。最後は左手の感覚が無くなるほどでしたが、いいカットが撮れました。

その崖の近くにある半過公園から撮影した太郎山山脈。左の岩鼻から虚空蔵山、上田市民の山・太郎山と続きます。虚空蔵山は、里山とは思えないほど崖だらけの険しい山ですが、地元の人が登山道を整備して、駐車場や標識も整っています。太郎山の様に気軽に登れる山ではありませんが、非常に面白い山です。太郎山からの縦走もできます。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。子檀嶺岳への行き方や写真も載せています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。その山の名前の由来や歴史をまず書いているので、歴史マニアにもお勧めします。
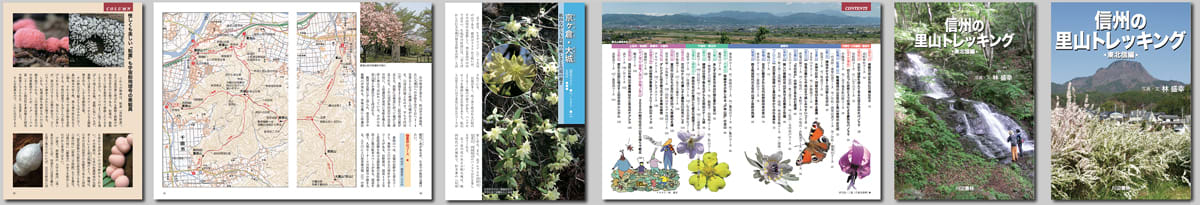
★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
























