徳富蘇峰の宣誓供述書、前回の続きです。
明治維新から、昭和初期を述べています。
明治維新から、昭和初期を述べています。
四 明治維新の動機と根本政策
維新の改革は、其の動機は今此処に悉(ことごと)く挙ぐる訳にはゆかぬが、最も大なる動機、即ち根本原因とも言ふべきは、幕府では到底日本国の独立が出来ない、幕府に任せて置けば、日本は諸外国の為めに侵略せられて、如何なる憂目(うきめ)を見、如何なる恥辱を蒙(こうむ)り、軈ては日本其物が亡滅するに至るも測られない。依って皇室を中心とし、日本を統一し、日本国民の全力を挙げて日本国を防禦し、完全なる独立国として存在せねばならぬと云ふ事であつた。之が即ち、殆ど大なる面倒なくして、改革が短時日の間に成就せられたる所以である。
従て維新以来の根本政策は、其の趣旨を遂行するに外ならなかつた。即ち第一は、先づ日本国を外力より安全なる地位に置く事である。第二は、日本国を完全なる独立国とする事である。第三は、日本国を、国際社会の仲問入りをなし、其の一として、若くは重もなる一として、国際上に列強並の働きをなさしむる事である。而して如上の目的を達する為めには、其の根本政策として定めたのが、即ち明治元年(一八六八)三月十五日発布せられたる「五条の誓文」である。五条の誓文が、我が国策の基調であつて、一切の事は之より割り出して来たものであつた。爾来殆ど八十年間、時としては横道に趨(はし)つた事もあるが、概して言へば、其の線に沿うて今日に至つた。
明治維新を政治的に指導したるは、三条、岩倉、西郷、大久保、木戸であつたが、其の大なる筋書を指導したる、即ち指導原則を与へたのは、必ずしも彼一人と言ふ事は出来ぬが、其の代表的一人は横井小楠である。前にも述べたる如く、五条誓文のインスピレーシヨンは、横井小楠が、其の原案の起草者若くは其の一人由利公正(ゆりきみまさ)に与へたものであつて、それは誰れよりも先づ由利公正が、明かに之を認識してゐる。横井小楠は、世の所謂る空理空想に趨る、所謂るドクトリナー(Doctrinaire)ではなかつた。彼れの反対者さへも、彼れの一派を「実学党」と称した程であつて、彼れは眼は天を眺めたるも、足は地を踏んでゐた。彼れは恒に理想を実際化する事を努めてゐた。彼れが維新の初め、其の故郷肥後より、朝廷の召命を承けて京都に喚び出されたる際に、彼れより先に朝廷の参与職に任じてゐた越前の由利公正―当時は三岡八郎―は、彼れを大阪に迎へたが、横井は由利に向つて、日本は洵(まこと)に幸運である。第一は、日本が万世一系の皇室を戴いてゐる事である。第二は、日本が世界列国に後れて、開かれたる事であると言うたと、由利は語つてゐる(『小楠遺稿』参照)。万世一系の事は、今此処にに語らず。横井が斯く言うた事は、西洋人が千辛万苦(せんしんばんく)して得たる一切の智識は、日本人が其儘之を学修する事が出来るのみならず、西洋の短を捨てて、其の長を取る事が出来る。それで労は少なくして、功は之に倍すると云ふ事を、意味したものであらう。而して横井は、其の書きたる物に依て、且つ其の語りたる物に依て見れば、少年であつた明治天皇に大なる望みを属(しょく)し、天皇に依て維新の大政が光を放つ事が出来ると、斯く信じてゐた。而して彼れは、軈て頑冥(がんめい)党の為めに暗殺せられたが、彼れの志は、彼れの門人でもあり、且つ友人でもある元田永孚(もとだながざね)に依て完成せられた。横井は、出来得べくんば自ら日本の使節となつて米国に押渡り、米国大統領の同意を得て、世界平和の会議を催しい世界平和の端緒を、日本に依て啓(ひら)く事を世界に対する第一の貢献である、と信じてゐた。但だ之は、其人亡んで、其の理想は実行出来ずして已んだ。横井は、支那に於ける理想的君主たる尭舜の次には、ワシントンを崇拝し、一国の元首たる者は、ワシントンを以て模範とせねばならぬと唱へてゐた事は、元田の横井に就て語つたる所に依ても、明白である(『小楠遺稿』参照)。彼は儒教の信者であつて「仁者敵無し」と云ふ言葉を、実行出来るものと考へてゐた。彼れの目的は政治の倫理化であつて、其の倫理化は、一家、一町村、一国より、延(ひ)いて世界に及ぽすべきものと、信じてゐた。従て維新の政府は、戦争に依て出で来つたが、維新の政府が将来の戦争を為さんが為めに出で来つた政府でなくして、現在の平和を一国的に維持し、軈は世界の平和を、国際的に維持する事を主眼とした事は、今更ら言ふ迄もない。
予は決して如上(じょじょう)の観察を、机上の空論に依て語る者ではない。維新政府を組織したる重もなる人物に就て、其の一人一人を吟味するも、未だ曾て侵略主義者が維新の根本政策を作為したとか、指導したと云ふ事は、事実の上に其の痕跡だも見出す事が出来ぬ。殊に日本の重もなる維新政府の政治家である岩倉、木戸、大久保等は、明治四年(一八七一)の末より、明治六年(一八七三)の半ば迄、アメリカより欧羅巴を巡回し、親しく欧米諸国の現状を見て、到底日本の現状では、欧米諸国と競争なぞは、出来るものではない。先づ第一に、日本の位地を向上せしむる事を本務とせねばならぬ。それには、凡有(あらゆる)る外国の長所を取り入れる事を急務とせねばならぬと云ふ事に、其の決心を固めて来た。従て維新政府が、軍国主義であるとか、軍国主義の卵であると云ふ事は、夢更ら無き事である。明治天皇は、維新の当初は未だ幼少であらせられて、自ら政治を判断するの資格は学修中であつたが、明治十年(一八七七)より以後は、漸次に天皇親政の、名ばかりでなく、実が行はれて来た。而して天皇の最も信頼せられたる政治上の相談相手は、前には岩倉、後には伊藤の二人であつた。此の二人とも、何れも平和的政治家であつて、何人も此の両人を以て、軍国主義者と見倣す者はあるまい。且つ又た、個人として、明治天皇に畏れながら最も深甚なる感化を与へ奉りたるは、日本人としては元田永孚である。元田永孚(もとだながざね)は、如何なる事を天皇に告げたかは、予が曾て出版したる『元田先生進講録』が、詳しく之を語つてゐる。彼れは横井小楠を縮小版としたやうな漢(おとこ)であつて、横井小楠の「荒削りなる疵(きず)を除(はら)つて、精金美玉」としたやうな人物であつた。其の意見も亦た其の通りであつた。外人で最も感化を及ぽしたのは、米国の前大統領グラント将軍であつて、明治天皇は明治十二年(一八七九)の秋、日本に来遊したるグラント将軍に向つて、随分立ち入つたる点まで問答された。当時明治天皇は、既に二十八歳の青年として、最も印象深くグラントの進言を、聞こし召された。グラントは、日本が余りに熱心に欧米文化を取り入れるに就て、拍車を加へたのでなくして、寧ろブレーキを加へた。
而して陛下に向つて、日本が完全なる独立国となり、外人の不当なる干渉より免れん事を祈つて已まなかつた。明治天皇が如何に平和的、世界協調的の典型的君主であらせられたかと云ふ事は、天皇御自身の歌集が、よく之を語つてゐる。此の如く明治政府の中心である明治天皇、天皇を輔翼する重もなる政治家、皆な悉く軍国主義者でなきのみならず、其の痕跡もなき程である。此の如き天皇、此の如き政府に向つて、世界侵略の陰謀などの、存在すべき理由なきは、予が殊更らに弁明を侯(ま)たざる所である。
要するに明治の中期迄は、日本は如何にすれば、完全なる独立国となる事が出来るかと云ふ点に就て、政府も人民も、其の憂身(うきみ)を窶(やつ)したした。凡そ日本人の心を悩ましたる、最も大なるものは、日本に治外法権の存在したる事、〔関税自主権の〕日本人の手に存在せざる事の二つであつた。此の税権・法権の回復は、如何なる犠牲を払うても、遂行せん事を期したが、それに就ては、日本の意見は、自ら二派に岐れた。一は速かに日本の文化の程度を引上げ、外国人が安心するやう、満足するやう、日本を欧米化し、之を実行すべしと云ふ意見と、一は日本は日本流で立て通し、欧米人も此儘では、永く日本人を継子(ままこ)扱ひをせねばならず、其の為めに欧米人に取つても寧ろ不便利なる事が多く、困却する事が多いから、欧米人より「我」を折らせて、向ふから条約改正を、日本に申し込む方が、寧ろ近か道であると云ふ論とである。即ち前者の欧米化主義に対抗して、条約励行論などが出て来た。即ち条約の文字通り、一点一画も変更せしめず、例へば外人の自由通行を十里以内と決めたる以上は、十里から一尺でも足を踏み出す事は出来ぬやうにして、外人に窮屈を感ぜしめ、閉口の余り対等条約を、彼れより申込ましめんとする意見であつた。是等の騒ぎで国内は沸騰したが、それらの事も、明治二十七年(一八九四~九五)以後に至つて、自然に落着する処に落着した。
即ち維新以来の、我が官民の努力が漸く欧米諸国に認識せられ、対等としては取扱はぬ迄も、三年たてば三つになると云ふだけの、日本の進歩生長を認めて、漸くグラント将軍が言うたる、完全なる独立国と殆どなつた事は、明治政府創立以来、三十年の後であつた。
五 近代日本に於ける内外の刺激
日本に向つて、支那の怖るるに足らざる誨(おし)へた者は、欧米諸国であつた。日本は其の教へを忠実に遵奉(じゅんぽう)したばかりでなく、それに輪をかけて、支那の恐るるに足らざる事を知つたが、同時に支那に対する尊敬と恐怖に、又た輪をかけて、欧米諸国に傾むけた。然し目本にも、中村敬宇の如きは、明治の初期に、支那侮るべからざる論を世の中に公けにし、日本人
の支那に対する態度を、改めん事を警告した。又た勝海舟の如きも、明治二十七八年戦役前後、日本人が支那与みし易しと有頂天になつた際に、支那人の方が、日本人より智慧分別が多いと、日本人の浮足を警(いま)しめた。此処に日清戦役に就て一言するが、日清戦役は、西暦第七世紀の頃、即ち今より千二百有余年前、天智天皇の朝に、支那と朝鮮に於て戦うたる、其の戦争の延長とも言ひ、若くは其の繰返しとも言ふ事が出来る。但だ前に於ては、朝鮮に於ける日本の勢力は、支那の為めに全く駆逐されたが、二十七八年の役には、朝鮮に於ける支那の勢力を殆ど駆逐し去つた。朝鮮が日本の防禦の第、線であつた事は、日本上古史以来の事であって、今に始まった事ではない日本が朝鮮から全く撤退した後は、日本は従来に倍して、九州の防禦を厳にした。然し軈(やが)ては、朝鮮を策源地として、蒙古の来襲を蒙むつた。幸に所謂「神風」の力で、蒙古軍は逐(お)ひ払ったが、それでも日本人は恐怖心が止まず、其の策源地を一掃せんが為めに朝鮮に対する出兵を企てたが、それは内治上の事情で中止となつた。明治六年(一八七三)に、西郷隆盛等の、所謂「征韓論」なるものも、其の真意は、日本と朝鮮とが攻守同盟を結び、露国に対抗せんとするのが、其の目的であつた。然し反対党は、其の為に却て露国との事件を惹起せん事を虞(おそ)れて、それに反対した。それで反対者も主張者も、総ての見地は、外国の勢力に対する防禦の方法及び方針に就て意見が分裂した迄であつて、朝鮮が日本防禦の第一線と云ふ事は、日本開關以来の常識であつて、誰れもそれを疑ふ者はなかつた。
話は元に還つて、支那は元来日本を物の数とも考へてゐなかつた。其の日本が、或は琉球に手を出し、台湾に手を出し、朝鮮に手を出すなどと云ふ事を見て、怪しからぬ事をすると考へ、単に日本を侮り賎(いやし)むばかりでなく、憎み、怒り、且つ怖るゝやうになつた。斯くて支那の慣用手段、遠交近攻を利用して、外国の勢力を引つ張つて来て、日本を牽掣(けんせい)し且つ復讐をした。之は支那人としては、決して賢明の仕業ではなかつた。少なくとも当時の所謂る支那分割の端なるものは、茲に開らけた。日本でも、支那戦争中より、支那と握手せん事を期待したる者は少なくなかつた。伊藤などの如き平和政治家は云ふ迄もなく、日清戦役に日本のモルトケの役目を勤めたる川上将軍の如きも、最も熱心に其事を考へてゐた。而して支那にも、日支提携する方が支那の長策であると考へた者も、皆無ではなかつた。然し其の多数に就て見れば、日本人は支那与みし易しと云ふ一念が行き渡り、支那に対しては、大なる研究もせず、又た大なる準備もせず、宛(あた)かも門前に在る石を、何時でも勝手に之を動かし得るものであるかの如く考へてゐた。支那の方では日本に対する憤慨心或は復讐心は、皆な其の胸中に燃えて、何かの機会に報復する所あらんと考へてゐた。然し当分の間は、日本には敵はぬから暫くは虫を殺して隠忍して、其の時節の到来を待つてゐた。此の如くにして、維新以来日本と支那は、隣国でありながら、又た文字を同じくしてゐながら、遂に相識(し)り相親しむと云ふ迄には至らなかつた。勿論個人間には相当の交際もあつたが、国としては徹頭徹尾表向だけの交際であつた。即ち打ち釈(と)けて協力するなどと云ふ事は、遂になかつた。今ま此処に日支事変の曲直などに就て、議論をする場合でないから姑(しばら)く措くが、日本人は支那与みし易しと云ふ一念の為めに、自国を失はんばかりに大なる代価を払うた。今少し日本人が支那を知り、支那を研究し、支那に向つて善処する途を得たならば、今日の如き事には立ち至らなかつたと思ふが、日本人は同時に二個以上の事を考へる余地を持たぬから、茲に至つたものであらう。兎に角日本人は、支那人を砂の如き民族と、考へてゐたが、支那人は日本人に対する反抗心、敵愾心、復讐心を利用し、我等の点から見れば寧ろ悪用し、濫用したと云ふべき程に、対日本の抵抗心を刺激煽動し、此の如くにしく日本は砂である支那人に向つて、セメントたる役目を勤め、今日では砂の塊りではなくして、眼前に突兀(とつこつ)た一ノのコンクリートの城を見るに至つたのである。此の如くにして、当初日本に向つて、国民的精神を寄与したる支那は、又た久しき距離を隔てて、日本より支那に向つて、利息まで附けて償還する事となり、此の如くにして、今日国民党や又た共産党までも出で来つたものであらうと判断する事が出来る。然して日本を、支那の馬に乗り替へたる米国なども、果してそれが得策であつたや否やは、今ま茲に明言する限りでない。何れ遠からず歴史が之を語るであらう。
日本には、所謂る軍閥なるものは無かつた。是れだけは、予は良心的に之を確言する事が出来る。予は老人であり、且つ壮年以来の新聞記者であるから、凡有る日本の人物に接触してゐる。殊に日清事件には自ら従軍し、日露事件には極めて密接なる立場より之を眺め、其他軍事に関する凡有る問題に対しても、予は常に意見を発表する事を揮からなかつた。具体的に言へば、日本の陸軍の巨頭は山県元帥であつて、此人が日本陸軍を背負つて立つてゐた。然るに此人は、軍人出身ではあつたが、内務大臣とし、又た二回ほど総理大臣とし、後には元老として一般政治に最も大なる感化を及ぼした。日本の軍制を改革して徴兵令を布きたるは、山県其人の力であつて、彼は之に依て、五十万、其の家族を合せて二百五十万の、武士たる特権階級を廃し、護国の義務を国民全般に頒つ事とした。彼は露国とも、出来得る限り衝突を避くべく、露帝のモスコウに於ける戴冠式には、自ら日本の代表として出掛けた。彼は日英同盟の最も熱心なる主張者であり、若くは賛成者であつた。彼れの大なる功績として見るべきは、日本に自治制度を布いたる事である。予は彼とは、政治上の意見が全く同一ではなかつたが、彼は恐らくは、近代百年に亙る日本に於ける大なる政治家の一人である。彼は軍国主義者ではなかつた。唯だ平和の為めに、我国防禦の為めに、軍備を充実する事を希望してゐた。彼は一般陸軍に対しては、刺激力ではなくして、恒に鎮圧力となつてゐた。(予が編著『山縣公傳』―正伝也―参照)之は同時に、海軍の中心勢力であつた西郷(弟)、山本、東郷等に就ても、言ふ事が出来る。殊に西郷と山本は世界協調論者であつて、我より進んで事を起こすなどと云ふ事は、絶対に反対した。其他予の知り得る範囲に於ては、陸海軍の重もなる人士は、其通りと言ふ事が出来る。例へば大山元帥の如きも、満洲軍の総司令官として日本を出立するに際し、戦争の責には我等奮(ふるい)て之に当る。然かも平和の政策は、公等決して其の時機を誤まる莫(なか)れと、慇懃(いんぎん)に言ひ残したと云ふ事である。故に大正の中期迄は、殆ど一切の事が秩序整然として、明治天皇の平和の意思を遵奉して行つたが、其の以後に於て我が政界に変調を来したのは、何故である乎。それは内と外との両者から、之を観察する必要がある。
先づ内から言へば、大正天皇の末期よりは、政党内閣が行はれ、或は官僚内閣が行はれ、或は政党と官僚との混合内閣が行はれ、種々の内閣が行はれた。然かも政党は横暴を極めて、国民少くとも良民の信用を殆ど失墜(しっつい)した。官僚内閣も亦た異つたる意味に於で、国民の信用を失うた。政治の争ひは、唯だ其の位地を得ん事の争ひであり、位地を得て後には唯だ其の利益を得ん事の争ひであつた。固(もと)より其間に、一貫の目的があつたでもなければ、一定の方針があつたでもない。唯だ全く手から口、其日暮しの政治であつて、跡は野となれ山となれ、唯だ現在の安きを貧り、所欲を達すれば足ると云ふやうな状態であつた。そこで政党に失望し、官僚に失望したる国民は、唯だ軍人の間に、若くは軍隊の間に、初めて国家に忠良なる人物を見出す事が出来ると考へた。而して軍人中の若者、即ち学校を出でて未だ年月を経ざる中少尉、遡(さかのぼ)つて漸(ようや)く中少佐位の所には、自ら日本改革の役目を、買つて出でたる者が出来た。之が爆発して、或は五・一五事件とか、二・二六事件とか云ふものが出で来つた。
若し世の中に、軍閥と云ふ言葉を用ふる事が出来れば、或は軍人中の寧ろ一小部分である此の一派一味を指して言ふ事が出来るかも知れぬが、然し軍其ものとしては、未だ曾て軍閥などと云ふものは、在り得なかつた。唯だ不幸なるは日本であつて、総ての腐敗から、総ての無能力から、取り残されたる最後の恃(たの)みであつた所の軍人階級も、いざとなれば政党官僚に劣らぬ醜態を暴露し来りたるは、洵(まこと)に以て遺憾の極みであるが、然し世間で称ふる、所謂る軍閥などと云ふものの存在してゐなかつた事は、予の語りたる所に依て、之を知る事が出来よう。
外からの刺激は、即ち第一回世界大戦以後であつて、従来日英同盟に依て、少なくとも東亜の安定は保たれてゐたが、世界大戦後間もなく、之は有れども無きが如き姿となつた。ヴエルサイユ会議に於ける日本は、同盟国の英国及び其の植民地から手厳しき取扱を受け、又た其の準与国とも云ふべき米国からは、尚更ら厳しくやりつけられた。軈(やが)てはワシントン会議となつて、此の会議で日英同盟は全く廃棄せられ、米英連合の力に依て、漸く一人前とならんとする日本は押さへ付けられた。兎角人は、相手側ばかり見て己れを考へる事はないが、若し世界大戦以後、或は更に遡つて日露戦争以後、米英諸国が如何なる態度を以て日本に臨みたるかを反省せば、思半ばに過ぎるものがあらうと思ふ。日本は漸く一人前となって、之からこそ列強と手を携へて、世界の舞台に乗り出す事が出来ようと考へた所、豈図らんや、荊棘(けいきょく)の重囲に陥つたやうな状態を自ら見出した。日本の諺に、「出る杭は叩かれる」と言ふが、日本は愈々(いよいよ)叩かれる時期に到達したのだ。明治維新の際には日本の人口は三千余万であつた。然るに大正の末期には、七千万を数ふるに至つた。人口は年々百万以上増加しつある。食糧不足は覿面(てきめん)に起つて来た。然かも日本は世界の何れの処に於ても、高札をたて、日本人入る可らずと云ふ事になり、折角入り込んだる土地からも、追放せられ、若くはせられんとする困難に立到つた。而して日本開国以来の親友であつた米国の如きも、日本を仮想敵として其の大海軍を建設した。露国は素(もと)より伝統的に日本の脅威として、日本に臨んでゐる。然かも隣国の支那は、相変らず遠交近攻の政策を掲げ、日本の出鼻を挫きつゝある。然るに日本の内閣なるものは、此の如き国家の危急を他所事(よそごと)に眺めて、唯だ得ざる者は得ん事を欲し、得たる者は失はざらん事を欲し、政権や利権の争奪のみを維(こ)れ事として、国家の安危存亡などは、殆ど顧みるに遑(いとま)なかつた。斯かる場合に於て、軍隊の若者等が憤慨したのも、相当理由ありと云はねばならぬ。又た国民の或者が、之に同情を表したのも決して偶然ではあるまい。之が即ち大正の末期から昭和の中期に亙る実際の日本の情勢であつたと、長き予の経験は、斯く観察せしむるものである。
















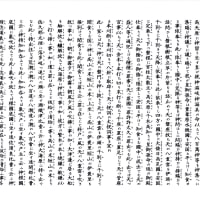

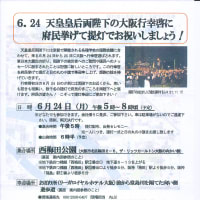

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます