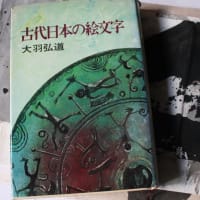深い山の奥から、コーン、コーンと木を伐る音がきこえてくる。
――ああ、ハルオさんが木を伐っているな・・・
と村人の誰もが思う。その音に木霊(こだま)するように、神楽歌が聞こえる。
――ハルオさんが歌っている・・・
と、また嘆息する。
そうだ、ハルオさん(綟川陽男さん当年60歳)は昨年の夏、山の事故で亡くなったのだ。そのことは村の誰もが知っているけれど、時々、こうして激しい風の吹く日などには、吹きすぎる風の音に混じって、「山守〈やまもり〉」が木を伐る音が聞こえる気がするのだ。
――ハルオさんは山守になったのだ・・・
誰もがまた、頷く。
そこで私は目が覚めた。長い夢を見ていたのだった。
諸塚村に伝わる「戸下神楽」(毎年、1月の最終土曜から日曜にかけて開催)と「南川神楽」(2月の第2土曜~日曜へかけて開催)が終わると、「冬神楽」のシーズンが終わり、暦の新しい一枚をめくるように春がくる。この二座は、どちらも24時間をかけて舞い継がれる古式の神楽だが、去年と今年は、新型コロナ感染症蔓延の影響で、中止(または村人・関係者のみでの奉納)となった。それで、私は巡って来たこの季節に、夢の中でこの神楽と愛すべき山の人々のことを追想していたのであった。
宮崎県諸塚村は、九州脊梁山地のほぼ中央部に位置する山岳の村である。北は高千穂、西は椎葉、南は米良の山脈に連なり、東は日向の山系を経てはるかに太平洋を望む。村の中心部を、椎葉の山脈を源流とする耳川が貫流する。
耳川に沿って日向・東郷・美郷とたどる国道218号線を遡ると、中流域で右折する山道がある。広大な諸塚の山塊へと分け入る道のひとつである。山の道は、およそ標高100メートルの地点から1000メートル級の山岳地帯へと、急な斜面を一気に登りつめる。道が、黒々とした照葉樹林帯を通り抜け、落葉広葉樹の森を過ぎて明るく展望が開けた所に、ぽっかりと、神様の忘れ物のような村がある。そこが、神秘の山地神楽を伝える戸下集落である。頑丈な骨組みと、瓦屋根の家が肩を寄せ合う戸数9戸の集落で、24時間をかけて神楽が舞い継がれるのだ。
村の入り口に幟幡が立ち、人々が集まってくる。風を受けて、神社の名前を染め抜いた旗がはためく。村の記憶と人々の哀歓を映す場所。神々のいますところ。それが神楽を伝える里である。
戸下神楽の「大神楽」は、10年に一度開催される大曲である。1日目の正午から翌日の正午まで、24時間をかけて50番が奉納される。
その大神楽一番の曲として「山守」という山の神神事が組み込まれている。
村の鎮守神社・白鳥神社での神事を終え、御神屋へと神々の行列が舞い入った後、「山守」役の神人と「警護」役の怜人とが、神楽宿の西方の山に入り、途中の山道でお神酒を酌み交わす。ここから先は、山守と警護だけが山に入る。他の誰人も同行を許されない。
山に入った山守は、かねて目星をつけておいた山中の「神の榊」を切り、蔓草を全身に巻きつける。その榊を伐るときの音が、山から里へと響いてくるのである。伐りとった榊を杖につき、つる草を纏い、笠を被った山守は、その時、「山の神」となる。
やがて山守=山の神は、二人の警護に先導され、一気に山を駆け下りてくる。他の警護が後に続く。集落の入り口に達した山守は、すでに神に変異しており、疾風のように村人や参拝者の間を駆け抜けて、御神屋の前に達する。この山守は「山人〈やまど〉」とも呼ばれる。
御神屋では「神主」が待ち受けていて、山人と問答をする。長い問答の中で、今宵一夜の神楽の場を訪れた山人は、まず仏法の理と四季の色彩を説きながら、仏道と神道の理を解き明かす。続く「山の本地」では、東南西北・中央の五方の山を語り、山の麓にまします山守が種々の宝や福を授けるという。問答はさらに続き、
――この山は誰山人の山ぞ・・・
という「山問い」の文言と「山鎮め」の詞章が入り、五色五行の法則が解き明かされた後、山人は手すり竹を乗り越えて、御神屋に上がる。
御神屋の中では神主と山人が対面し、山人がこの村の諸願成就のために隠れ笠と隠れ蓑を譲る。引き出物が渡されると、村人の代表がとっくりと盃を持って出て、仲直りの歌が歌われる。そうして、御神屋を舞い巡りながら、
――此の山は 精ある山か精なくば 山守すえて我が山にせん
――嬉しさに 我は此処にて舞い遊ぶ 妻戸も開けず 御簾も下ろさず
と神歌が歌われ、舞い終える。
山守神事とは、諸塚山の山神が、神楽の場に現れ、宝物を授けて村人と一夜を共に過ごし、山神の守護と山の幸を約束する儀礼であり、神楽の古形である。
ここで、この連載の中で「山守」「山森」「モリ」などという儀礼が遠く東北地方にまで分布し、「山守」の地名のある場所には縄文時代の遺跡があり、仮面をかぶった土偶や土面が発掘されているという事例を思い起こせば、九州脊梁山地の神楽に伝わる「山守」が列島の古層を伝える神事儀礼であることが把握できるであろう。古記録に現われる「山守」「山人」については後述。
この「山守」の神事を勤めるのが、この村の旧家、綟川(もじかわ)家の長男であり、直近の大神楽(2016年)で山守役を務めたのが、ハルオさんであった。
ハルオさんは、気さくな人柄で、神楽の出番も数多くこなし、神楽に対する理解も深く、その所作は神楽人(かぐらびと)そのものといった美しさで観客を魅了した。そして自分の出番以外の時間帯には、客席へ出て応対したり、焚き火の傍で談笑したり、また台所に行って裏方を務める女性たちと打ち合わせをしたりと、縦横の活躍をし、伝承者の減少に悩む神楽座を牽引して来た一面も持つ。
そのハルオさんがつとめた大神楽の「山守」である。
山から駆け下って来たハルオさんは、すでに山の神に変異していた。人が神に変身する瞬間というものを、麓で待ち構えていた私どもは、まざまざと目撃したのである。
この写真は、ハルオさんが山から下り、走り過ぎてゆく一瞬を捉えた一枚である。私はここぞという場所を選び、待ち構えていて、山の狩人が一矢で獲物を仕留める時の呼吸でシャッターを切り、得た作品である。これまで一度も発表したことはないが、いま、ここに哀悼の意を込めて、公開することとした。*現在データが行方不明につき探索中。
九州脊梁山地の山々には、猪と戦って死んだ猟犬や苦楽を共にした馬などの家畜が死んだとき、裏山の大木の根方や巨岩の脇などに葬り「カクラ様」として祀る習俗がある。この時点で動物たちも山の神さまとなり、家や村を守護するのである。
ハルオさんも、今は山の神さまの一柱となり、朴訥ではあるが古風を伝えるこの村と、戸下神楽の行く末を見守っていることであろう。


![森の神話/「前衛」の位置・瑛九の仕事[第三期:空想の森アートコレクティブ展/静かな森へ<VOL:19>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/3d/59/c63f4f184eb28c3ea79ebbd0299cc1dc.jpg)
![森の神話/「前衛」の位置・瑛九の仕事[第三期:空想の森アートコレクティブ展/静かな森へ<VOL:19>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/1f/84/4feee5b6f83e1f62a666de3ce1cd16c7.jpg)
![森の神話/「前衛」の位置・瑛九の仕事[第三期:空想の森アートコレクティブ展/静かな森へ<VOL:19>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/15/19/f6fdf608e738af14ec38ef834bfd8388.jpg)
![森の神話/「前衛」の位置・瑛九の仕事[第三期:空想の森アートコレクティブ展/静かな森へ<VOL:19>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/0f/f0/42bab9e7cf1ce6336aaa7270ce925ae6.jpg)
![森の神話/「前衛」の位置・瑛九の仕事[第三期:空想の森アートコレクティブ展/静かな森へ<VOL:19>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/f0/42bab9e7cf1ce6336aaa7270ce925ae6.jpg)
![「版画」の底流と現代版画の地力[第三期:空想の森アートコレクティブ展/静かな森の夕べ<VOL:18>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/78/6e/7c6fa56a8c3ab363ae84fc1a261a0714.jpg)
![森のホタルと「日本美」という美の領域[第三期:空想の森アートコレクティブ展/静かな森の夕べ<VOL:18>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4a/51/a9ae18b3ffb2cd910e990e3507c93483.jpg)