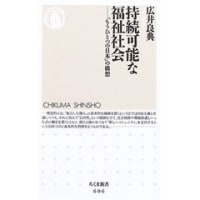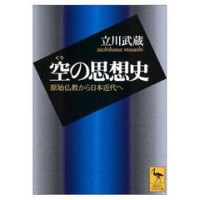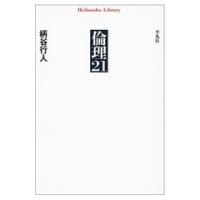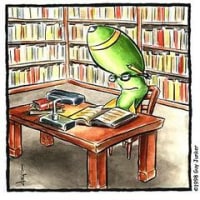大学にもよるのだろうが、大体、来年度の授業の時間割が決まり、教科書選びなどが行われるのが今の季節だ。研究室にも英語教科書会社のセールスマンが盛んに訪ねてくる。
いろいろ見本を持ってきてくれるのだが、大学生の知的レベルと実際、仕事で使うのに求められる英語のレベルに見合うような教科書は驚くほど少ない。20年くらい前だったら中学校の教科書だったのではないかと思うレベルのものも大学生用の教科書として流布しているようだ。私自身の経験を振り返っても、高校のリーダーの時間には大学教養レベルの副読本を使っていたし、通信教育のZ会などで難しい英文を読まされていたので、いざ大学に入ってみて、英語教科書が簡単なのに驚かされたが、今、英語を教える側に回ってみると、そうした教科書しかないのがよくわかった。書店で売っているような市販の英語教材には、良いものも少なくないが、それらは自習用で解答がついているので、授業テキストとして使えないのが辛いところだ。
最近は、TOEICの需要が高いので、TOEIC対策の教科書が多いのだが、これもまた問題形式だけTOEICを真似てはいるが、難易度は中学~高校1年レベルの基礎的なものが多い。「なんちゃってTOEIC」教科書としかいえないような代物である。こうした教科書で勉強していても本番の試験では歯が立たないに違いない。
セールスに来る人には気の毒だが、いつも「一番難しいのはどれか」とか、「もっと難しい教科書は?」とばかりたずねているのだが、「それじゃあ売れないんですよ」とか、「○○大学でも使っているんですよ」などと言い訳をされるばかりだ。つい先日も、かつては比較的難しい教科書を作っていた会社の人が来たので、リーディングの「上級(アドバンスト)」の見本を置いていってもらったのだが、後で見てみると、「2000語」レベルということだった。2000語では、Penguin Readersでも中級レベルである。しかも少しでも難しそうな単語には全て注で日本語訳がついている。難関大学の入試でも3000~5000語は必要とされているはずなので、これでは受験英語より簡単なものを大学に入ってから読ませることになる。現在の日本の大学英語の教科書の多くは、英米の小学校2、3年生の国語教科書程度だという厳しい現実を重く受け止めなくてはならない。
何といっても語彙力が語学力を大きく左右することは否定できない。TimeやNewsweekを辞書なしで読み、CNNニュースを聞いて理解できるレベルというのは、大体、海外で仕事をするのに必要なレベルなのだろうが、8000~10000語の理解語彙が必要だと言われている。2000語レベルの教科書を「上級」として大学生に売っている場合ではないのである。
中高6年間英語を勉強したが、新聞一つ読めないのは、日本の英語教育が悪いとよく言われるが、現在の公立中高の英語の授業時間はトータルで900時間であるという。学生が一日に起きて、活動している時間が仮に15時間だとすると、900時間は、60日、つまり英語圏で生活する2ヶ月程度に過ぎず、中高でトータルで読む英語の量も『ニューヨーク・タイムズ』一日分にもならない。絶対量が少なすぎるので、これでは6年間やっても新聞も読めない、話せなくてもむしろ当たり前なのだろう。
問題はその後である。戦後の教育が、教育水準・知識水準のナショナル・ミニマムを引き上げることを第一目標にしてきたとしても、全国民が高校までに英語で新聞を読めるようにするのはあまりにも重い、非現実的な目標である。イギリスやアメリカの植民地でもないので、英語で新聞を読む必要もないと思う人も多いだろう。やりたい人がやればいい、そこそこのレベルで終えておこう。近年の高校までの指導要領はその方向なのかもしれない。
しかし国語教育と英語教育には本質的な違いがあるはずだ。国語教育の水準が下がり、国民の書ける漢字や読める漢字が減ったとしても、日本人「みんな」が読めない、書けなくなっているのだから、構わないといえば構わないのかもしれない。文部科学省が「小学3年生までに習う漢字」といった具合に指導要領で集権的に指示しても、国語審議会が常用漢字を減らしても、さして問題ないのだろう。
だが日本の役所が、例えば日本人の高校1年生が学ぶ英単語はこの位の数で、と決めることは、日本の大学入試問題作りの指標となることはさておき、グローバルに見て、どれほどの意味があるのだろうか?新学習指導要領では、いわゆる「制限語彙」の規定が厳しく、中学校で900語、高1の「英語1」で中学プラス400語の1300語、さらに高2の「英語2」でプラス500語の1800語と定めている。現在の高校の英語教科書は1800語という極めて限定された語彙で書かれた英文なのである。1970年と比較すると、高校で習う英単語数は、ほぼ半減している。このように日本の英語教科書は中学から大学までレベルダウンし続けても、実際に英語圏で使われている英語が簡単になるわけではない。むしろ日本の学校で習う英語と、英語圏で使われている英語のギャップが広がり、自分で勉強しなければならない余地が増えるばかりである。2000語レベルで終わってしまっては、あと6000語、自分で勉強しないとまともに新聞も読めない。そんな「なんちゃって英語教科書」ばかり量産して、「英語ごっこ」に興じている場合ではなかろう。
実際に、留学生向けの試験であるTOEFLの難易度は上がる一方であり、日本人受験生の平均点が下落し続けるのも当然である。
現在、アメリカの大学で研究している友人の日本人医師と話していた時に、彼が「英語はしょせん猿真似だからな」とつぶやいたのには、目を開かれる思いだった。帰国子女だった彼の実感が言わせたせりふなのだろうが、実際、英語を道具として学ぶとしたら、結局、ネイティブの真似をするしかなく、それ以上でも以下でもなく、日本で新しい語彙を生み出せるわけでもないのだ。だとすれば苦しくても、英語で新聞を読んだり、そのレベルの英語を書くように努力しないと、結局、英語をマスターすることにはならないはずだ。
「悪貨は良貨を駆逐する」というように、実際、2,3年前に使った教科書でも少しでも本格的な英語教科書は次々、市場から消えていき、イラストと写真ばかりが充実し、中学レベルの英語を並べた同工異曲の教科書ばかりが跋扈している。難しい教科書は採用率が低いか、クレームが多いのかもしれないが、大学英語教科書会社にも、日本人の英語力向上に貢献したいという良心が少しでもあるならば、新聞英語レベルの教科書をもう少し発行し続けてほしいと切に思う。
いろいろ見本を持ってきてくれるのだが、大学生の知的レベルと実際、仕事で使うのに求められる英語のレベルに見合うような教科書は驚くほど少ない。20年くらい前だったら中学校の教科書だったのではないかと思うレベルのものも大学生用の教科書として流布しているようだ。私自身の経験を振り返っても、高校のリーダーの時間には大学教養レベルの副読本を使っていたし、通信教育のZ会などで難しい英文を読まされていたので、いざ大学に入ってみて、英語教科書が簡単なのに驚かされたが、今、英語を教える側に回ってみると、そうした教科書しかないのがよくわかった。書店で売っているような市販の英語教材には、良いものも少なくないが、それらは自習用で解答がついているので、授業テキストとして使えないのが辛いところだ。
最近は、TOEICの需要が高いので、TOEIC対策の教科書が多いのだが、これもまた問題形式だけTOEICを真似てはいるが、難易度は中学~高校1年レベルの基礎的なものが多い。「なんちゃってTOEIC」教科書としかいえないような代物である。こうした教科書で勉強していても本番の試験では歯が立たないに違いない。
セールスに来る人には気の毒だが、いつも「一番難しいのはどれか」とか、「もっと難しい教科書は?」とばかりたずねているのだが、「それじゃあ売れないんですよ」とか、「○○大学でも使っているんですよ」などと言い訳をされるばかりだ。つい先日も、かつては比較的難しい教科書を作っていた会社の人が来たので、リーディングの「上級(アドバンスト)」の見本を置いていってもらったのだが、後で見てみると、「2000語」レベルということだった。2000語では、Penguin Readersでも中級レベルである。しかも少しでも難しそうな単語には全て注で日本語訳がついている。難関大学の入試でも3000~5000語は必要とされているはずなので、これでは受験英語より簡単なものを大学に入ってから読ませることになる。現在の日本の大学英語の教科書の多くは、英米の小学校2、3年生の国語教科書程度だという厳しい現実を重く受け止めなくてはならない。
何といっても語彙力が語学力を大きく左右することは否定できない。TimeやNewsweekを辞書なしで読み、CNNニュースを聞いて理解できるレベルというのは、大体、海外で仕事をするのに必要なレベルなのだろうが、8000~10000語の理解語彙が必要だと言われている。2000語レベルの教科書を「上級」として大学生に売っている場合ではないのである。
中高6年間英語を勉強したが、新聞一つ読めないのは、日本の英語教育が悪いとよく言われるが、現在の公立中高の英語の授業時間はトータルで900時間であるという。学生が一日に起きて、活動している時間が仮に15時間だとすると、900時間は、60日、つまり英語圏で生活する2ヶ月程度に過ぎず、中高でトータルで読む英語の量も『ニューヨーク・タイムズ』一日分にもならない。絶対量が少なすぎるので、これでは6年間やっても新聞も読めない、話せなくてもむしろ当たり前なのだろう。
問題はその後である。戦後の教育が、教育水準・知識水準のナショナル・ミニマムを引き上げることを第一目標にしてきたとしても、全国民が高校までに英語で新聞を読めるようにするのはあまりにも重い、非現実的な目標である。イギリスやアメリカの植民地でもないので、英語で新聞を読む必要もないと思う人も多いだろう。やりたい人がやればいい、そこそこのレベルで終えておこう。近年の高校までの指導要領はその方向なのかもしれない。
しかし国語教育と英語教育には本質的な違いがあるはずだ。国語教育の水準が下がり、国民の書ける漢字や読める漢字が減ったとしても、日本人「みんな」が読めない、書けなくなっているのだから、構わないといえば構わないのかもしれない。文部科学省が「小学3年生までに習う漢字」といった具合に指導要領で集権的に指示しても、国語審議会が常用漢字を減らしても、さして問題ないのだろう。
だが日本の役所が、例えば日本人の高校1年生が学ぶ英単語はこの位の数で、と決めることは、日本の大学入試問題作りの指標となることはさておき、グローバルに見て、どれほどの意味があるのだろうか?新学習指導要領では、いわゆる「制限語彙」の規定が厳しく、中学校で900語、高1の「英語1」で中学プラス400語の1300語、さらに高2の「英語2」でプラス500語の1800語と定めている。現在の高校の英語教科書は1800語という極めて限定された語彙で書かれた英文なのである。1970年と比較すると、高校で習う英単語数は、ほぼ半減している。このように日本の英語教科書は中学から大学までレベルダウンし続けても、実際に英語圏で使われている英語が簡単になるわけではない。むしろ日本の学校で習う英語と、英語圏で使われている英語のギャップが広がり、自分で勉強しなければならない余地が増えるばかりである。2000語レベルで終わってしまっては、あと6000語、自分で勉強しないとまともに新聞も読めない。そんな「なんちゃって英語教科書」ばかり量産して、「英語ごっこ」に興じている場合ではなかろう。
実際に、留学生向けの試験であるTOEFLの難易度は上がる一方であり、日本人受験生の平均点が下落し続けるのも当然である。
現在、アメリカの大学で研究している友人の日本人医師と話していた時に、彼が「英語はしょせん猿真似だからな」とつぶやいたのには、目を開かれる思いだった。帰国子女だった彼の実感が言わせたせりふなのだろうが、実際、英語を道具として学ぶとしたら、結局、ネイティブの真似をするしかなく、それ以上でも以下でもなく、日本で新しい語彙を生み出せるわけでもないのだ。だとすれば苦しくても、英語で新聞を読んだり、そのレベルの英語を書くように努力しないと、結局、英語をマスターすることにはならないはずだ。
「悪貨は良貨を駆逐する」というように、実際、2,3年前に使った教科書でも少しでも本格的な英語教科書は次々、市場から消えていき、イラストと写真ばかりが充実し、中学レベルの英語を並べた同工異曲の教科書ばかりが跋扈している。難しい教科書は採用率が低いか、クレームが多いのかもしれないが、大学英語教科書会社にも、日本人の英語力向上に貢献したいという良心が少しでもあるならば、新聞英語レベルの教科書をもう少し発行し続けてほしいと切に思う。