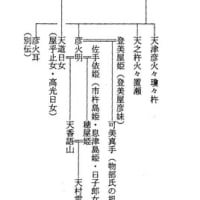前回のブログで原出雲が九州であったなら、古事記の<八俣大蛇>のヒロイン・櫛名田比売を祀り大蛇退治
の伝承を持つ神社が九州にもあるのではないかと探したところ、肥前(佐賀県神埼市)の古社「櫛山櫛田宮」
(元荘園で順徳天皇から1213年に賜った御宸筆の額を掲げている。)の<櫛田神社>の存在を知りました。
興味深いことには弥生時代の大規模な遺跡・吉野ヶ里にほど近い場所にあった事、また八俣大蛇神話で八稚女
を襲うのは<高志の大蛇>と記されているが、櫛田神社の南3キロほどの所に<高志(たかし)神社>があり
本来は<こし>と読むべきと思われるが、その境内に弥生時代の遺跡が見つかりました。
発掘調査の結果は「弥生時代前期末から中期中頃の甕棺墓38基、中期前半の祭祀遺構2基、井戸跡4基、土
壙9基、貝塚などが発掘され、遺跡の北側に墓地、西側に貝塚、南側に集落が配されていました。」
21世紀の今、櫛田神社の境内から弥生時代(紀元前4ないし5世紀から紀元後3世紀)の痕跡を見つけることは
不可能ですが、神木とされる<琴の楠>になんらかのメッセージが隠されているのでは?と思いました。
楠(くすのき)はクスノキ科の常緑高木で、本州の茨城県以西、四国、九州、台湾、中国の暖地に広く分布して
おり、佐賀県では県の花にしている。九州にはクスノキが多く、縄文杉より太い巨樹が9本もあって、鹿児島県
姶良郡蒲生町の八幡神社にある「蒲生のクス」は日本一の巨樹であるという。古来クスノキ科のタブノキと共に
重要な船材として重用されていました。
私は楠に関してひとつ疑問に思っていたことがありました。
20年程前のこと、夫のテニス仲間と長崎に「くんち」を見に行きました。諏訪神社の神様へ町内ごとに出し物
(大きな船形の山車やクジラの引物、傘舞、龍のお練りなど)を造り、小高い丘にある諏訪神社の境内まで氏子
たちが運び上げ神様に見て頂くために引き回すという勇壮な祭りでした。見物客は神様に成り代わって「持って
こーい! 持って来い!」と掛け声をかけて会場は一層盛り上がる楽しい祭礼でした。
境内には大きな楠が青々と葉を茂らせており、ご神木ということでした。ところが御柱祭で有名な信州の諏訪
大社の御神木は杉であり、神紋は梶の葉紋なのです。一般的に出雲系の神社の神木は杉であり長崎の諏訪神社の
楠に違和感をおぼえていました。今回<琴の楠>にメッセージ性を感じたので長崎くんちの諏訪神社を検索して
みると・・・・
『鎮西大社諏訪大社 (長崎市上西山町)
主祭神 建御名方神 と 妃・八坂刀売神
嘗ては境内の「蛭子社(えびすしゃ)」前に<三柱鳥居>があった。』
と記されており、さらに八坂刀売神の父は綿津見神(安曇磯良)と伝えられていたのです。
なんと長崎の諏訪神社の祭神・建御名方神と妃・八坂刀売神が対馬の仁位の和多都美神(磯良)と繋がることを
三柱鳥居が教えてくれたのです。あと二柱の神は誰か?謎は残りますが、今回のテーマ「琴の楠」の謎解きを優先
します。
肥前神崎に坐す櫛田神社の祭神は櫛名田比売ですが、出雲神話の「八俣大蛇」は弥生時代に異種族か異部族が侵入
してきて起こった争いを反映したもので、弥生時代から上代において小国が誕生したのち最も大きな力を持った王
を<大国主>としたと思われますが、伝承から「菅之八耳=安曇磯良」であろうと推定しました。
しかし史書を編纂した大和朝廷はその歴史や王名を消し去りました。が、それを良しと考えない人々がおり、あの手
この手で真実を伝えようと知恵を絞り<暗号>を残し、「三柱鳥居」や「琴の楠」もその仕掛けのひとつと思います。
というわけで安曇磯良と繋がる<琴の楠>を永留久恵著『古代史の鍵・対馬』で探すことにしました。すると<琴>
という地名が上県の東側にあり、そこに<琴崎(きんさき>大明神>という海神を祀る古社がありました。
対馬の琴崎大明神は琴村の琴崎海岸にあり、海に面して鳥居が建ち、海上から社に向かう階段が設けられているが
縁起によると海神の姿を「金鱗の蛇」と表現している。古社らしく「神功皇后の三韓征伐の時、当社沖に停泊して
いた船の碇が海底に沈んだため安曇磯良が潜って引き上げた。」という伝説があり江戸時代には<琴崎大明神>と
称し<和多積神(安曇磯良)>と信じられていたそうです。また境内には「山元しこ明神」も祀られていました。
しかしこの琴崎大明神は中世以降の神仏混肴の両部神道が盛行して古い社号が廃れて、権現社とか、明神社と呼ばれる
ようになり、古い祭神の名も正確に伝えられていないらしい。現在は『対馬島誌』に記載された式内社の資料によって
「胡ロク神社」に比定されている。<コロク>とは<矢を入れて背負う道具。やなぐい。>の事。
海神を祀る神社に<やなぐい>がナゼ?と不思議に思いましたが、ある説では海が大荒れになった時に、海神(龍神)
が静まるように海に向かって矢を放ち祈ったのではと説いていましたが、私は志賀海神社の歩射祭は山誉祭という
服属儀礼の一環として行う行事なので、この時点で安曇側が敗者である事を認識すべきではないかと思いました。
だから<八尽くし><八稚女>から消え去るべき運命の敗者<菅之八耳(安曇磯良)>の伝承を伝えようと設定したと
思うのです。
「胡ロク神社」の御神体が<やなぐい>ならば、戦いで矢を射つくして空っぽになった<やなぐい>を祀っているのでは
ないかと気がつきました。以前に伏見稲荷神符の絵解きをした時に☓印の先が折れ曲がった記号があり、それが富氏の
いう出雲王朝の紋<違い矛>が敗れて折れた形と推理しましたが、同様にこの空っぽの<やなぐい>も和多積神(安曇
磯良)側が戦いに敗れて矢が尽きた象徴であろうと思います。
そしてもう一つ「胡ロク神社」は「山元しこ神社」とも呼ばれていました。醜(しこ)は醜女(しこめ)では<みにく
い>醜男(しこお)では<勇猛な、強い>意味をもたせています。記紀で大国主命は沢山の呼称で呼ばれており、その
一つに古事記では<葦原色許男神>書紀では<葦原醜男>があります。この呼称は『八幡宮御縁起』等に語られる安曇
磯良そのものです。縁起では「海中に久しく住みたる故に、カキやヒシ等という物、顔にひしと取り付いて、あまりに
みぐるしかりければ、浄衣の袖をときて顔に覆いたれ・・・」と書かれています。琴崎大明神(胡ロク神社)の<安曇
磯良>と出雲の<大国主命>が異名同体という証拠が<醜男>だったのです。
葦原中国が九州である事に気が付いた事がキッカケで出雲神話の大国主命とは綿津見神である安曇磯良と解きました。