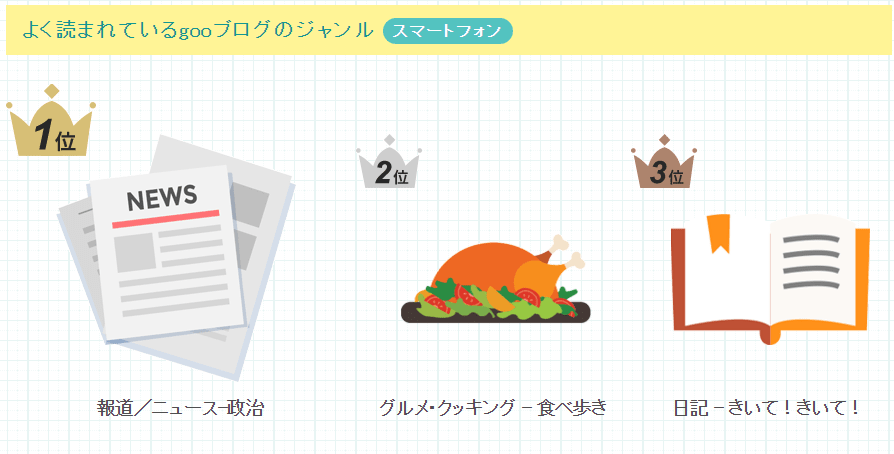代表選挙に言及する人がいて、育ちの悪い人の発想に呆れるとともに、育ちの悪い人は国会議員をお引き取りいただいた方がいいのかな、という思いを禁じ得ません。
政府は、民泊に関する新法の要綱をまとめて、平成29年2017年通常国会以降に法案を提出する方向性となりました。
これまでは、行政指導、政令、特区法改正などで対応するかまえでした。
今回初めて旅館業法を読んで気づきました。意外にもわずか13条の短い法律。
経営の許可は県知事。法律には、旅館の相続、衛生に必要な措置、宿泊者名簿、近隣の学長などの意見陳述が盛り込まれています。関係法律は風俗営業法や子ども子育て支援法も含みます。このため、監督官庁は、厚生労働省、国土交通省、県庁・総務省、警察庁、内閣府の少子化担当と防災担当、財務省、文部科学省などを含むことになります。
このためか、河野行政改革・規制改革相が、都内のシンポジウムで、新法の必要性に言及したようです。
民泊新法は、仲介業者の許認可と、損害賠償の強制加入が柱となりそうです。この場合、大企業の既得権益をつくり、まもる法律となりかねません。
[旅館業法の本則部分を全文引用]
旅館業法
(昭和二十三年七月十二日法律第百三十八号)
最終改正:平成二七年六月二四日法律第四五号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年六月二十四日法律第四十五号 (未施行)
第一条 この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第二条 この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2 この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3 この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
4 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
5 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
6 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
第三条 旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号の一に該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一 この法律又はこの法律に基く処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
二 第八条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して三年を経過していない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
3 第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(大学を除くものとし、次項において「第一条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)
二 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項 に規定する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除くものとし、以下単に「児童福祉施設」という。)
三 社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)第二条 に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定めるもの
4 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)は、前項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内の施設につき第一項の許可を与える場合には、あらかじめ、その施設の設置によつて前項各号に掲げる施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、学校(第一条学校及び幼保連携型認定こども園をいう。以下この項において同じ。)については、当該学校が大学附置の国立学校(国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校をいう。)であるときは当該大学の学長、高等専門学校であるときは当該高等専門学校の校長、高等専門学校以外の公立学校であるときは当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園であるときは、地方公共団体の長)、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の私立学校であるときは学校教育法 に定めるその所管庁、国及び地方公共団体以外の者が設置する幼保連携型認定こども園であるときは都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長)の意見を、児童福祉施設については、児童福祉法第四十六条 に規定する行政庁の意見を、前項第三号の規定により都道府県の条例で定める施設については、当該条例で定める者の意見を求めなければならない。
5 第二項又は第三項の規定により、第一項の許可を与えない場合には、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を申請者に通知しなければならない。
6 第一項の許可には、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を附することができる。
第三条の二 前条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)たる法人の合併の場合(営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該旅館業を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旅館業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。
2 前条第二項(申請者に係る部分に限る。)及び第三項から第六項までの規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該旅館業を承継する法人」と読み替えるものとする。
第三条の三 営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第三条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第三条第二項(申請者に係る部分に限る。)及び第三項から第六項までの規定は、第一項の承認について準用する。
4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る営業者の地位を承継する。
第三条の四 営業者は、旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性にかんがみ、営業の施設及び宿泊に関するサービスについて安全及び衛生の水準の維持及び向上に努めるとともに、旅館業の分野における利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している状況に対応できるよう、営業の施設の整備及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。
第四条 営業者は、営業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
3 第一項に規定する事項を除くほか、営業者は、営業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。
第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
第六条 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
第七条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、営業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させることができる。
2 当該職員が、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第七条の二 都道府県知事は、営業の施設の構造設備が第三条第二項の規定に基く政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該営業者に対し、相当の期間を定めて、当該施設の構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第八条 都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項第三号に該当するに至つたときは、同条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。
一 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百七十四条 、第百七十五条又は第百八十二条の罪
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)に規定する罪(同法第二条第四項 の接待飲食等営業に関するものに限る。)
三 売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第二章 に規定する罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第二章 に規定する罪
第八条の二 国立大学の学長その他第三条第四項に規定する者は、同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある営業の施設の構造設備が同条第二項の規定に基く政令で定める基準に適合しなくなつた場合又は営業者が同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内において第四条第三項の規定に違反した場合において、当該施設の清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、前二条に規定する処分について都道府県知事に意見を述べることができる。
第九条 第八条の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
2 第八条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第九条の二 国及び地方公共団体は、営業者に対し、旅館業の健全な発達を図り、並びに旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進するため、必要な資金の確保、助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第十条 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者
二 第八条の規定による命令に違反した者
第十一条 左の各号の一に該当する者は、これを五千円以下の罰金に処する。
一 第五条又は第六条第一項の規定に違反した者
二 第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十二条 第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
第十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第十条又は第十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
[旅館業法の本則部分の全文引用おわり]
このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
(http://miyazakinobuyuki.net/)
[お知らせはじめ]
宮崎信行の今後の政治日程(有料版)を発行しています。
「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い
なお、Twitterアカウントは「一時凍結」が続いておりますので、ツイッターはしていません。
このブログは以下のウェブサイトを活用して、エントリー(記事)を作成しています。
衆議院インターネット審議中継(衆議院TV)
参議院インターネット審議中継
国会会議録検索システム(国立国会図書館ウェブサイト)
衆議院議案(衆議院ウェブサイト)
今国会情報(参議院ウェブサイト)
各省庁の国会提出法案(閣法、各府省庁リンク)
日本法令索引(国立国会図書館)
予算書・決算書データベース(財務省ウェブサイト)
インターネット版官報
[お知らせ終わり]