「自由・平等・人権・民主主義」とハサミは使いよう(その1)

最近、日本や世界の政治にかかわるニュースを見たり聞いたり読んだりしていると、自由・平等・人権・民主主義といった言葉が、とても大安売りで使われていますね。
これらの言葉は、現代の自由主義諸国(おっと、私もたちまち使ってしまいました)では、「普遍的価値観」と呼ばれて、たいへん重宝されています。
普遍的価値観とはまた、大ぶろしきを広げたものですが、こうした言葉を「普遍的」と呼ぶことそのものが、アメリカを中心とした自由主義諸国(おっと、また)の戦略なのですね。現代社会では、みんながこれらの言葉には弱いので、看板として大いに使えると感じてしまうのでしょう。「朝鮮民主主義人民共和国」なんて、実態とまるで合わないスゴイ国名をつけている国さえあります。
ところで今の日本の言論界でこれらの言葉が使用される場合、それらはいつも両義性、両価性を帯びています。両義性、両価性――ambiguity――つまり「二つ以上の意味や価値を持っているようにとれること」。
ですから私たちは、これらの言葉を聞きとるときには、それがどういう文脈で使用されているのかに注意しなくてはなりません。また私たち自身がこれらの言葉を使うときには、それをどういう価値観のもとに使っているのかに自覚的でなくてはなりません。前者に関しては、まあ、それほど誤解の余地はないと言えますが、特に後者の場合、その人の思想がもろに現れます。何の疑いもなく肯定的に使っているのか、それともこれらの言葉の価値に対して否定的に使っているのか、はたまた懐疑的に、アイロニカルに使っているのか、方便として使っているのか等々。
たとえば「自由」。
日本国憲法で謳われているさまざまな自由は、何人も奴隷的拘束や思想弾圧を受けてはならないという規定ですから、これは原則的に保障されるべき大切な規定です。しかし、責任の伴わない無限定の自由が保障されているかといえば、それは違いますね。「個人の自由」は、野放図に許容されるとしばしば他人を侵害し、公益に抵触します。
ひところ「自由教育」なる理念のもとに、子どもへの指導・管理・強制をほとんどしない教育機関がはやりましたが、これなどはとんでもない倒錯です。社会的良識が発達していず、責任を免除されている未熟な子どもに自由を許したら、授業を聴かない自由、教室で漫画を読む自由、おしゃべりしたり飲食したり携帯をかけたりする自由、先生に逆らう自由、学校に行かない自由なども認めることになり、教育は成り立ちません。じっさいにこんなことを提唱していたバカ論者がいたのです。
また先ごろ、特定秘密保護法案の国会通過を巡って、一部のマスコミが「知る権利・報道の自由を侵すものだ」というネガティブキャンペーンを大々的に張りましたが、これなども、国民の安全を保障するための国家機密をみだりに漏らしてはならないという当たり前の趣旨を理解しない、まことに身勝手な主張というべきでしょう。この法律が施行されても、別に報道の自由は侵害などされず、これまでどおり保障されます。一部マスコミはナイーブな反権力感情だけを盾にして、自分たちが情報をリークしてもらえなくなるのではないかという恐れから、無関係な国民を巻き込んで煽動しているのですが、国民はこんな反安倍政権キャンペーンにたぶらかされてはなりません。
なおこの問題については、当ブログに拙論を掲載しましたので、ご関心のある方はどうぞ。
http://blog.goo.ne.jp/kohamaitsuo/e/13d043deb6f1e242766bf85f2c67d388
また1月10日発売の月刊誌『Voice』2月号にも拙稿を寄せています。
さらにいま、TPP交渉の年内妥結の可否が云々されています。もともとこのTPPというのは、国境を超えて市場を自由に開放せよというアメリカの一部グローバル企業や投資家の要求を通そうとするもので、これが認められると、それぞれの国家主権やその地域に根差した慣習や文化に破壊的な影響を与えることは明らかです。
この新自由主義のグローバリズム攻勢については、東谷暁氏、中野剛志氏、三橋貴明氏、柴山桂太氏、施光恒氏、関岡英之氏ら、多くの優れた論客が早い時期から何度も国益に反するものとして警鐘を打ち鳴らしてきました。それにもかかわらず、安倍政権は日米同盟という外交・軍事上の「ご縁」をそのまま経済関係にまで延長して、平然と対米従属を受け入れようとしています。ここでは私は、安倍政権を批判することになります。
TPPのような経済的条約における「自由」理念をそのまま信じることは、弱肉強食的な競争至上主義を肯定することであり、日本の国益にとって有害であるのみならず、途上国、新興国にとっても経済的な主権を強国の富裕勢力に奪われることを意味します。
しかし逆に、北朝鮮や中国のように、自由な言論も政治活動も許されず、政府に対する批判的言動が直ちに弾圧され取り締まられ粛清されるような独裁国家に対しては、自由の価値を叫び続けることに大きな意義があります。これはおそらく、その国に住んでみればすぐに実感できることで、逆に日本がいかに思想・言論・表現・信教などの自由が保障された恵まれた国であるかもわかろうというものです。恵まれすぎていて多様な見解・主張が乱れ飛び、結局は「暖簾に腕押し」になってしまっているわけですが。
以上のように、「自由」とは、それだけとしては単なる抽象的な言葉にすぎず、どういう具体的文脈の中で使われるのかという背景と不可分のかたちでその価値が測られるのでなくてはなりません。
同じことは、「平等」や「人権」という言葉にも当てはまります。
たとえば、金融資本の自由取引が行き過ぎて世界経済を混乱させ、失業率が高まって社会格差が極端に開いてしまうような事態が起きた時には(現にいま世界的にそうなっているのですが)、公共体が適切に介入し、「平等」理念に基づいて雇用創出や所得の再配分を実現させる政策が必要とされます。現代のような複雑な社会システムの下では、どのように介入するかがまさに問題なのですが。
またアメリカにおける黒人の公民権獲得のために闘ったキング牧師や、先ごろ亡くなった南アのマンデラ氏のように、不当な人種差別を受けている現状を打破するために、「平等」を強く訴えることはぜひとも必要です。
しかし日本の戦後教育の世界では、悪平等主義がはびこってきました。機会の平等を保障することは、近代国家の教育政策として当然のことです。ところが、いつしかそれが結果の平等をも実現しようという非現実的な理想に置き換えられました。個々の子どもには驚くべき能力格差があるという当たり前の事実を認めることがタブー視されるようになったのです。東京都の学校群制度、偏差値追放、ゆとり教育、大学定員の供給過剰、面接重視を目指す昨今の入試改革案など、みなこの流れです。いま、これらのどこに問題があるかについては詳説しませんが、戦後教育における「改革」なるものがことごとく失敗してきたことは確かなところです。そうしてその失敗の元凶が、平等主義イデオロギーの支配にこそあるということも。
さらに、最近の「一票の格差」についての違憲判決や、「婚外子相続分が嫡出子の二分の一」についての違憲判決のように、その背景にどういう具体的状況があるかということを見ない形式的平等主義は、まことに困ったものです。
これらについても、当ブログで論じたことがありますので、ご関心のある方は、以下のURLへどうぞ。
一票の格差問題:http://blog.goo.ne.jp/kohamaitsuo/e/130814b7041b2847b8be69d676d9d488
婚外子相続問題:http://blog.goo.ne.jp/kohamaitsuo/e/a77b97ae04df91d61a6febf3c0bc3dcb
日本では「人権派」というと、憲法11条をタテにとって、何でも自分たちの特殊な要求と主張を通そうとする種族を意味します。要するにサヨクあるいは「地球市民」派ですね。死刑廃止論者、人権擁護法案提唱者、「子どもの人権」論者、ジェンダーフリー論者などがこれに当たります。この人たちは、国家というものの存在意義や歴史的意味がわかっていないために、「正義」のよりどころをただひたすら反国家的な感情に求めます。公共精神のかけらもない幼稚な人たちですが、そういう幼稚な議論がけっこう通ってしまうところが問題です。
しかし日本国憲法というものが現実に存在して、そのなかで「基本的人権」の規定が謳われている以上、時に応じてこの規定およびその土台になっている人権思想を利用する必要が生じてくるのも事実です。たとえば、拉致被害者の生命や自由が無視されてきた状況に対して、私たち日本国民は、「人権の大切さ」という旗印を大いに掲げる必要があるでしょう。
私事で恐縮ですが、私はあるご縁から、明らかに冤罪と思われる事件に少しばかり関わった経験があります。これは、その当事者の職を不当に奪う行政措置がなされたことに対する抗議文書を書くという形をとったのですが、こういう場合、憲法を頂点とする法体系に則って訴訟に立ち向かわなくてはなりませんので、当然、その行政措置は憲法違反(つまり人権侵害)であるという論陣を張ることになります。
また、ノーベル平和賞を獲得した中国の人権活動家・劉暁波(りゅう・ぎょうは)氏のように、過酷な弾圧のなかで闘ってきた人の思想的よりどころが、「人権」という概念の価値に依っていることは明らかです。そうして、それは正しいことだと思います。
このように、「人権」という概念をひたすらお札のように絶対化して拡張解釈するのもはき違えだし、いっぽう、圧政や弾圧や不当な措置が現にあるところでは、この概念を「普遍的価値」として掲げていくことも有効な意味をもつと考えられます。要するにそれは政治状況、社会状況に応じて使い分けるべき概念だということになるでしょう。

最近、日本や世界の政治にかかわるニュースを見たり聞いたり読んだりしていると、自由・平等・人権・民主主義といった言葉が、とても大安売りで使われていますね。
これらの言葉は、現代の自由主義諸国(おっと、私もたちまち使ってしまいました)では、「普遍的価値観」と呼ばれて、たいへん重宝されています。
普遍的価値観とはまた、大ぶろしきを広げたものですが、こうした言葉を「普遍的」と呼ぶことそのものが、アメリカを中心とした自由主義諸国(おっと、また)の戦略なのですね。現代社会では、みんながこれらの言葉には弱いので、看板として大いに使えると感じてしまうのでしょう。「朝鮮民主主義人民共和国」なんて、実態とまるで合わないスゴイ国名をつけている国さえあります。
ところで今の日本の言論界でこれらの言葉が使用される場合、それらはいつも両義性、両価性を帯びています。両義性、両価性――ambiguity――つまり「二つ以上の意味や価値を持っているようにとれること」。
ですから私たちは、これらの言葉を聞きとるときには、それがどういう文脈で使用されているのかに注意しなくてはなりません。また私たち自身がこれらの言葉を使うときには、それをどういう価値観のもとに使っているのかに自覚的でなくてはなりません。前者に関しては、まあ、それほど誤解の余地はないと言えますが、特に後者の場合、その人の思想がもろに現れます。何の疑いもなく肯定的に使っているのか、それともこれらの言葉の価値に対して否定的に使っているのか、はたまた懐疑的に、アイロニカルに使っているのか、方便として使っているのか等々。
たとえば「自由」。
日本国憲法で謳われているさまざまな自由は、何人も奴隷的拘束や思想弾圧を受けてはならないという規定ですから、これは原則的に保障されるべき大切な規定です。しかし、責任の伴わない無限定の自由が保障されているかといえば、それは違いますね。「個人の自由」は、野放図に許容されるとしばしば他人を侵害し、公益に抵触します。
ひところ「自由教育」なる理念のもとに、子どもへの指導・管理・強制をほとんどしない教育機関がはやりましたが、これなどはとんでもない倒錯です。社会的良識が発達していず、責任を免除されている未熟な子どもに自由を許したら、授業を聴かない自由、教室で漫画を読む自由、おしゃべりしたり飲食したり携帯をかけたりする自由、先生に逆らう自由、学校に行かない自由なども認めることになり、教育は成り立ちません。じっさいにこんなことを提唱していたバカ論者がいたのです。
また先ごろ、特定秘密保護法案の国会通過を巡って、一部のマスコミが「知る権利・報道の自由を侵すものだ」というネガティブキャンペーンを大々的に張りましたが、これなども、国民の安全を保障するための国家機密をみだりに漏らしてはならないという当たり前の趣旨を理解しない、まことに身勝手な主張というべきでしょう。この法律が施行されても、別に報道の自由は侵害などされず、これまでどおり保障されます。一部マスコミはナイーブな反権力感情だけを盾にして、自分たちが情報をリークしてもらえなくなるのではないかという恐れから、無関係な国民を巻き込んで煽動しているのですが、国民はこんな反安倍政権キャンペーンにたぶらかされてはなりません。
なおこの問題については、当ブログに拙論を掲載しましたので、ご関心のある方はどうぞ。
http://blog.goo.ne.jp/kohamaitsuo/e/13d043deb6f1e242766bf85f2c67d388
また1月10日発売の月刊誌『Voice』2月号にも拙稿を寄せています。
さらにいま、TPP交渉の年内妥結の可否が云々されています。もともとこのTPPというのは、国境を超えて市場を自由に開放せよというアメリカの一部グローバル企業や投資家の要求を通そうとするもので、これが認められると、それぞれの国家主権やその地域に根差した慣習や文化に破壊的な影響を与えることは明らかです。
この新自由主義のグローバリズム攻勢については、東谷暁氏、中野剛志氏、三橋貴明氏、柴山桂太氏、施光恒氏、関岡英之氏ら、多くの優れた論客が早い時期から何度も国益に反するものとして警鐘を打ち鳴らしてきました。それにもかかわらず、安倍政権は日米同盟という外交・軍事上の「ご縁」をそのまま経済関係にまで延長して、平然と対米従属を受け入れようとしています。ここでは私は、安倍政権を批判することになります。
TPPのような経済的条約における「自由」理念をそのまま信じることは、弱肉強食的な競争至上主義を肯定することであり、日本の国益にとって有害であるのみならず、途上国、新興国にとっても経済的な主権を強国の富裕勢力に奪われることを意味します。
しかし逆に、北朝鮮や中国のように、自由な言論も政治活動も許されず、政府に対する批判的言動が直ちに弾圧され取り締まられ粛清されるような独裁国家に対しては、自由の価値を叫び続けることに大きな意義があります。これはおそらく、その国に住んでみればすぐに実感できることで、逆に日本がいかに思想・言論・表現・信教などの自由が保障された恵まれた国であるかもわかろうというものです。恵まれすぎていて多様な見解・主張が乱れ飛び、結局は「暖簾に腕押し」になってしまっているわけですが。
以上のように、「自由」とは、それだけとしては単なる抽象的な言葉にすぎず、どういう具体的文脈の中で使われるのかという背景と不可分のかたちでその価値が測られるのでなくてはなりません。
同じことは、「平等」や「人権」という言葉にも当てはまります。
たとえば、金融資本の自由取引が行き過ぎて世界経済を混乱させ、失業率が高まって社会格差が極端に開いてしまうような事態が起きた時には(現にいま世界的にそうなっているのですが)、公共体が適切に介入し、「平等」理念に基づいて雇用創出や所得の再配分を実現させる政策が必要とされます。現代のような複雑な社会システムの下では、どのように介入するかがまさに問題なのですが。
またアメリカにおける黒人の公民権獲得のために闘ったキング牧師や、先ごろ亡くなった南アのマンデラ氏のように、不当な人種差別を受けている現状を打破するために、「平等」を強く訴えることはぜひとも必要です。
しかし日本の戦後教育の世界では、悪平等主義がはびこってきました。機会の平等を保障することは、近代国家の教育政策として当然のことです。ところが、いつしかそれが結果の平等をも実現しようという非現実的な理想に置き換えられました。個々の子どもには驚くべき能力格差があるという当たり前の事実を認めることがタブー視されるようになったのです。東京都の学校群制度、偏差値追放、ゆとり教育、大学定員の供給過剰、面接重視を目指す昨今の入試改革案など、みなこの流れです。いま、これらのどこに問題があるかについては詳説しませんが、戦後教育における「改革」なるものがことごとく失敗してきたことは確かなところです。そうしてその失敗の元凶が、平等主義イデオロギーの支配にこそあるということも。
さらに、最近の「一票の格差」についての違憲判決や、「婚外子相続分が嫡出子の二分の一」についての違憲判決のように、その背景にどういう具体的状況があるかということを見ない形式的平等主義は、まことに困ったものです。
これらについても、当ブログで論じたことがありますので、ご関心のある方は、以下のURLへどうぞ。
一票の格差問題:http://blog.goo.ne.jp/kohamaitsuo/e/130814b7041b2847b8be69d676d9d488
婚外子相続問題:http://blog.goo.ne.jp/kohamaitsuo/e/a77b97ae04df91d61a6febf3c0bc3dcb
日本では「人権派」というと、憲法11条をタテにとって、何でも自分たちの特殊な要求と主張を通そうとする種族を意味します。要するにサヨクあるいは「地球市民」派ですね。死刑廃止論者、人権擁護法案提唱者、「子どもの人権」論者、ジェンダーフリー論者などがこれに当たります。この人たちは、国家というものの存在意義や歴史的意味がわかっていないために、「正義」のよりどころをただひたすら反国家的な感情に求めます。公共精神のかけらもない幼稚な人たちですが、そういう幼稚な議論がけっこう通ってしまうところが問題です。
しかし日本国憲法というものが現実に存在して、そのなかで「基本的人権」の規定が謳われている以上、時に応じてこの規定およびその土台になっている人権思想を利用する必要が生じてくるのも事実です。たとえば、拉致被害者の生命や自由が無視されてきた状況に対して、私たち日本国民は、「人権の大切さ」という旗印を大いに掲げる必要があるでしょう。
私事で恐縮ですが、私はあるご縁から、明らかに冤罪と思われる事件に少しばかり関わった経験があります。これは、その当事者の職を不当に奪う行政措置がなされたことに対する抗議文書を書くという形をとったのですが、こういう場合、憲法を頂点とする法体系に則って訴訟に立ち向かわなくてはなりませんので、当然、その行政措置は憲法違反(つまり人権侵害)であるという論陣を張ることになります。
また、ノーベル平和賞を獲得した中国の人権活動家・劉暁波(りゅう・ぎょうは)氏のように、過酷な弾圧のなかで闘ってきた人の思想的よりどころが、「人権」という概念の価値に依っていることは明らかです。そうして、それは正しいことだと思います。
このように、「人権」という概念をひたすらお札のように絶対化して拡張解釈するのもはき違えだし、いっぽう、圧政や弾圧や不当な措置が現にあるところでは、この概念を「普遍的価値」として掲げていくことも有効な意味をもつと考えられます。要するにそれは政治状況、社会状況に応じて使い分けるべき概念だということになるでしょう。












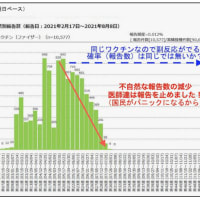

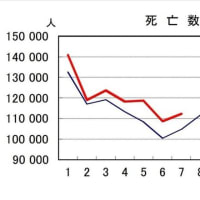
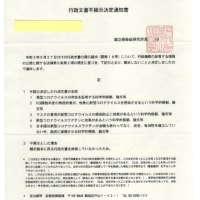
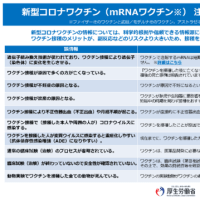

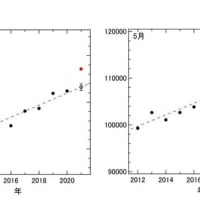

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます