 左上に青山城
左上に青山城築城期:南北朝期
遺 構:土塁・土橋・空堀・枡形虎口・子堀
青山城と同様に愛知川の川筋には、高野城、小倉城、曽根城、中戸城、鯰江城、上岸本城などが築かれている。
これらは城砦は、南北朝期から戦国期にかけて愛知川流域を支配していた小倉氏、およびその支族達によって築城されたのもである。
 50m×60mの方形範囲内に幅約9m、深さ3.6mの空堀を三方に廻らし、上辺で約7~9m、主郭内敷地から測って約2mの高さの土塁を廻らした堅固な構築となっています
50m×60mの方形範囲内に幅約9m、深さ3.6mの空堀を三方に廻らし、上辺で約7~9m、主郭内敷地から測って約2mの高さの土塁を廻らした堅固な構築となっています 青山城は愛知川右岸の河岸段丘上に築かれている。
青山城は愛知川右岸の河岸段丘上に築かれている。青山城は鯰江城、井元城と同様に愛知川右岸の台地上に築かれた城郭。
青山城は、青山氏によって築かれた。 青山氏は、小倉城主小倉氏の一族で青山実貞・青山勝重・青山信兼らが佐々木六角氏に仕えた。 青山氏は、その後織田信長に属してた。
近くには鯰江城があり、この鯰江城を天正元年(1573)に織田方の柴田勝家が攻めた際に、近くに付城を築いたとされているが、この青山城の構造を見ていると、まさにここがその付城として使われた。
守山を出た信長公は百済寺に入り、ここに2、3日滞在した。近在の鯰江城に佐々木右衛門督六角義治が籠っており、これを攻略しようとしたのである。信長公は佐久間信盛・蒲生賢秀・丹羽長秀・柴田勝家らに攻撃を命じ、四方(小倉城・青山城・井元城・上岸本城)より囲んで付城を築かせた。
このとき、近年になって百済寺が鯰江城をひそかに支援し、一揆に同調しているという諜報が信長公の耳にとどいた。それを知った信長公は激怒して4月11日寺に放火し、百済寺の堂塔伽藍は灰燼に帰してしまった。焼け跡は目も当てられない有様であった。----
ーーーー小谷落城 浅井下野・備前父子成敗、羽柴筑前跡職仰付けらるるの事
・・ 小谷城は陥ちた。落城後、浅井父子の首は京に後送されて獄門にかけられ、十歳になる長政嫡男も捕らえ出されて関ヶ原で磔にかけられた。元亀以来というもの浅井氏に苦汁を舐めさせられつづけてきた信長公は、ここに年来の鬱憤を晴らしたのであった。
戦後、江北の浅井氏遺領は羽柴秀吉に一職進退の朱印状が下された。秀吉は年来の武功を認められ、名誉の至りであった。
9月4日、信長公は佐和山に入り、柴田勝家に六角義治の籠る鯰江城の攻略を命じた。柴田はすぐさま兵を寄せて鯰江を囲み、義治を降伏させた。こうして各所の平定に成功した信長公は、9月6日晴れて濃州岐阜へ凱旋を果たした。----
 シハイスミレ?
シハイスミレ? アカバナフキノトウ
アカバナフキノトウ 「若林運動公園」到着
「若林運動公園」到着
 「若林運動公園」の先の山へ
「若林運動公園」の先の山へ 日吉神社・善勝寺の裏手(宮林公園横)の檜林の中に状態良く遺構が残されている。
日吉神社・善勝寺の裏手(宮林公園横)の檜林の中に状態良く遺構が残されている。
青山三衛門は足利義輝に従って戦死しており、また、青山與三郎、同虎丸は信長に仕え本能寺で戦死するなど、中央政権との繋がりも深いものがあった。
愛知郡は中世を通じて佐々木六角氏の支配下におかれ、六角氏被官となった在地土豪の城館が多く存在しています。永源寺の高野城、愛知川沿いにはほぼ集落ごとに在地土豪の城館が残っています。青山城は史跡の指定も何も受けていませんが、一見の価値がある城跡です。
近江の城といえば安土城や観音寺城等複数の郭が幾重にも取り囲む壮大な城もありますが、単郭方形城館という正方形の平地の廻りを高い土塁で囲み、さらにその外側を深い空堀で囲むという単純なお城です。
鎌倉時代以降にみられる屋敷の廻りに水堀を廻す方形居館から発展したという説もあります。(近江の中世城郭において特に甲賀郡の山城に顕著に見られる構造の城です)
城跡の遺構は、愛知川河岸段丘上にあり、東南から西北方向に約200m、南西から北東方向に約150m位の規模で残されています。発掘調査等を行われていませんので詳細な遺構は分かりませんが、居館跡とみられる主郭部は、50m×60mの方形範囲内に幅約9m、深さ3.6mの空堀を三方に廻らし、上辺で約7~9m、主郭内敷地から測って約2mの高さの土塁を廻らした堅固な構築となっています。愛知川側の現在絶壁になっている所に開口部があり、枡形の窪地になっています。開口部の右手の土塁上には、礎石が残っており、櫓等の建物があったと思われます。主郭内敷地にも礎石や井戸跡があります。西北側(公園側)の堀が障子堀になっており、一部土橋と思われる進入路があります。このようにほぼ築城時の姿を留めている城館跡です。




 おぉぉぉ・・・城址は明確。深い空堀が(実際2m位落ちたら)、本当にはまったら簡単には上がれない高さ。
おぉぉぉ・・・城址は明確。深い空堀が(実際2m位落ちたら)、本当にはまったら簡単には上がれない高さ。
 土塁と空堀・・・すごい。実際は土塁+空掘なので、体感では4m位の高低差。空堀の土を「土塁」に積み上げ
土塁と空堀・・・すごい。実際は土塁+空掘なので、体感では4m位の高低差。空堀の土を「土塁」に積み上げ

 曲輪周囲の空堀
曲輪周囲の空堀

 南側(愛知川)の櫓台?見張り櫓跡カ?
南側(愛知川)の櫓台?見張り櫓跡カ? 





 「日吉神社と善勝寺」の上が、青山城址。愛知川堤防から遠望。
「日吉神社と善勝寺」の上が、青山城址。愛知川堤防から遠望。























本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!











 現地説明板
現地説明板 左手の道は主曲輪横に出る小倉新道で、近年拡幅された道。この道は堀切だった地形を利用されている。
左手の道は主曲輪横に出る小倉新道で、近年拡幅された道。この道は堀切だった地形を利用されている。




 道は主曲輪横に出る小倉新道で、近年拡幅された道。
道は主曲輪横に出る小倉新道で、近年拡幅された道。 浅い堀切
浅い堀切 ひら虎口か、散策路か
ひら虎口か、散策路か

 今も、居住者か。
今も、居住者か。













 井元城跡縄張図
井元城跡縄張図  (滋賀県文化財学習シートより)重ね馬出
(滋賀県文化財学習シートより)重ね馬出 城域全体図(長谷川博美氏踏査図2009年)
城域全体図(長谷川博美氏踏査図2009年) 本春日神社殿東の石積から、無理やり登城!
本春日神社殿東の石積から、無理やり登城!

 春日神社本殿東側土塁
春日神社本殿東側土塁 春日神社本殿北側土塁
春日神社本殿北側土塁

 綺麗に手入れされ、ショウジョウバカマ群生の薄紫色で迎えてくれた!
綺麗に手入れされ、ショウジョウバカマ群生の薄紫色で迎えてくれた!
 城は、方形の主郭とその周囲に廻らされれた土塁と空堀があり、主郭東側には重ね馬出の遺構が良く残っている。 重ね馬出の遺構自体あまり見られないことから、貴重な遺構。
城は、方形の主郭とその周囲に廻らされれた土塁と空堀があり、主郭東側には重ね馬出の遺構が良く残っている。 重ね馬出の遺構自体あまり見られないことから、貴重な遺構。

















 春日神社に向かって左手の空き地内から斜面を登っていく坂道があり、坂道を登り切ったあたりで、郭を囲う空堀の底につながっています。
春日神社に向かって左手の空き地内から斜面を登っていく坂道があり、坂道を登り切ったあたりで、郭を囲う空堀の底につながっています。 春日神社入口西側から左手に神社裏手に登る道がある。 この道を登り切るとそこには井元城の空堀と土塁が現れる。北西一帯の河岸段丘の檜林の中に井元城はあった。
春日神社入口西側から左手に神社裏手に登る道がある。 この道を登り切るとそこには井元城の空堀と土塁が現れる。北西一帯の河岸段丘の檜林の中に井元城はあった。  春日神社の参拝者用無料駐車場
春日神社の参拝者用無料駐車場 国道307号線 春日橋から、妹南信号を左折
国道307号線 春日橋から、妹南信号を左折 春日神社の参拝者用無料駐車場を利用。(県道217号線を永源寺方面) 春日橋から、妹南信号を左折、春日神社の鳥居を過ぎすぐ。
春日神社の参拝者用無料駐車場を利用。(県道217号線を永源寺方面) 春日橋から、妹南信号を左折、春日神社の鳥居を過ぎすぐ。 春日神社の参拝者用無料駐車場を利用。
春日神社の参拝者用無料駐車場を利用。




















 現在の曽根城
現在の曽根城
 土塁か
土塁か 見張り櫓跡か
見張り櫓跡か 土塁跡か
土塁跡か

 門前に「豊国山万福寺」説明板は
門前に「豊国山万福寺」説明板は




 曽根城址(遠景)JAのカントリーは、ヨーロッパ城のよう!
曽根城址(遠景)JAのカントリーは、ヨーロッパ城のよう!
 目印の県道229号線の三叉路(この手前に路肩駐車)の河川段丘上の左上が城址。
目印の県道229号線の三叉路(この手前に路肩駐車)の河川段丘上の左上が城址。 ここを左に!
ここを左に! この左が城址(下から)
この左が城址(下から) 坂道を登った角から攻め込みました(城址裏手)
坂道を登った角から攻め込みました(城址裏手) 西方向
西方向 南方向(愛知川)の土塁(河川段差を利用した)丘上
南方向(愛知川)の土塁(河川段差を利用した)丘上 南方側(愛知川)の土塁(河川段差を利用した)
南方側(愛知川)の土塁(河川段差を利用した) 上段の郭址10m×10m(鯰江城側)に祠?石仏?
上段の郭址10m×10m(鯰江城側)に祠?石仏? 下段の郭址10m×10m(西側)に祠
下段の郭址10m×10m(西側)に祠 下段の郭址
下段の郭址 城址裏手
城址裏手 車を駐車した所か振り向いて、南東の土塁(櫓台)
車を駐車した所か振り向いて、南東の土塁(櫓台) 市三宅城(真宗大谷派 都賀山 蓮生寺)
市三宅城(真宗大谷派 都賀山 蓮生寺)








 境内より土塁
境内より土塁 寺の南側に50mほど土塁とその外側に堀が残す。
寺の南側に50mほど土塁とその外側に堀が残す。 土塁の竹に子供のジャングルジムのように活用、土塁は維持され、手入れもされている(子供達の安全の為か)
土塁の竹に子供のジャングルジムのように活用、土塁は維持され、手入れもされている(子供達の安全の為か)




 志那街道の道標
志那街道の道標


























 源平合戦の屋島の戦いで扇の的を射止め、弓の名人として名高い那須与一の次男で宗信.
源平合戦の屋島の戦いで扇の的を射止め、弓の名人として名高い那須与一の次男で宗信. 八幡神社は、宗信が1239年(平安時代後期)に京都の岩清水八幡宮の応神天皇の分身を奉り建立しました。また、近くの称名寺は、宗信が晩年になって親鸞上人の弟子となり出家して1258年に建立したものです。この寺の住職さんはそれ以来、那須の姓を名のっています。
八幡神社は、宗信が1239年(平安時代後期)に京都の岩清水八幡宮の応神天皇の分身を奉り建立しました。また、近くの称名寺は、宗信が晩年になって親鸞上人の弟子となり出家して1258年に建立したものです。この寺の住職さんはそれ以来、那須の姓を名のっています。 土塁の痕跡
土塁の痕跡 文治元年(1185年)の源平の戦いの際、屋島の戦いで「弓矢の名手」として名を上げた那須与一宗高の次男の石畠民部大輔宗信がこの地を領して那須城を築き、佐々木氏に従ったとされます。 <八幡神社説明板より>
文治元年(1185年)の源平の戦いの際、屋島の戦いで「弓矢の名手」として名を上げた那須与一宗高の次男の石畠民部大輔宗信がこの地を領して那須城を築き、佐々木氏に従ったとされます。 <八幡神社説明板より>






 那須城の隣に「弘誓山称名寺」
那須城の隣に「弘誓山称名寺」


 安孫子の集落の中心に安孫子神社が。
安孫子の集落の中心に安孫子神社が。
 同じく集落の中央に浄光寺という立派なお寺もありました。
同じく集落の中央に浄光寺という立派なお寺もありました。 安孫子神社・・・「山芋の里 あびこ」
安孫子神社・・・「山芋の里 あびこ」


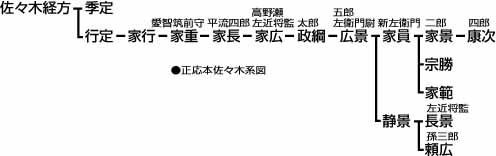
 常禅寺山門入り口に”八町城跡”と彫られた石柱がある。
常禅寺山門入り口に”八町城跡”と彫られた石柱がある。 常禅寺山門
常禅寺山門






 常禅寺の土塁
常禅寺の土塁










 ●閂(かんぬき)●嵯峨源氏渡辺氏流
●閂(かんぬき)●嵯峨源氏渡辺氏流 
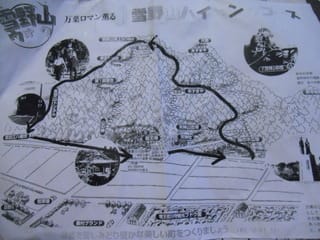




 ここからハイキングスタート!
ここからハイキングスタート!



 中腹の見晴らし台
中腹の見晴らし台






 結構きつい!
結構きつい!
 これも山上古墳だが、雪野山城の虎口!
これも山上古墳だが、雪野山城の虎口!
 雪野山古墳到着
雪野山古墳到着







 山頂より西望む…近江富士(三上山)の頭(頂部)も見える
山頂より西望む…近江富士(三上山)の頭(頂部)も見える


 土塁
土塁














 龍王寺は創建1300年。
龍王寺は創建1300年。











 つくしが・・・!
つくしが・・・! 雪野山全景 (竜王町川守側より)
雪野山全景 (竜王町川守側より) 2004年の「
2004年の「






 土塁痕(八幡神社)
土塁痕(八幡神社) 城郭遺構は社殿の裏に土塁を確認
城郭遺構は社殿の裏に土塁を確認 交差点の常夜塔
交差点の常夜塔

 彦根市周辺の荘園
彦根市周辺の荘園
 雨壺山に立つ駒札
雨壺山に立つ駒札


 北に
北に 北に
北に 西側の平削地、20年前に斎場があり、現在は広場公園になっています、切通し部に西登山口
西側の平削地、20年前に斎場があり、現在は広場公園になっています、切通し部に西登山口 新神社 駐車場の西端の「しめ縄石」が、登り口
新神社 駐車場の西端の「しめ縄石」が、登り口
 5m程登ると、唯一の【案内板】
5m程登ると、唯一の【案内板】 破損の灯篭・石垣用?の石・・・300年は?
破損の灯篭・石垣用?の石・・・300年は? 石段は、はっきりあるが落ち葉が
石段は、はっきりあるが落ち葉が







 雨壺山頂上、標高:136.9m(一等三角点:雨壷山)
雨壺山頂上、標高:136.9m(一等三角点:雨壷山) 西に下りて行きました
西に下りて行きました 西に下りる登山道は、竹林を進むと
西に下りる登山道は、竹林を進むと
 小塁や堀切が・・・
小塁や堀切が・・・

 スマホで方位確認
スマホで方位確認










 土塁の様な!
土塁の様な!





 公園側に下りました。西登山口、標識もなく分りつらい!
公園側に下りました。西登山口、標識もなく分りつらい! 向かいに地蔵・石仏が
向かいに地蔵・石仏が 左が登り口(出口)ですが、解りにくい!・・・正面は県道・仏壇店倉庫ヵ
左が登り口(出口)ですが、解りにくい!・・・正面は県道・仏壇店倉庫ヵ