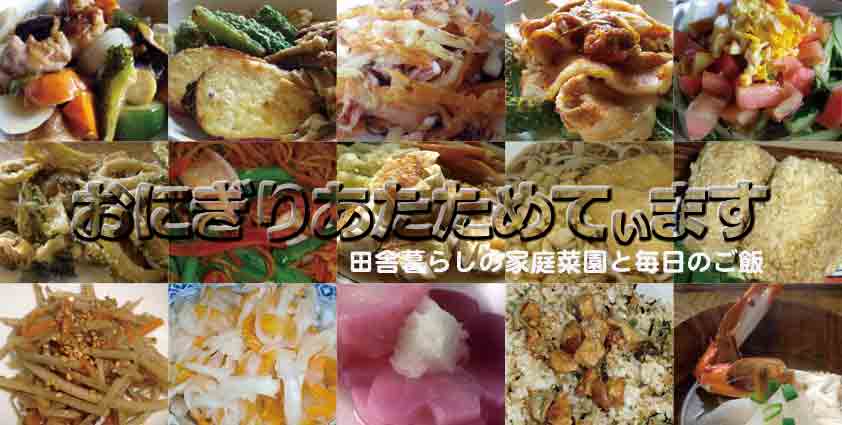
群馬県館林市という所に所用で行って来ました。真夏に最高気温を記録したところです。
折角なので、少しばかり観光してみました。駅前から「歴史の小路」という見所があるのですが、分かり辛く見落としてしまった箇所もありましたが、お目当ての「館林城土橋門」まで行き着けました。「館林城」は、五代将軍・徳川綱吉の居城として有名ですよね。まあ、当人は江戸に居たのでしょうが。

駅前から先ず最初に見えるのが、「竜の井」。城沼に棲む竜神の妻が、かつてここにあった寺を守るため、この井戸に姿を消したという伝説があるそうです。

「外池商店」。江戸中期、近江国から移住して来た、造り酒屋の和泉屋さんです。明治33年に味噌、醤油の製造業に変わり、現在は酒の小売業を行っているそうです。

「鷹匠町長屋門」。旧野辺町の豪農・松澤家の長屋門を、武家屋敷長屋門として、平成21年に新築したそうです。門の両脇が、奉公人の長屋や物置となっているので、そう呼ばれていますが、これだけの長屋門を構えた農家って、どれだけの分限者だったのか。




「鷹匠町武家屋敷武鷹館」。江戸時代、館林は鷹狩用の鷹を育成する鷹匠が住んでいたことから鷹匠町と呼ばれており、この鷹匠町にある武士の住宅ということで一般公募により、「武鷹館」と名付けられたそうです。
旧館林藩士住宅、長屋門、付属住宅があり平成11年に館林市指定重要文化財に指定されました。


「館林城復原土橋門」。館林城は、城沼に西から狐の尾のように突き出した半島に中心を置く平城だったことから、別名・尾曳城と呼ばれています。現在の館林市の中心部にあります。
築城は、弘治2(1556)年赤井照康によるという説が一般的ですが、信憑性は疑わしく不明です。
戦国時代には、上杉氏、武田氏、小田原北条氏による三つ巴の攻防に巻き込まれ、天正18(1590)年に、石田三成率いる豊臣軍に攻められ、降伏を勧めて開城しました。
同年、徳川家康関東入封に伴って、徳川四天王・榊原康政が10万石で城主となり、城下町を整備、寛文元(1661)年、後の徳川綱吉が城主となり、五代将軍になってからは将軍を輩出した徳川宗家に関わる重要な地として、江戸幕府に位置付けられ、最後の城主秋元氏まで江戸幕府の重鎮を務めた7家の居城として栄えたそうです。
しかし、城の建物の大半は明治7(1840)年に焼失し、三の丸跡地にわずかに土橋門が復元されているのみで、市役所などの敷地に利用されています。
小さな町にも、深い歴史を感じます。由緒のある城ですので、復元されないのが残念です。
また、案内がずさんで地図も分かり辛いので、「歴史の小路」に案内板などを立てていただくと嬉しいのですが。
事情があり、久し振りの名所巡りだったので(約3年以上振り?)、楽しく過ごせました。日本各地を巡って思うのですが、余程の大都市以外は、駅前や市内って寂れていますよね。いずこも、市中心部よりも広い土地を確保出来る外れに大型スーパーなどが出店しているせいでしょうが、その土地に初めて触れるのは駅前。閑散とされていると、旅の意気込みが「しゅん」と消沈してしまいます。
地方では車社会なので、住んでおられる方には不便はないのでしょうが、旅人は、駅前や市中心部の活気を感じ、土地の人と触れ合いたいものです。
この日も、ほとんど観光している人はいませんでした。ウォーキングの市民の方や小中学生の姿がちらほら。んっ、休日なに制服? あっ部活動かなにかでしょう。
ただ、館林市の方は親切な方が多く、道を尋ねても皆さん親切に教えてくださいました。ひとりの方は、どいこかへお出掛けの途中のようでしたが、道から奥まった所にある「館林城復原土橋門」前までお話をしながら案内してくださいました。
こういった人の優しさに触れると、旅が楽しくもなり、その地を好きになりますよね。観光プラスひとの温かさが旅の醍醐味です。今回見逃してしまった所もありますので、また機会があれば訪ねたいと思います。
































