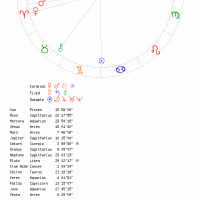もう、終わりだ。
心の中でつぶやく。これを聞いた裕貴がどう思ったのか。軽蔑の視線を向けられるのが恐ろしく、三浦はうつむき、手元を見つめた。
「まさか。言いがかりはやめてください。そうでしょ、孝生さん?」
さきほどと同じように、裕貴が同意をうながす。けれども、三浦は沈黙を通した。
「……まさか、本当なの?」
信じられない、という風に裕貴が訊ねた。震える声に、三浦は忌避の感情を読み取り心が深く傷ついた。
いったんふさがったはずの傷口から、再び血が流れ出すような感覚が生じる。新たに傷がつくよりも、治りかけの傷に爪を立てられた方が、痛みが強い。
三浦は心の痛みに耐えながら、白くなるほど強く手を握った。
「馬鹿ねえ。答えないってのは、本当だからに決まってるでしょ?」
どうしたら他人を効果的に傷つけられるか知りつくしているのか、裕貴の叔母が嘲りの言葉を発した。
「あんたは違っても、こいつはホモって事よ。金か体か知らないけど、あんたはこの男に食い物にされるところだったってわけよ」
「違う! そんなんじゃない!」
叔母の言いように耐えきれなくなり、三浦が叫ぶ。金も体も目当てではない。ただ、温もりがほしかった。
傷ついた動物が二匹、身を寄せ合っていたわりあうような、そんな時間を得難く思うようになっていただけだ。
「俺にそんな気持ちはこれっぽっちもなかった!」
喋りながら、三浦は自分の言葉が空回りしているのを感じた。
まただ。あの時と同じだ。銀行で、聞く耳を持たない相手には何を話しても無駄だと思い知らされた時の、あのどうしようもない虚しさが甦る。
「……帰れ」
「はぁ?」
低く押し殺した声が聞こえなかったのか、裕貴の叔母が小馬鹿にしたように聞き返す。
「もう、話は終わりだ。あんたたちは帰ってくれ」
そう言うと、三浦は強引にふたりの客を追い返した。コートを着るのもそこそこに、玄関の扉を閉めた。
自分勝手なふるまいであったが、自分の過去を知る人間といけすかない女と同じ空間にいる事が、三浦には耐えられなかった。
「クソっ!」
玄関の鍵を閉めると、三浦は玄関の壁を叩いた。
「孝生さん……。えっと……。コーヒー、片付けた方がいい?」
遠慮がちに、裕貴が声をかけてくる。三浦はふり返ろうとしたが、先ほどの震える声を思い出した途端、体が凍りついてしまう。
壁に顔を向けたまま、三浦が低い声でうなるように言った。
「おまえは出て行かないのか?」
「え?」
「俺がホモだってわかって気持ち悪いんだろう?」
ほんのついさっき、裕貴の声に感じた三浦を避けたいという感情、そして傷ついた衝撃が生々しく甦る。
世界中で、自分だけがひとりだと思い知らされたような孤独感に襲われる。
それはもちろん、錯覚であったがそれを考える余裕は、今の三浦にない。
「気持ち悪くないよ。孝生さんがどういう趣味でも、僕は孝生さんが好きだよ」
――典型的な社交辞令。本心からではない言葉。まるで、道徳の教科書に載っているような答えだな――
そんな言葉、まともに信じると思っているのか? 昔、おまえと同じような事を言っていた奴が、陰でなんと言っていたか。
一瞬でも、そんな言葉に救われたと思った過去の自分は……なんと愚かだった事か。
それが嘘だとわかった時、心は倍傷ついた。もうあの時と同じ轍は踏まない。踏んで溜まるか!!
フローリングのきしむ音。背後から裕貴の近づく気配がする。
「玄関は寒いし、早くリビングに戻りなよ。今晩は雪になるかもって天気予報で言ってたよ」
裕貴は三浦に触れずに、声だけかける。
やっぱり、俺に触るのはイヤって事か。
ほんの少し前、真実を――三浦の性癖を――知るまでは、あんなに俺にくっつきたがっていたっていうのに。
そう内心でつぶやいた瞬間、三浦の口からくぐもった声がもれる。
声はすぐに笑声に変わった。自嘲か、開き直りか。どちらともつかない複雑な感情が三浦の精神と肉体を支配した。
急に笑い出した三浦をいぶかしんだか、裕貴が恐る恐る呼びかける。
「孝生さん、どうしたの?」
「出て行け」
三浦の冷たい声が廊下に響き、裕貴が息を飲んだ。
「そんな……。急にどうしてそんなこと言うのさ」
「いいから今すぐ出て行け」
三浦は振り返ると、裕貴の顔を見ずにリビングへ向った。
リビングの隅に置いてあった、警察から取って来たばかりのディバッグを持ち上げ、また玄関へ向って歩き出す。
「忘れものだ」
強引に裕貴の胸元にディバッグを押し付け、腕を掴んだ。
「あっ!」
強引に腕を引かれ、裕貴の足がたたらを踏んだ。三浦は裕貴の事などお構いなしに、玄関の扉を開け、裕貴を思い切り外に向かって突き飛ばした。
「あぁっ!」
玄関の段差を踏み外して、裕貴が地面に倒れ込んだ。そこへ、三浦はたたきに置いてあった裕貴の靴を放り投げ、扉を閉めた。
すかさず鍵をかけ、そのまま大股で寝室へ向うと、ベッドにうつぶせに倒れ込んだ。
「これでいいんだ。これで……」
裕貴を追い出した事を正当化するように、力無い声で自分に言い聞かせる。
裕貴がコートを着ていない事に気づいたが、すぐにまあいいか、と考えた。
今は裕貴も自分の財布を持っているんだ。寒けりゃ、タクシーを拾ってホテルに行くなり、ファミレスに入るなりするだろうさ。
そう心の中でつぶやいた時、窓の方から裕貴の声がかすかに聞こえて来た。
「……孝生さん、開けて、開けてってば!」
「あいつ、まだ玄関にいるのか……」
まあいい。放っておけば、いずれ諦めて立ち去るだろう。そう考えて目を閉じるが、裕貴の声は止む気配がない。
「うるさいな」
蛇口からぽとんぽとんと水滴が落ちるほどの大きさの声だが、無性に三浦の癇に障った。自分はもしかしたら、間違った事をしているのではないか。そんな疑念が生じる。
そうだ。雨戸を閉めればいいんだ。
三浦がベッドから起き上がり、ナイトテーブルに置いてあったリモコンを手にした。
電動シャッターのスイッチを押すと、かすかに音をたてながら雨戸が閉まり、裕貴の声は完全に聞こえなくなった。
改めてベッドにあおむけになり、両目を腕で覆った。泣きたい気分であったが、幸い、涙は出なかった。
*** *** ***
「孝生さん! 孝生さん!!」
寒さに震えながら、裕貴が扉を叩き続ける。もう、三十分ほどもこうしているだろうか。
その間、三浦の返事は一度もない。もう一度呼びかけようとした時、裕貴の鼻先をみぞれ交じりの雨粒がかすめた。
「今晩は雪になるんだっけ……。っ!」
掠れた声でつぶやくや、裕貴が咳き込みはじめる。叫びっぱなしですっかり喉が枯れている。
「どうしよう。コンビニに行って、温かい飲み物でも買って来た方がいいのかなぁ……」
手袋もせず扉を叩き続けた手は、すっかり凍えて強張っていた。揉み手をするように両手を握り合わせて暖めようと試みるが、ちっとも効果はない。
コートもなしに外にいるのだから、当然、全身が冷え切っている。
「はぁ……」
白い息を吐きながら、ディバッグを地面に敷いて、その上に座った。少しでも風の当たらない場所を選んで、両手で体を抱き締める。
孝生さん……どうして急に僕を追い出そうとしたんだろう。
もちろん、原因はわかっている。同性愛者という事を、古川という男に暴露されたから。
裕貴がわからないのは、それを暴露された事が、どうしたら出て行け、という結論になるのかだった。
『気持ち悪くないよ。孝生さんがどういう趣味でも、僕は孝生さんが好きだよ』
それは、裕貴の心からの言葉だった。なのに、その言葉を聞いた時、三浦の気配が明らかに変わった。はっきり言えば、凶暴になった。
もしかしたら、僕があの時に考えていた事が、ばれたのかもしれない。
再び凍えた手に息を吐くと、裕貴は白い物の混じりはじめた空を見上げた。
あの時、三浦が自分を襲ったらどうしよう、と考えたのだ。廊下に押し倒され、衣服をはがされ、肌に口づけや手指による愛撫を受ける妄想が、頭をよぎった。
それは、何とも言えず甘酸っぱい痛みを裕貴の下肢に生じさせた。抱かれたい、という欲望が。
「でも、孝生さんは僕には興味ないみたいだし……」
意識してしまうと、触るのもためらわれた。肩に触れただけで感じそうな自分が怖かった。
どうせなら、この家に初めて来た日の翌日、孝生さんが性欲処理をしろと言った時、しちゃえば良かった……。
あの時は、突然何を言い出すのか、と驚いたんだっけ。僕を追い出すための口実っていうのは当たってたけど、口実に性欲処理を持ち出したのは、孝生さんがホモだったからか。
一度だけ、浴室で見た三浦の全裸を思い出す。立派な、成熟した男の体だった。
その体に組み伏せられ、広い背中に腕を回し、抱きあったら、どんな気分がするものか。
想像するだけで、胸が締めつけられる。きっと、涙が出るほど幸せな気分になれるのではないか、と考えてしまう。
しかし、現実は――三浦に追い出され、こうして自分で自分を抱き締めている。
「孝生さん、僕の事嫌いなっちゃったのかなぁ……。僕はこんなに好きなのに」
好き、という言葉を口にのせると、胸が苦しくなった。何度も繰り返したはずの単語なのに、持つ意味合いがいつの間にか変わっている。
この瞬間、裕貴ははっきりと意識した。自分が、三浦を愛している事を。
「孝生さん……」
三浦の名を呼ぶと、好きという感情と拒否されたという悲しみの入り混じった甘くて苦い感情が込み上げてくる。気がつけば、地面は雪で覆われ、うっすらと雪で白く覆われていた。
冷え切った体は、さっきから震えが止まらない。
「まずい。このままだと熱が出ちゃうよ」
座っているのもつらくなってきた。冷たい地面に崩れるように横たわり、目をつぶると、マッチ売りの少女を思い出した。
朝までこのままだったら、僕、あんな風に死んじゃうのかなぁ……。
まさか、まさかね……。
*** *** ***
いつもより早く眠ったせいか、三浦は中途半端な時間に目覚めてしまった。
「ん……」
かすかに、新聞配達のバイクが走る音が聞こえる。バイクは家の前で停止した。
「新聞が届いたか……。やる事もないし、新聞でも読むか」
妙に頭の芯が冴えていて、再び眠れそうにない。不安な時、三浦はいつもこうなる。こうなっては気分転換をしても落ち着かないのだが、ただベッドに寝転がっているだけよりは、よほど生産的だと考えた。
「寒いな」
寝室から廊下に出た途端、寒気に襲われる。肩をすくめ、両手で体を抱きしめながら階段を降り、サンダルをひっかけて玄関の扉を開けた。
扉の外に広がる光景に、三浦は目を見開いた。
「雪だ……。結構積もってるな」
そうひとりごち、一歩外に出た三浦が目を見開き、鋭く息を飲んだ。
「裕貴……!」
三浦の足元に、目を閉じて、体を丸めた裕貴が転がっていた。
「どうしてこんな所で寝てるんだ」
しかし、三浦の声にも裕貴はぼんやりと目を開けるだけだった。
「孝生さん……」
雪に消えてしまいそうな小さな声で呼びかけると、裕貴が無邪気な顔で笑った。
あまりにも純粋な笑顔を向けられて、三浦は動揺してしまう。
なんて顔で笑うんだ。……いや、待て。裕貴の呼吸が荒い。もしかして熱があるのか?
三浦が急いで裕貴を抱き起こす。握った手が冷たい。海で裕貴を拾った時よりもずっと。
「もしかして、あれからずっとここに……?」
裕貴は三浦の問いにうなずいて答えた。声を出すのもつらそうに見える。
「俺が悪かった」
気がついたら、謝罪の言葉を口にしていた。三浦は裕貴を抱き上げると、急いで寝室に向かった。
ベッドの上に裕貴を横たえ、靴を脱がした。ズボンと上着を脱がして掛け布団をかける。
「孝生さんの匂いがする……」
ふんわりと幸せそうに裕貴が笑う。
「そんな事言ってる場合じゃないだろう。ちょっと待ってろ。今、体温計を……」
三浦は自宅に体温計がない事を忘れていた。体温計だけではない。氷枕もなければ、冷却シートも置いていない。冷えた体を温めるための湯たんぽや、風邪薬さえもない。
「鎮痛剤だけはあったな……」
鎮痛剤には、確か解熱効果もあったはずだと思い直して、三浦は仕事部屋の机の引き出しから鎮痛剤を取り出すと、台所で白湯を作って寝室に戻る。
「ほら、薬だ」
裕貴の体を抱き起こし、背後から支えながら薬を口に入れ、白湯を飲ませた。
「ありがとう」
「礼なんかいい」
「……孝生さん、手を握ってくれる? 手も足も冷えちゃって……」
弱々しい訴えに、三浦は即座に応じた。冷え切った右手を両手で握り締める。
「おまえ、俺に触られてもいいのか?」
「うん。できれば一緒に寝てほしい。寒いから、抱き締めて暖めてほしい」
そう訴えられて、三浦は一瞬逡巡した。さすがに手を握るのとは訳が違う。
こいつ、俺の事避けてたんじゃないのか? 俺の誤解だったのか……。気持ち悪いと思ってないなら、抱き締めるくらい構わないか。いやいや。そういう訳にもいかないな。
自分が同性愛者とわかっても、変わらず慕ってくれる裕貴が愛おしい。この想いを抱いたまま抱き締めたらどうなるか。
さすがに襲いはしないが、頬や髪にキスくらいはしてしまいそうだ。それはさすがにまずいし……。 要は湯たんぽがあればいいんだよな。
「そうだ」
燃えないゴミの中に、洋酒の空き瓶があった事を思い出した。ウィスキーのボトルに熱湯を入れ、バスタオルでくるめば、即席の湯たんぽになるのだ。
学生時代、北国出身の友人が子供の頃はそうしていた、と聞いた覚えがある。
「寒いなら、湯たんぽを作ってやる。ちょっと待ってろ」
三浦は湯たんぽを作りに階下へ向った。これで何度目の往復になる事か。けれども、それが面倒だと全く思わなかった。
一度にみっつも湯たんぽを作り、裕貴の脚の間と足の先に置いた。残りのひとつは、裕貴に抱かせ、手を温めさせる事にした。
「これでいいだろう?」
「……うん。ありがとう」
わずかに間をおいて裕貴がうなずいた。
今にも泣きそうな裕貴の顔に、三浦はよほど気分が悪いのだろう、と考えた。
「のど乾いてないか? それとも、ひとりになって眠りたいか?」
「んと……これだけ熱が高いと眠れないし。……孝生さん、ここに居てくれる」
潤んだ瞳で三浦を見つめながら、裕貴が訴える。掛け布団から手を出して、三浦に差し出した。その動きにつられるように、裕貴の右手を握った。
さっきより、温まって来た。良かった、と内心で安堵のため息をつく。
「ふふっ。――寝室、入れてもらっちゃった」
「馬鹿。今はそんな事、どうでもいいだろう?」
「思っていたより普通の寝室だね。ベッドがダブルでびっくりした」
「ベッドは広い方が快適だからで、特に意味はないからな」
裕貴に、セックス目的でベッドに連れ込んだと誤解されないようにと、慌てて三浦が弁解した。
「うん。わかってる。孝生さん、快適なのが好きなんだよね」
そう言うと、裕貴が淡く微笑み目を閉じた。
眠くなってきたかな……。いい傾向だ。
三浦は裕貴の額に左手を当てて、熱を確かめた。
「それでも、まだかなり熱いな……」
裕貴が眠ったら、コンビニに冷却シートとスポーツドリンク、他にも必要な物があれば買ってこようと決めた。
じきに、裕貴の呼吸が規則正しい物へと変わり、三浦が手を離そうとする。
びくん、と裕貴の手が動いて、三浦の手をぎゅっと握ってきた。まるで、離さないとでもいうように。
「起きたのか?」
そう小声で尋ねるが、裕貴に反応はない。しかし、三浦の手をしっかりと握ったままだ。
ふと、亡くなったばかりのリクの事を思い出した。自力で食事もできなくなり、息を吸うのもつらそうであったが、それでも三浦が撫でるとわずかに呼吸が穏やかになり、眠りに落ちた。眠った、と思って手を離すと、その瞬間目を開けて、じっと三浦を見つめる。
離れちゃイヤ。と、全身で訴えかけたリクに、今の裕貴はとても良く似ている。
「けどまあ、ずっとこのままってワケにもいかないしな」
ぽんぽん、と布団の上から裕貴の体を優しく叩くと、三浦はそっと手を引き抜いた。床から立ち上がると、クロークからコートとマフラーを手に寝室を出た。
コンビニに行こうと外に出ると、雪はいつの間にか止んでいて、雲の合間からぼんやりと月が姿を現していた。