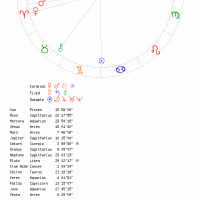それから二日後の朝。裕貴の熱も下がり、ほぼ平熱に落ち着いた。
「体調が良くなったといっても、今日一日は油断せずに温かくして大人しくしてるんだぞ。明日になったらいつも通りにしていいから」
体温計を見ながら三浦が言うと、裕貴がどこか寂しげにうなずいた。
まるで、熱が下がった事が嬉しくないとでもいうように。
「元気になって、嬉しくないのか?」
「嬉しいよ、もちろん。元気になったら散歩にも行けるし」
奥歯に物が挟まったような返事に、三浦の疑問が余計に深まる。
「何かあったのか?」
「何かって? 何もないよ。それより、できれば今日から散歩に行きたいんだけど……ダメ?」
ベッドの隣に敷いた、真新しい布団に横たわりながら、裕貴が真剣な顔で頼んでくる。
「病み上がりで外に出るのか?」
「昼間ならいいでしょ? ちゃんと温かい格好をしていくから。それに、ずっと寝てばっかりいたから、体を動かしたいんだ」
裕貴の言い分をもっともだと考え、三浦がうなずく。
「それもそうだな。昼飯を食べたらすぐに散歩に行こうか」
「うん。楽しみにしてる」
三浦の許可を得て、ようやく裕貴が笑顔を浮かべた。
いったい、なんだって言うんだ? こいつの反応は、相変わらずよくわからない。
この後は朝食の時間で、裕貴がパジャマの上から三浦のカーディガンを着た。
パジャマは、布団と一緒に三浦が買ってきた物だ。カーディガンは、この間買った裕貴の服がすべて春物だったため、三浦の手持ちの中で丈が長めの温かな物を貸している。
ベビーアルパカの薄くて軽い茶色のカーディガンに裕貴は丁寧に袖を通し、マザーパールのボタンを留めた。
「……そのカーディガン、そんなに気に入ったのならおまえにやるぞ」
「え? でも、悪いよ」
「おまえの服は、最初に着ていたセーター以外、全部春物だろう? まだまだ冷える日もあるし、羽織り物で一枚くらい冬物があった方がいい。俺のお古で悪いけど」
「じゃあ、お言葉に甘えさせてもらおうかな。……本当にありがとう、孝生さん」
花がほころぶように微笑むと、裕貴がカーディガンを着た己の体を愛しげに抱き締めた。
「おまえ、そんなに喜ぶほど寒かったのか?」
あまりの喜びように三浦が尋ねると、裕貴が頬を紅潮させた。
「違うよ!」
「じゃあ、どうして?」
「え? あ、あぁ……。えっと、そう……です」
「それ一枚で足りないなら、他にもセーターとか冬物をやろうか? まだ袖を通してないのがあったはずだ」
「いい。いいよ! これだけで十分だから!!」
顔を真っ赤にさせて裕貴が申し出を断る。
それからふたりは朝食を食べ、裕貴は寝室に戻った。三浦は掃除、洗濯と家事をこなし、いったん寝室に顔を出してから仕事部屋に行き、パソコンの電源を入れた。
例のゲームは、ここ三日ほどバタバタしていたので、だいぶおざなりになっている。
それでも、タイミングが良かったのか、いくつか指値を入れていた分が決済され、やる気と関係なく残高は増えていた。
「これはこれでいい事だが……、なんとなく複雑な気分だな」
損をしてばかりの人間からすれば、嫌味な事このうえない発言だが、三浦はゲームとしてFXをしているのだから、勝ち負けよりは、自分が主体的に行動している、という実感の方が大切だった。
そうして十一時になり、三浦は昼食の準備のために仕事部屋を出た。いつもより少し早目の昼食だが、その方が散歩に早く行けるし裕貴も喜ぶだろう、と考えての事だ。
昼食のメニューは鍋焼きうどん。三浦はパスタやパンなどの方が好きだったが、裕貴が和食好きだとわかって、病気の間くらいは好きな物を食べさせたい、と思っていた。
案の上、裕貴は鍋焼きうどんを見て、歓声をあげた。
「おもちも入ってるんだ。それに半熟卵も! おいしそう!!」
「たくさん食べろ。もちろん、無理はしなくてもいいけど」
「食べる。もう、ほとんど体調は戻っているんだ。……それもこれも、孝生さんのお陰だね」
ふうふうと熱々のうどんを冷ましながら食べる裕貴を、三浦が微笑ましい気分で見守る。
あまり好きではないはずのうどんが、どうした事か、とても美味に感じてしまう。
体の内側から温まった所でコートを着て散歩に出かける。
「久しぶりの外だ。……まだやっぱり寒いや」
この間と同じように嬉しげであったが、今日の裕貴は大人しく三浦の左隣を歩いている。
「裕貴、俺のこっち側に来い」
三浦が裕貴を反対側に移動させる。さりげなく三浦は風よけになると、裕貴の背中に腕を回した。すると、裕貴がおずおずと三浦の腕に手を伸ばした。
「う、腕に……つかまっていい?」
「いいぞ」
病み上がりのため、裕貴が慎重になっているんだろうと考え、三浦が腕組みを許可する。裕貴が三浦の腕にすがるように両腕を絡ませた。
裕貴が楽しげに三浦を見上げる。すっかり当たり前となった大好きと物語るまなざしが、向けられる。
こいつの場合、好きといっても、保護者として好きってだけだが。
それでもいい。同性愛者とわかっても、態度を変えないでいてくれるだけでありがたい。
、セックスするだけが恋愛でもなく、愛する者を見守るだけの関係もあっていいだろう。シラノ・ド・ベルジュラックのように。
十歳年下の青年を見つめながらそんなことを考える。海岸に着くと、裕貴が感嘆するように息を吐き、そして海を見つめた。
白い波頭を見つめる裕貴の瞳は、不思議と強い意志を感じさせた。まるで、何かを決意したように。
あまり波打ち際に近づかないよう気をつけながら、砂の上をふたりは並んで歩く。
ふたりともほとんど喋らず、時折視線を交わし合うだけだが、その空気がとても心地良かった。
リクがいた時も、こんな風だったな。
裕貴のまなざしから伝わる、安心や信頼、そして愛情は何にも増して得難く思う。
波の音と風の音を聞きながら歩いていると、裕貴が小さく声をあげた。
「なんだろう、これ?」
裕貴が砂に半ば埋もれた薄青の欠片を拾いあげた。
「ああ。それはシーグラスだな」
「シーグラス?」
「ガラスの欠片が波に洗われるうちに、角が取れて曇りガラスのようになった物だ」
「ふぅん。……綺麗だねぇ」
裕貴がシーグラスを日に透かした。曇りガラス越しの光は淡く、どこか儚ささえ感じられた。
裕貴がシーグラスをポケットにしまうと、また、三浦の腕に腕を絡めた。
「持って帰るのか?」
「うん。いい記念になるかなって思って」
「記念? シーグラスなんて、珍しくもないだろう?」
「そうだけど……」
裕貴がシーグラスを通した光のような笑みを浮かべた。
「……そんなに気に入ったのなら、穴を開けてキーホルダーか何かにしたらどうだ?」
「キーホルダーか。だったら、携帯ストラップにしようかなぁ」
たかがガラスの欠片に裕貴が夢中になっている。くだらない、と思わなくもない。それでも、裕貴の楽しそうな様子を見ていると、三浦も嬉しくなってしまった。
「――そろそろ帰るか」
「もう?」
三メートルほど先を歩いていた裕貴が名残惜しげな声で答える。
「もう一時間経った。それに、明日また散歩の時、ここに来ればいいだろう?」
「そう……だね。明日があるよね」
こくん、とうなずくと裕貴が三浦の元にやってきた。
帰宅した後は、リビングでお茶をして夕食を整える。
裕貴が元気になったので、久しぶりに三浦は酒を飲む事にした。
最初はシャンパンで乾杯し、瓶が空になったので今度は白ワインの瓶を開けた。
裕貴は思ったよりいける口で、三浦とほぼ同じペースでシャンパンやワインを飲んでいた。
「孝生さんちのお酒は、おいしいね」
「どうせ飲むなら旨い方がいいからな」
「ワインはあんまり好きじゃなかったけど、こんなにおいしいならいくらでも飲めちゃうなぁ」
酔いが回ってきたのか、グラスを口に運ぶ裕貴の目元や頬が、うっすらと赤く染まっている。
「孝生さん」
舌足らずの声で呼んだかと思うと、裕貴がソファに寝そべり、三浦の太腿に頭を載せる。
「酔いが回ったか?」
「違うよ。犬だから、犬っぽく振る舞ってるの」
「まだ犬ごっこか」
「ごっこじゃないよ」
苦笑する三浦を裕貴が真剣な目で見上げる。潤んだ瞳、半開きの唇には色気としかいいようのない艶があった。
「大好き。世界で一番、大好き」
ソファの背もたれに手をかけ、裕貴が三浦の上に覆いかぶさる。
「リクも、こういう事、した?」
「あぁ。俺の肩や胸に前足をかけて、顔を舐めてきたりしたなぁ」
懐かしく思いながら口にすると、裕貴が頬をペロリと舐めた。
「うわっ!」
「こんな感じ?」
「舐めるのはよせ」
「ん……。じゃあ、キスならいい?」
トロンとした目で裕貴が三浦の頬に唇を押し当てる。ワインの芳香が鼻孔を掠めた。
裕貴が三浦の首に腕を回し、上半身を密着させながら何度も顔に口づける。
***ここからかなり恥ずかしいシーンになるので割愛します。ファイルをダウンロードすることで読めるようにいたしますので、もう少々お待ちください***