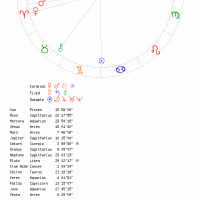「びっくりしたよ。大学の試験が終わって家に帰ったら、当然のように叔父さん一家がいたんだ。その時にピンときた。こいつらが、家の鍵を盗んだんだ……って。その上、しれっとした顔で『一軒家におまえひとりじゃ寂しいだろうから、一緒に住んでやる事にした』……って言うんだよ。信じられる!?」
「……災難だったな」
叔父一家のあまりのずうずうしさに、三浦も呆れ返る。
「出て行ってほしい、って言ったんだけど、全然聞かないんだ。こっちは試験もあるから、昼間は家を空けなきゃいけない。その間に、あいつらは家の中を好き放題に散らかして、おまけに金目の物を売ったりしてた」
「そりゃ、犯罪だぞ」
「僕もそう言った。だけど、困っているおまえを助けているんだって、逆に居直られて……。こっちはただでさえ消耗していたから、もう、パニックになっちゃって……。そのうちに、借金取りまでうちに来るようになった。どうやら叔父さんは、借金取りから逃げるためにうちに来たみたいだった」
……確かに、そんなことになれば家にも帰りたくないだろう。そう三浦が内心でつぶやいた。
「春休みに入ってからは、地獄だった。外出しても外はうるさいし、友達と遊んでいても話を合わせる気力もなくて。家に帰れば借金取りが来て、おまけに叔父さん一家が大騒ぎ。テレビは大音量でつけるし、いとこたちは泣いたり走り回ったり。極めつけは……借金取りに来られるのが嫌だったら、遺産を寄こせってしつこく迫って来た」
「…………」
「遺産と保険金と賠償金で、僕、結構お金持ちなんだ。あぁ……だから、孝生さんに買ってもらった服とか靴とか生活費も、あとでちゃんと返すね」
気だるそうに言うと裕貴が力なく微笑んだ。こんな時にすら、裕貴は三浦を気遣う。その健気さに、三浦の胸が締めつけられる。
「気にするな。飼い犬の面倒を見るのは、飼い主の責任だ。それにたぶん、俺はおまえ以上の金持ちだ。気にするな」
三浦の励ましの言葉に、裕貴が軽く眉を寄せる。
「そうなの? でも、やっぱり悪いよ。家事だって孝生さんの方が上手いし。本当に僕は何の役にも立ってないから」
「こっちは十年以上ひとり暮らしをしているんだぞ。家事が上手くて当然だ」
「今日は警官までここに来て、迷惑かけちゃったし……」
「あんなのは迷惑のうちに入らない」
三浦が力強い言葉に、握ったままの裕貴の手が温かくなっていった。
「ありがとう。孝生さん。僕、孝生さんに迷惑かけっぱなしなのに、こんなに優しくしてくれて。なのに、僕は何も返せない。……ごめんなさい」
「いてくれるだけでいい」
「……」
「俺は自分でもわからなかったが、リクがいなくなって、随分寂しい思いをしていたらしい。だから、おまえがリクのように俺を慕ってくれるだけで十分なんだ」
……その他にも、いろんな物を返してもらってるしな、と三浦が心の中でつぶやいた。
例えば、こうして気遣うという行為や、誰かに喜んでもらうと自分も嬉しくなるとか。
そんなプリミティブな、人間本来の素朴なありようを再確認できた気分だった。
こどもの頃は当たり前のように持っていた感情だったが、ひとりで孤独に暮らすうちに、すっかり忘れてしまっていた。それだけに、とても新鮮で懐かしい感覚だった。
しかし、全てを正直に告げるのも面映く、三浦は曖昧な言い方で誤魔化すと、裕貴の手を離し肩に回した腕を外した。
一瞬、寂しそうな目で裕貴が三浦を見上げたが、すがるような真似はしなかった。
「パスタ、すっかり冷めちゃったね。せっかく作ってくれたのに、ごめんなさい」
「さっきから、おまえは謝ってばかりだな」
三浦が立ち上がり、冷たくなったパスタの皿を手にした。
「こいつはもう片付けよう。俺は食欲がなくなった。おまえもそうだろう?」
しょんぼりした裕貴の頭に三浦が手を置き、ぽんぽんと動かした。
「腹が減ったらサンドイッチでも作るさ。じゃなかったら、外に早めの夕食を食いに行けばいい」
「家にいたい」
「わかった」
三浦がパスタとサラダの皿を下げに台所へ行くと、同じように自分の皿を持って裕貴が後からついて来た。
「温かい飲み物でも飲むか。コーヒーとミルク、ティーバッグの紅茶、あとはココアがある。どれがいい」
「孝生さんと同じでいい」
「じゃあ、紅茶だな。ちょっと洋酒を垂らすと体が温まる」
三浦は食器の片づけは裕貴に任せ、自分は紅茶を淹れることにした。
「孝生さんって、コーヒーはかなりいい豆を使ってるのに、紅茶はティーバッグなんだね」
食器を食器洗浄機にセットしながら、裕貴が話しかけてくる。
「俺はコーヒー党なんだよ。コーヒーの豆の良し悪しはわかるが、紅茶はさっぱりだ。それに、ティーバッグといっても、うちのは旨いぞ」
ティーパックの入った箱をかざして見せると、裕貴がのぞき込んできた。
「本当だ。知らないメーカー。おいしいの?」
「ティーバッグの中ではかなり。といっても、お歳暮でもらったんだが」
お歳暮の贈り主は、いわゆる広域指定暴力団の幹部で地元の組長なのだが、それはさすがに言えなかった。
銀行員時代の営業先、その社長の父親が組長だったのだ。どこでどう噂が流れたのか知らないが、三浦に財テクの才能があることを聞きつけ、資産運用――ぶっちゃけて言えば、暴力団の資金稼ぎ――を依頼してきたのだ。
組の事務所ではなく、傘下の消費者金融の事務所で話し合いをした時に出て来たのがこの紅茶だった。
お世辞で『旨いですね』と言ったら、組長がそれを覚えていて、毎年お歳暮として届けられるようになったのだ。
その話は『いずれ気がむいたら』という事でお茶を濁しつつ断ったのだが、お歳暮が届く限り、組長は三浦を諦めてない、という証拠でもあった。
お湯が沸くとケトルの中にティーバックを浸す。
こいつには糖分も必要だな。ロシアンティーに変更するか。
「いちごのジャムとマーマレード、どっちが好きだ?」
「いちごかな」
「じゃあ、いちごのジャムにワインを入れて……っと」
カップにジャムと赤ワインを入れ、スプーンで軽く混ぜてから紅茶を注いだ。自分の分の紅茶には、ブランデーを風味づけ程度に入れる。
紅茶を淹れ終わると、片付けを終えていた裕貴の待つリビングへカップを持って戻る。
裕貴の隣に座ると、あからさまにほっとした顔になった。甘えん坊の子犬が、カップを手にして紅茶を飲み、口を開く。
「孝生さん。僕、あとで警察に行く」
思いつめた顔で裕貴が言った。きっと、裕貴にとっては一大決心だったのだろう。
「その気になったか」
「うん。孝生さんには迷惑をかけているんだし、あんまりわがまま言っちゃいけないから」
「じゃあ……四時になったら散歩に行って、帰って来たら車で警察に行くか。夕食は適当にどこかの店で食べよう。それとも、遅くなるが家に帰ってきてからにするか?」
「外食でいいよ」
さっきは家にいたいと言った裕貴だが、『わがままを言っちゃいけない』という言葉を貫徹するつもりなのか、外食に賛成した。
無理しなくてもいい、と言おうと思ったが、本人が外食でいいと言っているのだから、外食で済ませようと思い直した。
「それじゃあ、せめて、静かな店にしよう。高森さんにいい店を聞いておく」
「ありがとう。お願いします」
ほんの少し改まった口調で言うと、裕貴が三浦を見つめて来た。
撫でろ、と言っている目だな……。
黒い瞳に誘われて手を伸ばしかけた時、時計の針が一時を回っている事に気づいた。
そろそろ、仕事――いや遊びか――に戻らないと……。
「すまない。俺は二階にあがる。今日はもう家事はしなくていいから。あとで携帯を持ってくるから自分で警察に連絡するんだぞ」
こっくりと裕貴がうなずくのを確認し、三浦が紅茶の入ったカップを手に仕事場へ移動する。
裕貴はまだ不安そうだな。何が気にかかっているのだろう?
そんな事を思いながら、三浦はパソコンの前に腰を下ろした。
*** *** ***
その後、三浦から携帯を借りて、裕貴は警察署に電話した。
遺失物を取りに行く事を告げ、電話を切る。テーブルに携帯電話を置くと、毛布にくるまった。寒いからではない。何かに包まれて安心したかったのだ。
「まさか、あの人達が捜索願を出していたなんて……」
裕貴が叔父夫婦を思い出し、眉を寄せた。
裕貴は叔父よりも、叔母の方が怖かった。裕貴の叔母は、女のエゴを非常に強く持った人間で、それをてらいなくむき出しにするタイプの人間だったから。
最初に家に上がり込んだ日のことだ。叔母の胸元を真珠のネックレスが飾っていた。
大粒の真珠のネックレスは、母の嫁入り道具のひとつでとても大切にしていた品だ。
妹の彩乃が年頃になったら譲ると約束していた物で、その日が来るのを妹はとても楽しみにしていた。
そのネックレスを勝手に持ち出されたのだ。当然、裕貴は気色ばんだ。
「そのネックレスは、母の物です。返してください」
「どうして? あんたが持っていてもどうしようもないじゃない。だから、あたしが使ってやるっていうのよ」
へ理屈もいい加減にしろという気分になった。
母と妹の想いを、大切な思い出を汚す叔母に、思わず裕貴が腕を伸ばした。殴ろうとしたのではない。ネックレスを外そうとしたのだ。
すると、叔母は大げさに悲鳴をあげた。家中、いや近所にまで響くような叫び声に、叔父と三人の従姉弟たちもやってくる。
「どうした!?」
「裕貴が私をぶったのよ」
「なんだと!!」
叔父が裕貴を睨みつけ、襟元を掴んだ。叔母は殴られたかのように頬に手をあててうつむいた。
「ちっ、違う――。僕は、ただネックレスを取り返そうと……」
裕貴が弁解を言い終えないうちに、叔父の拳が裕貴の腹に入った。思いがけない一撃によろめいた所で、小学校三年と一年の従兄弟が裕貴の腕と太腿にむしゃぶりつく。
「お母さんにひどい事をするな!」
「謝れよ!」
小さい従兄弟たちは、本気で母が殴られたと信じている。裕貴を敵だと認識して、険しい瞳を向けて来た。
小学校五年生の従妹が、叔母の元へ気遣わしげな顔で近づき、裕貴を睨みつけている。
叔父の暴力よりも、十歳以上年下の従姉弟たちの反応の方が、裕貴にはやりきれなかった。
どんなに嘘つきで最低な女でも、子供たちにとっては大切な母親なのだ。
「あ……」
こどもの純粋な敵意に晒されて、裕貴から抵抗の意思が奪われた。立ちつくす裕貴に、叔父が何度も拳をふるった。
その時、藍原家の中の力関係が決まった。叔父夫婦の敵意と醜悪さに耐えながら、自分の部屋と大学を往復する日々がはじまったのだ。
「嫌な事を思い出しちゃった……」
「――何やってるんだ?」
「孝生さん! お仕事、終わったの!?」
大好きな保護者に向かって裕貴が笑みを向ける。どんな嫌な思い出が裕貴を襲おうとも、三浦が姿を現わすと、すぐに笑顔になれる。
「今日はイマイチだったから、早めに手じまいにした。……どうだ。少し早いが散歩に行くか?」
「うん」
被っていた毛布を畳んで裕貴が立ち上がった。コートを着て外に出ると、遅れて三浦がやって来た。そのまま並んで言葉少なに海岸へ向かう。
風に吹かれながら、裕貴は海を見つめた。水平線が遠くに見える。
ふたりで静かに海を見ていると、心が穏やかになり、満たされていく気がした。
「そろそろ帰ろう。風が強くなってきた」
優しく肩に手を置かれて裕貴がうなずいた。
孝生さんが傍にいたら、僕は全然寒いなんて思わないんだけどなぁ……。
白いマフラーに顔を埋めながら、そんな事を考える。そうして家に帰ると、三浦の運転するハイエースに乗って警察へ向った。
事前に連絡をしていたからか、簡単に裕貴のディバッグは返してもらえた。
ナイロン製のカジュアルなデザインのバッグを受け取り、念のために中身を確認する。
財布、携帯、ハンカチ、ティッシュ。ipodに――家の鍵。
「無くなっている物はないか?」
「貴重品も含めて全部あるよ。現金もカードも、そのまま」
「いい人が拾ってくれたんだな」
「うん。すごいね。――すごい」
金品は盗まれていても仕方ないと諦めていたが、それでも無事に帰って来ると不思議な喜びが込み上げてくる。
孝生さんの住む街の人。どこの誰かは知らないけれど、ありがとう。
心の中で礼を述べると、裕貴は三浦の顔を見上げた。
孝生さんと出会ってから、いろんな事がいい方向に向かっている気がする。
小さな喜びが、とても大きな物に感じる。そう感じられることが、嬉しい。
「ありがとう」
「何がだ?」
裕貴がほほ笑むと、三浦が不可解、という風に顔をしかめた。
ふたり並んで小さな待合室を通り抜け、警察署の玄関を出て、駐車場へと向かった。
いや、正確には向かおうとした。
「見つけた!」
その声に、裕貴の足が止まった。受け取ったばかりのディバッグを落としそうになる。
「あんた、今までどこをほっつき歩いていたのよ!」
紫色のフェイクファーのコートを着た叔母が、まっすぐに裕貴に向って歩いてきた。
「知り合いか?」
異変を察したのか、裕貴を庇うように三浦がさりげなく背後に回った。
「叔母さん……」
つぶやきにも似た裕貴の返答に、三浦の顔が険しくなる。しかし、その三浦以上に険しい顔をしていたのは、裕貴の叔母の方だった。
「どこをほっつき歩いてたのかって聞いてんのよ!!」
そう言うや否や、叔母が裕貴に平手打ちをくらわせようと、手を振り上げた。
首をすくめ、目を閉じて、衝撃に裕貴が身構える。
「待ちな。あんた――山口さんだっけ? どうして裕貴を殴ろうとするんだ?」
ドスの利いた声で三浦が叔母に問いかける。
「あんた誰? とっとと腕を離しなさいよ!!」
「俺は裕貴の友人だ。友人が突然殴られそうになったら、普通は助けるもんだ」
「……離さないつもり? 大声を出すわよ?」
「ご自由に」
叔母と三浦のやり取りを聞きながら、裕貴は『まずい』と思った。
早く手を離さないとこの叔母がどんな言いがかりをつけるか――。
そう思うだけで、心臓を素手でつかまれるような不安が裕貴を襲う。
不幸な事に、裕貴の予想は当たった。
「誰か! この男が私に乱暴を!!」
金切り声をあげて、叔母が助けを求める。すぐに入口近くで見張りをしていた警官が、三人の元へ駆けつけてくる。
「どうしたんですか?」
「この男が、急に私の腕を掴んで暴力をふるおうとするんです。早く、この男を逮捕して!」